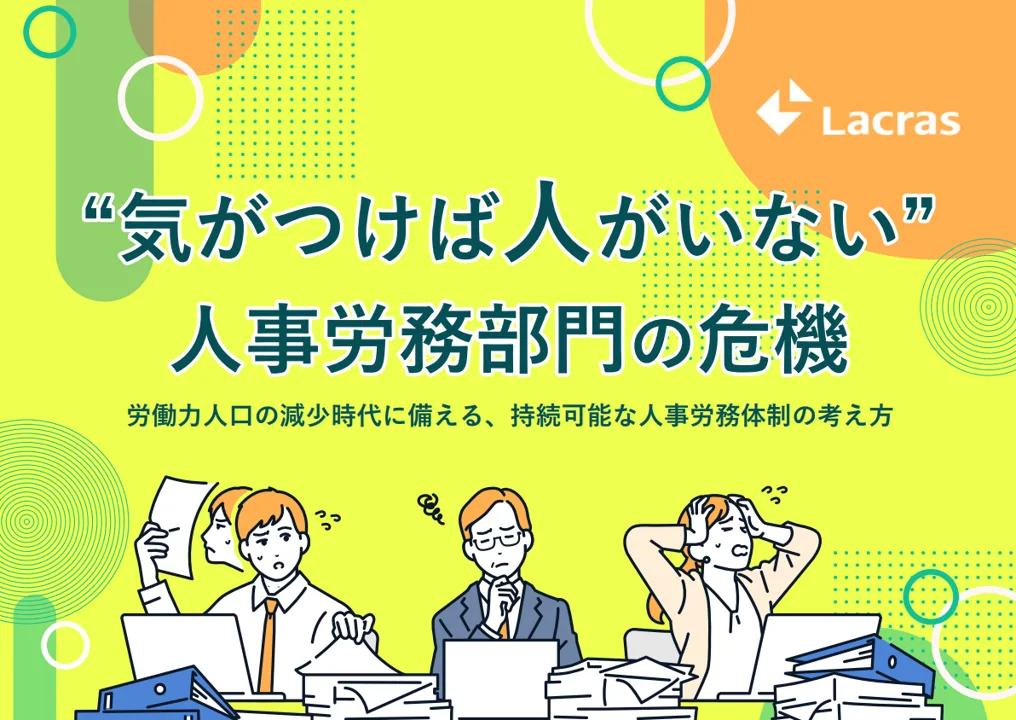賞与評価の重要性とは?|不当査定を防ぐための基準や実践的手法、就業規則のポイントを解説

本記事では、賞与評価の重要性と、公正・公平な評価に不可欠な項目、評価の基本的な流れなどを解説します。また、賞与評価の実践的な手法や、不当査定を避けるためのポイントなども紹介していきます。これから賞与評価の仕組みを設計する方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
賞与(ボーナス)を支給し、その効果を最大化させたいのであれば、「賞与の評価」を適切に行うことが重要です。主観的な評価をしてしまうと、従業員に不満や違和感などを生じさせてしまう問題が起きます。それはつまり、賞与評価のやり方を誤ると、逆効果にもなってしまうということです。
こうしたトラブルを防ぐためには、客観性が高く公正・公平な仕組みを設計することが必要なのです。
そこで本記事では、賞与評価の重要性と、公正・公平な評価に不可欠な項目、評価の基本的な流れなどを解説します。後半では、賞与評価の実践的な手法や、不当査定を避けるためのポイントなども紹介していきます。
これから賞与評価の仕組みを設計する方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
賞与(ボーナス)評価の重要性
賞与評価とは、いわゆるボーナスの金額を決めるために行う評価のことです。一般には「賞与査定」や「ボーナス査定」と呼ばれたりもします。
賞与評価を適切に行うためには、それらが企業および従業員に与える影響と重要性を理解することが大事です。ここではまず、「ボーナスを支払ううえでなぜ適切な評価が重要になるのか?」を考えていきましょう。
適切な賞与評価が従業員に与える影響と重要性
適切な評価にもとづく賞与の支給は、従業員のモチベーション向上につながるものです。
その理由は、企業側からの「賞与の支給」および「適切な評価」が、行動意欲を高める働きかけとなる『外発的動機づけ』の役割を担うことが多いからとなります。
たとえば、営業活動を頑張って、今回はじめて部門1位の成績をあげた従業員(Aさん)がいると仮定します。そこでAさんの業績を適切に評価したうえで、従来よりも高い賞与を支給すると、「努力が認められた。頑張って良かった」といったポジティブな想いから、仕事へのモチベーションが高まりやすくなるでしょう。
さらに、そうした前向きな想いは、仕事のパフォーマンスや生産性を高めることにもつながっていきます。
適切な賞与評価が企業に与える影響と重要性
適切な評価にもとづく賞与の支給で従業員のモチベーションやパフォーマンスが向上すると、前述したように組織全体の生産性も高まりやすくなります。
また、賞与を受け取った従業員に生まれる「自分はきちんと評価されている」とか「この組織のためにもっと頑張ろう」といったポジティブな想いは、評価を行った上司および組織への愛着や信頼につながっていくかもしれません。それはいわゆる、「従業員エンゲージメント」や「従業員満足度」といったものでしょう。
従業員エンゲージメントの向上は、離職率を低下させるうえでも大切にしたい要素です。
近年のビジネス環境では、終身雇用の崩壊や人材の流動化、キャリアの多様化などの背景から、若手を中心とする人材の離職が起こりやすくなっています。また、売り手市場の業界も多く、自社に合った優秀な人材の獲得に苦戦する企業も少なくない状況です。
こうしたなかで、自社に愛着を持ち高いモチベーションで仕事に取り組む人材を増やすためには、適切な評価にもとづく賞与支給などが大きな鍵になってくるでしょう。
なお、従業員エンゲージメントについては、下記の記事でも詳しく解説していますのでご覧ください。
賞与評価(賞与査定)のトラブル事例
ここまでご紹介したとおり、適切な賞与評価は従業員と企業(組織)の両方に多くのメリットをもたらすものです。しかし、その重要性を理解せず、主観的な賞与評価を行ってしまった場合、組織の成長を妨げる問題やトラブルに発展することがあります。
ここでは、主観的な賞与評価によって起こり得る2つのトラブル事例を紹介します。
事例(1)査定基準の不透明さによるトラブル
賞与評価の失敗から最も起こりやすいのが、査定基準の透明性および公平性が低いことによる不満です。たとえば、上司が以下2人の賞与査定を行なったと仮定します。
|
【Aさん】上半期の売上2,000万円、営業部門1位、入社3年目 【Bさん】上半期の売上600万円、営業部門6位、入社2年目
|
上記に並ぶ数字だけを見ていくと、売上・部門内順位・社歴のすべてが高いAさんの評価のほうが高く、賞与の額もBさんよりも多くなると判断されるのが自然です。
しかし、そこに上司の主観が入った場合、以下のように上司にしかわからない「個人的な視点・評価・事情」から、透明性や公平性が著しく低い評価になることがあります。
|
|
不透明かつ不公平な評価基準により、AさんよりもBさんの評価が高くなった場合、両者のなかに「なぜこういう評価になったのだろう?」という疑問が生まれやすくなります。
また、営業成績が良かったAさんには「自分の何が悪かったのか?」とか「どうすればBさんよりも高評価になるんだ?」といったネガティブな感情(違和感・不信感・不満)が生じる可能性が高いでしょう。
ネガティブな想いが蓄積すれば、仕事へのモチベーションも低下しますし、場合によっては離職の動機につながることもあります。本人の自己査定と会社側の査定に大きな乖離があれば、最悪の場合には訴訟を起こされて労働紛争になるかもしれません。
いずれにせよ、不明確で曖昧な基準による賞与評価は、被査定者である従業員からの信頼を失う要因になる可能性が高いと考えられます。
事例(2)退職者の賞与査定に関するトラブル
退職者(退職予定者)の場合、「賞与の目的・意味・査定基準」の認識が会社とずれていた場合に、トラブルになることがあります。たとえば、「賞与を全額もらってから辞める予定だったのに、かなり減額されていた。納得がいかない……」といったトラブルです。
そもそも、賞与の支給目的や支給対象などのルールは、会社が独自に設定できるものです。
そのため、たとえば会社側で「弊社の賞与は今後への期待値を含めている」というルールを就業規則で明示していれば、離職によって“今後への期待”からはずれる退職者に対しては、賞与の減額や不支給を選択できるかもしれません。
しかし、退職者がこのルールを知らなかったり、異なる解釈もできる文面だったりする場合、「なぜ減額されるのか?」「なぜ支給されないのか?」といった苦情が来てしまう可能性もあるでしょう。
賞与評価の基準項目
賞与評価で従業員に不満や不公平感を生じさせないためには、客観的な視点を持ち、適切な流れで評価を進めていくことが重要です。そこでポイントになるのが、複数の評価項目を使う方法です。
ここでは、賞与評価で使われることが多い3つの評価項目について、概要と具体例、ポイントを紹介しましょう。
(1)業績評価
業績評価とは、一定期間内の定量的な成果で評価をする考え方です。具体的には、「売上」「販売個数」「プロジェクトの完了度」といった数値化できる項目を使い、評価を行います。
業績評価を取り入れやすいのは、営業職でしょう。
営業職の場合、たとえば「売上1,000万円のAさん」と「売上5,000万円のBさん」が対象となる場合に、2人の業績に注目すれば、「Bさんのほうが多くの売上をあげているから、賞与の評価も自ずと高くなる」などの評価を行えます。
このように、定量的な成果を出すことが求められる部門や職種の場合、業績評価を重視することで公正・公平な評価を行いやすくなります。
(2)能力評価
能力評価とは、業務を遂行するうえで必要なスキルや知識などに着目する評価です。
業績評価では、必要スキルの「習得度」はもちろんのこと、知識やスキルの「活用度」に着目する場合もあります。重視されるポイントは、以下のように多岐にわたるでしょう。
|
|
能力評価は、人材および組織の中長期的な成果や成長につながる項目です。
たとえば、営業職のAさんが新人OJTを担当する場合、新人への指導やサポートを丁寧に行うと、自分の営業活動に支障が出るかも知れません。それはつまり、業績評価が下がる可能性を意味します。
しかしそこで能力評価を行うと、「新人への指導力」や「若手へのサポート力」といった項目で高い評価となり、Aさん本人および営業チーム全体の中長期的な成長に貢献していることが見えてくるでしょう。
(3)行動評価
行動評価とは、別名「コンピテンシー評価」と呼ばれるものです。コンピテンシーとは、“ハイパフォーマー”と呼ばれる高い業績やパフォーマンスをあげている人材に共通する行動特性を指す概念です。いわゆる業務遂行力に近いものになります。
たとえば、営業成績トップの人に、以下の行動特性があったと仮定します。この場合、以下のコンピテンシーに近い行動を選択・実践していれば、評価が上がるイメージです。
|
|
コンピテンシーをもとに評価や教育を行うと、組織としてのビジョンや方針も浸透させやすくなるでしょう。
賞与査定の基本的な流れ
賞与は各社が独自に支給できるため、査定や計算の仕方なども基本的には各企業が自由に決定可能です。しかし、従業員のモチベーション向上などの効果を最大化するためには、多くの企業が実践する基本的な流れを意識して制度設計することが理想となります。
ここでは、賞与査定における基本的な流れと各ステップについて解説しましょう。
ステップ1:賞与査定の期間とルールを決める
まず、自社の賞与における「査定期間」や「査定基準」などを決めて就業規則に記載し、その内容を従業員に周知します。
一般的な賞与は、6ヵ月ごとに年2回の支給です。支給月を7月と12月にする場合、以下の2期間で査定を行うことが多いでしょう。具体的には、査定終了月から支給月までの3ヵ月間で査定評価を進めていくイメージです。
|
【7月支給の賞与】前年10月~3月 【12月支給の賞与】4月~9月
|
賞与ルール内で査定期間を示すことで、透明性が高く公平・公正な評価を行いやすくなります。
ステップ2:各項目を5段階で評価する
従業員と評価者における認識のズレを最小限にするためには、先ほど紹介した業績評価・能力評価・行動評価について、それぞれを以下のように5段階で評価していくのがおすすめです。
| 5 | 目標値をはるかに超えた達成をした |
| 4 | 目標値をわずかに超えた達成をした |
| 3 | 目標値を達成した |
| 2 | 目標値に対して成果がわずかに不足した |
| 1 | 目標値に大きく及ばなかった |
たとえば、営業職の業績評価では、査定期間前に売上や販売個数などの具体的目標を設定します。そして、査定期間の終了後に、成果および目標の達成度を5段階で評価していくイメージです。
評価者と被評価者の認識を合わせるためには、上記でいう「わずか」「大きく」「はるか」といった表現の意味を具体的に示すことが重要です。
たとえば、「販売個数100」という目標に対して、1~10個の不足であれば「目標値に対して成果がわずかに不足した」、11個以上の不足なら「目標値に大きく及ばなかった」などの定義づけをする必要があるでしょう。
ステップ3:総合評価ポイントから“ランク”と“評価係数”を算出する
たとえば、賞与を「基本給×〇ヵ月×評価係数」の式で計算する場合、5段階評価の数字を使って評価係数を算出します。具体的には、以下のようなイメージになります。
| ランク |
総合評価ポイント (5段階評価の合算) |
評価係数 |
| S | 21ポイント~ | 1.7 |
| A | 16~20ポイント | 1.4 |
| B | 11~15ポイント | 1.1 |
| C | 6~10ポイント | 0.8 |
| D | ~5ポイント | 0.5 |

賞与評価の透明性を高め効果を最大化する実践ポイント
賞与評価による従業員の不満や違和感を減らし、その効果を最大化するためには、いくつかのポイントを意識した制度設計が必要です。ここでは、5つのポイントを挙げて詳しく見ていきましょう。
ポイント(1)評価基準の明示化
賞与評価による従業員の不満や違和感を減らすためには、評価基準を中心とするさまざまなルール・情報を明示化して、各自が「今期は〇〇だから賞与がこの金額になったのか!」と納得できる状態にすることが大切です。
評価基準の明示化は、たとえば従業員本人が「次のボーナスは今期よりも3万円アップさせたい!」と思ったときに、査定基準およびルールから適切な目標を逆算し、達成に向けた計画および努力を行えることにもつながります。
査定基準の明示化によって「これだけ頑張れば賞与もこのぐらいアップする」というイメージを具体化することは、評価者に対する不信感や違和感の解消とあわせて、従業員のモチベーションや生産性を高める効果をもたらすでしょう。
ポイント(2)評価シートの活用
上司と部下における評価の乖離を防ぐためには、「賞与評価表」や「賞与査定表」と呼ばれる評価シートを活用するのも一つの方法です。以下のような項目で構成されたシートを使うと、客観的かつ公平・公正な評価をしやすくなります。
|
|
上司と部下の間でこうしたシートが共有されていると、違和感や不満を覚えた部下側から「この項目は自分的に頑張ったと思うのですが、なぜこの評価なのでしょうか?」といった具体的な質問をしやすくなるはずです。
職種ごとの項目や判定基準のイメージがつかみにくい場合は、厚生労働省が公開している各種資料を参考にしてもよいでしょう。
<参考>:職業能力評価基準(厚生労働省)
<参考>:職業能力評価シートについて(厚生労働省)
<参考>:判定目安表(評価ガイドライン)一覧表(厚生労働省)
また、人事評価のデジタルツールを導入済みの場合は、その仕組みを活用してもよいかもしれません。ツールによっては、上司だけでなく部下も自己評価を行い、お互いの認識が合っているかを確認できるものもあります。
ポイント(3)定量的評価と定性的評価のバランス
たとえば、営業職や販売職などの評価では、売上や販売個数などの数字(定量的な実績)が重視されがちです。しかし、評価者である上司およびメンバーが定量的な実績および評価を重視しすぎると、以下のようなケースが正当化されてしまう可能性があります。
|
(1)販売個数を伸ばしたいがために、不都合な説明を怠った (2)個人の営業活動に力を入れるために、展示会の手伝いを一切しなかった (3)営業成績1位になるために、同僚Aさんの顧客を奪った など
|
また、各メンバーが個人の定量的な実績・評価だけに固執した場合、同じチームで働く同僚は競い合う対象(ライバル)になってしまいます。その場合、たとえば「新人・若手を先輩がみんなでフォローする」とか「みんなで支え合って大きな商談を成功させる」といった協働の精神も著しく低下するかもしれません。
また、「とにかくたくさん売って、数字さえあげればやり方は問わない」という考え方に固執すると、お客様のニーズを無視した「押し売り」のようなことが多発したり、結果として顧客満足度の低下やクレームの多発が起こったりするかもしれません。
こうした悪循環を防ぐためには、たとえば「販売職としてのあり方」や「顧客ニーズのくみとり方」「他のメンバーへの思いやり」といった定性的な要素も大切にしながら、バランスを考えた評価システムを構築する必要があるでしょう。
ポイント(4)中長期的な視点を持つ
賞与評価の仕組みを設計・導入・実践するうえでは、組織と個人の成長や持続可能性を含めた中長期的な視点を持つことが重要です。
たとえば、営業部門における以下の仕事や活動は、どちらかといえば即時的な効果が得られにくいものですが、営業部門および営業職本人が中長期的に成長していくうえでは、どれも欠かせない取り組みになるでしょう。
|
|
たとえば、ある営業担当Aさんとお客様との間にトラブルが生じたとき、そのフォロワーやサポートを行うメンバー(Bさん・Cさん)は、自分の営業活動を行えなくなります。しかし、BさんとCさんの力でトラブルが早く解決すれば、SNS炎上などの予防も可能となり、会社全体への大きな貢献になるはずです。
そこで、トラブル対応中のBさんとCさんの売上が0円だったとしても、会社の中長期的な信頼や成長に大きく貢献していれば、その内容を適切に評価する仕組みが必要となります。
特に売上や販売個数などの目先の数字が優先されやすい部門では、本人および組織の中長期的な成功・成長につながる「過程」に着目した評価項目も意識的に用意する必要があるでしょう。
ポイント(5)評価面談を必ず行う
賞与評価を行ったあとは、その内容について評価者と被評価者との間で話し合ってもらう評価面談の機会を設けます。評価面談のポイントは、「評価内容の合意をとること」と「フィードバックを行うこと」の2点です。
評価内容の合意とは、上司と部下の認識のズレを最小限にする「すり合わせ」です。
たとえば、Aさんの売上が非常に悪く、部門内で最下位だったと仮定します。しかし、その背景には、「展示会の準備に力を入れていた(展示会は大成功)」とか「トラブルを抱えた後輩のサポートを続けていた」といった“上司が気づかない貢献”があるかもしれません。
こうした貢献に気づかず「売上が最下位だから賞与も最低ランクで……」といった評価を一方的に行うと、展示会準備や後輩のサポートといった貢献が無視されることになり、不満や不信感の要因になってしまうでしょう。
著しい認識のズレを解消するためには、業績などが著しく低下した理由や背景に関心を持つことが重要です。また、上司が気づかない「陰の貢献」の影響で評価が下がってしまった場合は、今回の評価見直しはもちろんのこと、評価項目および基準の再設計も必要になるかもしれません。
そして評価面談では、次につながるフィードバックも必要です。そこで重要となるのが、未来の成長や目標達成につながる意見や助言を行う『フィードフォワード』という考え方になります。フィードフォワードのポイントは、以下の2つです。
|
|
たとえば、新人Aさんの営業成績がとても悪く、賞与評価も下がってしまったと仮定します。このときにフィードフォワードの考え方を使うと、以下のような助言によってAさん本人の気持ちを前に向かせられることができるでしょう。
|
今期の売上は1,500万円で、これまでと比べてだいぶ低めだったね。でも、テレアポ営業も毎日続けているみたいだし、営業日報の内容を読む限りでは、努力の方向性として間違っていないと思うよ。来期も今期と同じ3,000万円で目標を設定してみたらどうだろうか。先輩Bさんの営業に同行するのもよいかもしれない。私からお願いしてあげようか。とりあえず今できることをコツコツ進めてみて。応援しているよ。
|
就業規則と賞与評価における法律的なポイント
賞与評価と従業員の認識に大きな乖離があり、そこへの適切な対処を行わずにいると、「不利益取り扱い」や「不当査定」として訴えを起こされる可能性もあります。そして、もし違法性が認められてしまった場合、債務不履行として損害賠償の支払いが命じられるかもしれません。
こうしたトラブルを防ぐためには、賞与評価に関する適切なルールを就業規則に記載することも重要です。ここでは、賞与評価のトラブル防止につながる就業規則の作成ポイントを紹介しましょう。
ポイント(1)就業規則と賞与に関する記載事項について
就業規則に記載する事項には、「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」の2種類があります。賞与の支給や評価に関する内容は、「相対的必要記載事項」です。相対的必要事項とは、事業場で定めをする場合に必ず記載しなければならない項目になります。
事業場で賞与の評価と支給をするのであれば、就業規則のなかに「評価方法」を記載しなければなりません。そこで評価方法や支給の仕組みが未記載の場合、従業員から訴えを起こされたときに、「ルール自体が存在しない=不当な減額・不支給である」と判断されてしまう可能性が生じるでしょう。
<参考>:就業規則を作成しましょう(厚生労働省)
ポイント(2)賞与評価と減額の限度について
就業規則に賞与の評価方法・計算方法・支給時期などが明記されている場合、賞与も給与と同じ「賃金である」と考えます。そこで注意すべきなのが、労働基準法の91条で定められた「減給の制裁」です。
減給の制裁とは、従業員の問題行為によって減給処分をするときに、減額幅に制限がかかることになります。具体的なポイントは、以下の2つです。
|
【1回の減額額】平均賃金の1日分の2分の1を超えてはならない 【減給の総額】1賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならない
<参考>:労働基準法に定められているその他の規定(厚生労働省)
|
たとえば、懲戒処分などを理由に賞与を不支給(0円)にする場合、上記の減額の制裁の限度を超える可能性が高いでしょう。このように違法性の高い減額の場合、裁判所の判断は「無効」となります。
ポイント(3)休業中の従業員に対する賞与支給について
私傷病や出産・育児・介護などの理由で休業中の従業員への対応は、就業規則内でどのように規定するかで考え方が分かれます。
まず、賞与支給日に在籍する全従業員を支給対象とする場合、休業者への支給が必要です。しかし、査定期間中の休業を欠勤として扱った場合、その日数に応じた減額は違法ではありません。
また、賞与は労働の対価としての意味があるため、査定期間中の出勤がなければ不支給にすることも可能です。就業規則内に「休業中は賞与の支給対象外」と明記してもよいでしょう。
ただし、たとえば産休・育休などの一部の休業だけを特別に不支給とするのは、違法になる可能性があります。また、査定期間中に一部出勤をしている従業員に対しては、個別の減額幅を決めて合意をとる必要があるでしょう。
ポイント(4)就業規則の周知と賞与評価
労働基準法の第106条では、就業規則を労働者に周知することを義務付けています。そのため、賞与評価に関する項目追加やルールを見直した場合は、その旨を以下のような方法で周知することが大切です。
|
(1)常時各作業場の見やすい場所に掲示する、または備え付ける (2)書面で労働者に交付する (3)磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する
<引用>:就業規則を作成しましょう(厚生労働省)
|
また、評価内容への納得感を高めるためにも、就業規則のなかで定めた評価ルールは全従業員に理解してもらう必要があるでしょう。
人事業務のアウトソーシングならラクラスへ
本記事では、賞与評価の重要性と、公正・公平な評価に不可欠な項目、評価の基本的な流れなどを解説してきました。賞与評価には多くの注意点があるため、人事部のなかでも負担に感じている方は多いのではないでしょうか。
もし人事業務における業務効率化をお考えであれば、ラクラスにお任せください。ラクラスなら、クラウドとアウトソーシングを掛け合わせた『BpaaS』により、人事のノンコア業務をアウトソースすることができコア業務に集中できるようになります。
ラクラスの特徴として、お客様のニーズに合わせたカスタマイズ対応を得意としています。他社では難色を示してしまうようなカスタマイズであっても、柔軟に対応することができます。それにより、大幅な業務効率の改善を見込むことができます。
また、セキュアな環境で運用されるのはもちろんのこと、常に情報共有をして運用状況を可視化することも心掛けています。そのため、属人化は解消されやすく「人事の課題が解決した」という声も数多くいただいております。
特に大企業を中心として760社86万人以上の受託実績がありますが、もし御社でも人事の課題を抱えており解決方法をお探しでしたら、ぜひわたしたちラクラスへご相談ください。