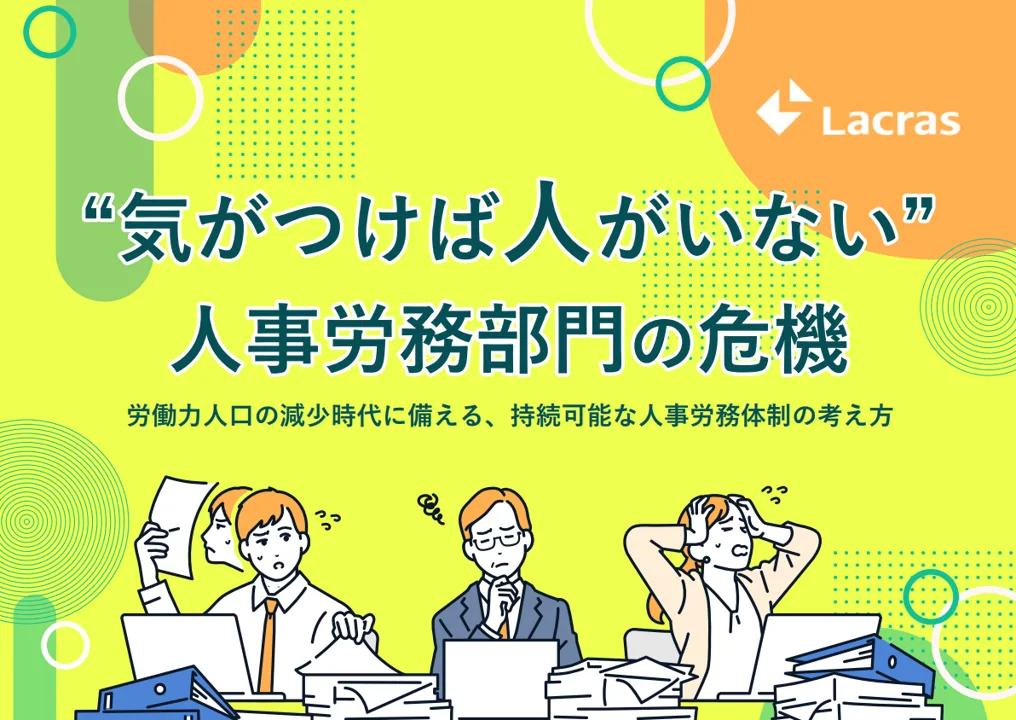職能給とは? 基本給・職務給制度との違いやメリット・デメリットを詳しく解説

本記事では、給与制度の設計で登場することが多い「基本給」や「職務給」などの概念と比較しながら、職能給がどういったものかを詳しく解説します。また、国でも導入を推進している「職務給制度」について、概要や移行時のポイントなどを紹介していきますのでぜひ参考にしてください。
人事部門が給与制度を設計するうえで一つの参考になるのが、「職能給」という考え方です。職能給は、多くの日本企業に採用されてきた制度であるものの、近年では見直しを検討する会社も増えるようになりました。
本記事では、給与制度の設計で登場することが多い「基本給」や「職務給」などの概念と比較しながら、職能給がどういったものかを詳しく解説します。記事の後半では、国でも導入を推進している「職務給制度」について、概要や移行時のポイントなどを紹介していきます。
これから自社の給与制度の見直しを図るうえで、「職能給」や「職務給」という仕組みに関心を持っている方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
職能給の基本理解
自社の現状に合った給与制度を設計するうえでは、まずは、かつての日本企業で一般的だった「職能給」などの仕組みについて基本概念を理解することが大切です。ここでは、職能給と比較されることが多い基本給や職務給などとの違いを見ながら、「職能給とは一体どういう仕組み・考え方であるのか?」を整理していきましょう。
職能給とは
職能給とは、従業員の職務遂行能力を基準として賃金を決定する給与制度(賃金制度・報酬制度)のことです。職能給をベースとする制度では、「年齢や勤続年数、経験年数が上がるにつれて、職務遂行能力が向上する」という考え方で評価を行います。
つまり、「自社で長く働くほど職務遂行能力が向上する」という考え方であり、それゆえに終身雇用および年功序列制度と相性がよい賃金体系だといえるでしょう。
なお、ここでいう職務遂行能力とは、職務に対する知識・技術・経験・資格はもちろんのこと、協調性やリーダーシップなどの適性を含めた能力全般を指すのが一般的になります。
職能給と基本給の違い
基本給は、所定の労働時間を満たすことで、毎月固定で支払われる賃金です。人事担当者の場合、採用活動や給与計算の際に“基本給”という言葉に触れたりするでしょう。(※給与計算の場合、少し意味が異なります。)
職能給は、基本給の構成要素の一つです。具体的な扱いは企業ごとに異なりますが、一般的には以下のパターンが多いでしょう。
|
【パターン(1)】職能給を基本給のなかに含めてしまう
【パターン(2)】基本給とは別の手当と位置づける
|
職能給と職務給の違い
職務給は、職能給と混同されやすい言葉です。職務給とは、従業員の業務内容や業績をもとに賃金を決める制度になります。
たとえば、営業部門のAさんが“難易度の高い商材”を取り扱うことになったと仮定します。そのAさんが前年比150%の売上を達成した場合、「難易度の高い仕事」と「高い業績」について評価を受け、賃金が上がるようなイメージでしょう。
職務給と職能給の大きな違いは、職務給の場合、仮にこのAさんが今年の新入社員であったとしても、「難易度の高い仕事」や「責任が大きい仕事」で「高い業績」を出せば、高い賃金につながりやすい点です。
これは、年齢・経験年数・勤続年数を重視する職能給との大きな違いになります。
職務給は、どちらかといえば「成果主義」に適した賃金体系であり、終身雇用&年功序列のもとで浸透した職能給とは大きく異なる考え方といえます。
なお、欧米では成果主義で人事評価を行う企業が多い特徴から、成果主義との相性が良い職務給について「欧米型の職務給」と言われたりします。これに対して職能給は日本企業の三種の神器だった終身雇用や年功序列との相性が良いことから「日本型の職能給」と言われることもあるようです。
職能給の特徴(決まり方とボーナスへの影響)
適切な職能給制度を設計するうえでは、「何を参考にして昇給・降給が行われるのか?」という基本的な仕組みを理解しておくことが大切です。また、報酬制度全体を見直すのであれば、賞与(ボーナス)と職能給の関係についても理解を深めておいたほうがよいでしょう。
ここでは、職能給の決まり方・上がり方・下がり方、賞与(ボーナス)との関係について詳しく見ていきます。
職能給の決まり方
職能給は、企業が独自に作成する「職能給表」や「号俸表」の内容をもとに決まることが多いです。そして職能給表は、以下2つの軸で決まるのが一般的でしょう。
| 号俸 | 等級 | |
| 概要 | 給与を決める単位や指標のようなもの。 本来は国家公務員の給与決定で使われていた。 |
能力や職務内容による序列。 |
| 基準 | 勤続年数や査定評価 など | 役職 など |
号俸では、新卒~定年までの期間を対象とするため、等級と比べて細かくたくさんの号が設けられる傾向があります。
なお、総務省では号俸表のサンプルを公開していますので、興味がある方はぜひチェックするとよいでしょう。
<参考>:賃金表の種類と正しい運用の仕方(総務省)
職能給の上がり方と下がり方
厳密な給与の上がり方・下がり方などの仕組みは、各企業が独自に決めるものです。しかし、職能給の場合は号俸と等級をもとに決定するため、一般的には以下のような状態になったときに基本給(職能給)が上がることが多いでしょう。
|
|
これに対して、自分の等級の役割を担えず基準をクリアできなかったり、人事評価の結果が悪く号俸が下がったりする場合、職能給もダウンする可能性が高まります。
職能給と賞与(ボーナス)の関係
職能給とボーナスを連動させるかどうかは、各企業における賞与制度の影響を受ける部分です。
たとえば、職能給=基本給であり、賞与が「基本給の◯ヵ月分+インセンティブ」のような基本給連動型である場合、職能給が従業員のボーナスに大きく影響するでしょう。一方で、賞与を決算連動型や業績連動型で支給する場合、職能給の影響はあまり受けないかもしれません。
いずれにせよ、賞与制度を設計するときには、職能給との関係性も含めて従業員から見てわかりやすい仕組みを考えたうえで、就業規則のなかで具体的に示す必要があります。
なお、賞与評価の考え方やボーナスの一般的な計算方法(基本給連動型・業績連動型・決算連動型)については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてチェックしてみてください。
【関連記事】賞与評価の重要性とは?|不当査定を防ぐための基準や実践的手法、就業規則のポイントを解説
【関連記事】賞与(ボーナス)の計算方法とは?平均支給額や税金・社会保険料計算の注意点も解説
職能給における企業と従業員のメリット
適切な給与制度を設計・運用するためには、職能給制度のメリット・デメリットを理解したうえで、「自社に合う仕組みかどうか?」を考えることも重要です。ここでは、職能給との相性が良い終身雇用・年功序列の仕組みのなかで、職能給制度を導入・運用するメリットとデメリットを見ていきましょう。
職能給制度で得られる企業側のメリット
職能給制度の導入・運用によって企業が得られる効果・メリットは、主に以下の2つです。
|
|
終身雇用&年功序列の仕組みと職能給制度を組み合わせた場合、従業員の年齢が上がり、社歴・経験年数が長くなることで賃金をアップしやすくなります。こうしたシステムの場合、賃金や等級をあげるために、定年頃まで長く働く前提で入社する人材が増えやすくなるでしょう。
ちなみに終身雇用&年功序列の組織では、ジョブローテーションが行われることが多いです。ジョブローテーションとは、定期的に職種や部署変更を行うことで従業員のスキル開発および人材育成をしていく仕組みです。
たとえば、新卒1年目~3年目までエンジニアをやっていた人材が、4年目から営業部になり、7年目からマーケティング部に移るなどのイメージでしょうか。
このようなジョブローテーションの場合、部署や職種の変更にともない仕事内容および難易度も変わることになりますが、そこで「職能給制度」を導入していれば、職種・部署変更後の仕事がどのような内容でも給料への影響は生じにくいでしょう。
職能給制度で得られる従業員側のメリット
終身雇用&年功序列と職能給制度の環境で働く従業員には、以下の2つのメリットが得られやすいでしょう。
|
|
先述のジョブローテーションのところで解説したとおり、職能給制度のなかで働くと、賃金を決めるうえで仕事内容・難易度・業績などが成果主義ほど重視されなくなります。
極端なことをいえば、さまざまな要因から今期の業績がふるわず残念な結果になったとしても、社歴が長く等級も高ければ、業績の影響をあまり受けることなく、それなりに高い賃金が得られることになるはずです。
また、職能給の場合、基本給や手当の金額は職能給表や号俸表の数字をもとに決まっていくため、たとえば「1年目の基本給は25万円、3年目は27万円、5年目は30万円……」というように、ある程度の予測をしやすい特徴があります。
従業員が職能給制度の会社で働くと、給与の変動も生じにくいことから、「マイホーム購入」や「起業」といった何らかの目的に向けた資金面の準備もしやすくなるでしょう。
増加する職能給制度のデメリットと問題点
近年のビジネス環境では、「日本型」としてこの国に長く浸透してきた職能給制度に、さまざまなデメリットやリスクが生じやすくなっています。
ここでは、会社と従業員に生じやすいデメリットと問題点を総合的に見ていきましょう。
問題点(1)
人材育成やモチベーション向上との相性が悪い
職能給制度は、人材の成長やモチベーション向上における起爆剤としての効果が低い仕組みです。
その理由は、同じ会社で長く働き社歴と等級を上げることで賃金アップするのが原則であり、成果主義では当たり前とされる「高い業績」「難易度の高い仕事」への挑戦や、それをなし得るための自己成長などは成果主義ほど求められないからです。
また、終身雇用&年功序列×職能給制度の環境では、20年や30年といった社歴でそれなりの賃金がもらえるようになっても、それと本人の成長度が比例しているとは限りません。
たとえば、社歴が長く賃金が高いのにも関わらずあまり業績をあげられない場合、「低賃金の若手より部内貢献度が低い」や「市場価値が低いから転職も難しい」といった状態から、本人にも劣等感が生じやすくなるでしょう。
劣等感を解消できないまま長く会社にとどまっている場合、やる気やモチベーションも損なわれやすくなってしまいます。
問題点(2)人件費の負担が増えやすい
年功序列×職能給制度の場合、会社では以下のように社歴が長い一方であまり良い業績をあげられない従業員にも、多くの賃金を支払わざるを得なくなります。
|
【Aさん】 【Bさん】 【Cさん】
|
職能給制度のもとで上記のような人材に多くの賃金を払い続けていると、資金面で余裕がなくなり、本当に高い業績をあげる従業員への適切な評価・報酬支払いが難しくなってしまいます。
問題点(3)スペシャリストの育成が難しい
終身雇用&年功序列×職能給制度は、どちらかといえばジョブローテーションのなかで従業員にさまざまな経験をさせて、幅広いスキルや知識を持つ「ゼネラリスト」を育てるための仕組みです。
ただ、たとえば「高度なIT技術を必要とするDXプロジェクトを実施することになり、社内でスペシャリスト育成を始めることになった」としても、非常に難しくなるでしょう。
理由としては、社歴や年齢×等級で報酬が決まり、高度なスキルや業績があまり評価されない仕組みのなかでは、スペシャリストを目指す人材に適切な動機づけおよび評価を行いづらいからです。
問題点(4)
優秀な若手やスペシャリスト人材が定着しない
終身雇用&年功序列×職能給制度の仕組みは、会社に多くの利益をもたらす以下のような人材に不満や不公平感をもたらしやすくなります。
|
|
その結果として生じやすくなるのが、優秀な人材のモチベーション低下や離職です。
優秀な若手やスペシャリスト人材の早期離職が多い場合、年功序列や職能給制度による理不尽な環境が離職要因になっている可能性もあるでしょう。

職能給制度の導入ステップ
職能給などの給与制度は、「導入さえすればOK」というものではありません。新しい制度の費用対効果を高めるためには、適切な流れで導入・設計・運用をしていく必要があります。そのステップを順に見ていきましょう。
ステップ(1)号俸表(職能給表)を作成する
職能給制度を設計するうえで重要になるのが、号俸と等級です。
号俸は、勤続年数や年齢、評価などで割り当てられた「番号(号)」を指標として基本給を決める考え方で、「号」の考え方で設計されたものを「号俸表」と呼びます。
総務省の資料では、号俸表について以下のように解説しています。
|
号俸表というのは、等級(所)と号(番地)ごとにそれぞれ基準額を
誰でもが職能資格等級に格付けられ、その時点で1号(初号)の金額以上の
号俸表は、1年1号ずつの昇号ですから人事考課などの査定によって
<引用>:賃金表の種類と正しい運用の仕方(総務省)
|
および等級の中身などは企業ごとに設計可能ですが、一般的には、総務省が公開している以下の一覧のような号俸表をつくるイメージになるでしょう。

<引用>:賃金表の種類と正しい運用の仕方(総務省)
なお、職能給制度で用いられる賃金制度は、上記の号俸表のほかにも「段階号俸表」や「昇給表」「複数賃率表」といったさまざまな種類があります。総務省が公開している情報を参照しながら、自社に合う職能給表を設計してみてください。
ステップ(2)昇格要件を決定する
職能給表が完成したら、次は等級が上がるための昇格要件を考えます。
具体的な要素としては各組織が大事にする価値観・職種・部門・仕事内容などの影響を受けますが、一般的には以下のような項目の基準を満たし終わったときに昇給できることが多いでしょう。
|
(1)技能 (2)知識 (3)経験(習熟) (4)責任 (5)資格 など
|
たとえば、具体化された上記(1)~(5)の内容について『それぞれが「3点以上」かつ「合計20点以上」になったときに5等級に昇格できる』といったイメージです。
公平・公正な制度設計では、昇格要件および基準を具体的にわかりやすくする必要があります。たとえば、(2)の“知識”については、「商品知識の社内テストで毎週90点以上を獲得している」のように、評価者と被評価者の両方が納得できる書き方をする必要があるでしょう。
ステップ(3)各等級の具体的な職能給を決定する
続いて、各号・各等級の職能給(金額)を具体的に決めていきます。
給与制度をうまく活用して優秀な人材の獲得や定着につなげるためには、市場相場に合った賃金体系にする必要があるでしょう。
ステップ(4)就業規則に記載する
労使間トラブルを防ぐためには、賃金・等級・人事評価に関する基本ルールを就業規則に記載し、労働基準監督署に届け出をしたうえで従業員に周知する必要があります。
ここでのポイントは、「賃金や等級の決まり方」を明示することに加えて、「降給・降級」の基準についてもきちんと言及しておく点です。たとえば、「各等級の基準を◯ヵ月連続満たせなかった場合、一部の例外を除き降級することがある。一部の例外とは……」のように記載しておくと、透明性の高い制度運用を行いやすくなるでしょう。
ステップ(5)従業員教育をする
従業員に対しては、就業規則の記載内容を周知するのはもちろんのこと、「自社ではどういった仕組みで昇給・昇格するのか?」などをしっかり伝えることが大切です。
職能給制度の場合、号俸表にもとづき賃金を決めていくため、ほかの仕組みと比べて従業員が混乱するような複雑性は少ないでしょう。しかし、万が一の労使間トラブルを防ぐためにも「どういったときに昇給し、どういったときに降給するのか?」を事前に共有しておくことが重要になります。
ステップ(6)運用とブラッシュアップを繰り返す
従業員への周知を終えたら、いよいよ新しい制度の運用に入ります。
人事評価・等級・給与制度の“運用”におけるポイントは、定期的なアンケートなどを通して従業員の声に耳を傾け、評価基準や制度全体のブラッシュアップを図っていく必要がある点です。
特に職能給制度の場合、優秀な若手や中途のスペシャリスト人材などから不満の声が上がりやすい傾向があります。こうした声に耳を傾け、不公平感や違和感を最小限にしていくことは、自社の人材マネジメント全体の悪循環を好循環に変えるうえでも大切なことでしょう。
企業の給与体系における今後の展望
これまで解説してきたとおり、終身雇用&年功序列制度と職能給制度を組み合わせたシステムは、「日本型」と呼ばれるほど長く浸透していました。しかし近年では、ビジネス環境に以下のような変化が生じてきています。
|
|
そのようななかで、職能給制度が優秀な人材の離職要因になるリスクが生じやすくなっていますので、自社の業績に貢献してくれる人材の定着・活躍を促すためには、終身雇用&年功序列の環境で当たり前とされていた仕組みや風土を変えることが重要です。
社歴が長い従業員に多くの賃金が支払われる“職能給”を軸とした賃金制度についても、時代の変化にともなって大転換が求められているのです。
近年注目される職務給制度とは
近年のビジネス環境では、たとえばコロナショックや原材料費・燃料費の高騰、生成AIの急速な普及などといった変化が次から次へと発生し、ひとつの仕事で計画的に成果を出し続けることの難易度が上がっています。
また、たとえばコロナ禍のように緊急事態宣言が発令されてしまうと、せっかく時間をかけて練り上げてきた計画やスケジュールがすべて水の泡になったりするかもしれません。
こうしたなかで重要になるのは、適切な評価と報酬などの付与を通じて従業員のモチベーションを維持・向上させる仕組みです。
そこで注目されているのが、厚生労働省も推奨している「職務給」です。
ここでは、現代のビジネス環境にマッチした賃金制度の設計を模索する方のために、厚生労働省の資料にもとづいて、「“職務給制度”の概要」や「従来制度から職務給制度に移行する際の注意点」などを解説します。
<参考>:職務給の導入に向けた手引き|日本における職務給の現状を理解しよう(厚生労働省)
職務給とは
厚生労働省では、職務給を「基本給における『役割・職務の重要度』に基づいて決定される部分」ととらえています。
<参考>:職務給(厚生労働省)
たとえば、営業部門のリーダーであれば「メンバーをまとめる役割」や「個人の業績を上げるサポートをする役割」「部門全体の営業成績をあげる重要度」などが基準になってくるはずです。
職務給の特徴は、これまで紹介してきた職能給における「号俸×等級」をベースとする考え方とは大きく異なるものです。職務給をベースとする給与制度では、「あの人は社歴が長いから賃金も高い」といった号俸に基づく考え方もなくなります。
<参考>:職務給の導入に向けた手引き|日本における職務給の現状を理解しよう(厚生労働省)
職能給から職務給に変えるメリットとは
従来の職能給から職務給へと変える最大の利点は、企業が各従業員に対して求める役割や業績が明確になる点です。それはつまり、従業員側も会社が自分に求める役割や業績を理解したうえで、それらをクリアするための計画や取り組みを実施しやすくなることを意味します。
さらにいえば、「いまの役職(等級)でこれだけの成果を出せば、賃金がこのぐらい上がるだろう」という予測もつきやすくなります。
自分の頑張りで目標を達成して予測どおりに賃金が上がると、成果を自らコントロールできることで仕事に面白さが生まれ、結果としてモチベーションや生産性の向上にもつながりやすくなるでしょう。
また職務給は、会社が求める役割・業績をきちんとクリアできた人を適切に評価できる仕組みでもあります。
職務給制度が適切かつ具体的な基準のなかで運用していくと、職能給制度のもとで優秀な若手人材に起こりやすかった不公平感や違和感も生じにくくなるはずです。
そうなると、優秀な若手人材や中途入社したスペシャリスト人材などが、社歴が短いなかでも自分の実力を適切に認めてもらうことになり、しっかりと報酬につなげていけることになるでしょう。
職能給から職務給制度に変えた場合の
デメリットとは
職能給から職務給制度に変えるなかで起こるのが、評価軸が大きく変わることで、以下のような人材の評価や賃金が著しく下がる可能性がある点です。
|
|
これらの従業員に共通するのは、「社歴が長い一方で、会社が求める業績を出せていない」ということです。
従来の職能給であれば社歴・等級が高ければそれなりの賃金をもらえる傾向がありましたが、そこで職務給制度を導入すると、「等級に見合った業績をあげられないと、社歴が長くても高い報酬は支給できない」という考え方への大変革が起こることになります。
また、職務給制度を導入すると、「社歴が短い人でも成果を出せば賃金が上がる仕組み」が構築されることになります。そのため、優秀な若手や中途人材の賃金がアップした場合、上記のような人材の不満は増大しやすくなるかもしれません。
その場合、従業員のモチベーションやパフォーマンスを下げないための配慮が求められるでしょう。
職能給から職務給制度への移行の流れ
先述のとおり、賃金制度を大きく変えた場合、一部の従業員に大きな不利益が及ぶ可能性があります。つまり、一部の従業員にとって労働条件の大幅な変更になる可能性があるというわけです。
そこで従業員側が変更内容に納得できず訴訟を起こした場合に、裁判所から「会社側からの一方的な不利益変更である」と認められると、変更が無効になるとともに損害賠償の支払いなどが発生してしまう可能性もあります。
こうした問題を防ぐためには、以下のステップで適切に移行手続きを進めていく必要があります。
ステップ(1)
制度変更後の賃金をシミュレーションする
最初に、職務給制度を導入することで各従業員の給与にどのくらいの影響が出るのかを確認します。
たとえば、これまで職能給制度のなかで社歴が長いことを理由にそれなりの賃金をもらっていた従業員がいたとします。その従業員が新制度では大幅な給与ダウンが生じる可能性がある場合、導入後の金額が「一般的な給与水準」や「同業他社の相場」の範囲内におさまるかどうかなどのシミュレーションも必要でしょう。
ステップ(2)
新しい制度(案)を従業員に説明する
次に行うのは、場合によっては給与ダウンになることもある新制度について、従業員から理解を得るための説明です。
導入目的や「業績が低い場合に賃金が下がる可能性がある」などのネガティブな話はもちろんのこと、「こういう工夫や取り組みをすることで賃金が大幅に上がる可能性もある」などのポジティブな対策も示しましょう。
一部の従業員から「納得できない」「受け入れられない」などの声があった場合は、評価基準などを調整しながら、個別に話をすることも必要です。
ステップ(3)すべての従業員から同意書をもらう
労働組合がある場合、会社と組合で労働協約を締結します。ただし、新制度の導入による不利益で労使間トラブルが起こるリスクを防ぐためには、全従業員から個別の同意書をもらえることが望ましいでしょう。
ステップ(4)就業規則を新しい内容に変更する
新制度の内容は就業規則にも記載します。
職能給制度の導入で結果として労働条件が変わることになり、その内容を就業規則で示す場合は、以下の2点に注意する必要があります。
|
(1)内容が合理的であること (2)労働者に周知させること
<引用>:労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)に関する法令・ルール(厚生労働省)
|
ステップ(5)新制度の振り返りと見直しをする
一定期間の運用を終えたら、全従業員にアンケートを行い、良かった点・悪かった点・早期に改善すべき点などを洗い出します。また、新制度によって多くの不満が出る可能性がある場合は、相談窓口を設置してもよいかもしれません。
人事担当者は不満を訴える従業員の声にも耳を傾け、新制度のなかで可能な限り賃金を上げるための「情報提供」や「サポート」などをおこなっていく必要があるでしょう。
人事労務のアウトソーシングならラクラスへ
本記事では、給与制度の設計で登場することが多い「基本給」や「職務給」などの概念と比較しながら、職能給がどういったものかを詳しく解説してきました。自社の給与制度の見直しを図るうえでは、多くのやるべきことや注意点があるため、人事部のなかでも負担に感じている方は多いのではないでしょうか。
もし人事労務における業務効率化をお考えであれば、ラクラスにお任せください。ラクラスなら、クラウドとアウトソーシングを掛け合わせた『BpaaS』により、人事のノンコア業務をアウトソースすることができコア業務に集中できるようになります。
ラクラスの特徴として、お客様のニーズに合わせたカスタマイズ対応を得意としています。他社では難色を示してしまうようなカスタマイズであっても、柔軟に対応することができます。それにより、大幅な業務効率の改善を見込むことができます。
また、セキュアな環境で運用されるのはもちろんのこと、常に情報共有をして運用状況を可視化することも心掛けています。そのため、属人化は解消されやすく「人事の課題が解決した」という声も数多くいただいております。
特に大企業を中心として760社86万人以上の受託実績がありますが、もし御社でも人事の課題を抱えており解決方法をお探しでしたら、ぜひわたしたちラクラスへご相談ください。