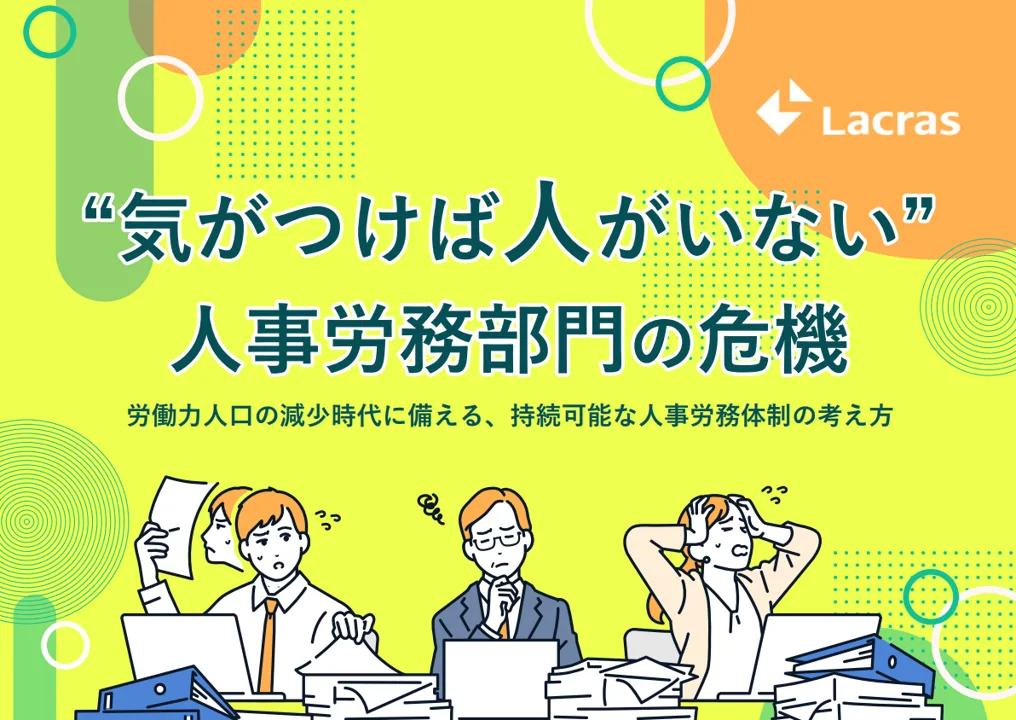オンボーディングとは?
実施のメリットと注意点、導入ステップや成功事例もご紹介

本記事ではオンボーディングの定義や必要性、メリットなどを解説します。また、オンボーディングの導入ステップや、あると便利なITツール、目標設定および効果測定に用いるオンボーディングKPIも紹介していきます。これからオンボーディングの導入を検討している人事のご担当者様は、ぜひ本記事を参考にしてください。
新人・若手の早期離職が増えるなかで注目されているのが、“オンボーディング”と呼ばれる取り組みです。各社のオンボーディング支援制度に盛り込める施策にはさまざまな種類があり、それらの効果を最大化するためには、適切な流れで制度設計をする必要があります。
そこで本記事の前半ではオンボーディングの定義や必要性、メリットなどを解説します。後半では、実践編としてオンボーディングの導入ステップやあると便利なITツール、目標設定および効果測定に用いるオンボーディングKPIを紹介していきます。
新入社員の定着率を高めるためにオンボーディング施策に関心を持っている方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
オンボーディングの定義と重要性
適切なオンボーディング支援制度を設計・導入・実施し、その効果を最大化するためには、「そもそもオンボーディングとはなにか?」という定義から理解していくことが重要です。
ここでは、“オンボーディング”という用語の意味と目的、必要性を確認していきましょう。
オンボーディングとはなにか
オンボーディングとは、新入社員を部署に馴染ませ、早期戦力化するためのプロセスです。
たとえば、高度なスキルを持つ優秀な人材を採用しても、同じ部署の先輩と親しくなることができず孤立したままでは、業務習得や自分の知見を発揮することも難しいでしょう。それはつまり、どんなに優秀な人材でも組織に馴染むことができなければ「宝の持ち腐れ」になってしまう可能性があることを意味します。
そこで行われるのが「オンボーディング」です。オンボーディングは、さまざまな施策を通して入社・配属された新しいメンバーがより早く組織に馴染み、大事な戦力として活躍できるためのプロセスをサポートする仕組みの総称です。この考えにもとづく一連の取り組みを、“オンボーディング支援制度”と呼んだりもします。
なお、オンボーディングは、“船や飛行機に乗り込む”という意味を持つ「on-board」が語源となっています。
オンボーディングの目的と必要性
オンボーディングの目的は、以下の2つです。
|
【組織社会化】新しく入った個人に、早く組織に馴染んでもらうこと 【早期戦力化】新しく入った個人に、早く組織で活躍してもらうこと
|
近年のビジネス環境では、終身雇用制度が崩壊し転職が一般化するなかで、新人の早期離職が起こりやすくなっています。
こうしたなかでオンボーディングは、新人を「早く組織に馴染ませること」と「早く活躍してもらうこと」の2つを支える特徴から、新卒採用における内定者フォローと同様にその重要性が増しているわけです。
逆にいえば、古い組織にありがちな「仕事は見て覚えろ」とか「新人は自ら積極的に先輩とコミュニケーションを図りなさい」といった上から目線のスタンスでは、新卒・若手の早期離職を防ぎづらい時代になっているのです。
オンボーディングとOJT・Off-JTの違い
オンボーディングと同様に新人の内定後に行うべきものに、OJT(On-the-Job Training)Off-JT(Off-the-Job Training)があります。
OJTとOff-JTの概要は、以下のとおりです。
|
【OJT】 現場で行う「職場内研修」のこと。
【Off-JT】 現場を離れて学ぶ「集合研修」のようなもの。
|
オンボーディングとOJT・Off-JTの大きな違いは、OJTとOff-JTが「知識・スキルの習得」に重きを置いた指導・サポートをするのに対して、オンボーディングは「知識・スキルの習得+組織に馴染むこと+早く戦力になること」まで広く支援していく点です。
たとえば、ある新人Aさんに対して、先輩Bさんが製品の組み立て方などを教える研修を実施すると仮定します。このケースで新人Aさんについて「組織に馴染ませること」と「早く独り立ちさせること」の2つを達成するためには、現場OJTで知識と技術を教えるだけでは足りません。
「組織社会化」と「早期戦力化」の両方を実現するためには、OJTによる知識と技術の習得に加えて、以下のようなオンボーディング施策も実施する必要があるでしょう。
(下記はオンボーディング施策の一例です)
|
【OJT】
【オンボーディング】
|
たとえば、「歓迎ランチ会」や毎週の「1on1」、「ブラザーシスター制度」といった仕組みは、新人Aさんと先輩たちにより深く充実したコミュニケーションをもたらす可能性が高いでしょう。
こうした場所で「今週はどうだった?」「なにか困っていることはある?」などのヒアリングが行われると、新人Aさんは言語化によるリフレクションをすることで、経験から学びを得て自己成長につなげる、いわゆる「コルブの経験学習モデル」を回しやすくなるはずです。
|
【コルブの経験学習モデル】
|
また、新人Aさんを早期戦力化するためには、直接的な指導・サポートを行うOJT担当Bさんを支える仕組みも必要です。オンボーディングでは「新人」はもちろんのこと、「新人を支えるOJT担当者および現場のメンバー」に着目した支援も行うことで、受け入れ部署の負担も解消していくのです。
こうした考え方も、対象者本人だけに着目するOJTやOff-JTとの大きな違いになるでしょう。
オンボーディングのメリット
オンボーディングで導入する仕組みは、企業や人材ごとに異なります。そのため、得られる効果やメリットも、導入施策の影響を受けて変わってきます。ここでは、正しい仕組みを導入できた場合に期待できる主なメリットを見ていきましょう。
オンボーディングによる「新入社員」のメリット
オンボーディングの仕組みがしっかりと運用されている会社に入社する新人のメリットは、オンボーディングの目的である「スムーズに馴染めて、早く戦力になれること」です。
たとえば、新卒社員と先輩社員の歳がかなり離れた組織の場合、新人には「話しかけづらい」とか「輪に入っても話が合わない」などの悩みやストレスが生じがちです。しかしそこに、新人歓迎のランチ会をはじめとする相互理解をするためのオンボーディング施策があると、新人と先輩の間に大きな年齢差があってもスムーズに距離を縮めやすくなるはずです。
また、早期の戦力化は、新入社員に仕事の面白さや“やりがい”をもたらすきっかけになります。
そこでたとえば「来月から新宿エリアのお客さんのフォローをお願いね!」などと大きな役割を与えられると、ワークエンゲージメントが向上して好循環が生まれやすくなるかもしれません。
そうなると早期離職する新人に起こりがちな「仕事がつまらない」や「こんなはずじゃなかった」などの悩みとは縁遠くなるはずです。
なお、ワークエンゲージメントについては以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひチェックしてみてください。
【関連記事】従業員満足度(ES)と従業員エンゲージメントの違いとは?高めるメリットや方法も解説
オンボーディングによる受け入れ部署のメリット
適切なオンボーディングを導入・実施すると、受け入れ部署だけでなくOJT担当の先輩、上司の負担もかなり減ります。従来は新人のサポートや育成が現場に丸投げされていたために、以下のような問題が起こりやすくなっていました。
|
|
しかし、人事部門が主導して「新人が組織に馴染み、早く戦力化するための仕組み」を設計・運用することで、これらの問題は解決しやすくなります。
人事部門が行うフォロー範囲は企業ごとに異なりますが、たとえば、現場に効果的なOJTを進めるノウハウがなく、新人の戦力化がスムーズに進まない場合、人事部門から「新人向けのマニュアル作成をする」「目標管理や戦力化までのロードマップの設計資料を提供する」といったことへの支援・提案ができるかもしれません。
また、そもそも現場が人手不足で新人を育てる余裕がない場合、人事部門と現場管理職との間で話し合いをしながら、新人を戦力化できる体制の整備を進めていくことも選択肢に入ってくるでしょう。
オンボーディングの仕組みを整備すると、新人の現場配属にともなう一方的な丸投げが解消されることで、人事部門と現場が協力し合いながら「人材育成の最適解」を目指しやすくなるのです。
オンボーディングによる会社全体のメリット
適切なオンボーディングを導入・実施することによって新入社員の組織社会化と早期戦力化が進むと、会社側には以下のように多くのメリットが生まれやすくなります。
|
(1)離職率の低下(定着率の上昇) (2)従業員のモチベーションやパフォーマンスの向上 (3)組織および個人の生産性の向上 (4)従業員エンゲージメントの向上 (5)採用・育成コストの減少
|
企業が中長期的なビジョン・目標を達成するうえでは、優秀な人材の力が不可欠になります。そこでオンボーディングの取り組みを行うと、上記の5つの効果が得られることで中長期的な人員計画も立てやすくなり、結果として会社が求めるゴールに到達しやすくなるでしょう。
オンボーディング支援制度の導入方法とは
オンボーディング支援の仕組みは、「導入さえすればOK」というものではありません。先述したメリットを最大化するためには、自社の課題解決につながるオンボーディング支援制度を適切な流れで設計・運用していく必要があります。
また、オンボーディングの場合、社会人未経験の「新卒社員」と経験豊富な「中途社員」では実施すべき施策も変わってきます。人事担当者は適切なオンボーディング施策を設計するためのポイントを理解したうえで、各人材や部門に合った施策を設計していく必要があるでしょう。
ここでは、オンボーディング支援制度の基本的な導入方法について見ていきます。
導入方法(1)
オンボーディングのゴールを設定する
最初に設定すべきことは、これから受け入れる新人に「半年~1年後、どういう姿・状態になってほしいか?」というゴールです。
この“ゴール”については、受け入れ部署や新人の属性(新卒中途・経験など)によっても変わります。
最初は下記のように抽象的なイメージで構わないでしょう。
|
|
ただし、新入社員を実際に受け入れる少し前の時期から、OJT担当が上記の内容を具体的な目標に落とし込み、新人に合意をしてもらったうえで実際の受け入れや研修に入っていく必要があります。
導入方法(2)
ゴール達成に必要な施策やプロセスを書き出す
次に、(1)で設定したゴールを達成するために、具体的に必要な施策を考えていきます。効果的なオンボーディング制度の設計では、基本的に以下の5つの軸にぶら下げる形で施策を検討するとよいでしょう。
|
【受け入れ準備】 【顔合わせ】 【組織の理解】 【成果の創出】 【ケアとレビュー】
|
導入方法(3)「誰が何をどうするのか?」を考える
次は、役割分担とやり方を決めていきます。具体的には(2)で書き出したプロセスについて、「誰が何をどうするのか?」を考えましょう。
たとえば、以下のようなイメージです。
|
【既存社員への紹介】 営業部門で歓迎ランチ会を4月30日に開催する。
【マニュアルの準備】 2026年4月入社(5月配属)の新人用として、現場の業務マニュアルを作成する。
|
導入方法(4)オンボーディング施策の実施
新入社員が配属されたら、(1)~(3)のステップで決めたオンボーディング施策を実施していきます。オンボーディングの効果を高めるうえで大切なことは、各施策を実施するメンバーおよび新人自身の状況に合わせてカスタマイズしていく点です。
たとえば、システム開発部門で大きなトラブルがあり、OJT担当である先輩や上司の負担が増大している場合、新人自身にその旨を説明したうえで、OJTおよび戦力化までのロードマップを少し変更するのも一つの方法です。
また、新人の理解力や適性面に問題があり、スケジュールどおりの業務習得が難しい場合も、新入社員のモチベーションを下げないフォローをしながら「いまできる最適な方法」で教育およびサポートをしていく必要があるでしょう。
導入方法(5)
オンボーディング施策の評価と見直し
最初に設定した半年もしくは1年の期間が過ぎたら、オンボーディングの成功要因と失敗要因の両方を洗い出し、改善につなげるサイクルを回していくことになります。
たとえば、現場での「歓迎ランチ会」だけでは新人の「組織社会化」が進まなかった場合、「ブラザーシスター制度」を取り入れたり、OJT担当者である先輩との出張を増やしたりするなどの施策を加えたほうがよいかもしれません。
一方で、特定部署で行った施策によって「組織社会化」と「早期戦力化」の両方がうまく進んだ場合は、ほかの部門や中途採用への応用も検討できるでしょう。
いずれにせよ、オンボーディング支援制度の効果を最大化するためには、実施後の評価と見直しを繰り返し、「自社に最適なオンボーディングの基本プランとはどういうものなのか?」を追い求めることが重要になります。
オンボーディング運用に必要な人的資源と物的資源
オンボーディング施策を実施するうえで必要となるのが、「2つの人的資源」と「3つの物的資源」です。前述の導入方法で施策を策定するうえでは、「必要なリソースを確保できるのか?」という視点も必要となるわけでます。
ここでは、各資源の概要を見ていきましょう。
2つの人的資源
オンボーディングに必要な人的資源は、「メンターおよびトレーナー」と「上司・同僚」です。それぞれには、以下の役割が求められます。
|
【メンター】
【トレーナー】
【上司】
【同僚】
|
3つの物的資源
オンボーディングに必要な物的資源は、「教材・マニュアル」「設備・スペース」「ITリソース」です。行える施策の範囲は、以下の資源をどこまで用意できるかで変わってくるでしょう。
|
【教材・マニュアル】
【設備・スペース】
【ITリソース】
|

オンボーディングを成功に導くITツール
オンボーディング支援制度を成功させるためには、経営層・人事部門・現場の管理職・OJT担当といった幅広い部門のメンバーが、「受け入れ準備」「顔合わせ」「成果の創出」「ケア・レビュー」といった非常に多くのタスクを実施する必要があります。
その過程で生じやすいのが、管理やコミュニケーションの問題です。
特に最近は、リモートワークの導入企業が増えるなかで、従来のように「先輩と新人が隣の席で仲良くなる」とか「同じオフィス内で仕事のやり方を指導する」といった直接的な関わり方ができないケースが多くなっています。
また、人事部門と新人の配属部署が物理的に離れている場合、どのようなOJTが行われているのか見えないため、適切なフォローや進捗管理などをすることが難しいかもしれません。
こうした時代に注目されているのが、オンボーディングを成功に導くさまざまなITツールです。
オンボーディングのITツールとは
オンボーディングのITツールとは、オンボーディングにおける以下のようなさまざまな課題を解決してくれるアプリやソフトウェアの総称です。
|
|
これらのツールの特徴は、製品ごとに機能が大きく異なる点です。そのため、たとえば「ナレッジ管理とエンゲージメント管理を効率化したい」といった場合、複数のツールを導入することも選択肢に入ってくるでしょう。
オンボーディングITツールの選び方
オンボーディングの効率化に向けてITツールを導入する場合、最初に行うべき作業は「自社におけるオンボーディング課題の明確化」です。それはつまり、「ITツールを導入して、どういう問題を解決したいのか?」について言語化する作業になります。
たとえば、自社の共通言語や沿革、業務マニュアルなどを一元管理したい場合、ナレッジ管理に特化したオンボーディングITツールを導入してもよいでしょう。また、新人との1on1の内容を目標管理に活かしたい場合は、コミュニケーションや進捗管理、フィードバックに強いITツールを選ぶと良いかもしれません。
いずれにせよITツールの費用対効果を高めるためには、「自社の課題をどのように解決できるのか?」という視点から選定作業を進める必要があります。
また、オンボーディングITツールの場合、種類によっては新人・現場のOJT担当者・管理職・人事部門など幅広い人が使用する可能性があります。そこで注意したいのが、操作性や運用面で支障がないかどうかです。
たとえば、PCやタブレット端末などの操作をあまり行わない部門でITツールを導入する場合、無料のトライアル版などを使ってもらい、現場の意見を聞くことが大切です。導入したITツールを“宝の持ち腐れ”にしないためにも、本番導入の前から幅広いユーザーの意見を聞くことが必要でしょう。
オンボーディングITツールの最新トレンド
昨今、普及が進んでいる生成AIは、オンボーディングITツールにも大きな変革をもたらしています。
たとえば、チャットボット型のAIエージェントは、社内手続きの方法や設備の使い方などの質問に対して、24時間体制で回答できるものです。このような仕組みがあると、新人の不安がスムーズに解消するのはもちろんのこと、質問に答える人事部門および上司・先輩の負担も軽減するでしょう。
また、生成AIによる目標達成への進捗モニタリング機能は、「困っている新人」の早期発見をすることで、忙しい上司やOJT担当者に適切なタイミングでフォローやサポートを促す効果をもたらしているようです。
これから効果の高いオンボーディングITツールを導入するのであれば、生成AIの技術が組み込まれたものに着目するのもよいかもしれません。
オンボーディングにおける
KPIと4つの評価指標
オンボーディングを評価し、最適な仕組みにブラッシュアップしていくうえでは、重要業績評価指標である“KPI”を設定することも大切です。KPIとは、最終的な目標達成に向けたプロセスの達成度合いを定量的に測定・評価するための中間指標になります。
オンボーディングで設定すべきKPIは、既卒・新卒や業種ごとに変わります。ここでは、一般的に使われる4つの指標とKPI設定のポイントを見ていきましょう。
(1)時間指標
新人の場合、「どれだけ早く適応・習得できているか?」を見るために、KPIに時間指標を設定することが多いです。たとえば、「はじめての訪問営業で取引完了するまでの時間」や「作業工程Aをマスターするまでの時間」などを設定するとよいでしょう。
(2)販売指標
販売指標は、新人の積極性や販売能力を見るうえで役立つものです。たとえば、「売上目標の達成率」や「一定期間の取引個数」などを設定するとよいでしょう。
ただし、新人が仕事を身につけるうえでは、成果を出すまでの過程や作業の質も重要です。時間や販売などの指標をKPIとして設定する際には、「どうやってその成果を出したのか?」という過程まで関心を持ち、評価を行う必要があるでしょう。
過程を評価することの重要性については、以下の目標設定に関する記事でも詳しく解説しています。ぜひチェックしてみてください。
【関連記事】人事評価における目標設定の基本とは?目標の活用法、運用時の注意点を詳しく解説
(3)研修・学習指標
この項目は、新人の学習理解度や進捗状況、モチベーションなどを把握するうえで役立つものです。たとえば、「eラーニングの完了ページ数」や「商品知識テストのスコア」などを設定するとよいでしょう。
(4)満足度指標
オンボーディングは、新入社員が組織に馴染み、満足した状態で活躍できてこそ本質的な成功であると考えられます。
ですから、オンボーディング施策の効果を見るうえでは、新入社員にアンケート調査などを行い、「会社への満足度」や「オンボーディング施策への評価」をしてもらうことも必要でしょう。
オンボーディングの成功事例 3選
これからはじめてオンボーディング支援制度の設計をする場合、行うべき施策が多すぎて、優先順位がつけられないこともあると思います。そういったときには、オンボーディングの実施によって社内に好循環が生じている企業の成功事例を参考にするのもよいでしょう。
ここでは、効果の高いオンボーディング施策で注目されている企業事例を3つ紹介していきます。
事例(1)GMOペパボ株式会社
GMOペパボ株式会社には「ペパボカクテル」という名称のオンボーディングプログラムがあります。
この「ペパボカクテル」におけるオンボーディング施策のポイントは、「事業部任せ」をやめて、全社共通プログラムにした点です。こうした取り組みを始めた背景には、組織活性化のために「会社・事業部・エンジニア組織」という3つの帰属意識を育てたいという経営層の思いがあったといいます。
また、中途入社者のリーダーシップを促すために、自分自身でやっていきたいことを表明してもらう「やっていきシート」という仕組みも導入しています。将来的には、みんなが生き生きと働ける組織をつくるために、職種や既卒新卒問わず、幅広い人がペパボカクテルを使えるようにブラッシュアップしていく方向性のようです。
<参考>:組織への「帰属意識」を育てる!オンボーディングプログラム「ペパボカクテル」の全貌(GMOペパボ株式会社)
事例(2)LINEヤフー株式会社
LINEヤフー株式会社のオンボーディングプログラムは、新卒と中途社員の両方に行われています。入社者が早期にパフォーマンスを発揮できるように、以下のような施策でサポートしている形です。
|
|
また、LINEヤフーでは、自社の運営アプリ「LINE」上に、社内カルチャーや福利厚生、人間関係の悩みなどのあらゆる相談ができる窓口を開設しています。この相談窓口はホテルのコンシェルジュをイメージした設計となっており、新入社員を新規顧客のように丁寧にサポートすることを大切にしているようです。
<参考>:人材成長支援〜パフォーマンス最大化のための成長促進〜(LINEヤフー株式会社)
事例(3)株式会社 博報堂
大手広告代理店の博報堂では、2016年頃から中途採用が急増したにも関わらず、現場の忙しさから適切な教育サポートを行えず、人材の定着不全が起きていた時期があったといいます。そうした過去への反省から、オンボーディングに力を入れ始めた経緯があります。
なかでも特徴的なプログラムは、「On Board School」です。
「On Board School」は、年に2回開催・隔週金曜日に実施しています。いわゆる新入社員が定期的に集まることで、キャリア同期の絆を作ったり、配属後の様子を観察できたりするメリットがあるようです。
また、「On Board School」のなかでは、博報堂独自の価値観や考え方の理解につながる以下のような教育プログラムも実施されています。
|
|
<参考>:博報堂のキャリア採用社員向けオンボーディングの取り組み【イベントレポート】ONBOARDING-SUMMIT 2021_No.2|野村秀之氏 講演
オンボーディング実施時の注意点
前述したとおり、オンボーディングは「導入・実施さえすればOK」というものではありません。実施する施策や運用方法が合わない場合、メリット以上に問題が生じて逆効果になってしまうこともあります。
そうした問題を防ぐためには、オンボーディングによるリスクおよび注意点を理解したうえで、自社に合う適切な制度設計および運用をすることが重要です。ここでは、4つの注意点を見ていきましょう。
注意点(1)明確な目的・目標を設定すること
オンボーディングによる失敗の多くは、目的や目標が設定されないなかで生じることが多いものです。たとえば、早期戦力化について目標設定する際には、「どういったスキルを使ってどのような成果を出せる状態なのか?」まで落とし込む必要があります。
たとえば、組織社会化の「馴染む」についても、以下のどこを目指すかによって行うべき施策は変わってくるでしょう。
|
|
注意点(2)組織全体で取り組むこと
オンボーディングを成功させるためには、その施策に携わる全メンバーの協力が必要です。つまり、人事部門だけが頑張っても成功しないのです。
そこで、これまで社内に新人の「組織社会化」および「早期戦力化」の仕組みがなく、人事部門と現場の連携も行われてこなかった場合は、受け入れ部門の管理職にオンボーディングの目的やメリットを理解・共感してもらうことから始める必要があるかもしれません。
「組織社会化」および「早期戦力化」の浸透までほど遠い状態の場合は、経営陣からオンボーディングの必要性についてメッセージを発信してもらい、そこから組織風土を変革する取り組みを進めたほうがよいでしょう。
注意点(3)
各新入社員の属性やニーズに合った施策にすること
オンボーディングの施策は、各人材の経験や既卒・新卒などの属性で変わるものです。
たとえば、経験豊富な30代中途人材の場合、新卒に不可欠な「ビジネスマナー研修」は不要です。
その代わりに、教育を通じて自社が大事にしている価値観や行動指針などを理解してもらい、自身のスキルと融合させてもらう必要があるでしょう。
多くの人に効果的なオンボーディングを実施するためには、各人材が「わからないこと」や「困っていること」などの“ニーズ”に耳を傾けることも重要なポイントになります。
人事労務のアウトソーシングならラクラスへ
本記事では、オンボーディングの定義や必要性、メリットなどを解説してきました。オンボーディングの導入や運用については多くの注意点があるため、人事部のなかでも負担に感じている方は多いのではないでしょうか。
もし人事業務における業務効率化をお考えであれば、ラクラスにお任せください。ラクラスなら、クラウドとアウトソーシングを掛け合わせた『BpaaS』により、人事のノンコア業務をアウトソースすることができコア業務に集中できるようになります。
ラクラスの特徴として、お客様のニーズに合わせたカスタマイズ対応を得意としています。他社では難色を示してしまうようなカスタマイズであっても、柔軟に対応することができます。それにより、大幅な業務効率の改善を見込むことができます。
また、セキュアな環境で運用されるのはもちろんのこと、常に情報共有をして運用状況を可視化することも心掛けています。そのため、属人化は解消されやすく「人事の課題が解決した」という声も数多くいただいております。
特に大企業を中心として760社86万人以上の受託実績がありますが、もし御社でも人事の課題を抱えており解決方法をお探しでしたら、ぜひわたしたちラクラスへご相談ください。