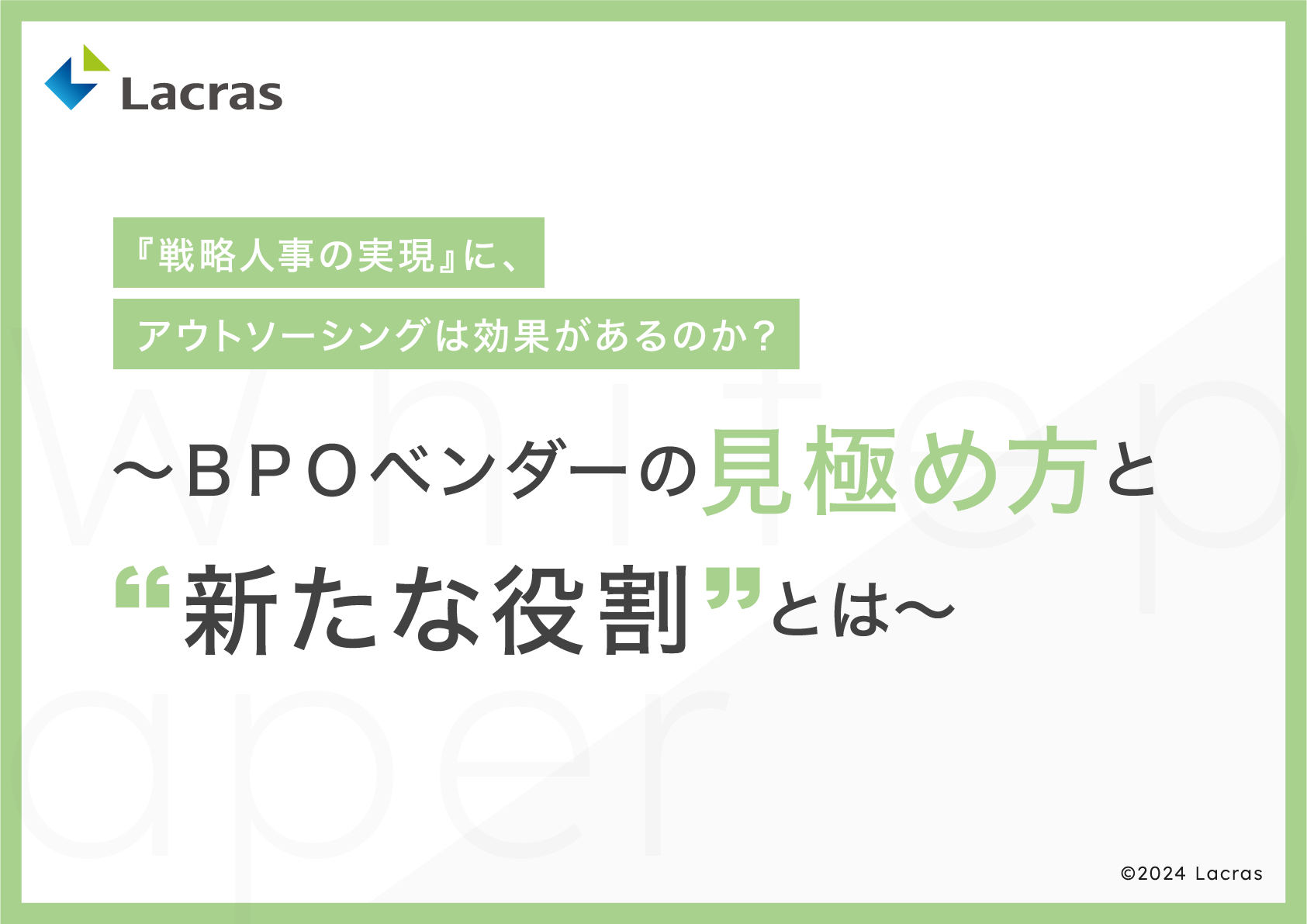賞与(ボーナス)の計算方法とは?平均支給額や税金・社会保険料計算の注意点も解説

本記事では、賞与の法律的な定義および種類、計算方法などを詳しく解説します。また、賞与計算を効率化する方法やよくある質問と回答も紹介していきます。これから賞与計算の実務に携わる方は、ぜひ本記事をチェックしてみてください。
自社で賞与(ボーナス)の支給を行っている場合、人事担当者は法律と自社ルールの両方を意識しながら評価・計算などの手続きを進める必要があります。
本記事では、賞与の法律的な定義および種類、計算方法などを詳しく解説します。また、記事の後半では賞与計算を効率化する方法やよくある質問と回答も紹介していきます。
これから賞与計算の実務に携わる方は、ぜひ本記事をチェックしてみてください。
賞与(ボーナス)とは?
賞与(ボーナス)の計算や支給手続きを適切に行うためには、まず「賞与がいったい何を指すのか?」について法律的な観点から理解することが重要です。ここではまず、賞与の定義と目的、賞与と給与の違いなどの基礎知識を整理しておきましょう。
賞与(ボーナス)とは
国税庁および労働基準法は、賞与の定義を以下のように示しています。
| 国税庁 | 労働基準法(第11条) |
| 賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいいます。 | 第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 |
| <引用>:No.2523 賞与に対する源泉徴収(国税庁) | <引用>:労働基準法第11条(e-Gov) |
上記をまとめると、労働基準法としての賞与は「賃金の一種」であり、税制上は「毎月の給与とは別に支払われる給与の一種」という定義になります。「毎月の給与とは別」という点では、臨時支給される「インセンティブ」や「特別手当」なども賞与に該当するケースが多いでしょう。
賞与の支給目的と給与との違い
賞与と給与の大きな違いは、給与がいわゆる『賃金支払の五原則』にもとづく事業主の義務であるのに対して、賞与は企業側が独自に支給できる点です。
<参考>:賃金の支払方法に関する法律上の定めについて(厚生労働省)
そのため、賞与支給に関する以下のルールは、企業が任意で決めることができます。
|
|
したがって、賞与支給の目的や意義なども、各社が独自に設定することができます。一般的には、以下のような目的や意義をもって、賞与を支給する企業が多いでしょう。
|
|
賞与の一般的な支給時期
賞与の一般的な支給時期は、夏と冬の年2回です。評価(査定)をして賞与額を決める場合、以下の評価対象期間・査定期間・支給月のなかで評価および計算手続きを進めていきます。
| 夏の賞与(ボーナス) | 冬の賞与(ボーナス) | |
| 評価対象期間 | 前年10月~3月頃 | 4月~9月頃 |
| 査定期間 | 4月~6月頃 | 10月~12月頃 |
| 支給月 | 6月~7月頃 | 11月~12月頃 |
賞与の平均的な支給回数
PERSOLグループの求人情報・転職サイトのdoda(デューダ)では、賞与の支給回数に関する調査を行っています。
<参考>:職種や年代でボーナス・賞与はどう変わる?ボーナス平均支給額の実態調査【最新版】(冬・夏、年代別、職種別の賞与)(doda)
同調査で最も多かったのは先ほども紹介した「年2回(夏、冬)」のパターンで、全体の75.3%という結果でした。このほかに、「年1回」が4.4%、「年3回以上」が5.5%だったようです。
賞与の平均支給額
賞与制度の設計を行う際には、事業所がある地域や業種の平均支給額を参考にするのもよいでしょう。
まず、厚生労働省が公表する「毎月勤労統計調査 令和7年2月分結果速報等」の「≪特別集計≫令和6年年末賞与(一人平均)」を見ると、支給事業所における労働者一人平均賞与額の数字にも、業種ごとに大きな開きがあることがわかります。
令和3年において、労働者一人の平均賞与額が「高かった業種」と「低かった業種」は以下の一覧のとおりです。
| 平均賞与額が高い業種 | 平均賞与額が低い業種 | |||
| 1 | 電気・ガス業 | 943,474 | 飲食サービス業等 | 83,199 |
| 2 | 情報通信業 | 707,303 | 生活関連サービス業 | 184,277 |
| 3 | 金融業・保険業 | 641,032 | その他のサービス業 | 236,048 |
| 4 | 鉱業・採石業等 | 612,066 | 医療・福祉 | 308,846 |
| 5 | 学術研究業等 | 588,937 | 卸売業・小売業 | 373,565 |
<引用>:毎月勤労統計調査 令和7年2月分結果速報等|≪特別集計≫令和6年年末賞与(一人平均)(厚生労働省)
また、日本労働産業ユニオンが2023年12月に実施した「ボーナスの金額調査アンケート」によると、以下の5府県の賞与平均額が高いことがわかっています。
| 都道府県別ボーナス平均額ランキング | ||
| 1 | 静岡県 | 124万円 |
| 2 | 愛知県 | 112万円 |
| 3 | 宮城県 | 106万円 |
| 4 | 福岡県 | 103万円 |
| 5 | 大阪府 | 101万円 |
<引用>:ボーナスの平均金額が高いのは意外な”あの”都道府県?【ボーナスの金額調査アンケート】(日本労働産業ユニオン)
日本労働産業ユニオンでは、上記の都道府県には自動車を中心とするさまざまな工場があるため、製造業の賞与平均が全体の金額を押し上げているという見解を示しています。
賞与における3つの種類
繰り返しになりますが、賞与額は各企業が独自のルールで設定することができます。しかし、一般的な企業では、いくつかの方法をベースに賞与額を決めることが多くなっています。ここでは3つの種類を挙げ、特徴とメリット・デメリットをそれぞれ見ていきましょう。
(1)基本給連動型賞与
基本給連動型賞与とは、その名のとおり従業員の基本給をベースに賞与額を決める方法です。一般には、以下のように基本給に一定割合を掛けて算出します。基本給連動型賞与は、最も多くの企業が採用する方法といえます。
【基本給連動型賞与の一般的な計算式】=従業員の基本給×◯ヵ月
基本給連動型賞与のメリットは、上記のようにシンプルな計算で賞与額を決められる点です。一方でデメリットは、個人の成果や業績が反映されず、勤続年数や役職に依存しやすいことです。
そのため、たとえば基本給の低い若手が「営業成績1位」などの高い業績をあげても、基本給連動型の仕組みのもとでは賞与額はあまり上がらないかもしれません。そうすると「基本給が低く、業績が著しく高い人」からの不満が生じやすくなるでしょう。
(2)業績連動型賞与
業績連動型賞与は、個人や企業の業績や目標の達成度などに応じて賞与額が変動するものです。
たとえば、ある商品の販売個数が過去最高を記録した場合、会社側では経営の健全性を保ちながら、それだけ多くの賞与を従業員に支払えます。また、会社の業績を個人の賞与に反映する仕組みは、営業職や販売職などのモチベーションを特に高めるものになるでしょう。
業績連動型賞与の場合、以下の計算式で支給額を算出することが多いです。
【業績連動型賞与の一般的な計算式】=基準額×評価係数
業績連動型のデメリットは、会社の業績が下がると従業員の賞与にも支障が出やすくなってしまう点です。
(3)決算賞与
決算賞与とは、決算で業績が良かったときに、決算月の前後でスポット的に支給する賞与です。決算賞与の計算式も業績連動型賞与と同じになります。
【決算賞与の一般的な計算式】=基準額×評価係数
決算賞与のメリットは、利益が大きく出たときだけの臨時支給となるため、経営の健全性および柔軟性を保ちやすい点です。また、「これだけの利益が出たからみなさんに還元を……」というメッセージを伝えることや報酬を支給することは、従業員にとってインパクトが強く、仕事へのモチベーションを高める要素にもなるでしょう。
また、企業側にも、決算前に賞与を支給することで法人税の節約ができるメリットがあります。
ただし決算賞与は、支給が不定期である特性上、従業員から見た収入安定の要素にはなりづらいです。また、当然ながら会社の業績が低迷してしまえば、支給が長期間発生しないこともあるでしょう。
基本給連動型で賞与額の公平性・透明性を高めるには
最も一般的な基本給連動型を採用する場合、賞与額が基本給の影響を受けることから、「業績が著しく高い一方で基本給が低い若手」などから不満が出やすくなる傾向があるのは前述したとおりです。
賞与支給の度に「自分は営業成績トップなのに、賞与はなぜかAさんより低い……」といったネガティブな気持ちが生じると、「自分はこの会社で認められていない」などの想いから、離職の意向につながってしまうかもしれません。
基本給連動型のデメリットともいえるこうした問題を防ぐためには、「従業員の基本給×1.5ヵ月」などの基本給にもとづく計算を行ったあと、「個人の業績評価による調整」を行うのがおすすめです。それはつまり、「基本給連動型と業績連動型のハイブリッド」といえます。
ここでは、「基本給連動型」で賞与計算をする場合に、賞与額の公平性・透明性を高めるためにすべき「個人の業績評価による調整」や「公平・公正な評価をするための準備」について解説します。
個人の業績評価による調整とは
個人の業績評価による調整とは、以下3つの評価項目についてチェックを行った結果を係数であらわし、各従業員の賞与額を「基本給×◯ヵ月×係数」の計算式で調整していくことです。
|
【業績評価】一定期間内の定量的な成果(売上・販売個数など)を評価するもの 【能力評価】業務遂行に必要なスキル・知識の習熟度や活用度などを評価するもの 【行動評価】高い業績をあげる人と同じ行動特性があるかどうかを評価するもの
|
具体的な係数は企業が独自に設定するものとなりますが、高い業績による係数の違いは、以下のように賞与評価の不公平感を解消する可能性が高いでしょう。
【Aさん(入社3年・営業成績1位)】
250,000円(基本給)×1.2(月)×3.0(係数)⇒900,000円
【Bさん(入社10年・営業成績15位)】
300,000円(基本給)×1.2(月)×1.1(係数)⇒396,000円
公平・公正な評価をするための準備
基本給連動型で公平・公正な評価をするためには、以下の準備が必要です。
|
|
上記3つの準備を行う理由は、評価から算出された賞与額について、従業員が納得できる状態をつくるためです。また、それは「上司による評価」と「部下の自己評価」の乖離を最小限にすることでもあります。
逆にいえば、これらの準備を行う前に業績評価による調整を実施してしまうと、「係数」の部分が不透明になります。そうすると従業員から見たときに「なぜこの賞与額になるのか?」といった疑問や違和感が生じやすくなるでしょう。
なお、賞与評価を公平・公正に行うためのポイントは、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ確認してみてください。
賞与の計算方法
賞与(ボーナス)支給額の手取りは、毎月の給与と同様に社会保険料と所得税を控除した金額です。基本的な考え方は、以下の計算式のとおりになります。
【賞与の手取り額】=賞与の総支給額-(社会保険料+所得税)
ここでは、賞与計算に影響する社会保険料と、所得税の種類および計算時のポイントを詳しく解説しましょう。
賞与計算と社会保険料
賞与計算で最初に控除するのは、以下の4種類の社会保険料です。
|
|
賞与における社会保険料計算では、それぞれ「標準賞与額×各保険料率」の計算式を使って算出した金額の2分の1を賞与総額から控除していく流れになります。標準賞与額とは、税引前の賞与総額から千円未満を切り捨てた数字です。給与計算で登場する標準報酬月額の代わりに標準賞与額を使うイメージでしょう。
<参考>:標準報酬月額・標準賞与額とは?(全国健康保険協会)
社会保険料の概要や各保険料などについては、以下の記事にて詳しく解説しています。ぜひチェックしてください。
【関連記事】社会保険料の計算方法は?|給与計算と賞与計算の違い、保険料の種類や注意点を解説
賞与計算と所得税(復興特別所得税)
賞与の支給時に源泉徴収すべき税金は、所得税と特別復興所得税の2種類です。
特別復興所得税とは、2011年3月に発生した東日本大震災からの復興財源に充てる目的ですので、2013年1月1日~2037年12月31日までの期間限定で所得税に2.1%を上乗せして徴収される特別税になります。
賞与に対する源泉徴収の計算方法は、以下の3パターンのどれに該当するかで異なります。
|
(1)通常の場合(「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合) (2)前月に給与の支払がない場合 (3)前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合
|
たとえば、最も一般的な(1)の場合、以下の流れで源泉徴収額を決定します。
|
(1)前月の給与から社会保険料等を差し引きます。 (2)「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の甲欄の扶養親族等の数に応じた上記①の金額の当てはまる行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている税率を求めます。 (3)(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×上記①の税率(この金額が、賞与から源泉徴収する税額になります。
|
この方法で源泉徴収額を算出するうえで必要な情報は、「前月の給与(社会保険料控除後)」「賞与額」「扶養親族等の数」の3つです。国税庁のページには、これらの情報を使ったシミュレーションも掲載されています。賞与の源泉徴収をはじめて行う人は、ぜひチェックしておくとよいでしょう。

賞与支給に必要な手続きと注意点
従業員に賞与を支給する場合、ここまでにご紹介した評価と計算のほかにも、行うべき事務手続きがあります。また、賞与の場合は、回数の違いで行う手続きが変わるルールにも注意が必要です。
ここでは、賞与支給の事務手続きに関係する2つの書類と注意点をそれぞれ見ていきましょう。
賞与支給に関係する2つの書類
賞与支給の手続きでは、「賞与明細書の発行」と「賞与支払届の提出」が必要です。各書類のポイントを見ていきましょう。
・賞与明細書の発行
賞与明細は、賞与支給の際に従業員に渡す支払明細書です。賞与明細は、所得税法第231条で定められた賞与支払者の義務になります。その条文は、以下のとおりです。
|
(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書) 第二百三十一条
<引用>:所得税法(e-GOV)
|
賞与明細書は、社会保険料の控除額および所得税の源泉徴収額の確定後に作成します。必ず記載する項目としては以下の3つです。
|
|
・賞与支払届の提出
賞与支払届は、事業主が従業員に賞与を支給したときに、日本年金機構に提出する書類です。正式名称は「被保険者賞与支払届」であり、賞与の支払日から5日以内に事務センターまたは管轄の年金事務所に提出するものになります。提出方法は、以下の4つです。
|
|
賞与の支給回数と賞与支払届に関する注意点
繰り返しになりますが、賞与支払届は日本年金機構に提出する社会保険料関連の書類です。
賞与支払届の対象になる賞与は、同じ性質のものが年3回以下の支給に限ります。それはつまり、年4回以上支給されるものについては、標準賞与額ではなく、いわゆる月給と同じ標準報酬月額の対象となるということです。
日本年金機構のホームページでは、「被保険者賞与支払届」の対象となる賞与と回数について、以下のように解説しています。
|
「被保険者賞与支払届」の対象となる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものです。なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外です。 (例)給与規程において7月、12月に「○○手当」の支給を規定している場合、支給月が年2回と明確に規定されているため、通常の報酬ではなく賞与となります。 <引用>:従業員に賞与を支給したときの手続き(日本年金機構)
|
賞与に関するよくある質問
賞与は、企業側で独自にルール設定などができる特性から、人事給与の担当者のなかに疑問や不安が生じやすい手続きでもあります。また、冬の賞与支給は年末調整の時期と重なることから、オペレーションの進め方に頭を悩ませることもあるでしょう。
ここでは、賞与に関するよくある質問とその答えを紹介していきます。
Q.基本給連動型で賞与を支給しています。業績の悪化に伴い、全従業員のボーナスを「支給なし」にすることは可能でしょうか。
賞与の支給や計算は、就業規則に書かれたとおりのルールで行うべきものです。ただし一般論として、たとえば業績が良いときに賞与をイレギュラーで増やすことは、従業員にとって嬉しい状況ですから、基本的に労使間トラブルにはなりません。
ただし、明確な規定がないなかで「業績が悪いから今期は支給なし」といったことを一方的に決めた場合、それは労働者の同意なき労働条件の変更となります。そのため、法律的に認められない可能性が高いでしょう。
何らかの理由で賞与額や査定要件などを変える可能性がある場合は、就業規則にその旨をしっかり記載し、従業員の理解を得ておく必要があります。
Q.これから退職する人の賞与については、どのように計算すればいいでしょうか。カットしても大丈夫でしょうか。
退職者の賞与に関しては、トラブルが生じやすいものです。その理由は、賞与支給後の退職を予定する従業員と事業主との間に、認識のズレが起こりやすいからです。
制度的な話をすれば、たとえば「賞与は今後への期待値を含めているため、退職者については◯◯の基準で減額することもある」といった文言を就業規則のなかに記載していれば、減額や不支給などの対応を行っても問題ありません。
一方で、就業規則を読む限りでは「退職予定者でも満額もらえそうな文言」がある場合、賞与支給を期待する退職者との間で認識のズレによるトラブルが起こりやすくなるでしょう。
賞与の評価および就業規則作成のポイントは、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひチェックしてみてください。
【関連記事】賞与評価の重要性とは?|不当査定を防ぐための基準や実践的手法、就業規則のポイントを解説
Q.12月には給与と賞与支給に加えて年末調整もあるのですが、どのタイミングで精算すべきでしょうか。
年末調整による源泉徴収は、本年の「最後」に行うのが理想です。理由としては、たとえば12月初旬に見積額で精算を行っても、本年最後の支払額(給与もしくは賞与の金額)と不一致が生じた場合は、年末調整をやり直す必要があるからです。
ただでさえ忙しい師走の時期に余計な業務を増やさないためにも、その年の支給額が確定する「本年の最後」に精算をすることが理想でしょう。
なお、12月支給の賞与と年末調整の関係については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひチェックしてください。
賞与計算を効率化する方法
賞与の計算業務は、毎月支払う月給と違って自社の独自ルールや回数など、注意しなければならないポイントがたくさんあります。
また、前述したとおり賞与の冬支給は多くの場合、年末調整シーズンと重なることが多くなります。そうした時期に発生する人事担当者の負担を減らすためには、給与・賞与計算のデジタル化やアウトソーシングを導入するのがよい方法といえるでしょう。
それぞれ具体的に解説していきます。
給与計算ソフトを活用する
給与計算ソフトとは、従業員の勤怠情報などを取り込み、給与・賞与の計算を自動で行うデジタルツールの総称です。最近ではクラウド上で動くものも増えており、1つのツール内で給与と賞与の計算、人事評価、採用管理、年末調整などを総合的に行える種類も登場しています。
こうしたツールを活用すると、社会保険料や所得税などの複雑な計算もミスなく簡単に行うことができます。また、計算後は賞与明細書などの書類もボタン1つで出力することが可能でしょう。
給与計算ソフトは、「計算ミスが多い」とか「全制度を理解しきれていない」といった担当者の強い味方になるはずです。
人事給与アウトソーシングを選択する
そもそも人手が足りず、「賞与計算が終わらず、年末調整に着手できない……」とか「月次や年次の仕事に追われて、人材戦略をつくる暇がない……」といった状況の場合は、人事給与のアウトソーシングを活用するのも選択肢の一つです。
人事アウトソーシングとは、人事部門の一部業務を切り出して外部の事業者に委託する業務形態のことです。たとえば、給与・賞与計算~年末調整までをアウトソーシングすると、人事担当者は各種計算および精算に追われることがなくなります。
また、年末調整を外部委託するタイミングで専用システムを導入すれば、年末調整の“紙の運用”で生じていた「申請書の配布・回収」といった業務からも解放されるでしょう。
人事業務のアウトソーシングならラクラスへ
本記事では、賞与の法律的な定義および種類、計算方法などを詳しく解説してきました。賞与の計算については多くの注意点があるため、人事部のなかでも負担に感じている方は多いのではないでしょうか。
もし人事業務における業務効率化をお考えであれば、ラクラスにお任せください。ラクラスなら、クラウドとアウトソーシングを掛け合わせた『BpaaS』により、人事のノンコア業務をアウトソースすることができコア業務に集中できるようになります。
ラクラスの特徴として、お客様のニーズに合わせたカスタマイズ対応を得意としています。他社では難色を示してしまうようなカスタマイズであっても、柔軟に対応することができます。それにより、大幅な業務効率の改善を見込むことができます。
また、セキュアな環境で運用されるのはもちろんのこと、常に情報共有をして運用状況を可視化することも心掛けています。そのため、属人化は解消されやすく「人事の課題が解決した」という声も数多くいただいております。
特に大企業を中心として760社86万人以上の受託実績がありますが、もし御社でも人事の課題を抱えており解決方法をお探しでしたら、ぜひわたしたちラクラスへご相談ください。