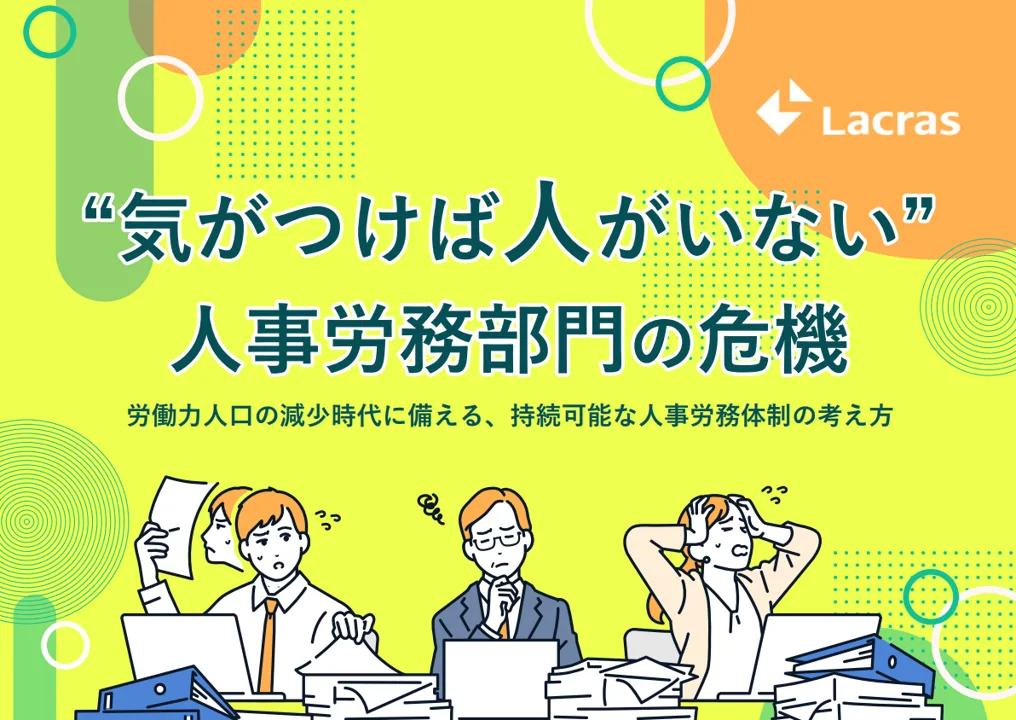ジョブクラフティングとは?
効果を高める実践法や組織風土変革のポイントを徹底解説

本記事では、ジョブクラフティングの定義や注目される背景、メリットなどを確認します。また、ジョブクラフティングの実践編として具体的な進め方や注意点、成功事例も解説していきます。従業員の主体性やワークエンゲージメントを高めたくてジョブクラフティングについて調べている方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
昨今、ビジネスの複雑性が増しており、従業員は仕事上の困難にも直面しやすくなっています。こうした状況で、従業員が自らの仕事をより満足できるものに変革するためのアプローチとして注目されているのが「ジョブクラフティング」です。
本記事の前半では、ジョブクラフティングの定義や注目される背景、メリットなどを確認します。そのうえで後半では、ジョブクラフティングの実践編として具体的な進め方や注意点、成功事例などを解説していきます。
従業員の主体性やワークエンゲージメントを高める目的でジョブクラフティングに関心を持っている方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
ジョブクラフティングとは
多くの従業員がジョブクラフティングを実践し、高い効果をあげるための仕組みづくりをするためには、「ジョブクラフティングとは、そもそもどのような概念なのか?」を理解する必要があります。
ここでは、厚生労働省が示す資料などを見ながら、ジョブクラフティングの定義やジョブデザインとの違い、近年注目される背景について確認していきましょう。
ジョブクラフティングの定義
ジョブクラフティングとは、仕事の満足度ややりがいを高めるために、自分の働き方に以下の3つの工夫を加える手法です。
|
作業クラフティング / 人間関係クラフティング / 認知クラフティング
|
「作業クラフティング」は、仕事の中身がより充実した内容になるように、仕事量や範囲、やり方などを変化させる工夫になります。
たとえば、『SMART』のようなフレームワークを使って具体的な目標を立てて達成すれば、成功体験を通じて満足感が高まりやすくなります。
「人間関係クラフティング」は、仕事で関わる人との関係性を調整・改善することで、仕事のやりやすさや満足感を高めるものです。
たとえば、上司との関係を改善して「前向きなフィードバックをもらう・褒められる」といった体験が増えると、そこから仕事のやりがいや満足度が高まりやすくなるでしょう。
「認知クラフティング」は、その仕事に携わる意味や目的を改めて捉えなおすことです。
たとえば、「上司に言われたから仕方なくやっている」から「自分のキャリアのためにやっている」に意味を変えると、前向きな姿勢やモチベーションが生まれやすくなるでしょう。
ここまで説明してきた“ジョブクラフティングにおける3要素”をまとめると、以下のとおりになります。
| 概要 | 詳細 | 具体例 | |
| 作業 クラフティング |
仕事のやり方に対する工夫 | 仕事の中身をより充実したものにするために、仕事量や範囲を変える工夫 |
・フレームワークを用いた目標設定 ・タスクの優先順位付け ・スモールステップ法にもとづくスケジュール管理 |
| 人間関係 クラフティング |
周囲の人への働きかけの工夫 | 仕事で関係する人との関わり方を調整することで、前向きなフィードバックやサポートをもらい、仕事への満足感を高める工夫 |
・職場の先輩に自ら積極的に提案や相談をする ・メンバーとのコミュニケーション時に必ず「ありがとう」を言う |
| 認知 クラフティング |
仕事の捉え方・考え方に関する工夫 | その仕事をやる意味や目的を捉え直したり、自分の興味関心と結びつけて考えたりすることで、前向きにやりがいを感じながら取り組む工夫 |
・いまやっている作業が自分の将来に与える意義を考える ・毎回「なぜそれをやるのか?」を考える習慣をつける |
<出典>:コラム2ー6図 ジョブ・クラフティングについて(厚生労働省)
ジョブクラフティングは、米イェール大学経営大学院のエイミー・レズネスキー准教授とミシガン大学のジェーン・E・ダットン教授によって2001年に提唱された理論です。彼らの論文では、ジョブクラフティングを「課題や対人関係における従業員個人の物理的又は認知的変化」と定義しています。
また、日本のジョブクラフティング研究の第一人者・東京都立大学教授の高尾義明先生は、以下のように、よりわかりやすい定義をされています。
|
はたらく人たち一人ひとりが、主体的に仕事や職場の人間関係に変化を加えることで与えられた職務から自らの仕事の経験を創り上げていくこと
|
また、武蔵大学教授の森永雄太先生は、ジョブクラフティングについて以下のように説明しています。
|
イキイキ感ややりがい、組織への愛着を持ってもらうためのもの
|
ジョブクラフティングとジョブデザインとの違い
ジョブクラフティングと混同されやすい言葉に、「ジョブデザイン」があります。
これらはどちらも、従業員のモチベーション向上や仕事の満足感・充実感アップを目指すうえで使われる概念です。しかし、そのアプローチ方法には、大きな違いがあります。
まず、ジョブクラフティングは先述のとおり、「従業員が自ら」仕事および人間関係に対する認知の捉え直しや工夫をする取り組みです。これに対してジョブデザインの主体は、「経営層や上司」になります。従業員の満足度を高めやりがいが得られるようにするために、経営層や上司が仕事の構造設計を行うことをジョブデザインと呼ぶわけです。
ジョブデザインでは、従業員は上司が設計した職務に対して「受動的な役割」を果たします。つまり、与えられた仕事を受け入れて、その枠内で作業を進めるわけです。これに対してジョブクラフティングでは、各従業員が自分の職務に対して「主体的かつ積極的」に改善・調整を行う点が大きく異なります。
ジョブクラフティングとジョブデザインの違いを整理すると、以下のようになるでしょう。
| ジョブデザイン | ジョブクラフティング | |
| 基本的な考え方 | 経営層や上司が、従業員の職務満足や内発的動機づけを高めるために、職務の構造設計や変更を行う | 従業員が自ら仕事の取り組み方や人間関係を変更し、自らの仕事体験をより良いものに創り上げていく |
| 実施する主体 | 経営層・上司(組織) | 各従業員(個人) |
| 従業員の存在 | 受動的存在 | 能動的存在 |
| アプローチの種類 | トップダウン的なアプローチ | ボトムアップ的なアプローチ |
ジョブクラフティングが注目される背景
近年ジョブクラフティングが注目される背景にあるのが、「VUCA」の時代になりビジネス環境にさまざまな課題や困難が生じやすくなっている状況です。
VUCAとは、以下の4つの言葉の頭文字をとった概念で、予測困難・不確実・複雑・曖昧な状況が重なる時代を指します。
|
|
コロナ禍や異常気象といった、誰もが経験したことがない出来事が多発する現代では、上司の勘や経験に頼る管理手法に限界が生じ始めています。
社内外でトラブルが起きた時、リーダーがいなければ適切な対処を行えません。しかし、トップダウンの組織にありがちな「上司の指示待ち」をメンバー全員が行っていては、VUCAのなかで生じる急速な技術革新や顧客ニーズの変化に対応しきれず、競合に遅れをとってしまうこともあるでしょう。
仕事がうまくいかない・成果がでないという状況が頻発するなかで従業員に高いモチベーションで業務に取り組んでもらうためには、それぞれの内面から湧き出る動機(内発的動機づけ)を強化したり、困難を乗り越えることから成功体験を得たりする仕組みが必要となります。ジョブクラフティングは、その仕組みの一つなのです。
組織がジョブクラフティングを
導入するメリット
ジョブクラフティングの仕組みを導入し、従業員に主体性や能動性が高まる好循環が起こると、組織全体には以下のようなメリットが生まれやすくなります。
メリット(1)従業員のモチベーション向上
ジョブクラフティングの取り組みを行うと、各メンバーは自分が携わる仕事やそこでの人間関係について、その意味ややり方を自ら考え試行錯誤をしながら自分にとって「充実したもの」や「前向きに取り組める状態」を目指すようになります。
そこで得られやすくなるのが、内発的動機づけに不可欠な要件である以下の3つです。
|
【目的】仕事自体が楽しい、やりがいを感じる 【自己決定感】自分で決断して行動している 【自己効力感】仕事の結果をある程度予測し、成果をコントロールできる
|
ジョブクラフティングによってこの3つが得られると、従業員の内側からポジティブな動機が生まれ、結果として高いモチベーションで仕事に取り組みやすくなるでしょう。
メリット(2)生産性の向上
各クラフティングのなかで個人が以下のような取り組みを実施すると、従業員個人およびチーム全体に生産性の向上をもたらします。
|
【作業クラフティング】
【人間関係クラフティング】
【認知クラフティング】
|
たとえば、上司から与えられた営業目標「年末までに5,000万円の売上を達成」に対して他人事では“やらされ感”が強くなってしまうため、モチベーションもパフォーマンスも上がりません。
しかし、そこで「これまでお世話になった上司への感謝の想いを営業成績で表現しよう」といったポジティブな意味づけや、目標設定・タスク管理などの見直しを自ら行うとどうでしょう。
より良い成果を出すこと自体に楽しみや面白さが生まれ、前向きな気持ちで生産性を上げていきやすくなるはずです。
また、各メンバーにおける“仕事の意味”や“人間関係のあり方”が変われば、チーム全体の生産性にも好循環が生まれやすくなるでしょう。
メリット(3)離職率の低下
ジョブクラフティングによって各自の内発的動機づけや“やりがい”が高まると、従業員側には、やりたくないことをやらされている状態による不満や不安が生じにくくなります。その結果、ネガティブな理由から離職を検討する必要がなくなるでしょう。
なお、厚生労働省の調査によると、自己都合退職する人の17.7%が「人間関係がうまくいかなかったから」を理由にあげていることがわかっています。仕事における人間関係は、働く人の離職意思に大きな影響をもたらす要因なのです。
<参考>:転職実態調査(厚生労働省)
こうしたなかで、各自が「人間関係クラフティング」の考え方にもとづいて周囲の人への働きかけの工夫を行うと、コミュニケーションにおける問題の多くが解消されやすくなるかもしれません。
また、自ら周囲に働きかけて関係性が変わると、「仕事のエンゲージメント(ワークエンゲージメント)」に加えて、会社そのものや上司・同僚への愛着をあらわす「従業員エンゲージメント」も向上しやすくなるでしょう。
エンゲージメントについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
ぜひチェックしてください。
【関連記事】従業員満足度(ES)と従業員エンゲージメントの違いとは?高めるメリットや方法も解説
ジョブクラフティングの実践ステップ
ジョブクラフティングの進め方には、さまざまな方法があります。ここでは、ジョブクラフティングの初心者でも実践しやすい4つのステップと基本的なポイントを紹介しましょう。
ステップ(1)業務内容の棚卸しをする
まず、自分が携わっている業務や日々のタスクを洗い出します。
例として「人事部門のリーダーAさん」の場合、以下のような仕事を洗い出せるでしょう。
|
【担当業務】
【「オンボーディング施策検討」に関する今月のタスク】
|
ステップ(2)自己分析と自己理解
ジョブクラフティングを平易な表現であらわすと、「“仕事そのもの”と“仕事で関わる人”との関係性を自らの工夫で改善して、やりがいや愛着を得られやすくすること」でもあります。
そのために必要となるのが「自分を知る作業」です。それは「自分自身の棚卸し」ともいえるでしょう。この作業は、多くの時間をかけて深くじっくり行うとよいものです。自分を知る作業では、以下のような項目を見ていくとよいでしょう。
|
|
自分を知ることで、「自分らしさ」を重視した工夫や周囲への働きかけにつながりやすくなるはずです。
たとえば、先述の人事担当者が社内のオンボーディング施策の導入・実施に力を入れている場合、仕事やそのプロジェクトでの人間関係について、以下のような気づきが得られるかもしれません。
|
【自分の強み】
【自分の弱み】
【仕事をするなかで楽しかった瞬間】
【仕事をするなかで嫌だった瞬間】
|
ステップ(3)3つのクラフティングに落とし込む
「携わっている仕事」と「自分自身」の棚卸しを終えたら、「自分のありたい姿」に近づくために行うべき工夫や働きかけを、以下の3つのクラフティングに落とし込んでいきます。先述の人事担当者の場合、以下のような工夫が考えられるでしょう。
| クラフティングの種類 | 実施する工夫・働きかけ |
| 作業クラフティング |
|
| 人間関係クラフティング |
|
| 認知クラフティング |
|
ステップ(4)施策の実施後に振り返りを行う
クラフティングのなかで行う工夫や働きかけは、「施策を決めて実施さえすればOK」ではありません。
クラフティングでは「自分らしく働き、多くの価値を創出できる状態」をつくるために、施策の実施後に振り返りを行い、そこで得た気づきからさらなる改善策を考えるPDCAのサイクルを回す必要があります。
さまざまな気づきを通して自分の仕事の取り組み方をブラッシュアップするからこそ、仕事や組織への愛着が高まり、その業務に携わることによる好循環が生まれやすくなるでしょう。

ジョブクラフティングを進める際のポイント
ここまで紹介したジョブクラフティングを各従業員が実践し、仕事と組織へのエンゲージメントや“やりがい”、モチベーションの向上につなげていくためには、その実践が妨げられない組織の風土が不可欠です。
ここでは、人事部門が主導して各自がジョブクラフティングをスムーズに行える組織風土づくりをしていくうえでのポイントを見ていきましょう。
ポイント(1)経営層の主導で行う
ジョブクラフティングは、「トップダウン型の組織」を「ボトムアップ型の組織」に変える取り組みとも関係します。
この考え方にもとづくさまざまな施策を成功させるためには、これまでトップダウン型組織のトップにいた経営層自身が人材管理に対する考え方を変え、それらを自ら組織に浸透させていく姿勢が必要です。
そこで重要となるのが、経営層から発信されるメッセージです。ジョブクラフティングを行える風土の醸成は、経営層のコミットメントがあってこそ成功するものでしょう。
ポイント(2)主体性を尊重する環境づくり
トップダウン型の組織では、経営層や上司が決めた事柄に対して、従業員が自分から行動を起こす「自主性」が高く評価される傾向があります。
これに対して、ジョブクラフティングによるボトムアップ型の組織で重視されるのは「主体性」です。主体性とは、目の前にある課題や目標に対して「私は何をすればよいか?」から自ら考え行動する概念になります。それはつまり、結果を出すまでの行動や考え方のすべてに対して自らが責任を持って行動することでしょう。
各従業員の主体性を尊重するためには、組織のなかにさまざまな仕組みをつくる必要があります。そのなかで大きなカギになるのが、「MVVの浸透」「心理的安全性の向上」「人事評価制度との連動」の3つです。
それぞれのポイントも続けて見ていきましょう。
ポイント(3)MVVの浸透
MVVとは、組織が目指すビジョン・ミッション・バリューのことです。それぞれの意味は企業ごとに異なるところもありますが、一般的には以下の意味で使われることが多いでしょう。
|
【ミッション】 【ビジョン】 【バリュー】
|
各従業員がジョブクラフティングを行えるようにするために、上記のMVVを社内に浸透させて、主体性を尊重する風土を醸成していく必要があります。
主体性の尊重にMVVが関係する理由は、会社が目指す方向性やあるべき姿などを各従業員が理解し、それを実践しようと努めるからこそ、「自ら考え、自ら動くこと」を尊重できるわけです。
逆にいえば、会社が向かう方向性やそれを実現するために不可欠な行動指針などを従業員が理解・実践できていない状態では、「上司からの指示待ち」をもたらすトップダウン型から脱却することは難しいでしょう。
ポイント(4)心理的安全性の高い環境の構築
ジョブクラフティングおよび主体性の尊重は、上司と部下、メンバー同士の間に「高い心理的安全性」があるからこそ実現できるものです。
心理的安全性とは、チームが目標達成や成果創出に向かうなかで、各メンバーが「自分の弱みを見せたり、一見ネガティブな意見を言えたりすることに、リスクを感じない状態」です。
Google社では2015年に「成功するチームをつくるのに最も重要なのは心理的安全性である」と提唱しています。
チームの心理的安全性が低く、メンバーが以下のように感じてしまう場合、失敗やリスクを最小限にするために「上司の指示を待つ・従う」といった選択をする可能性が高いでしょう。
|
|
一方で、組織の心理的安全性が高く、多くの従業員が以下のように感じている場合、ジョブクラフティングによる周囲への働きかけや工夫も行いやすくなるはずです。
|
|
これからジョブクラフティングを行える仕組みを整備していく場合は、まず各チームの心理的安全性を測定することから始めてみるとよいでしょう。
ジョブクラフティングによる個人および組織の好循環は、経営層がコミットメントした「MVVの浸透」と「心理的安全性の高い組織づくり」を両輪でまわすなかで生まれていくものなのです。
ポイント(5)人事評価制度との連動
ジョブクラフティングを浸透させるためには、主体的な人材を高く評価する仕組みを設計・導入することも重要です。
たとえば、「(上司からの指示を待たずに)自ら考え、自ら行動しているか?」や「チームのためになる意見を積極的に発信できているか?」といった人事評価の項目を設けると、ジョブクラフティングを意識した主体的な行動が高く評価されることになります。
また、人事評価と報酬・等級が連動していれば、ジョブクラフティングを行うことへのモチベーションも上がりやすくなるでしょう。
ただし、これまでトップダウン型で人材の管理や評価を行っていた場合、評価者である管理職の考え方を大きく変える「評価者教育」が必要となります。評価者教育などを通して管理職の意識変革ができてこそ、トップダウン型からの脱却が進みやすくなるでしょう。
ジョブクラフティングの効果を高めるうえでの注意点
ジョブクラフティングによる個人および組織の好循環を高めるためには、2つの点に注意する必要があります。それぞれ見ていきましょう。
注意点(1)業務の属人化を防ぐ
ジョブクラフティングでは、各メンバーが自分の仕事に対して責任を持ち、主体的に業務の再設計などを進めていきます。そこで注意したいのが、再設計した本人しか中身がわからない「属人化」の問題です。
たとえば、給与計算の主担当であるAさんが、副担当のBさんが産休に入っている間に業務の大幅な再設計と改善を行ったと仮定します。この場合、Bさんが産休明けで会社に出てきたときに「給与計算のやり方が大きく変わっていて、私には理解できない……」といった問題が生じるかもしれません。
このような問題を防ぐためには、各メンバーが「我々の仕事はチームで行っている」という認識を持ち、自分が再設計した内容をマニュアル化して積極的に共有したり、ほかのメンバーに対して「給与計算のここを改善したいのですがどう思いますか?」などと人間関係クラフティングの働きかけを行ったりすることが必要になります。
自分という「個人」の満足度や“やりがい”を高めるための工夫ばかりに固執するのではなく、メンバーとの関係をより良くすることにも意識を向けると、「組織のなかでの私」が良い形で活かされやすくなります。
その結果として、メンバー間の心理的安全性やエンゲージメントの向上にもつながっていくでしょう。
注意点(2)上司の意識を変革する
ジョブクラフティングによる主体性の尊重などを進めるうえでカギになるのが、上司の姿勢や意識です。
たとえば、上司がトップダウン型の認識のままでいる場合、部下の主体的な工夫が「無断で勝手にやった」などと判断されてしまうかもしれません。また、こうした一方的な決めつけが著しければ、ジョブクラフティングの土台となる「心理的安全性の高い組織づくり」も難しくなるでしょう。
ちなみに上司の意識は企業風土の影響を大きく受けているため、一朝一夕で変えることが難しい側面があります。
そのため、トップダウン型が長く続いてきた組織にジョブクラフティングを導入する際には、人事評価制度の評価者教育にフォローアップの仕組みを設けて、それなりの時間をかけながら意識および行動変容につなげていく必要があるでしょう。
ジョブクラフティングの成功事例
近年のビジネス環境では、長く続くVUCA時代のなかでジョブクラフティングの考え方に関心を持ち、従業員の主体性を尊重する方向に舵を切る企業が増えるようになりました。
そのようななかで注目されているのが、東京ディズニーリゾートで掃除を担当する「カストーディアル」の事例です。
もともとカストーディアルは、「ただのお掃除係である」という偏見に近い理由から、同社では不人気職種でした。かつては不満も多く離職率も高い職種だったようです。
しかし、カストーディアルの仕事について「来場者をおもてなしする一員」という意味付けを行い、会社側の扱いも大きく変えたことで、各メンバーが自ら「来場者に楽しんでもらうための取り組み」を主体的に考え、実行するようになっていきました。
最近ではパントマイムのような動きで移動をしたり、バケツの水を使って地面にキャラクターの絵を描いたりするカストーディアルもいるのです。そうして、カストーディアルの主体的な行動が良い意味で注目されることが多くなってきました。
そして現在では、東京ディズニーリゾート内の人気職種の一つになっているといいます。
この東京ディズニーリゾートの事例が示すとおり、各メンバーのなかに仕事への不満や違和感などが存在する場合、それはジョブクラフティングを始めるきっかけになるかもしれません。このような例を参考にしながら、ぜひとも個人と組織に変革を起こしてみてください。
ジョブクラフティングに関するよくある質問
ジョブクラフティングは、経験の浅い人事担当者にとって少し複雑な施策かもしれません。また、実際にジョブクラフティングを始めるにあたっては、そのためのタスクやスケジューリングで頭を悩ませることもあるでしょう。
ここでは、そんな人事担当者の皆さんのために、ジョブクラフティングに関するよくある質問とその答えをわかりやすく解説します。
Q.ジョブクラフティングの効果は
どのくらいで出るもの?
ジョブクラフティングの効果が出るまでの期間は、企業の現状や規模によって変わります。
たとえば、スタートアップ期の小さなベンチャー企業などの場合、少人数のメンバー間で自分たちの行動指針を決めて、「心理的安全性の高い組織づくり」や「各自が失敗を恐れず主体的に行動すること」などを目指すと、1年以内の短期間でジョブクラフティングの効果が得られるかもしれません。
一方で、トップダウン型での運営が長く続いた大企業の場合、経営層・管理職・現場メンバーというすべての固定概念や意識を変革する必要がありますから、数年単位の中長期的な取り組みになる可能性が高いでしょう。
Q.ジョブクラフティングの取り組みは
何から始めればいい?
ジョブクラフティングを実施するうえで組織風土の変革が必要となる場合は、まず経営層にコミットしてもらえる状態をつくる必要があります。
経営層がコミットするということは、経営層がジョブクラフティングおよび主体性の尊重の重要性に気づき、「これまでトップダウン型などのスタンスで管理してきた自分自身も変わる必要性を感じ始めた」という状態になります。
自社の現状に危機感を抱いた経営層から「自社にもジョブクラフティングを取り入れてみたい」と人事部門に打診する形であれば、取り組みを始めやすいかもしれません。
そうして経営層の主導で組織がトップダウン型からボトムアップ型に移行し始めていけば、MVVの浸透や心理的安全性が高い状態がある前提で、先ほど紹介した以下の4つのステップに入っていきやすいはずです。
ステップ(1)業務内容の棚卸しをする
ステップ(2)自己分析と自己理解
ステップ(3)3つのクラフティングに落とし込む
ステップ(4)施策の実施後に振り返りを行う
以上のことから、ジョブクラフティングの仕組みを取り入れる際には、まず自社のマネジメント型(トップダウン型・ボトムアップ型)やMVVの浸透度、心理的安全性の高さなどの現状分析を行うことから始めてみるとよいでしょう。
ジョブクラフティングにおける今後の展望
世の中の混迷が増し、戦略どおりにビジネスを進めることが難しくなっている現代。ジョブクラフティングの重要性は、従業員の主体性や内発的な動機づけ、仕事へのやりがいを高める「大切な装置」という意味で、今後も高まっていくことが予想されます。
また、VUCAの時代のビジネスでは、生成AIの著しい進化が示すとおり、市場環境や顧客ニーズの変化を察知し、柔軟かつ迅速に意思決定するスピード感も求められます。こうしたなかで競合優位性を保つためには、ジョブクラフティングの仕組みづくりをきっかけに、トップダウン型からボトムアップ型のマネジメントに変革することが必要です。
また、ジョブクラフティングを軸とする組織に変わる取り組みは、近年のビジネス環境で起こりやすい「若手の早期離職」や「慢性的な人材不足の問題」を解消するきっかけにもなるでしょう。
人事労務のアウトソーシングならラクラスへ
本記事では、ジョブクラフティングの定義や注目される背景、メリットなどを確認してきました。ジョブクラフティングの実践には多くの注意点があるため、人事部としても進めていくのはリソース面で負担に感じている方も多いのではないでしょうか。
もし人事業務における業務効率化をお考えであれば、ラクラスにお任せください。ラクラスなら、クラウドとアウトソーシングを掛け合わせた『BpaaS』により、人事のノンコア業務をアウトソースすることができコア業務に集中できるようになります。
ラクラスの特徴として、お客様のニーズに合わせたカスタマイズ対応を得意としています。他社では難色を示してしまうようなカスタマイズであっても、柔軟に対応することができます。それにより、大幅な業務効率の改善を見込むことができます。
また、セキュアな環境で運用されるのはもちろんのこと、常に情報共有をして運用状況を可視化することも心掛けています。そのため、属人化は解消されやすく「人事の課題が解決した」という声も数多くいただいております。
特に大企業を中心として760社86万人以上の受託実績がありますが、もし御社でも人事の課題を抱えており解決方法をお探しでしたら、ぜひわたしたちラクラスへご相談ください。