有給休暇の給与計算方法と注意点を徹底解説!取得促進の取り組みもご紹介
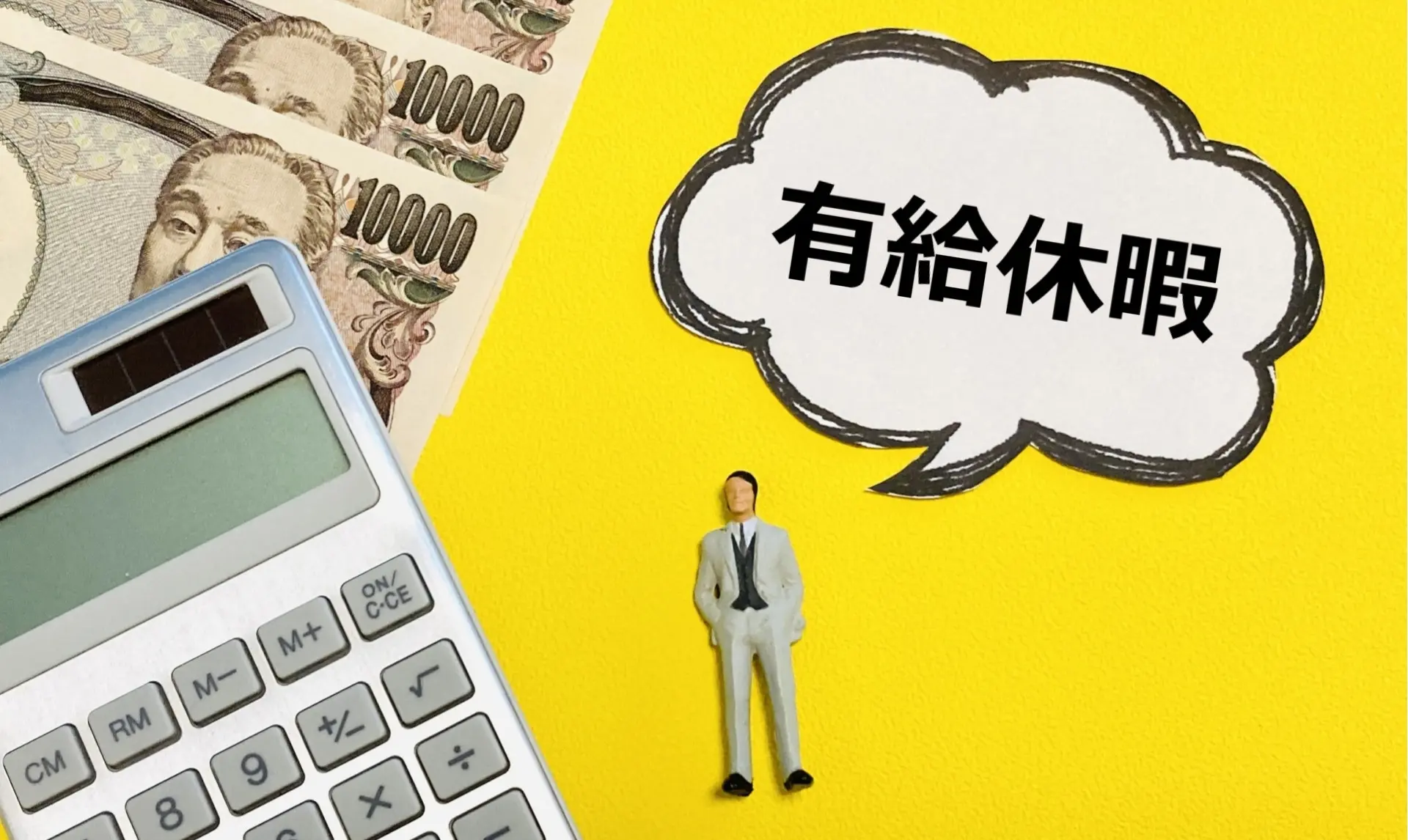
本記事では、有給休暇の概要を確認したうえで、「有給休暇取得日における3つの給与計算方法」をご紹介します。また、有給休暇の給与計算が間違っていたときの対処方法や、従業員の有給休暇取得を推進するための取り組みも解説してまいります。監修者:社会保険労務士 伊藤大祐
給与計算において、有給休暇は複雑な要素の一つです。有給休暇には複数の計算方法があることから、特に新任の担当者は、「どの計算方法を採用すべき?」と迷いやすい傾向があります。
そこで本記事では、有給休暇の概要を確認したうえで、「有給休暇取得日における3つの給与計算方法」をご紹介します。後半では、有給休暇の給与計算が間違っていたときの対処方法や、従業員の有給休暇取得を推進するための取り組みも解説してまいります。
これから給与計算の業務に携わるうえで、有給休暇取得日の取り扱い方や計算時のポイントを詳しく理解したい方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
有給休暇とは
そもそも有給休暇とは、労働基準法で規定された年次有給休暇のことです。
有給休暇は、一定期間勤続した従業員がゆとりある生活や心身の疲労回復をできるようにするために、「取得しても賃金が減額されない休暇」になります。
有給休暇の付与要件と日数
従業員に有給休暇が付与される要件は、以下の2つです。
|
(1)雇い入れの日から6か月経過していること (2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
|
この2つの要件を両方クリアすると、業種・業態に関係なくすべての労働者に10労働日の有給休暇が与えられます。また、最初に有給休暇が付与された日から1年が経過し上記(2)の要件をクリアした場合、11労働日の有給休暇が新たに与えられる仕組みです。
有給休暇の付与日数は以下の表のように増えていき、雇入れの日から起算した勤続時間が6年6か月以上で最大の20労働日が与えられます。

<引用>:年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。(厚生労働省)
<参考>:年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています<PDF>(厚生労働省)
有給休暇は取得が義務化された
2019年4月より、使用者である企業側が年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、有給休暇日数のうち5日について時季を指定して取得させることが義務付けられるようになりました。
ここでポイントになるのが、企業側が一方的に時季を指定して無理に休ませるのではなく、時季指定にあたっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めることが求められる点です。また、従業員が自ら申し出て取得した年次有給休暇
や、計画的付与によって取得した日数のうち、5日分までは、時季指定義務の対象から控除できます。
この時季指定義務は、企業規模にかかわらずすべての企業に適用されるものです。また、管理監督者を含むすべての労働者に適用されます。
有給休暇取得日の3つの給与計算方法
有給休暇の給与計算は、以下の3つのうちどの金額をベースにするかで算出方法が変わります。
| メリット | デメリット | |
| 1.通常の賃金を支払う | 従業員の理解を得られやすい | 支払い金額が他の計算方法より高くなりやすい |
|
2.労働基準法の平均賃金 |
支払い金額が少なくなりやすい | 手間がかかる |
|
3.標準報酬日額をもとに支払う |
あまり手間がかからない | 労使協定を締結する必要がある |
既存企業の場合、上記のいずれかがすでに選択されていて、その方法で有給休暇取得日の給与計算が行われていることになります。(ただし、「3.標準報酬日額をもとにする方法」は、労使協定の締結が前提となる特殊な運用方法ですので注意が必要です)
ここでは、上記3つの方法について、それぞれの計算式や具体例を紹介しましょう。
(1)「通常の賃金を支払う」場合の給与計算方法
「通常の賃金を支払う」のは、最も一般的な方法です。この方法のメリットは、従業員が有給休暇取得日も出勤日と同じイメージで給与を受け取れる点になります。
これに対してデメリットは、以下のように賃金の支払い方法ごとに計算式が変わるため、給与計算の複雑性や担当者の負担が増大しやすくなることです。また、ほかの2つの方法と比べて支払い金額が高くなりやすい特徴もあります。
ただし、月給の場合、下記の計算式で算出した金額を支払うことは少ないといえます。主に有給休暇を取得した分の賃金を控除しないことで結果として支給したかたちをとります。
|
《有給休暇を1日取得した場合の計算式》
|
特定の条件で「正社員とパート・アルバイトが有給休暇を1日取得した場合」について、どのくらいの有給休暇取得時給与額になるかを見てみましょう。
|
▼正社員(月給)
▼パート・アルバイト (時給)
|
この要件の場合、1日あたりの有給休暇取得時給与額は下記のようになります。
| 計算式 | 1日あたりの有給休暇取得時給与額 | |
| 正社員(月給) | 360,000円÷20日=18,000円 | 18,000円 |
| パート・アルバイト (時給) | 1,400円×6時間=8,400円 | 8,400円 |
なお、パート・アルバイトの場合、予定のシフト時間を1日の所定労働時間として計算します。
(2)「労働基準法の平均賃金を支払う」場合の給与計算方法
労働基準法の平均賃金とは、直近3か月の賃金総額を賃金計算期間の暦日数で割った金額のことです。
たとえば、月末締め・翌月20日払いの会社で働く従業員について、直近3か月の給与が以下の状況だったと仮定します。
|
|
この場合の平均賃金の額は、上記3か月の給与の合計額を、当該期間の暦日数で割ることで算出します。具体的には、以下のイメージになるでしょう。
|
(245,000円+255,000円+265,000円)÷92日=765,000円÷92日≒8,315.2円
|
有給休暇取得日の給与計算で平均賃金を使用する場合、上記の「原則的な方法」のほかに、最低保証額を算出する「例外的な計算方法」があります。一般的には、先述の方法と例外的な方法の2種類の計算を行い、額が高いほうを選択します。
「原則的な方法」と例外的な「最低保証額の計算方法」には、以下のような違いがあります。
|
|
有給休暇取得日の給与を平均賃金で支払う場合、月給の正社員、時給のパート・アルバイトとも、同じ考え方で計算することが可能です。以下のケースについて、計算例を見ていきましょう。
|
▼正社員(月給)
▼パートアルバイト・パートアルバイトタイマー(時給)
|
この要件の場合、1日あたりの有給休暇取得時給与額は下記のようになります。
| 原則の計算方法 | 最低保証額の計算方法 |
1日あたりの有給休暇取得時給与額 (高いほうを選択) |
|
| 正社員 | 1,080,000円÷92日≒11,739.1円 | 1,080,000円÷60日×60%=10,800円 | 11,739円 |
| パート・アルバイト | 400,000円÷92日≒4,347.8円 | 400,000円÷45日×60%≒5,333.3円 | 5,333円 |
「平均賃金」を使用すると、ほかの方法と比べて人件費をおさえやすくなります。ただし、給与の金額は従業員のモチベーションに影響しますので、その点は意識しなければなりません。また、詳細は後述しますが、1日あたりの有給休暇取得時給与額が最低賃金よりも低い場合、法律に抵触することになってしまいますので注意が必要です。
(3)「標準報酬日額をもとに支払う」場合の給与計算方法
標準報酬月額とは、健康保険・厚生年金の被保険者である従業員が受け取る報酬月額(毎月の給料など)を区切りの良い幅で区分したものです。健康保険の標準報酬月額は、全50等級、厚生年金の標準報酬月額は、全32等級に区分されています。
各従業員の標準報酬月額における区分は、以下の全国健康保険協会のサイトから確認します。給与明細で毎月引かれている健康保険料と「都道府県別の保険料額表」を照らし合わせてみてください。(協会けんぽに加入している企業で勤務している場合)
有給休暇取得日の給与計算に標準報酬日額を用いる場合、以下のように非常にシンプルな計算式で有給休暇1日あたりの有給休暇取得時給与額を算出することができます
|
【有給休暇1日あたりの給与額】標準報酬月額÷30
|
ではまた、特定の条件において正社員およびパート・アルバイトの有給休暇1日あたりの給与額を計算してみましょう。
|
▼正社員(月給)
▼パート・アルバイト
|
この要件の場合、1日あたりの有給休暇取得時給与額は下記のようになります。
| 計算式 | 1日あたりの有給休暇取得時給与額 | |
| 正社員 | 360,000円÷30=12,000円 | 2,000円 |
| パート・アルバイト | 98,000円÷30≒3,266.7円 | 3,270円 |
上記のアルバイト社員における1日の所定労働時間が5時間の場合、各都道府県の最低賃金を大幅に下回る可能性が高くなってしまいます。この場合、都道府県の最低賃金をチェックしたうえで、再計算や調整をする必要があるでしょう。
労働基準法を守るためには、1日あたりの有給取得時給与額を「最低賃金×1日の所定労働時間」よりも高くすることがポイントになります。
3つの方法における給与計算結果の違い
ここまで紹介した正社員の計算結果をまとめると、3つの方法のうちどれを選ぶかによって、金額面に以下のような開きが生じることが見えてきます。(※具体的な金額は、従業員の勤務実態などの影響を受けるものです。)
|
▼正社員(月給)
|
| 計算方法の種類 | 計算式 | 1日あたりの有給休暇取得時給与額 |
| (1)通常の賃金を支払う | 360,000円÷20日=18,000円 | 18,000円 |
| (2)労働基準法の平均賃金 |
【原則】1,080,000円÷92日≒11,739.1円 【最低保証】1,080,000円÷60日×60%=10,800円 |
11,739円 |
| (3)標準報酬日額をもとに支払う | 360,000円÷30=12,000円 | 12,000円 |
このケースについて上記の(1)(2)(3)を比べると、通常の賃金をベースとした「18,000円」が最も高くなることがわかります。
退職時の有給休暇の計算方法は?
退職を予定している従業員に有給休暇が残っている場合、すべて消化されることもあるでしょう。この場合も、先述の3パターン((1)通常賃金(2)平均賃金(3)標準報酬日額)のいずれかを使い給与計算を行うことになります。
ここで1つ注意点があります。それは、有給休暇は従業員の権利であるため、会社側が退職日までの有給消化を拒むことはできない点です。また、原則は有給の買い取りもできないことになっています。
しかし実際は、引き継ぎなどの都合で退職日までに有給休暇を消化できないこともあるでしょう。その場合は、退職日時点で未消化となった有給休暇を、その日数に応じた手当として支給することは法律上の問題はありません。
たとえば、9月20日に、ある従業員の月末(9月30日)での退職が決まったと仮定します。この従業員に未消化の有給休暇が15日残っていて、業務の引き継ぎなどを考慮すると退職日までに消化できる有給休暇日数が3日だとしましょう。この場合、12日分(15日-3日)を手当として支給できることになります。

有給休暇の給与計算における注意点
有給休暇に関連する勤怠管理や給与計算を行う際には、いくつか注意点があります。ここでは4つを挙げて解説していきましょう。
注意(1)都道府県ごとの最低賃金を下回らないようにする
最低賃金は、使用者が従業員に最低限支払わなければならない賃金の下限額です。仮に会社が支払う額が最低賃金以下だった場合、使用者にはその差額を支払うことが求められます。
また、支払う賃金が最低賃金を下回る場合、次のような罰金が課せられることがあります。
|
【最低賃金法】
【労働基準法】
|
注意(2)有給休暇と皆勤手当の関係を理解する
各社が定めた所定労働日数のうち、一定日数以上の出勤をした従業員に支給される制度が皆勤手当です。これは法律で定められたものではなく、各企業が独自に導入する制度になります。
皆勤手当を導入した場合に注意したいのが、有給休暇を取得した従業員に「皆勤手当の対象外とする」などの不利益を与えた場合、労働基準法附則第136条の違反になってしまうことです。労働基準法附則第136条では、以下のように定めています。
|
第百三十六条 使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
<引用>:労働基準法(e-GOV法令検索)
|
有給休暇の取得は、労働者の権利です。そこでもし会社が、皆勤手当を理由に有給休暇取得を妨げた場合、労働基準法の規定に抵触することになります。自社で皆勤手当などの独自制度を導入する場合は、有給休暇の取得希望者が萎縮しない仕組みにする必要があるでしょう。
なお、厚生労働省のホームページでも類似の事例について回答しています。興味がある方は、ぜひチェックしてみてください。
注意(3)有給休暇取得時における通勤手当の支給ルールを明確化する
通勤手当は、通勤に要する費用を支給するものです。有給休暇を取得した従業員は通勤していないわけですから、有給休暇取得日の通勤手当を不支給とすることは法律上問題ありません。
ただし、通勤手当として定期代を支給している場合、有給休暇取得の有無に関わらず「3か月に1回、3万円分の通勤定期を買う」といった形で従業員に金銭的な負担が生じることになります。そのため、このケースでは、有給休暇取得日分の電車代やバス代を控除することなく、そのまま支給することが自然な運用になるでしょう。
従業員の通勤手段ごとに通勤手当の支払いルールが異なる場合は、有給休暇取得時の考え方や支給方法を決めたうえで、就業規則(給与規程)に記載しておくことが重要です。
注意(4)有給休暇の管理そのものにミスやヒューマンエラーが生じることがある
従業員の有給休暇は、必ずしも予定どおりに取得できるとは限りません。たとえば、インフラ系の大事な業務でトラブルが起きたり、ほかの担当者が病欠になったりした場合、その日の取得を取り止めて出勤することもあるでしょう。
また、家の用事で午前中2時間だけ不就業となる予定だったのが、結局用事が終わらず、終日有給休暇になることもあるかもしれません。
このようなケースで「申請済みの有給休暇キャンセル」や「欠勤から有給休暇取得への申請変更」などが適切に行われていない場合、そのデータを取り込んだ給与計算で間違った結果を算出してしまう可能性がでてきます。
こうしたトラブルを防ぐためには、給与計算に大きな影響を与える勤怠管理においても、入力・申請・管理の適切なオペレーションを整備していく必要があるでしょう。
有給の給与計算が間違っていた時の対処とは
有給休暇に関する給与計算が間違っていた場合、最初に行うべきことは従業員への説明と謝罪です。それから、給与の再計算と給与明細の訂正・差し替えを行います。そして、最後に行うべきことが、過不足分の給与精算です。
精算では「給与支給の当月中に間に合うかどうか?」を判断基準に、3パターンのいずれかを選択することになります。各パターンのポイントを簡単に見ていきましょう。
(1)未払い・不足の場合(当月中に間に合うとき)
誤った給与計算で不足が生じたときは、賃金支払いの5原則に基づき、なるべく当月中に支払うことが重要になります。仮に当月中の支払いができない場合は、賃金支払いの5原則を定めている労働基準法第24条に抵触することになるので注意が必要です。
<参考>:賃金の支払方法に関する法律上の定めについて教えて下さい。(厚生労働省)
(2)未払い・不足の場合(当月中に間に合わないとき)
当月中の精算ができなくても、できる限り急ぐことには変わりません。その理由としては、以下の2つになります。
|
|
遅延損害金とは、給与を本来支払うべき日の翌日から発生する利息のようなものです。精算が遅れるほど、遅延損害金は膨らむことになります。遅延損害金の詳細については、以下の記事をチェックしてください。
給与計算でミスが発覚! 適切な対処方法とリスク、効果的な防止策を解説
(3)過払いの場合
仮に給与を過払いしていた場合、民法703条に基づき会社は従業員に対して給与の不当利得返還請求を行うことが可能です。ただし、従業員が過払いに気づかず既にお金を使ってしまっていて返還が難しい場合、対応が少し複雑になります。
たとえば、給与を支払った当月中の調整が難しい場合、翌月以降の給与から控除をする「調整的相殺」と呼ばれる手段が選択されることが多いでしょう。調整的相殺を行う際には、従業員への合理的配慮などが必要となります。
給与計算で不足・未払い・過払いが生じたときの対処方法についても、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
有給休暇の取得を促進する取り組み
有給休暇に関する人事部門の仕事には、給与計算のほかに取得率(消化率)を上げる取り組みがあります。近年では厚生労働省でも有給休暇取得の推進に力を入れており、以下のような広報を集中的に行っている状況です。
ここでは、有給休暇を取得しやすい環境をつくるために「人事部門が行える施策」の一例をご紹介しましょう。
施策(1)有給休暇を取得しやすい風土をつくる
日本企業のなかには、以下のような昔から続いてきた古い慣習や価値観の影響から、有給休暇の取得をはじめとする労働者の権利を行使しづらい傾向が少なからずあるようです。
|
|
有給休暇を取得しやすい環境をつくるためには、人事部門が新たな制度などを導入することとあわせて、上記のような古い風土・価値観を変えていくことが大切です。それはつまり、働く人の外側(環境)と内面(マインド)の両方に変化を起こすことになります。
社内の風土を大きく変えるためには、経営陣などの上層部から「有給休暇取得の重要性」や「メリハリある働き方をする効果」などを朝礼や研修でアナウンスしてもらうことも効果的です。また、部下が萎縮しない環境をつくるためには、上司も率先して有給休暇を取得したり、若手に取得を勧めたりする姿勢も必要となるでしょう。
有給休暇取得に関する独自の制度や取り組みは、経営陣~管理職~現場のマインドが変わってこそ高い効果を発揮するようになります。
施策(2)業務の属人化→標準化を目指す
特定の従業員しか業務内容を知らない「属人化」も、有給休暇取得が難しくなる要因です。
誰もがより良いタイミングで有給休暇を取得できるようにするためには、特定の人への依存をやめて、幅広い人が業務に従事できる「標準化」を目指す必要があります。たとえば、新人でもわかりやすいマニュアルを整備することも、標準化の第一歩になるでしょう。
人事部門のほうで促進のアナウンスやさまざまな施策を実施してもなかなか有給休暇の取得率が上がらない場合は、「現場に業務の属人化が生じていないか?」から確認していくのもよいかもしれません。
施策(3)従業員の有給休暇日数を可視化する
有給休暇の取得促進に関して適切なアプローチをするためには、「誰に何日の有給休暇が付与されていて、そのうち何日が消化されているか?」をリアルタイムでチェックできる仕組みがあることが理想です。
こうした仕組みがあると、たとえば、「第1営業部は今月8割の人が有給休暇をとっているのに、第2営業部は2割以下」といった気づきから、適切なところに適切なアプローチをかけやすくなります。また、有給休暇データの可視化は、取得を促す上司の声かけを後押しするものにもなるでしょう。
現在の組織に有給休暇日数を可視化する仕組みがない場合は、有給休暇管理機能がついた勤怠管理システムなどを導入するのもよいかもしれません。
給与計算のアウトソーシングならラクラスへ
本記事では、有給休暇の概要を確認したうえで、有給休暇取得日における3つの給与計算方法を紹介してまいりました。有給休暇の給与計算が間違っていたときの対処方法についてもお伝えしましたが、給与計算は人事担当者にとって大きな負担になると感じた方も多いと思います。
もし、給与計算のアウトソーシングを実現して人事業務を高品質化したいとお考えであれば、ラクラスにお任せください。ラクラスなら、クラウドとアウトソーシングを掛け合わせた『BpaaS』により、人事のノンコア業務をアウトソースすることができコア業務に集中できるようになります。
ラクラスの特徴として、お客様のニーズに合わせたカスタマイズ対応を得意としています。他社では難色を示してしまうようなカスタマイズであっても、柔軟に対応することができます。それにより、大幅な業務効率の改善を見込むことができます。
また、セキュアな環境で運用されるのはもちろんのこと、常に情報共有をして運用状況を可視化することも心掛けています。そのため、属人化は解消されやすく「人事の課題が解決した」という声も数多くいただいております。
特に大企業を中心として760社86万人以上の受託実績がありますが、もし御社でも人事の課題を抱えており解決方法をお探しでしたら、ぜひわたしたちラクラスへご相談ください。
この記事の監修者:社会保険労務士 伊藤大祐
社労士試験合格後、社労士事務所勤務を経て、ソフトバンクグループのシェアードサービス企業で給与計算業務に携わるとともに人事システムの保守・運用を担う。その後、人事業務のアウトソーシングサービスを提供する企業の立上げに参画。主に業務構築、システム運用に従事。
その他、人事領域以外のアウトソーシング企業等での勤務も経験し2019年に独立。
現在、人事・給与計算システムの導入支援を中心に社労士として顧問企業の労務面のサポートも行う。






