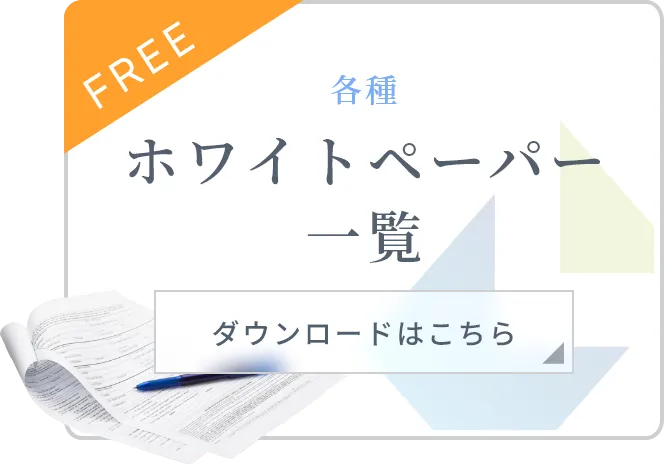年末調整の代行サービスとは? アウトソーシングできる業務や業者選びのポイントを6つ紹介

本記事では、年末調整における代行サービスの概要とアウトソーシングできる主な業務、メリットなどを紹介します。記事の後半では、実際に年末調整の代行サービスを選ぶ際にチェックしたい6つのポイントや料金相場も解説していきますので、人事給与部門の担当者の方は、ぜひ参考にしてみてください。
近年では、新卒採用の長期化や働き方改革などの影響から、人事給与部門の負担が増加しやすくなっています。こうしたなかで注目されているのが、『代行サービス』の活用を通じて年末調整による担当者負担を軽減する、というものです。
そこで本記事では、年末調整における代行サービスの概要とアウトソーシングできる主な業務、メリットなどを紹介します。記事の後半では、実際に年末調整の代行サービスを選ぶ際にチェックしたい7つのポイントや料金相場も解説していきます。
毎年発生する“年末調整”の負担を軽減したい人事給与部門の担当者の方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
年末調整の代行サービスとは
年末調整の代行サービスとは、人事給与部門が行う“年末調整の業務”を代行してくれるアウトソーシングサービスの総称です。まずは「年末調整業務の概要」と「法律の観点での年末調整代行サービスの正当性」について確認していきましょう。
年末調整の業務とは
年末調整は、給与から源泉徴収された「税額の年間合計額」と「実際の年税額」を一致させる精算手続きの総称です。
事業者は、毎月(毎日)の給与支払いをする際に、源泉徴収税額表にもとづき所得税および復興特別所得税の源泉徴収を行います。ただし、事業者が源泉徴収した1年間の税額(合計額)は、給与支払いを受ける本人の年間給与総額に対して納めなければならない年税額とは一致しないのが通常です。
そこで年末調整では、1年間に支払った給与総額が決まる年末に年税額を正しく計算しなおし、既に徴収した税額と過不足の差額を徴収もしくは還付する手続きを行います。
<参考>:令和6年分年末調整のしかた(国税庁)
年末調整の代行は違法にならないのか?
年末調整をアウトソーシングすることに関して、インターネット上では時に「年末調整の代行サービスは違法ではないか?」といった声が見受けられます。
結論からいうと、税理士が関わる年末調整の代行サービスであれば「合法」です。その理由は、年末調整には税理士にしかできない独占業務が含まれるからです。税理士法の第52条では、このことを以下のように定めています。
|
税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。 <引用>:6 税理士法違反行為 問6-1 非税理士により行うことが禁止されている税理士業務とはどのようなものですか。(国税庁)
|
これに対して、たとえば社会保険労務士には、年末調整に関する業務独占資格がありません。ですから、いつも給与計算などを委託しているからといって社会保険労務士に年末調整の代行をお願いすることは違法となります。
年末調整の代行サービスにアウトソーシングできる業務
年末調整の代行サービスでは、様々な業務を受託しています。ここでは、一般的にアウトソーシング対象となる業務を9つ挙げて解説していきましょう。(※実際の代行範囲は契約業者やプランによって異なります。詳細を知りたい方は、各社のホームページを確認するか、直接お問い合わせください。)
業務(1)年末調整システムの事前設定
年末調整の具体的な業務は、「紙申請」と「Web申請」で大きく異なってきます。そのため、年末調整の関連業務を代行業者がトータルでサポートする場合、Web申告システムの事前設定にも対応してもらえることが多いでしょう。
業務(2)年末調整開始の案内・各種申告書の発送
年末調整が「紙申請」の場合、申告に必要な申請書や案内などの一式を代行業者側で印刷・発送します。
一方で「Web申請」の場合は、対象者にWebシステム上での入力・申請をお願いすることから、代行業者はその案内をメールなどで送信するのが一般的です。
業務(3)従業員からの問い合わせ対応
証明書の取得や情報入力時には、以下のような問い合わせが発生しがちです。
|
「〇〇控除を受けるためには、どの申請書を使えばいいの?」 「〇〇画面の入力方法がわからない・・・」 「〇〇控除でも、控除証明書は必要になる?」 など
|
このような問い合わせがある場合、代行業者は電話やメールなどで対応します。
業務(4)申告書の回収、督促の連絡
アウトソーシングされる代行業者では、対象者に配布した各申告書類や控除証明書の回収も行います。回収時は、何らかの方法で受領確認するのが一般的です。
期日までに提出(申告)しない対象者には、督促の連絡も行います。提出者・未提出者のリストを作成し、企業担当者に情報を共有することも多くあります。
業務(5)申告書類のデータ化
「紙申告」の場合、各対象者から回収した申告書類と証明書の内容を専用システムに入力し、企業の給与計算システムで使う所得税の控除データを作成します。(※「Web申告」の場合は各対象者が自分で入力します)
また、給与システムのフォーマットに合わせてデータを加工することも可能です。
業務(6)申告書類と各種証明書のチェック
知識と経験を豊富に持つ担当者が、対象者から提出(申告)された情報や各証明書類のエビデンスを確認します。この際、些細な入力ミスなどは代行業者側で修正することもあります。
業務(7)不備・督促の連絡
期日までに提出しない対象者には、アウトソーシングされる代行業者が督促の連絡を行います。代行業者による連絡は、入力内容や添付書類に不備があった場合にも行われます。
業務(8)紙書類のファイリングと保管
回収済みの紙書類は、指定の方法で並び替えやファイリングしたうえで納品されます。なかには、紙書類の保管まで行える業者もあります。
業務(9)給与支払報告書や源泉徴収票の発送
代行業者のなかには、源泉徴収票や給与支払報告書などの仕分け・発送に対応しているところもあります。
年末調整の代行サービスを活用するメリット
アウトソーシングできる業務について見てきましたが、では年末調整の代行サービスを活用すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、3つを挙げて解説していきます。
メリット(1)担当者の負担を大幅に軽減できる
年末調整の代行サービスにおける最大の効果は、年末調整の業務にともなう担当者の負担を大幅に軽減できる点です。
年末調整には、書類の配布・回収・内容の確認・データの電子化……と多くの工程があります。また、従業員によって提出書類も異なるため、それを一つひとつ確認するのはかなりの手間になるでしょう。
そこで代行サービスを活用すれば、年末調整にともなう業務の大半を専門業者が担当者の代わりに実施してくれるわけです。たとえば、年末調整の対象者が30人いる場合、その従業員への案内や書類の配布、回収などを代わりにやってもらえることイメージすれば、かなりの負担軽減になることがわかるでしょう。
代行サービスの活用で年末調整にともなう負担が減ると、人事給与部門の担当者はコア業務に専念しやすくなるはずです。
メリット(2)申告ミスや漏れを予防できる
年末調整の業務では、確認すべき項目や必要書類がとても多くあります。
そのため、対象者が大勢いる場合には、担当者の負担が増えることで集中力が低下し、チェック漏れやミスが起こりやすくなるかもしれません。また、経験が少ない担当者にとっては、税金の計算方法や制度を理解するだけでも難易度の高い業務になるでしょう。
その点、アウトソーシングサービスを提供する企業は、年末調整や税金計算のプロフェッショナルである税理士と提携するなど、体制を構築している場合がほとんどです。年末調整の背景にあるさまざまな制度も熟知していますので、常に正しい数字での書類作成が可能となるでしょう。
【関連記事】年末調整の間違いに気づかないとどうなる?訂正方法や5つの“ミス防止対策”なども解説
メリット(3)業務の電子化を進めやすくなる
年末調整の代行サービスのなかには、業務の電子化が含まれているものがあります。
従来の年末調整は、対象者に紙の証明書を配布し、そこに必要書類などを入力してもらうアナログな方法が一般的でした。一方で近年は、担当者の負担を減らし業務効率化につなげる目的などから、国税庁でも年末調整手続きの電子化を推進するようになっています。
<参考>:年末調整手続の電子化に向けた取組について(国税庁)
また、最近のビジネス環境では、リモートワークの普及や働き方改革の影響から、従業員の働く場所も多様化し、従来と比べて紙書類の配布・回収も難しくなりました。
アウトソーシングとして請ける企業の体制にもよりますが、年末調整の代行サービスを利用することで業務の電子化が進み、時代に合った対応がしやすくなるでしょう。

年末調整の代行サービスを選ぶ際の6つのポイント
年末調整の代行サービスには、さまざまな機能があります。多くのサービスのなかから自社に合うものを選ぶうえで「どのアウトソーシング会社がよいのか」と迷ってしまうこともあるでしょう。ここでは、選ぶうえで重要なポイントを6つ挙げて、解説していきましょう。
ポイント(1)導入実績や効果はあるか
年末調整は、非常に複雑であるとともにミスや漏れが許されない業務です。
そのような業務を安心して任せられる委託先を選ぶうえでは、ホームページやサービス資料の内容を通して「どのような企業に対して、どのくらいの導入実績があるか?」を確認することが重要になります。
また、自社のニーズにマッチするサービスを選ぶためには、アウトソーシングの導入効果を確認する必要もあるでしょう。
ポイント(2)申告内容のチェックや問い合わせ対応まで可能か
次に確認するのは、アウトソーシングする委託先が「どこまでの代行に対応しているか?」です。
たとえば、委託先の代行範囲が「個人の控除データ作成のみ」の場合、紙の申告書配布・回収、データ内容のチェックといった手間のかかる業務は、従来どおり社内で行なう必要が出てきます。
年末調整による担当者の負担を大幅に改善したい場合には、代行可能な範囲がなるべく広いサービスを選ぶ必要があるでしょう。
ポイント(3)従業員の負担も軽減できる仕組みがあるか
年末調整は、従業員にとっても手間がかかることが多い手続きです。そこで年末調整の代行サービスを活用すれば、従業員の負担も軽減しやすくなります。
たとえば、Web申請に対応したサービスを選ぶと、リモートワーク中の従業員は申告書の情報入力を自宅でできるようになります。Web申請なら「申告書の用紙を取りに来てもらう」や「提出に来てもらう」といったオペレーションも不要になるのです。
このように従業員の負担を軽減できる仕組みがあれば、従業員の満足度も高まることになるでしょう。
ポイント(4)問い合わせ対応のためのカスタマーサポートはあるか
対象者からの問い合わせ対応も、人事担当者の大きな負担になるものです。また、代行サービスの導入で年末調整のやり方や流れが変わると、担当者と対象者のそれぞれに以下のような問題が生じやすくなります。
|
【対象者】操作方法などで不安や疑問点が増える 【担当者】操作方法などに関する問い合わせが増える
|
これらの問題を解消するうえでは、問い合わせ対応のためのカスタマーサポートがある代行サービスを選ぶことも重要です。経験豊富な代行業者が問い合わせ窓口を担当すれば、従業員も「問い合わせをしているのに、なかなか返事がこない……」といったストレスは生じにくくなるでしょう。
ポイント(5)業務フローや導入範囲等のカスタマイズはできるか
本当の意味での負担軽減を目指すのであれば、自社の業務フローに合った柔軟な対応やカスタマイズ、部分導入などができるサービスを選ぶことが理想です。
部分導入や柔軟性の高いサービスを導入すれば、新たなシステムに慣れるまでの時間を短くできたり、対象者の不満が生じにくくなったりと多くのメリットがあります。
また、カスタマイズが可能なサービスを活用することにより、企業側の導入・運用コストも削減しやすくなるでしょう。
ポイント(6)情報セキュリティに対する姿勢・仕組みはあるか
年末調整は、対象者本人と家族の個人情報を扱う業務ですのでセキュリティを重視する必要があります。
代行サービスを実施するアウトソーシング会社を選ぶ際は、システム面のセキュリティ機能に加えて、情報を取り扱うスタッフへの教育や体制整備などが的確に行われているかも確認する必要があります。
なお、情報処理関連の公益社団法人やNPO、自治体などのなかには、外部委託先を選ぶときに使える情報セキュリティのチェックシートを公開しているところもあります。
これらのシートは外部委託全般に使える汎用的なものですが、参考までに目を通しておいてもよいかもしれません。
<参考>:外部委託先に関するセキュリティ要件のチェックシート(埼玉県)
【おすすめの資料】システム?業務委託?もう悩まない!年末調整 関連サービスの選び方
年末調整の代行サービスの料金相場
アウトソーシング会社を選ぶポイントについて見てきましたが、続いては料金相場です。
年末調整の代行サービスの費用相場は、一般的に従業員1名あたり1,000円~3,000円ほどとされています。
ただし、自社の業務に合わせたカスタマイズや部分委託などの場合は、料金も変わってきます。また、アウトソーシング会社によっても料金体系は異なります。
年末調整代行サービスの利用を検討する場合は、各業者のホームページやサービス資料の確認をしたうえで、専用フォームなどから問い合わせをしてみるとよいでしょう。
問い合わせの際には、「必ず委託したい業務」や「自社ならではの業務フロー」などを事前に整理して伝えると、より具体的な返答や見積もりをもらいやすくなるはずです。
年末調整の代行サービスを活用する際の注意点
続いて、年末調整の代行サービスを活用する際の注意点を3つ挙げ、解説していきます。
注意点(1)主契約のほかに費用がかかることがある
年末調整の代行費用は、主契約のほかに費用がかかることがあります。
たとえば、年末調整の代行だけの対応はNGで、「給与計算とセット」や「顧問契約が前提」といった契約が求められるケースもあります。
そのため、代行サービスを導入する場合には「年末調整の業務に限定した比較検討」はもちろんのこと、「トータルでの契約内容」や「費用がどのくらいになるか」といった確認もしておいたほうがよいでしょう。
注意点(2)委託先は早めに選ぶ必要がある
年末調整の作業は、10月~翌1月にかけて行われるものです。そこで代行サービスを活用する場合、年末調整の準備が始まる10月までに以下のことを終わらせる必要があります。
|
|
なかには「サービスの申し込み受付は7月末まで」や「遅くとも8月末までに契約締結」としているアウトソーシング会社もあります。また、9月に入ると、申し込みが集中することで受託してもらえないこともあるかもしれません。
自社に合った業者と確実に契約を締結したいのであれば、半年前には委託先の選定や相談を開始したほうがよいかもしれません。
注意点(3)部分委託では課題・目的の明確化が特に重要となる
年末調整の業務を部分的に委託する場合、費用対効果を高めるためにも、現状の課題・目的を以下のように明確化しておくことが重要になります。
|
「申告書の回収と督促に、多くの工数がかかっている……」 「人事担当者は採用活動で不在が多いため、問い合わせ対応は必ずお願いしたい……」 「紙からWeb申告に切り替えたいが、システム導入や運用面で不安がある……」 など
|
年末調整の部分委託で使えるコストが限られている場合には、課題や目的に優先順位をつけることもポイントの一つです。そうすることで、代行業者への相談や見積もり依頼なども進めやすくなるでしょう。
年末調整の代行サービスならラクラスへ
本記事では、年末調整の代行サービスについて解説させていただきました。もし年末調整の手続きの負担を軽減したいとお考えでしたら、ぜひラクラスにご相談ください。
ラクラスの年末調整BPOサービスなら、必要な機能と業務をフルパッケージ化しています。また、カスタマーサポートも実施していますし、カスタマイズ対応も可能です。
AI-OCRとオペレーターの目視を組み合わせた読取代行により、品質と効率の両立を実現しており従業員は証明書の情報入力が不要になります。また、人事担当者の回収とチェックも必要ありません。
クラウドシステムはすべて国内で運用されており情報セキュリティも万全ですし、大企業向けに開発された様々な設定やオプションもご用意しています。導入を検討いただくうえで何かご不明点などありましたら、お気軽にご相談ください。

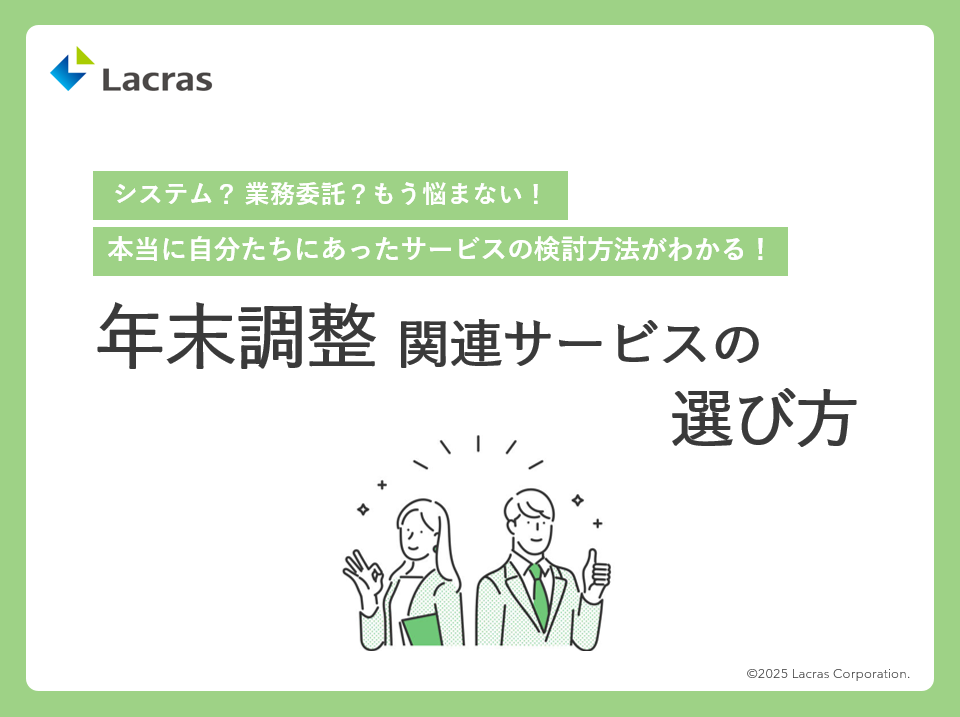
.png)