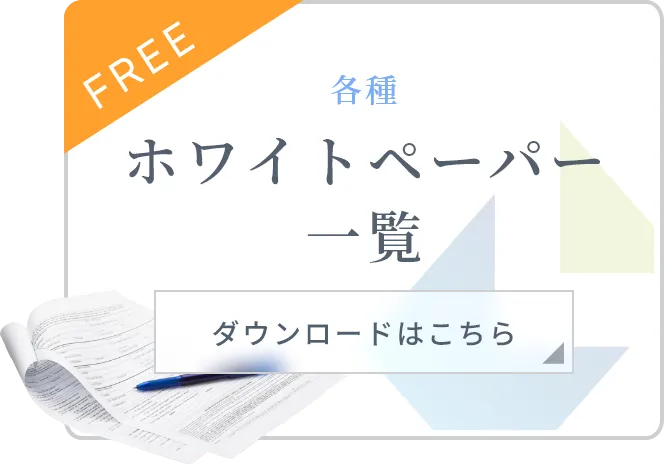年末調整の間違いに気づかないとどうなる?訂正方法や5つの“ミス防止対策”なども解説

本記事では、年末調整の担当者が間違いに気づかない場合に起こる問題や、気づいたときの対処方法などをパターン別に解説していきます。記事の後半では、「年末調整を間違えないために導入すべき対策」も紹介します。年末調整の間違い対策を検討されている方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
年末調整での間違いは、誰もがなるべく避けたいものです。しかし、年末調整の際には、担当者がチェックなどをしっかり実施していても、従業員側の事情で再計算などのやり直しが発生することもあります。
年末調整での間違いを防ぎ、期限までに計算や納税などの手続きを無事に終わらせるためには、「間違いにくい仕組み」や「間違ってもすぐに再調整できる対策」を講じることが重要になります。
そこで本記事では、年末調整の担当者が間違いに気づかない場合に起こる問題や、気づいたときの対処方法などをパターン別に解説します。記事の後半では、「年末調整を間違えないために導入すべき対策」も紹介していきます。
年末調整の間違い対策を検討されている方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
年末調整の間違いに気づかないとどんな問題が起きるか?
年末調整は、原則として「絶対に間違ってはいけないもの」です。担当者が誤った内容で申告・納税などの手続きを行い、そのことに気づかない場合、従業員および会社にはさまざまな問題が生じてしまいます。
ここではまず、担当者が年末調整の間違いに気づかず、すぐに再計算・再申告されなかった場合に起こる主な問題を確認していきましょう。
問題(1)従業員が支払うべき税金に過不足が発生する
年末調整は、給与所得者である従業員が「本来払うべき年税額」を再計算したうえで、給与から源泉徴収された「1年間の税額(合計額)」との調整・精算を行う手続きです。
そこで年末調整による申告内容に間違いがあると、「すでに源泉徴収された税額」と「本来払うべき年税額」に乖離が生まれることになります。その結果として起こりやすくなるのが、以下のような問題です。
|
・従業員が支払うべき税額に対して、会社の源泉徴収による納税分だけでは足りない状態になる ・不足分の申告と納税を従業員本人にしてもらう必要が生じる ・納めすぎた税金の還付が受けられなくなる など |
具体的なポイントは後述しますが、年末調整の間違いが放置された場合、お金と手間の両面で従業員に迷惑がかかってしまう可能性が高いでしょう。
<参考>:令和6年分 年末調整のしかた<PDFファイル>(国税庁)
<参考>:還付申告(国税庁)
問題(2)加算税や延滞税などが課せられる
「本来おさめるべき年税額」に対する「年末調整による申告・納税額」の不足や、手続きのミスで納付が行われない場合にペナルティとして延滞税・加算税が課せられる可能性が高くなります。
延滞税は、源泉徴収税が法定納期限までに納付されない場合に、納期限~納付するまでの日数に対してかけられる利息のようなものです。
令和3年1月1日以降は、原則として以下の割合で延滞税が課せられます。
|
【納期限までの翌日~2ヵ月を経過する日まで】原則として年7.3% 【納期限までの翌日~2ヵ月を経過した日以降】原則として年14.6% |
<参考>:延滞税について(国税庁)
これに対して加算税は、以下4つのうち要件に該当するものが課せられる可能性が高いでしょう。
|
【過少申告加算税】期限内申告について、修正申告・更正があった場合 【無申告加算税】①期限後申告・決定があった場合、②期限後申告・決定について、修正申告・更正があった場合 【不納付加算税】源泉徴収等による国税について、法定納期限後に納付・納税の告知があった場合 【重加算税】仮装隠蔽があった場合
<出典>:加算税の概要<PDFファイル>(財務省)
|
いまご紹介した延滞税と加算税は、いわゆる“行政罰”のようなものです。それに加え、事業主に以下のような問題があると判断された場合、所得税法第240条の違反でいわゆる“刑事罰”が科せられる可能性もあります。
|
【源泉徴収税の適切な徴収・納付が行われない場合】 10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金 |
|
【源泉徴収税の徴収自体をしていない場合】 1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金 |
<参考>:所得税法第240条(e-GOV法令検索)
ペナルティの具体的な内容については、国税庁の最新情報を確認してください。
<参考>:確定申告を間違えたとき(国税庁)
<参考>:【申告が間違っていた場合】(国税庁)
問題(3)業務の負荷が増えてしまう
詳細は後述しますが、年末調整の手続きに間違いが生じると、それを正しい内容に訂正して申告・納税するまでに、以下のように多くの作業が発生することになります。
|
・税務署とのコミュニケーション ・従業員本人とのコミュニケーション ・各種書類の訂正 ・再計算 ・再申告 ・精算 ・納税 など |
また、申告ミスで発生する延滞税は、利息のように日々増えていくものです。それらを最小限に抑えるためには、迅速な訂正対応が必要となります。
ただし、人事労務部門の仕事は「年末調整だけ」ではありません。
税務署からの通知によって、年末調整の再計算を最優先で行う必要が生じた場合、人事労務部門の大事な役割である「人材採用」「新人教育」「人事評価制度の設計」「労務管理」「人材配置」といった業務にも支障が出る可能性があるでしょう。
年末調整の間違いに気づく3つのパターン
年末調整の間違いに気づき、再申告をするための作業に入るまでの流れは、大きく分けて以下の2つです。
|
・社内の担当者もしくは従業員本人が間違いに気づく ・税務署からの指摘で間違いに気づく |
社内の担当者もしくは従業員本人が間違いに気づいた場合、再申告に向けた作業にすぐ入ることも可能です。ただし、再申告に向けてやるべき作業は、源泉徴収票の発行「前と後」で大きく異なります。したがってこの場合は、さらに2パターンに分かれるでしょう。
次に、税務署からの指摘がくるのは、対象年の翌8月以降になることが多いです。その理由としては、住民税の計算時期(5~6月)と税務署職員の人事異動(7月)の影響によるものといえます。
こうした背景から、年末調整の間違いに気づき訂正に入るまでの流れには、以下3つのパターンがあることが見えてきます。
|
(1)年末調整の担当者もしくは従業員本人が「書類の提出期限“前”(源泉徴収票の発行前)」に気づいた場合 (2)年末調整の担当者もしくは従業員本人が「書類の提出期限“後”(源泉徴収票の発行後)」に気づいた場合 (3)税務署からの指摘で間違いに気づいた場合 |
ここからは、これらの3パターンについて、年末調整の訂正(やり直し)に入るまでの考え方を確認しましょう。
(1)【期限“前”に間違いに気づいた場合】年末調整のやり直し対応
企業が社内で年末調整の修正を行えるのは、「翌年1月末日まで」かつ「源泉徴収票の発行前」までです。「翌年1月末日」というのは、給与支払報告書を市区町村に提出する期限になります。
ただし実際には、源泉徴収税の納付期限である1月10日(特例の場合は1月20日まで)を意識した対応が必要です。
その理由は、多くの場合、源泉徴収票の発行・交付も「翌年1月末日」を待たずに終えている可能性が高いからです。源泉徴収票を発行してしまうと、企業側でのやり直しはできません。
(2)【期限“後”に間違いに気づいた場合】年末調整のやり直し対応
給与支払報告の提出期限である「翌年1月末日が過ぎる」もしくは「源泉徴収票の発行を終えてしまう」の段階になると、企業側でのやり直し(修正・訂正)はできません。
そのため、この場合には翌年の2月16日~3月15日までの間に、従業員に自分で確定申告をしてもらう必要があります。
(3)【税務署から間違いを指摘された場合】年末調整のやり直し対応
税務署からの通知(指摘)がくるのは、前述したとおり翌年の夏以降となります。これは給与支払報告書などの提出期限である「翌年の1月末日」よりも遅い時期です。
ただし、企業には源泉徴収義務があります。
源泉徴収義務とは、従業員を雇って給与を払ったり、弁護士や税理士に報酬を支払ったりした場合に、支払金額に応じた所得税および復興特別所得税を差し引き、国に納める義務のことです。
税務署からの指摘の多くは追加徴収です。これは企業が「源泉徴収義務を果たしていないこと」への指摘ともいえるでしょう。
税務署から間違いが指摘された場合は、その時期が翌年の夏以降であっても、企業側で年末調整のやり直し対応を行い、源泉徴収義務を果たす必要があります。
<参考>:源泉徴収義務者とは(国税庁)
年末調整の間違いが発覚したときの正しい訂正方法
企業側で行う年末調整の訂正対応は、「源泉徴収票の発行前」と「税務署からの指摘後」で大きく異なります。ここでは、それぞれの訂正~再申告~納税までのポイントを確認しましょう。
【源泉徴収票の発行前】年末調整の訂正ポイント
「翌年1月末日まで」かつ「源泉徴収票の発行前」の場合、企業側での訂正(再調整)・再計算が可能です。基本的には、以下いずれかの対応になります。
|
【計算ミスがあった場合】 該当箇所に二重線を引き、再計算で算出された正しい情報を記載する。
【扶養親族などに変更があった場合】 対象従業員にヒアリング後、必要な書類を回収する。書類の内容にもとづき、正しい情報に訂正する。 |
【税務署からの指摘後】年末調整の訂正・再申告ポイント
税務署から指摘(通知)があった場合、以下の流れで訂正~再申告~納税までの作業を進めていきます。
(1)通知内容の確認
税務署から通知が届いたらすぐに内容を確認します。場合によっては延滞税などがかかっているため、年末調整の訂正対応は迅速に行うことが重要です。
(2)対象データの確認とヒアリング
通知に記載されている従業員のデータを確認し、担当者と対象従業員のどちらに問題があるかを切り分けましょう。
担当者のミスではないことが判明した場合は、従業員へのヒアリングをすぐに行います。ヒアリングを通して従業員本人の申告漏れなどが判明した場合は、正しい内容の必要書類を提出してもらうことになります。
(3)年末調整の再計算と納付
必要書類を回収したら、正しい情報での再計算と精算を行います。申告済みのデータと今回の結果で還付・追徴になることが判明した場合、過不足額のみを現金もしくは振込で精算します。
従業員に対しては、それ以降に支払う給与から順次精算することも可能です。この場合、給与もしくは賞与の控除項目に年末調整の差額精算をするための項目を用意し、還付・追徴の金額を反映する必要があります。
<参考>:年末調整後に給与の追加払や扶養親族等の異動があった場合の再調整<PDFファイル>(国税庁)
なお、過不足額の精算方法は、国税庁でも公開しています。具体的なやり方やポイントを確認したい方は、必ずチェックしておきましょう。

年末調整で間違いが起こりやすい項目と訂正ポイント
年末調整の場合、間違いが起こりやすい項目はある程度決まっています。再計算をなるべく早く終わらせるためにも、以下の3つの項目への訂正方法は押さえておいたほうがよいでしょう。
(1)扶養親族が変更になった場合
たとえば、従業員に以下のようなライフイベントがあった場合、扶養家族の人数に変動が生じているかもしれません。
結婚 / 出産 / 離婚 / 再婚 / 同居の家族の死去 /
引っ越し(親などとの同居・別居に伴うもの)など
ただし、特定の人が扶養親族になるためには、以下の4要件すべてに該当する必要があります。
|
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2)納税者と生計を一にしていること。 (3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) (4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
<参考>:扶養控除(国税庁)
|
たとえば、ある従業員の1年間に結婚・出産・引っ越しのライフイベントがあった場合、従業員本人は「どこからどこまでの人が扶養親族になるのか?」などを認識していないこともあるかもしれません。
従業員のライフイベントに変化が生じたときには、丁寧なヒアリングを通じて「適切な扶養家族の情報」を把握する必要があるでしょう。
なお、扶養家族の変動時に訂正するのは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。年末調整を紙で運用をしている場合は、当該箇所に二重線を引き、線の上下に修正内容を書き込んでもらいましょう。扶養控除申告書の異動事由欄に書き込む方法でも問題ありません。
上記の方法で訂正できるのは、「従業員に源泉徴収票を交付する前」もしくは「翌年1月末日まで」になります。
<参考>:年末調整後に給与の追加払や扶養親族等の異動があった場合の再調整<PDFファイル>(国税庁)
(2)保険料控除や住宅ローン控除を修正する場合
保険料控除や住宅ローン控除の内容を、訂正もしくは追加申告するケースです。控除の記載内容を訂正する場合は、保険料控除申告書の当該箇所に二重線を引いて正しい内容を記載します。
年末調整後に保険料の支払いがあった場合、源泉徴収票の交付前(翌年の1月末日まで)であれば、保険会社から発行された書類(保険料控除申告書)を確認したうえでの訂正が可能です。場合によっては、年末調整後の翌年1月末日までに保険料を支払い、証明書類を提出する前提で、年末調整が行われることもあります。
この場合、12月に年末調整を実施した段階では、証明書類がありません。当該従業員が期日(翌年の1月末日)までに証明書類を提出しない場合は、書類がない分を差し引いた金額で再計算を行い、不足分を徴収する形をとります。
なお、保険料や住宅ローンなどの控除は、本人に確定申告してもらう方法でも申告可能です。確定申告をお願いする場合、申告期間のアナウンスをしてあげるとよいでしょう。
<参考>:年末調整後に給与の追加払や扶養親族等の異動があった場合の再調整<PDFファイル>(国税庁)
(3)従業員本人や配偶者の年収に変更がある場合
基礎控除や配偶者(特別)控除は、本人もしくは配偶者の年収の影響を受けるものです。たとえば、配偶者の年収が大幅に増え、いくつかのボーダーラインを超えた場合、配偶者控除が受けられなくなる可能性があります。
ただし、配偶者の年収は、前述した保険加入や住宅ローンの利用などと比べて、企業側では把握しづらい情報となります。年収情報のチェック漏れを防ぐためには、以下の項目について従業員ごとに比較できる一覧表を作っておくこともおすすめです。
|
・収入金額 ・所得の確定金額 ・所得の見積金額 |
これらの項目を比較できる表を「所得の確定金額」が高い順に並び替えたうえで、「所得の確定金額」と「所得の見積金額」に配偶者特別控除の区分をあらわす記号を入れておくと、再申告の可能性が高い従業員の抽出がしやすくなるでしょう。
<参考>:配偶者特別控除(国税庁)
<参考>:年末調整後に給与の追加払や扶養親族等の異動があった場合の再調整<PDFファイル>(国税庁)
<参考>:令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書<PDFファイル>(国税庁)
年末調整で“納付額が過大”な間違いが生じたときの対処方法
税務署から年末調整の間違いが指摘されるのは、多くの場合「会社の源泉徴収税が納税不足であるとき」です。一方で、計算ミスなどで納税額が過大になった場合、年末調整の再計算によって還付を受けるかどうかは任意となります。
仮に計算ミスで対象従業員から多くの源泉徴収税を徴収してしまい、その分を本人に現金で支払った場合、次の2つの方法のいずれかを選択して還付を受けることが可能です。
1つ目のシンプルな方法は、納税地の所轄税務署長に「源泉徴収税の誤納額還付請求書」を提出し、還付を直接受けるものです。
2つ目として、給与所得に対する源泉徴収税の場合、納税地の所轄税務署長に「源泉徴収税の誤納額還付請求書」を提出し、誤納額が生じた日以降の源泉徴収税から控除してもらう方法も選択できます。
<参考>:源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求 (国税庁)
<参考>:年末調整の過不足額の精算(国税庁)
年末調整で間違いに気づかない状況を防ぐための対策
ここまで紹介したとおり、年末調整の間違いを訂正する作業は、担当者および従業員に多くの負担をもたらすものです。年末調整の間違いを防ぎ、仮に間違いが生じたときにも迅速な修正対応を行えるようにするためには、いくつかの準備や対策を講じておくことが重要になります。
ここでは、代表的な5つの対策と各ポイントについて紹介しましょう。
対策(1)早めに書類を配布する
担当者および対象従業員の確認漏れなどを防ぐためには、余裕をもったスケジュールのなかで年末調整を進めることが必要です。
なかでも特に重要になるのは、対象従業員に対して早めの書類の配布を行うことです。自社の年末調整が専用ソフトウェアで運用されている場合は、入力開始のアナウンスを早めに行うようにしましょう。
時間的な余裕がたくさんあれば、注意事項の丁寧な確認や、疑問が生じたときの問い合わせなどにも時間をかけやすくなるでしょう。
対策(2)基本情報の変更やライフイベントの報告を周知しておく
扶養親族の変更を早く適切に行うためには、以下のようなライフイベントが生じたときに、人事担当者に報告してもらうルールを導入することも必要です。
結婚 / 出産 / 離婚 / 再婚 / 同居の家族の死去 /
引っ越し(親などとの同居・別居に伴うもの)など
このルールによってライフイベント報告が集まるようになると、その情報を一覧表で管理して年末調整手続きに役立てることも可能となります。
対策(3)担当者の知識レベルを上げる
限られた期間のなかで効率的かつ適切な年末調整を行うためには、担当者の知識レベルを上げることも必要です。豊富な知識と経験があれば作業時間も短くなり、心身の疲れ等によるチェックミスも起こりにくくなるでしょう。
担当者の知識・経験が豊富であれば、不明点の問い合わせをする従業員側にもストレスが生じにくくなるはずです。
【関連記事】年末調整業務の進め方ガイド|担当者がやるべき手続きの流れや必要書類の種類などを解説
対策(4)複数人でチェックする体制を整備する
いわゆる“ヒューマンエラー”を防ぐためには、年末調整の全業務を1人の担当者に任せるのではなく、複数のメンバーが少なくとも2回の確認をするダブルチェック体制の整備も必要です。
特に年末調整の主担当が新人や若手の場合、ミスと不安の両方を解消する仕組みとしてもダブルチェックの導入は必須になるでしょう。
対策(5)年末調整の電子化を進める
近年では、働く場所や働き方が多様化するなかで、国税庁でも年末調整の電子化を推進するようになりました。年末調整の電子化によって専用ソフトウェアを導入すると、さまざまな数字が自動計算されることになります。この場合、控除額の検算は不要です。
また、専用ソフトウェアでは、おかしな情報の入力時にエラーが表示されることから、紙の運用で生じていた「字が汚くて読み取れない」や「数字項目に漢字が入っている」などの問題も起こらなくなるでしょう。
年末調整の代行サービスならラクラスへ
本記事では、年末調整の間違いに気づかないとどうなるのかを解説させていただきました。さまざまな対策もご紹介しましたが、もし「年末調整の手続きをミスなく確実に進めていきたい」とお考えでしたら、ぜひラクラスにご相談ください。
ラクラスの年末調整BPOサービスなら、必要な機能と業務をフルパッケージ化しています。また、カスタマーサポートも実施していますし、カスタマイズ対応も可能です。
AI-OCRとオペレーターの目視を組み合わせた読取代行により、品質と効率の両立を実現しており従業員は証明情報の入力が不要になります。また、人事担当者の回収とチェックも必要ありません。
クラウドシステムはすべて国内で運用されており情報セキュリティも万全ですし、大企業向けに開発された様々な設定やオプションもご用意しています。導入を検討いただくうえで何かご不明点などありましたら、お気軽にご相談ください。


.png)