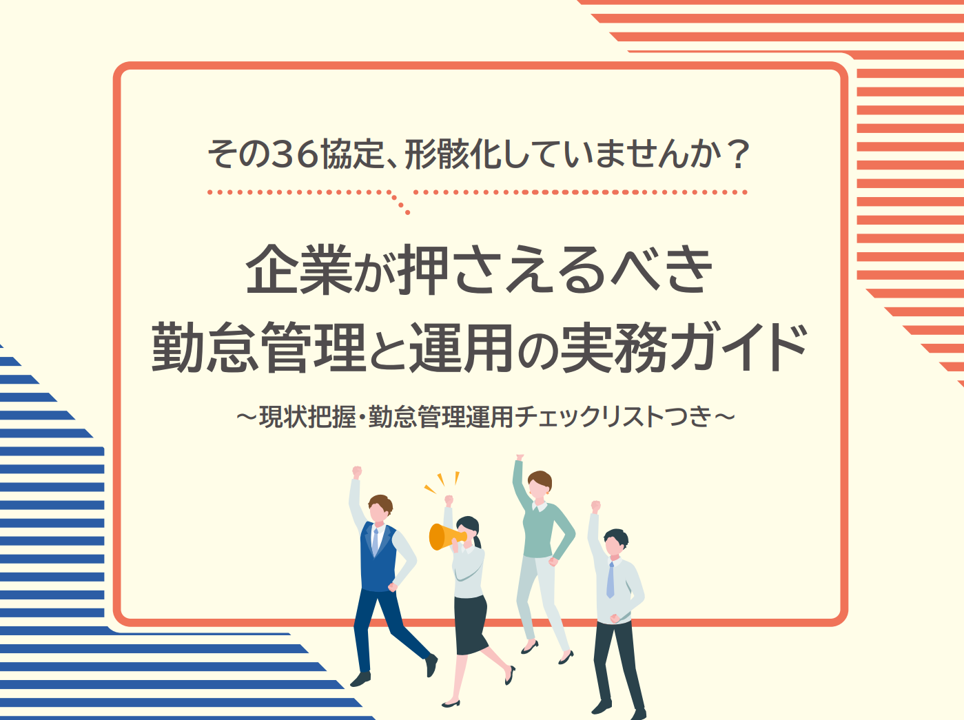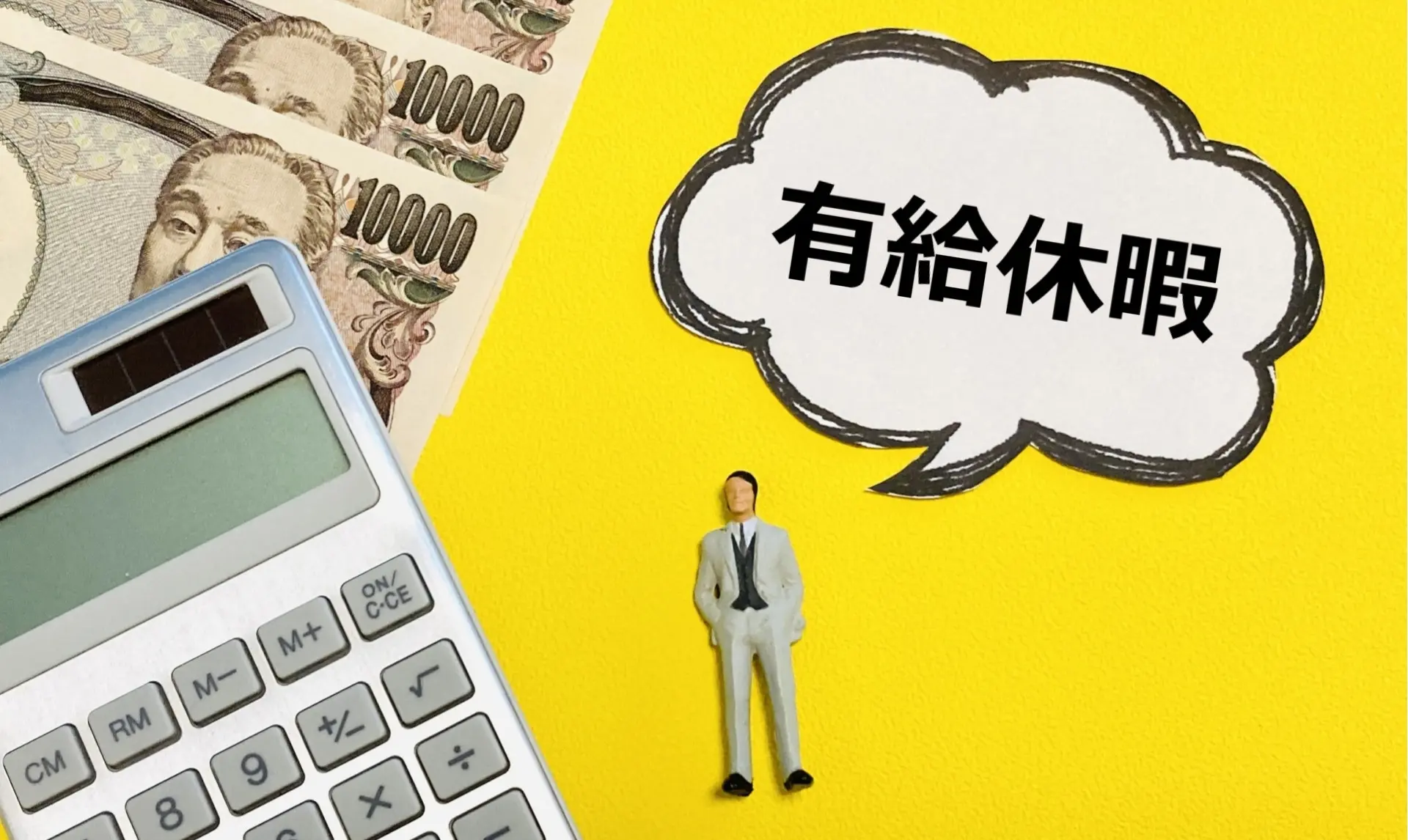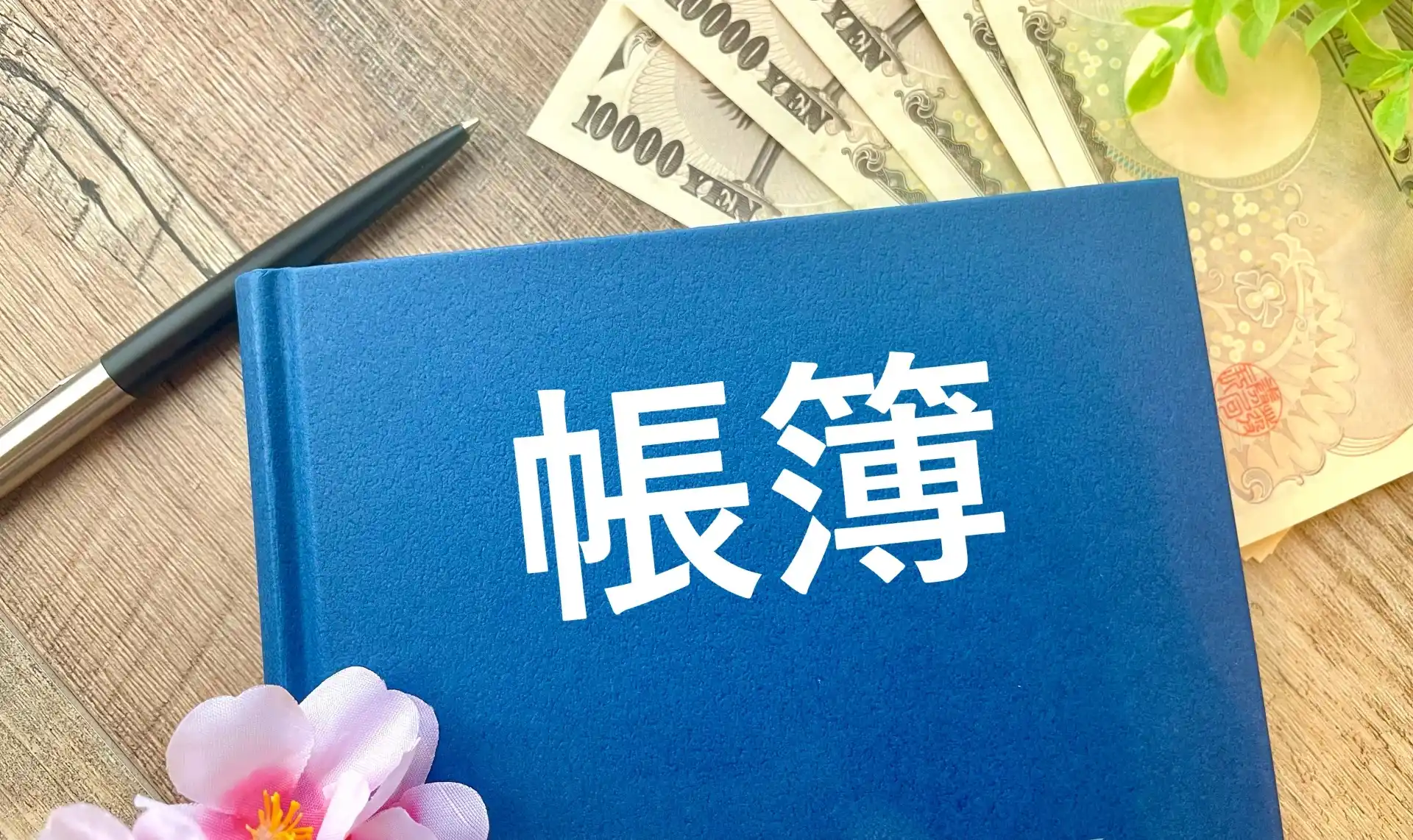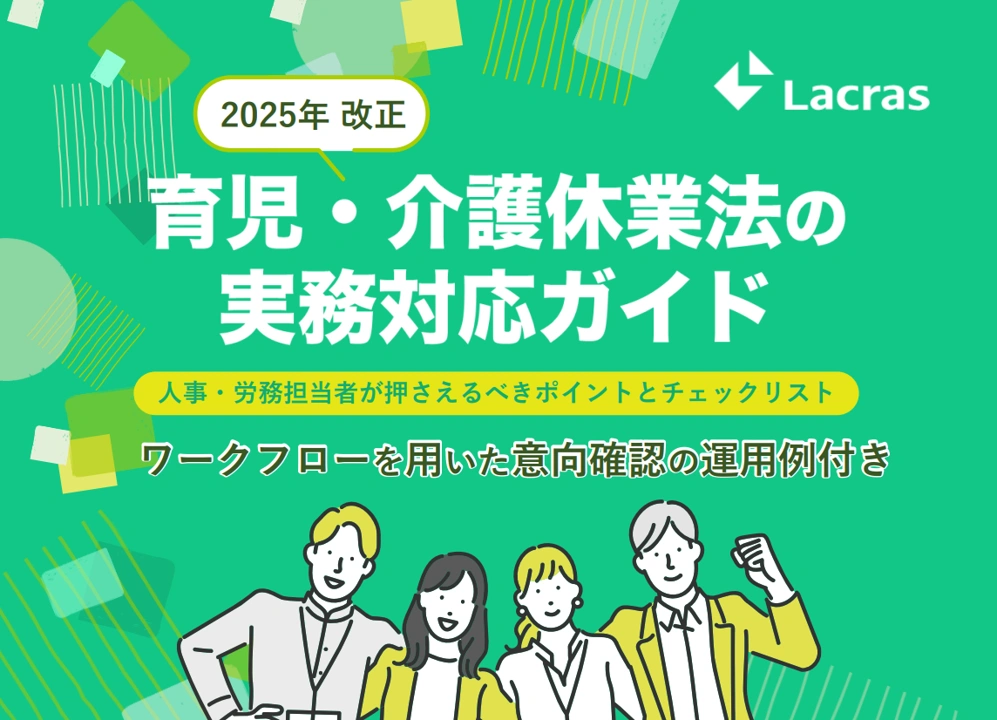36協定の特別条項とは?罰則付き上限時間の詳細と締結手続きのポイントを解説

本記事では、特別条項付き36協定について、概要や意義、2019年4月より施行された罰則付き上限規制の具体的内容などを解説します。また、適切な労務管理を行うことの重要性なども触れていきます。これから社内で特別条項付き36協定の締結を検討している方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
企業活動をするなかで大きなトラブルが生じた場合、その業務を担当する従業員に事態が収束するまでの間、労働時間を増やしてもらう必要がでてくることがあります。こうしたケースの備えとしては、『特別条項付き36協定』を定めるのが一般的です。
そんな36協定の特別条項には、2019年4月から罰則付き上限規制などの新ルールが設けられるようになりました。(※中小企業への適用は2020年4月)こうしたなかで適切な特別条項付き36協定の締結および労務管理をするためには、法律知識をしっかり理解する必要があります。
そこで本記事では、特別条項付き36協定について、概要や意義、2019年4月より施行された罰則付き上限規制の具体的内容などを解説します。記事の後半では、実践編として特別条項付き36協定の締結方法や、この協定が発動されるなかで適切な労務管理を行うことの重要性なども解説していきます。
これから社内で特別条項付き36協定の締結を検討しているとか、この協定の発動で時間外労働や休日労働が増えるなかで安全配慮義務を守っていきたいと考えている方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
36協定の特別条項とは?
基本概念を理解しよう
36協定の特別条項を遵守し適切な労務管理を行うためには、「36協定がどういうものか?」を理解したうえで、特別条項の意義や設けられた背景などを知ることが重要です。
ここでは“36協定の特別条項”における基本概念として、36協定の概要と目的を確認していきましょう。
36協定の概要と目的
36協定とは、労働基準法第36条にもとづく労使協定のことです。
労働基準法にもとづく労働時間は、原則として法定労働時間(1日8時間・週40時間)の範囲内におさめる必要があります。
しかし、企業がビジネスを行うなかでは、繁忙期やトラブル対応などを理由に、法定労働時間を超える時間外労働(残業)および休日労働を労働者に求めざるを得ないケースもあるでしょう。36協定は、こうしたケースが想定される場合に締結されるものです。
企業は、労働者の代表もしくは労働組合と36協定を締結し、労働基準監督署に届出をしてはじめて、法定労働時間を超えた時間外労働や休日労働を労働者に求められる状態になります。
逆にいえば、36協定を締結・届出をしなければその会社の労働時間は「法定労働時間の範囲内」に制限されます。その状況で従業員に残業や休日出勤を求めた場合には、労働基準法の違反になってしまうでしょう。
36協定のこうした特徴から、厚生労働省では36協定を「時間外・休日労働協定」とも呼んでいるのです。
<参考>:36(サブロク)協定とは(厚生労働省)
36協定の特別条項とは
36協定の特別条項とは、企業が事業活動をするなかで、後述する「特別な事情」が生じたときに適用される労使協定のことです。
具体的には、36協定で設定できる時間外労働の上限(限度時間)「月45時間・年360時間」を超えた時間外労働・休日労働を求めることが可能になるもので、一般的に、「特別条項付き36協定」と呼びます。
36協定の特別条項における
「臨時的かつ特別な事情」とは
特別条項付き36協定は、いつでも自由に発動できるものではありません。労働基準法第36条第5項では、特別条項を発動できる「臨時的かつ特別な事情」について、以下のように定めています。
|
第一項の協定においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。
<引用>:e-Gov 法令検索|労働基準法
|
上記の内容を平易な言葉であらわすと、「全体として1年の半分(6ヵ月)を超えない一定の限られた時期において、突発的・一時的に仕事量が増えるなどの状況から限度時間を超えた時間外労働および休日労働が必要となるケース」ということでしょう。
具体的な要件は、企業の人員数および事業状況などの影響を受ける形になりますが、一般的には、以下のような事態が生じたときに、特別条項の発動が認められるケースが多いです。
|
|
なお、岐阜八幡の労働基準監督署が公開する以下の資料では、新型コロナウイルス感染症の影響で仕事を休む従業員が増えて、残りの従業員だけで働くことになった場合について解説しています。資料によれば、そのことが36協定に明記されていなくても一般的には「特別条項の理由として認められる」ようです。
<参考>:新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた適切な労務管理<PDF>(岐阜八幡労働基準監督署)
36協定の特別条項の意義と必要性
36協定の特別条項は、先述の「発動が認められるケース」でも触れたとおり、企業活動を続けるうえで絶対に乗り越えなければならないトラブル対応などをするうえで、非常に重要な役割を担う制度です。
また、2019年から続いたコロナ禍や想定外の自然災害などが生じるなかでは、労使の合意にもとづく特別条項があることで看護師や介護士といったエッセンシャルワーカーが稼働できる時間が増え、地域社会の医療・福祉などが守られるという側面もあるでしょう。
そういった意味で36協定の特別条項は、企業のステークホルダーにとっても重要な意味を持つ制度の一つです。しかし、実際に働く従業員の健康を守るためには、国が定めた罰則付き月上限を意識した内容にする必要があります。
ここからは、36協定における特別条項のさらに細かな要件や上限規制などのルールを詳しく見ていきましょう。
36協定の特別条項における上限時間
まず、36協定の特別条項が発動されると、一般の36協定の上限である「月45時間・年360時間」の限度時間を超えた時間外労働・休日労働を求めることが可能です。
ただし、2019年4月より36協定で定める時間外労働に「罰則付きの上限」が設けられるようになりました。臨時的な特別の事情により特別条項を発動する場合も、企業側では以下の①~④のすべてを意識した労務管理を行う必要があります。
| 時間外労働 | 時間外労働と休日労働の合計 |
| ①年720時間以内 | ③ 月100時間未満 |
| ②月45時間を超えられるのは、 年6ヵ月が限度 |
④「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か⽉平均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内 |
<出典>:
時間外労働の上限規制|わかりやすい解説<PDF>(厚生労働省)
上記内容の一部を要約すると、企業側では特別条項の有無に関わらず、1年を通して常に時間外労働と休日労働の合計を「月100時間未満」「2~6ヵ月平均80時間以内」にしなければならないということです。
また、時間外労働が45時間以内に収まり特別条項にならないケースであっても、たとえば「時間外労働が35時間、休日労働が65時間」のように合計が月100時間以上になると、それは労働基準法違反です。
36協定および特別条項のルールに違反した場合、罰則として30万円以下の罰金もしくは6ヵ月以下の懲役が科せられる可能性があります。
注意しましょう。
<参考>:
時間外労働の上限規制|わかりやすい解説<PDF>(厚生労働省)
特別条項付き36協定の締結手続きにおけるステップ
特別条項付き36協定は、一般の36協定と同様に労使間での合意と労働基準監督署への届け出などの手続きを経てはじめて発動できる状態になるものです。社内ですでに36協定が締結されていて、そこに特別条項の規定を加える場合には、定期的な更新手続きに近いイメージで作業を進めることになるでしょう。
ここでは、新任の人事担当者向けに「特別条項付き36協定を締結するための基本的なステップ」を解説していきます。
ステップ(1)労働者の代表を選出する
36協定は、「使用者」と「労働者の代表」が締結するものです。労働者の代表とは、以下のいずれかになります。
|
(1)労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合 (2)上記(1)の労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者
<引用>:
|
(2)については、「民主的な方法で選出された者であること」という要件があります。いわゆる“管理監督者”に該当する人は、仮に労働者の信任が得られても「労働者の代表」になることはできません。
厚生労働省の資料では、過半数代表者の選任にあたり留意すべきポイントを以下のように記載しています。
|
<引用>:
|
ステップ(2)
労使間での協定内容に関する話し合い
特別条項付き36協定の内容について、労働者の代表と話し合いをしていきます。労使間交渉や協議における大切なポイントは、必要な情報を可能な限り提供したうえで誠実かつ建設的な話し合いをすることです。
特別条項の場合、時間外労働や休日労働が中長期的に続くわけではないにせよ、労働者の心身の負担になることは否めません。また、多くの従業員に疲労や心身の負担が蓄積して現場にさらなるトラブルが生まれるようでは本末転倒です。
「臨時的かつ特別な事情」のなかで発動する特別条項の内容を決める際には、会社としての希望や理想を押し通すのではなく、実際にその働き方をする労働者側の意見に耳を傾けたうえで、お互いの合意点を見つけていく姿勢が求められるでしょう。
なお、労使間の話し合いで決めるべき内容は、「一般の36協定(一般条項)」と「限度時間を超える場合(特別条項付き36協定)」で以下のように大きく異なります。
|
【一般の36協定(様式第9号)】
<引用>:
|
|
【限度時間を超える場合(様式第9号の2)】
<引用>:
|
ステップ(3)
合意内容の書面化と特別条項付き36協定の作成
労使間での協議が終了したら、合意した内容で労使協定書を作成します。そこには、使用者と労働者の代表それぞれの署名または記名押印も必要です。
特別条項付き36協定の場合は、先述のとおり「様式第9号の2」という様式に労使間で決めた内容を記載していきます。
なお、厚生労働省では以下のようにわかりやすい記載例を公開しています。特別条項付き36協定の書き方については、ぜひ以下を参考にしてください。

<引用>:36協定届の記載例(特別条項)<PDF>(厚生労働省)
様式第9号の2の記入用紙は、以下のページからダウンロードすることができます。
<参考>:主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)(厚生労働省)
ステップ(4)労働基準監督署への届け出
特別条項付き36協定を作成したら、労働基準監督署に届け出を行います。届け出方法としては、以下の3つが用意されています。
|
(1)窓口での届け出 (2)郵送での届け出 (3)電子申請(e-Gov)による届け出
|
具体的な届け出方法や必要書類については、厚生労働省の資料に記載されていますのでご確認ください。
<参考>:届出方法について(36 協定届)-窓口または郵送で届け出る場合-<PDF>(厚生労働省 福岡労働局)
<参考>:労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について(厚生労働省)
なお、36協定の場合、効力発生日までに労基署へ届出が必要です(遡及適用は不可)。協定の効力開始日に発動できるようにするために、開始日を意識した届け出が必要でしょう。
労働基準監督署への届け出が受理されると、受付印が押された控えが戻されます。電子申請の場合は、受付通知がその代わりになります。
ステップ(5)従業員への周知
特別条項付き36協定の内容は、必ず従業員に周知しなければなりません。
ここでのポイントは、就業規則と同様に全従業員が閲覧できる状態にすることです。周知を怠った場合、労働基準法第106条の違反で30万円以下の罰金になる可能性がありますので注意しましょう。

特別条項付き36協定と
適切な人事労務管理のポイント
特別条項付き36協定は、期限までに完了させなければならない重要業務や大規模トラブル対応などが起こり、一般の36協定のルールを超えた時間外労働や休日労働が必要な場合に発動されるものです。
それは会社にとって「やむを得ない状況」かもしれません。しかし理由がどうであれ、時間外労働や休日労働が増えることで、従業員の心身に負担が生じる可能性は否めないでしょう。
こうしたなかで企業側では、厚生労働省が公開する「36協定の締結に当たって使用者が留意すべき事項」などを参考にしながら、適切な人事労務管理を実施していく必要があります。
<参考>:36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針<PDF>(厚生労働省)
ここでは、特別条項付き36協定を締結した企業が配慮すべき人事労務管理のポイントを見ていきましょう。
ポイント(1)臨時的に限度時間を超えて労働する事由を具体的に定める
特別条項付き36協定を設ける場合、発動事由となる「臨時的な特別な事情(事由)とはどういうものか?」をなるべく具体的に定める必要があります。また、その事由を考えるうえでは、「恒常的な長時間労働を招く恐れがないか?」を見極めることも大切です。
たとえば、ここまでに何度か紹介してきた厚生労働省の資料にもあるように「予算、決算業務」や「大規模クレームへの対応」などは、一般的には臨時的であり適切な事由でしょう。
<参考>:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説<PDF>(厚生労働省)
これに対してたとえば、慢性的な人手不足やマネジメント不能などの背景から、限度時間の超過が年6回以上も生じる可能性がある場合、人員の配置から見直す必要があるかもしれません。
特別条項付き36協定を発動する可能性のある事由を明確にすることで、その状況が「限度時間の超過で対応できるものか?」「根本原因から解決すべきか?」の見極めもしやすくなるでしょう。
ポイント(2)
時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめる
特別条項付き36協定を締結しても、従業員の負担を考えれば、時間外労働および休日労働は必要最小限にとどめる必要があります。これは、使用者には労働者に対する安全配慮義務を負う責任があるからこそ留意すべきポイントでしょう。
なお、厚生労働省の資料では、1週間あたり40時間を超える労働時間が月45時間を超えて長くなるほど、脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まるとしています。さらに、1週間あたり40時間を超える労働時間が月100時間または2~6ヵ月平均で80時間を超える場合も、脳・心臓疾患の発症との関連性が強くなるようです。
従業員に健康な心身でベストパフォーマンスを発揮してもらうためにも、特別条項36協定を発動する使用者は、時間外労働および休日労働を最小限に留めるシフト調整などをしていく必要があるでしょう。
<参考>:36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針<PDF>(厚生労働省)
ポイント(3)労働者の健康・福祉を確保する
労働者に限度時間を超えて労働させる場合、働く人の健康・福祉を守る施策を労使協定に加えることが望ましいとされています。具体的には、以下の9つのなかから自社の業務や環境に合う施策を可能な限り実施する必要があるでしょう。
|
(1)医師による面接指導 (2)深夜業の回数制限 (3)終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)、 (4)代償休日・特別な休暇の付与 (5)健康診断 (6)連続休暇の取得 (7)心とからだの相談窓口の設置 (8)配置転換 (9)産業医等による助言・指導や保健指導
<引用>:36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針<PDF>(厚生労働省)
|
ポイント(4)
1ヵ月未満で働く労働者は目安時間を意識する
1ヵ月未満の短期間で働く労働者の場合、時間外労働は以下の目安時間を超えないように努める必要があります。
| 労働期間 | 目安時間 |
| 1週間 | 15時間 |
| 2週間 | 27時間 |
| 4週間 | 43時間 |
<参考>:36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針<PDF>(厚生労働省)
特別条項付き36協定と
時間外労働に関する違反と罰則
特別条項付き36協定を締結・発動するためには、36協定および時間外労働に関する法律違反と罰則についても理解しておく必要があります。また、法律を遵守し適切な労務管理を行ううえでは、36協定などに違反したときに生じるリスクも知っておくことが大事です。
36協定と時間外労働に関する法令違反と罰則
従来の36協定では、「協定の未締結」もしくは「協定の時間を超過した」場合に労働基準法第32条の違反になるルールでした。しかし2019年4月以降は、36協定で定める時間数に上限が設けられたことで、労働基準法第36条第6項を意識した労務管理の重要性が増しています。
36協定に関連する法律、違反内容、罰則をまとめると、以下のようになります。
| 関連法律 | 違反内容 | 罰則 |
|
労働基準法 第32条違反 |
36協定を締結せずに 時間外労働をさせた場合 |
6ヵ月以下の懲役または 30万円以下の罰金 |
|
36協定で定めた時間を超えて |
||
|
労働基準法 第36条第6項違反 |
36協定で定めた時間数にかかわらず、時間外労働と休⽇労働の合計時間が |
|
|
36協定で定めた時間数にかかわらず、時間外労働と休⽇労働の合計時間 |
<出典>:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(厚生労働省)
特別条項付き36協定違反によるその他のリスク
特別条項付き36協定に限ったことではありませんが、労働時間や休日などに関する法令違反をした場合に生じやすいのが、以下の3つのリスクです。
|
(1)労働者の心身に不調が生じるリスク (2)組織全体のパフォーマンスや生産性が低下するリスク (3)ステークホルダーからの信用が低下するリスク
|
まず、36協定のルールを守れないほど多くの時間外労働・休日労働を求めた場合、それは働く人の心身にたくさんの負担をかけることになります。
また、時間外労働・休日労働が増えると疲労回復も難しくなりますから、個人および組織全体のパフォーマンスや生産性は低下しやすくなるかもしれません。
たとえば、残業や休日出勤が増えて休息があまりとれない状態が続くと、仕事をしっかりこなすための集中力や判断力が低下し、結果として「トラブル対応中であるのにも関わらず、さらなるトラブルが生まれる」などの悪循環が生じたりもするでしょう。
こうしたなかで起こるのが、従業員・顧客・取引先といったステークホルダーからの信用低下です。
自社の従業員に関しては、36協定違反による労働時間の超過から会社への不信感が募り、離職意思につながることもあるでしょう。また、パフォーマンスが低下した組織にミスや作業品質の低下といった問題が多発すれば、顧客や取引先離れを招くかもしれません。
ビジネスに不可欠な社内外の信用を崩壊させないためには、36協定のルールはもちろんのこと、安全配慮義務を意識した労務管理を行いながら、従業員の健康と安全を守り続ける必要があるのです。
特別条項付き36協定の新様式
36協定の届出書は、令和3年4月1日(2021年4月1日)から新様式に変わっています。新様式の変更点は以下の3つです。
|
(1)36協定届の様式が一般条項と特別条項に分かれた (2)署名押印が不要になった (3)内容確認用のチェック欄が追加された
|
それぞれポイントを詳しく見ていきましょう。
ポイント(1)
36協定届の様式が一般条項と特別条項に分かれた
新様式の最も大きな変更点としては、一般条項と特別条項が別様式になったことです。
従来は特別条項の有無に関わらず第9号の様式が使われていましたが、時間外労働に罰則付き上限規制が設けられて特別条項に関する記載項目が増えたことで、一般条項と特別条項が以下のように分かれるようになりました。
|
|
ポイント(2)署名押印が不要になった
新様式の36協定届では、「署名押印が不要になった」のも大きなトピックです。ただしこれは、労働基準監督署に届け出る「36協定届」と、使用者と労働者の代表が締結する書面「協定書」を別にする場合に限ります。
36協定届が協定書を兼ねる場合は、従来どおり署名押印が必要です。
ポイント(3)
内容確認用のチェック欄が追加された
新様式の36協定届には、罰則付き上限規制が導入されたことから、締結内容の適正化を図る目的でチェックボックスが追加されるようになりました。
新様式で届け出をする場合、記入時に以下のポイントが確認できるようになっています。
|
|
<参考>:2021年4月から、36協定届の様式が新しくなります!(厚生労働省 宮城労働局)
特別条項付き36協定に関するよくある質問
「36協定」および「特別条項付き36協定」に罰則付き上限規制が設けられたことで、協定締結や労務管理の際に注意すべき事項が増えることになりました。また、2021年4月からは新様式も導入されたことで、36協定は新任の人事担当者にとって疑問や不安が生じやすい手続きになっているでしょう。
ここでは、特別条項付き36協定について、人事担当者からよくある質問とその回答の一部を紹介していきます。
Q.当事業所には時間外労働と休日労働を合計して80時間を超える月がまったくありません。この場合、何を意識して労務管理を行えば良いでしょうか。
そのような状況で意識すべきポイントは、以下の3つです。
|
<出典>:時間外労働の上限規制|わかりやすい解説(厚生労働省)
|
仮にこの事業所の時間外労働と休日労働の合計が80時間を超えた場合、上記の3つに加えて以下の2つを意識した労務管理が求められるでしょう。
|
<出典>:時間外労働の上限規制|わかりやすい解説(厚生労働省)
|
Q.今回はじめて特別条項付きの36協定届を作成するのですが、記入例や注意ポイントが記載された資料はありますか?
特別条項の様式第9号の2の用紙と記載例は、厚生労働省 東京労働局のページよりダウンロード可能です。
<参考>:時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)(厚生労働省 東京労働局)
記載例には、以下のように各項目の注意点も詳しく書かれています。はじめて36協定届を作成する場合は、この資料を見ながら記入作業を進めていくとよいでしょう。

<引用>:時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)(厚生労働省 東京労働局)
Q.時間外労働に罰則付きの上限規制が設けられたことで、労務管理が従来以上に複雑でデリケートな業務になっています。
何か良い管理方法はないでしょうか。
時間外労働および休日労働の上限規制を守るためには、アラート機能がある労務管理システムを活用するのがおすすめです。労務管理システムとは、タイムカード管理、入社・退社時の手続き、マイナンバー管理といった一連の手続きをオンライン上で行えるITシステムの総称です。
具体的な機能は契約サービスごとに異なりますが、勤怠管理機能があるシステムの場合、時間外労働や休日労働が著しく多い従業員について、アラートを鳴らす機能が備わっていることが多いでしょう。
近年のビジネス環境では、労働者の働き方が多様化するなかで人事担当者の業務が複雑化しやすくなっています。また国では、労働者の健康や安全をさらに守るために、時間外労働の上限規制のような制度改正を今後も行う可能性が高いでしょう。
こうした背景から労務管理そのものが複雑化するなかで適切なマネジメントを行うためには、自社に合ったITシステムやアウトソーシングを導入し、担当者の負担を減らしながら管理の精度を上げる工夫が必要となるでしょう。
人事労務のアウトソーシングならラクラスへ
本記事では、特別条項付き36協定について、概要や意義、2019年4月より施行された罰則付き上限規制の具体的内容などを解説してきました。適切な労務管理を行うことは多くの注意点があるため、人事部のなかでも負担に感じている方は多いのではないでしょうか。
もし人事業務における業務効率化をお考えであれば、ラクラスにお任せください。ラクラスなら、クラウドとアウトソーシングを掛け合わせた『BpaaS』により、人事のノンコア業務をアウトソースすることができコア業務に集中できるようになります。
ラクラスの特徴として、お客様のニーズに合わせたカスタマイズ対応を得意としています。他社では難色を示してしまうようなカスタマイズであっても、柔軟に対応することができます。それにより、大幅な業務効率の改善を見込むことができます。
また、セキュアな環境で運用されるのはもちろんのこと、常に情報共有をして運用状況を可視化することも心掛けています。そのため、属人化は解消されやすく「人事の課題が解決した」という声も数多くいただいております。
特に大企業を中心として760社86万人以上の受託実績がありますが、もし御社でも人事の課題を抱えており解決方法をお探しでしたら、ぜひわたしたちラクラスへご相談ください。