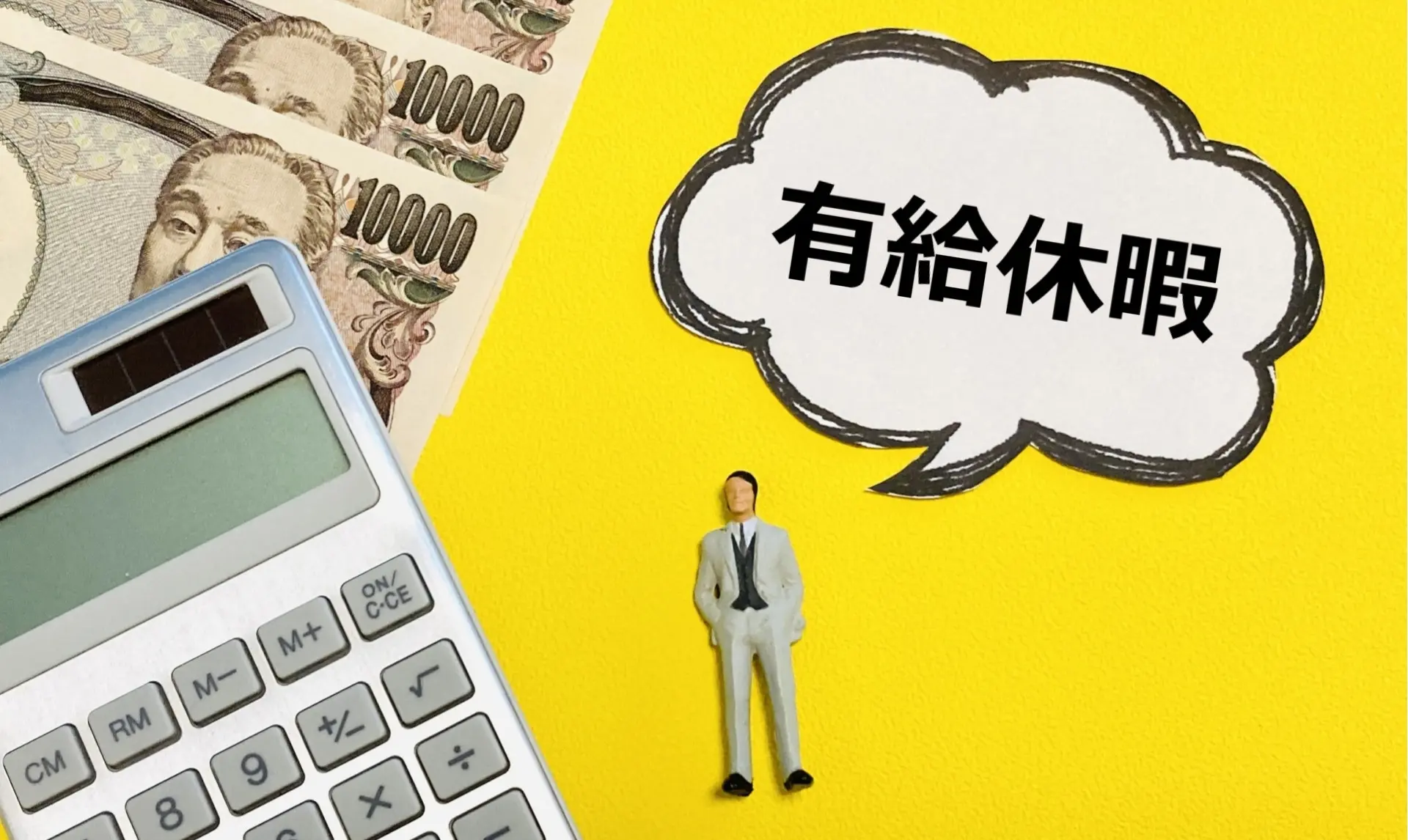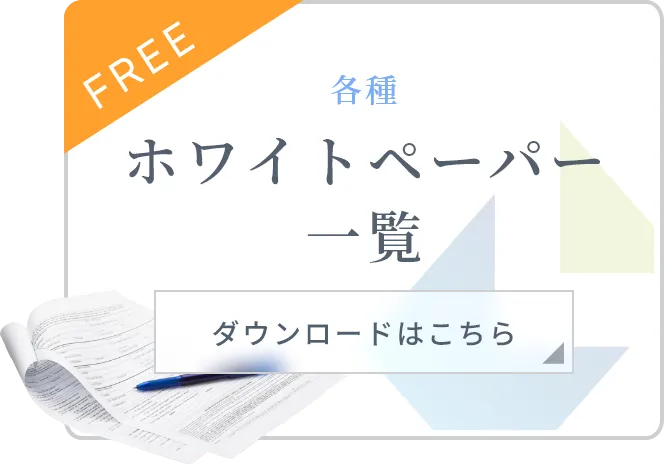法定三帳簿とは? 必須記載項目や作成方法、保存期間などを詳しく解説
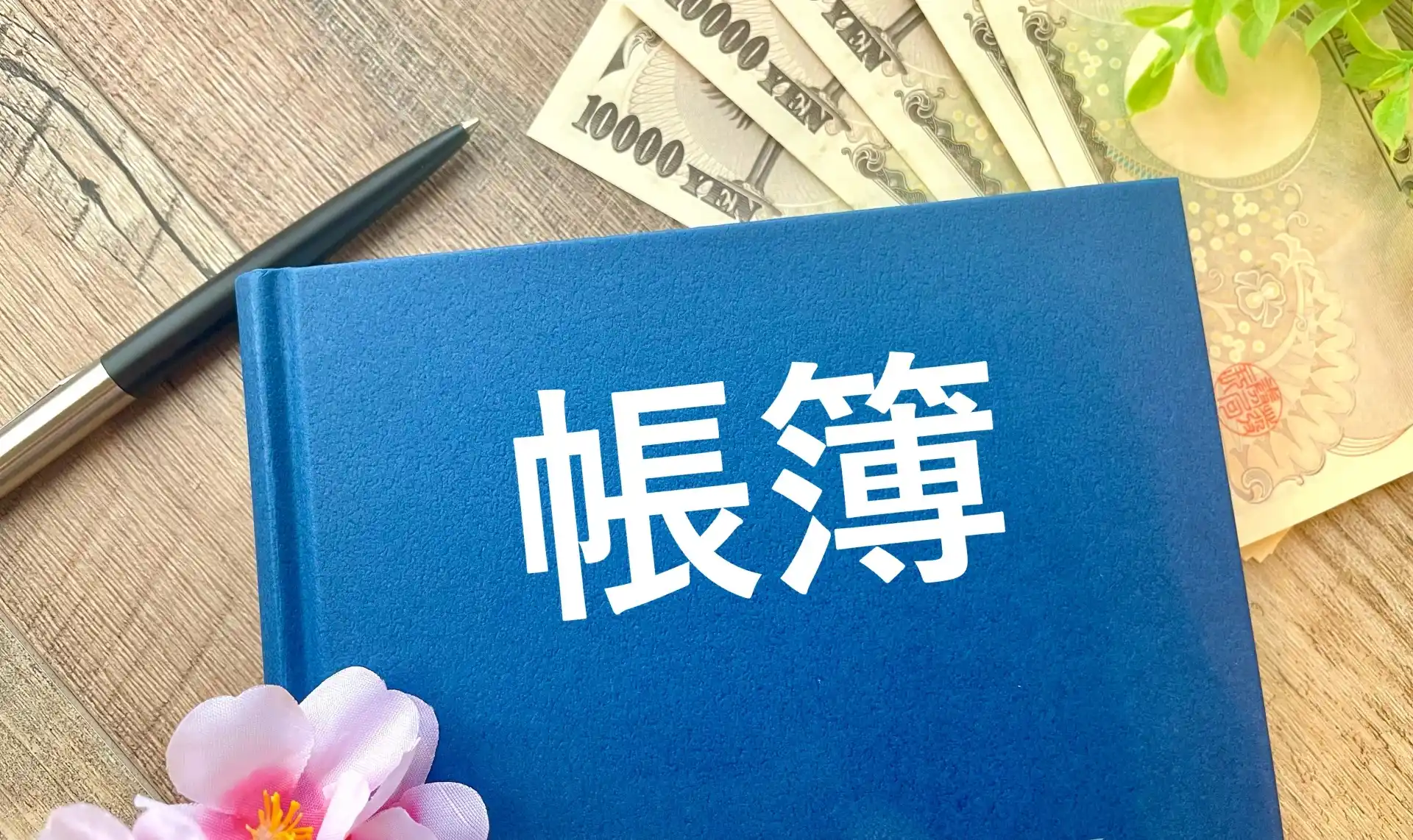
本記事では、法定三帳簿の概要を確認したうえで、法定三帳簿に該当する労働者名簿・賃金台帳・出勤簿の詳細を解説します。また、法定三帳簿の保存期間や正しい保存が行われなかったときに起こる「臨検」のポイントも紹介していきますので、ぜひ最後までお読みください。
法定三帳簿の作成・保管は、人事給与担当者が行う大事な業務の一つです。
法定三帳簿の適切な管理をするためには、この概念が指す管理簿の種類や記載項目、保存期間などを理解しておく必要があります。また、仮に適切な管理が行われなかったときに課せられるペナルティやリスクなども知っておいたほうがよいでしょう。
そこで本記事では、法定三帳簿の概要を確認したうえで、法定三帳簿に該当する労働者名簿・賃金台帳・出勤簿の詳細を解説します。記事の後半では、法定三帳簿の保存期間や正しい保存が行われなかったときに起こる「臨検」や刑事罰などのポイントも詳しく紹介していきます。
適切な労務管理を行うために、法定三帳簿の記入方法や管理方法などを調べている方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
法定三帳簿とは?
まずは法定三帳簿の概要から見ていきましょう。法定三帳簿とは、労働基準法が労働者を雇用する事業者に対して整備・保存を義務付けている以下3つの法定帳簿のことです。
|
<参考>:ととのえましょう 法定帳簿<PDFファイル>(出雲労働基準監督署)
<参考>:労働者を雇用したら帳簿などを整えましょう<PDFファイル>(厚生労働省)
ここからは、各法定帳簿の概要、記載対象、記載項目、様式・フォーマットを詳しく解説していきます。
法定三帳簿の種類(1)労働者名簿とは
法定三帳簿の1つ『労働者名簿』とは、労働者個人の情報を記載した名簿のことです。労働基準法第107条で義務付けられた書類であり、旧工場法時代から存在する帳簿になります。
労働者名簿の記載対象
労働者名簿は、原則として「事業所ごと」「労働者ごと」に作成すべきものです。正社員・パートタイマー・アルバイトといった雇用形態は関係なく、自社が雇用するすべての従業員について作成するものとなります。
ただし、以下の人たちについては、労働者名簿に関する考え方が大きく異なりますので注意しましょう。
| 対象者 | 労働者名簿に関する考え方 |
| 派遣労働者 | 派遣労働者の名簿管理は、派遣元企業の役割です。派遣先企業に作成・管理の義務はありません。 |
| 日雇い労働者 | 日雇い労働者に対して、名簿作成・管理の義務はありません。(労働基準法第107条) |
| 経営者・役員 |
いわゆる社長や取締役などは、労働基準法の労働者に該当しないため、労働基準法上は名簿での管理は不要です。 ただし、会社役員も社会保険事務所の調査では、被保険者として調査対象となるため、法定帳簿の作成・管理が必要となります。 |
| 在籍出向中の従業員 | 出向先で労働契約上の雇用関係が発生することから、出向元・出向先の双方で労働者名簿の作成・管理が必要です。 |
| 移籍出向中の従業員 |
移籍した時点で自社(出向元)との雇用関係がなくなります。 労働者名簿の作成義務があるのは、出向先だけです。 |
労働者名簿の記載項目
労働者名簿には、以下の8項目の記載が義務付けられています。
|
(1)労働者氏名 (2)生年月日 (3)履歴 (4)性別 (5)住所 (6)従事する業務の種類 (7)雇入年月日 (8)退職や死亡年月日とその理由・原因
|
「(3)履歴」に記載するのは、社内の昇進・異動などの履歴です。原則は社内履歴になりますが、自社で必要であれば、最終学歴や過去の職歴などを記載しても問題ありません。
「(6)従事する業務の種類」も、社内での役割や業務内容を記載します。ただし、労働基準法施行規則第53条第2項では、労働者数が30人未満の事業に対して、(6)の記入は“任意”としています。
労働者名簿の様式・フォーマット
労働者名簿のフォーマットは、上記の項目さえ満たしていれば自由です。Excelや専用ソフトによる作成も可能ですし、厚生労働省のホームページでも労働者1人につき1ページのWordテンプレート(様式第19号)を公開しています。自分たちが管理しやすい様式を使いましょう。
<参考>:主要様式ダウンロードコーナー (労働基準法等関係主要様式)(厚生労働省)
<参考>:ととのえましょう 法定帳簿<PDFファイル>(出雲労働基準監督署)
<参考>:労働者を雇用したら帳簿などを整えましょう<PDFファイル>(厚生労働省)
法定三帳簿の種類(2)賃金台帳とは
『賃金台帳』は、賃金計算のベースとなる基本帳簿です。労働基準法第108条で義務付けられた帳簿になります。
賃金台帳の対象者
賃金台帳は、「事業場ごとに」「自社で働くすべての人」について作成するものです。
賃金台帳の作成は、労働者名簿では作成不要だった日雇い労働者や経営層についても必要です。また、在籍出向の場合は、二重契約関係があることで出向元・出向先の双方に作成が義務付けられます。移籍出向の場合、出向元での作成は不要です。
賃金台帳の記載項目
賃金台帳では、以下の項目を記載する必要があります。
|
(1)氏名 (2)性別 (3)基本給・手当などの種類と金額 (4)賃金計算期間(給与の締め日) (5)労働日数 (6)労働時間数 (7)時間外労働時間数 (8)深夜労働時間数 (9)休日労働時間数 (10)控除項目と金額
|
上記のなかで大きなポイントになるのは、「(5)労働日数」と「(6)労働時間数」です。
これらの項目では、対象者が「(4)賃金計算期間」内に働いた日数と時間を記載します。たとえば、1日8時間勤務の従業員が、月22日の通常出勤に加えて5時間×2日の休日出勤をした場合、以下の式で算出した数字を記載することになるでしょう。
|
|
賃金台帳の様式・フォーマット
賃金台帳でも、上記の10項目が正しく記載されていれば、自社独自のフォーマットを使用することができます。厚生労働省や東京労働局のホームページからも、Wordやpdf形式の様式をダウンロードできますので確認しておきましょう。様式第20号が常用、第21号が日雇い専用です。
<参考>:主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)(厚生労働省)
<参考>:様式集(厚生労働省 東京労働局)
<参考>:ととのえましょう 法定帳簿<PDFファイル>(出雲労働基準監督署)
<参考>:労働者を雇用したら帳簿などを整えましょう<PDFファイル>(厚生労働省)
法定三帳簿の種類(3)出勤簿とは
出勤簿とは、労働時間を記載した帳簿です。実は、労働基準法には「出勤簿」という文言がありません。しかし、「出雲労働基準監督署」の資料には、出勤簿について以下の説明文が書かれています。
|
<引用>:ととのえましょう 法定帳簿<PDFファイル>(出雲労働基準監督署)
|
そして、厚生労働省が公開している「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、出勤簿に関して以下の内容が記載されています。
|
労働基準法第109条においては、「その他労働関係に関する重要な書類」について保存義務を課していますが、始業・終業時刻など労働時間の記録に関する書類もこれに該当し、3年間保存しなければならないことを明らかにしたものです。 具体的には、使用者が自ら始業・終業時刻を記録したもの、タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書、労働者が自ら労働時間を記録した報告書などが該当します。
<引用>:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン<PDFファイル>(厚生労働省)
|
出勤簿の記載対象
出勤簿には、法律で定められた必須項目がありません。厚生労働省の資料では、以下の4つを記載項目の一例として示しています。
|
(1)出勤簿やタイムレコーダー等の記録 (2)使用者が自ら始業・終業時刻を記録した書類 (3)残業命令書及びその報告書 (4)労働者が記録した労働時間報告書等
|
<参考>:労働者を雇用したら帳簿などを整えましょう<PDFファイル>(厚生労働省)
出勤簿の様式・フォーマット
出勤簿では、様式も任意です。上記で示したとおり、タイムカードの記録や残業命令書・報告書といった日々の勤怠管理で使っているものを活用することも可能でしょう。
なお、厚生労働省の以下資料にも、出勤簿の一例が掲載されています。自社で新たに作成する場合には、参考にするとよいかもしれません。
<参考>:労働者を雇用したら帳簿などを整えましょう<PDFファイル>(厚生労働省)
2019年から法定帳簿に加わった「年次有給休暇管理簿」とは
平成31年(2019年)4月1日から新たに作成が義務付けられた法定帳簿として「年次有給休暇管理簿」があります。「年次有給休暇管理簿」は、その名のとおり年次有給休暇の管理をするための帳簿になります。
年次有給休暇管理簿は、登場からまだ日が浅いことから、日本国内での知名度もあまり高くありません。しかし、厚生労働省の管轄である労働基準監督署などでは、従来の法定三帳簿に年次有給休暇管理簿を加えた「法定四帳簿」の作成・管理を義務付けています。
ここでは、年次有給休暇管理簿の概要を見ていきましょう。
<参考>:ととのえましょう 法定帳簿|労働基準法で規定された代表的な4帳簿<PDFファイル>(出雲労働基準監督署)
年次有給休暇管理簿の作成対象
年次有給休暇管理簿の作成対象は、年10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者です。作成対象には、管理監督者も含まれます。管理監督者の範囲については、厚生労働省が公開している資料で確認してください。
<参考>:労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために<PDFファイル>(厚生労働省)
年次有給休暇管理簿の記載項目
年次有給休暇管理簿では、以下の3項目を必須記載項目としています。
|
|
なお、年次有給休暇管理簿は、以下の「労働基準法施行規則第24条の7」にもとづき作成するものです。
|
使用者は、法第39条第5項から第7項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第1基準日及び第2基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第55条の2において「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存しなければならない。
<引用>:年次有給休暇管理簿を作成しましょう!<PDFファイル>(川崎北労働基準監督署)
|
年次有給休暇管理簿の様式・フォーマット
年次有給休暇管理簿のフォーマットは、上記の3項目をすべて記載していれば任意で構いません。また、先に引用した「川崎北労働基準監督署」の資料では、管理簿の具体例も紹介されています。自社で独自のフォーマットを作成する際には、ぜひ参考にしてください。
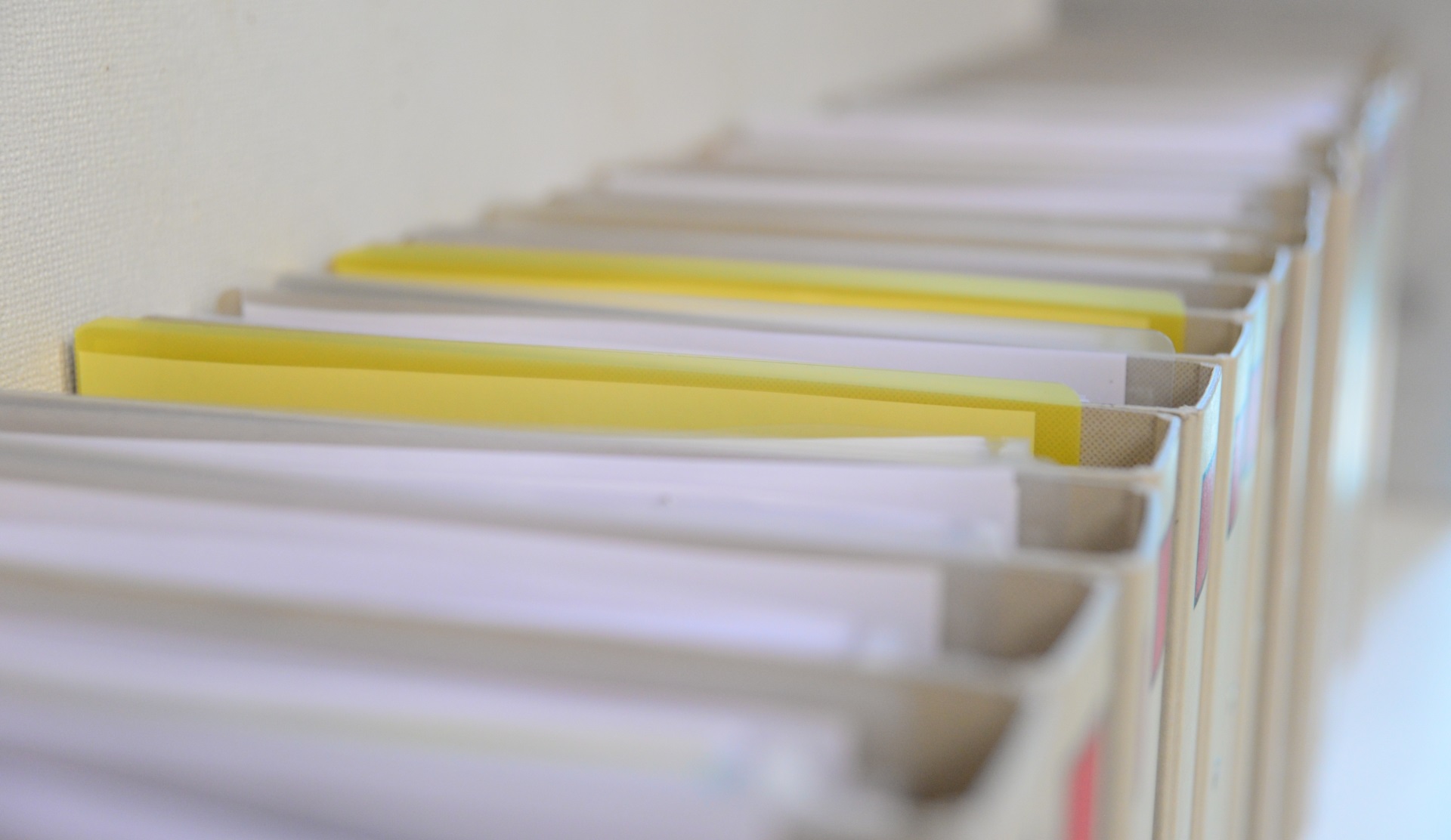
法定三帳簿の保存期間とは
では、法定三帳簿に話を戻しましょう。法定三帳簿は、2020年4月1日施行の改正労働基準法によって「5年間の保存」が必要になりました。ただし、現在は経過措置として「3年間」となっています。その旨が書かれた労働基準法第143条は以下のとおりです。
|
第百九条の規定の適用については、当分の間、同条中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。
|
また、労働基準法第109条では、法定三帳簿の保存期間について、以下のように定めています。
|
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
|
2025年1月現在は、「3年」で問題ありません。ただ、現在が経過措置であることを考えると、将来的に「5年」の保存をするための準備をする必要があるでしょう。
また、法定三帳簿の「3年(もしくは5年)」には、それぞれに起算日があります。各書類の保存・廃棄の判断では、起算日を必ず意識するようにしましょう。
【労働者名簿】労働者の死亡・退職・解雇の日から「3年」
【賃金台帳】労働者の最後の賃金について記入した日から「3年」
【出勤簿等】労働者の最後の出勤日から「3年」
【年次有給休暇管理簿】労働者に最後に年次有給休暇を与えた期間を終えてから「3年」
法定三帳簿を正しく保存しないとどうなるのか
法定三帳簿は、労働基準監督署や社会保険事務所の調査・各種手続きなどで必要な書類です。これらの作成・保存は、使用者の義務でもあります。
もし適切な管理が行われていないことが発覚した場合、まず行われるのが労働基準監督官による「臨検調査」や「是正勧告」などの行政指導です。行政指導は、臨検で法定三帳簿の作成・保存義務違反が発覚した場合に行われるものとなります。
なお、この行政指導に法的な拘束力はありません。ただし、労働基準監督署からの行政指導にも従わない場合、労働基準法第120条に基づき、30万円以下の罰金(刑事罰)が課せられる可能性があります。
違反が疑われる場合の「臨検」とは
「臨検調査」すなわち臨検とは、法定三帳簿の作成・保存の義務などの法律違反が疑われる事業者に対して、労働基準監督官が実施する立ち入り調査のことです。
臨検が発生する事態を防ぐためには、「臨検がなぜ発生するのか?」や「臨検はどういうものか?」を理解したうえで、法定三帳簿の適切な作成・保存義務を果たす必要があるでしょう。
ここでは、法定三帳簿に関係する臨検の概要を解説します。
臨検はなぜ行われる?(臨検における4つの種類)
臨検には、以下の4種類があります。
【定期監督】管轄企業に対して定期的に実施されるもの
【災害時監督】労働災害の原因解明や再発防止を目的に実施されるもの
【申告監督】労働者からの申告を受けて実施されるもの
【再監督】すでに是正勧告を受けている企業に対する、2回目以降の臨検のこと
臨検は上記のとおり、何の問題もなさそうな企業に対しても定期的に実施されるものです。したがって、法定三帳簿の作成・保管などは、定期的に行われる臨検のために必ず実施しなければなりません。
また、労働基準法違反の疑いで行われる臨検は、従業員の申告がきっかけになることも多くあります。たとえば、「最近はまったく残業代が支払われていない」や「◯月の休日出勤がなかったことにされている」などの申告があった場合、労働基準監督署側で違反内容の悪質性や嫌疑の程度を考慮したうえで、臨検の実施判断をすることになります。
このほかに、助成金における不正受給の疑いなどがある場合も、抜き打ちでの臨検が行われるようです。
臨検の一般的な流れと内容
臨検は、基本的に以下の流れで進められます。ただし、何らかの不正が疑われる場合、ありのままの帳簿などを確認する目的から、予告なしの抜き打ち訪問が実施されることもあります。
|
(1)予告 (2)立ち入り調査 (3)事業者への結果報告 (4)労働基準監督官への報告書提出
|
臨検は基本的に、労働基準監督官が2名で行うものです。当日の監督官は、自分の身分証を示したうえで訪問の目的を伝え、労務管理の責任者に面会を求めてきます。調査の流れやチェック項目は違反の内容によって変わってきますが、原則は以下の流れで進められることが多いでしょう。
|
(1)法定三帳簿の確認 (2)労務管理の責任者または事業主へのヒアリング (3)勤務実態と書類の照合・確認 (4)労働安全衛生法に関する状況確認 (5)労働者へのヒアリングや事業場内の立ち入り調査 (6)口頭による指示・改善指導
|
臨検を通して大きな問題が判明した場合、口頭ではなく書面による指導が行われます。書面の種類としては、以下の3つです。
|
(1)指導票(法令違反ではないものの改善が必要なとき) (2)是正勧告書(法令に違反しているとき) (3)使用停止等命令書(労働者に急迫した危険があり、対処に緊急を要するとき)
|
口頭もしくは書面で改善指導などを受けたときには、労働基準監督官の指示を守って適切な対処を迅速に行う必要があります。
臨検を拒むことは可能なのか?
臨検は、労働基準法などの法律にもとづき行われるものです。労働基準法第101条1項でも以下の条文を示していることから、「臨検は拒めないもの」と認識すべきでしょう。
|
《労働基準監督官の権限》 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
<引用>:労働基準法(e-GOV法令検索)
|
また、労働基準監督官には、臨検監督を実施する行政上の権限に加えて、労働基準法違反の罪に関して、犯罪捜査を行える司法警察官と同様の権限が与えられています。したがって、労働基準監督官が裁判官から捜索差押許可状の発付を受けた場合、いわゆる“ガサ入れ”が行われる可能性もあります。注意しましょう。
法定三帳簿を作成・保存するときの注意点
法定三帳簿の作成・保存には、ミスやトラブルが起こりやすいポイントがあります。ここでは、4つの注意点を挙げて解説していきましょう。
注意点(1)必須記載項目が記載されていない
法定三帳簿には、それぞれに必須記載項目が定められています。こうした項目が1つでも不足していた場合、定期の臨検などで「適切な作成が行われていない」と指摘されるかもしれません。
特に、自社独自の様式で作成・管理をする場合、必須記載項目がすべて網羅されているかの確認が必要となるでしょう。
注意点(2)日雇い労働者や出向者などの取り扱い
法定三帳簿の対象者は、書類ごとに異なります。なかでも特に注意すべきなのは、日雇い労働者や出向者などです。たとえば、日雇い労働者の場合、労働者名簿の作成は不要ですが、賃金台帳と出勤簿は作成しなければなりません。
近年では、政府が推進する働き方改革などの影響から、雇用形態なども多様化しています。こうしたなかで適切な帳簿の作成を行うためには、働き方や契約形態別の労務管理方法を一度整理しておいたほうがよいかもしれません。
注意点(3)事業場ごとの作成・保管
法定三帳簿は、事業場ごとに作成・保管すべきものです。仮に小さな営業拠点などで事務手続きを行う担当者がいない場合は、本社の人事部などで作成したものを即座に共有するオペレーションなども必要でしょう。
また、臨検が抜き打ちで行われることを考えると、作成した法定三帳簿の保管場所を人事や総務などの部門内で共有しておくことも重要になります。
注意点(4)労働時間を自己申告してもらう際の注意点
事業場の外で勤務する従業員などに労働時間を自己申告してもらう場合、たとえば本人が記載した「勤務表の内容」と、人事部が管理する「法定三帳簿」に乖離が生じない方法を考えることも重要です。
仮に、個人が記載した勤務表と法定三帳簿の内容に乖離が生じた場合、それも「適切な労務管理が行われていない」などの判断につながる可能性があります。労働時間を自己申告してもらう必要がある場合は、労使間で合意した数字を一覧で管理する仕組みづくりも検討しましょう。
なお、厚生労働省が示すガイドラインも仕組みづくりの参考になるものです。ぜひチェックしてみてください。
人事業務の課題解決ならラクラスへ
本記事では、法定三帳簿に該当する労働者名簿・賃金台帳・出勤簿について解説してまいりました。法定三帳簿の保存は正しく行わなければ刑事罰にまでなってしまうため、人事部のなかでも負担に感じている方は多いのではないでしょうか。
もし「業務負担の解消」など、人事業務における業務効率化をお考えであれば、ラクラスにお任せください。ラクラスなら、クラウドとアウトソーシングを掛け合わせた『BpaaS』により、人事のノンコア業務をアウトソースすることができコア業務に集中できるようになります。
ラクラスの特徴として、お客様のニーズに合わせたカスタマイズ対応を得意としています。他社では難色を示してしまうようなカスタマイズであっても、柔軟に対応することができます。それにより、大幅な業務効率の改善を見込むことができます。
また、セキュアな環境で運用されるのはもちろんのこと、常に情報共有をして運用状況を可視化することも心掛けています。そのため、属人化は解消されやすく「人事の課題が解決した」という声も数多くいただいております。
特に大企業を中心として760社86万人以上の受託実績がありますが、もし御社でも人事の課題を抱えており解決方法をお探しでしたら、ぜひわたしたちラクラスへご相談ください。