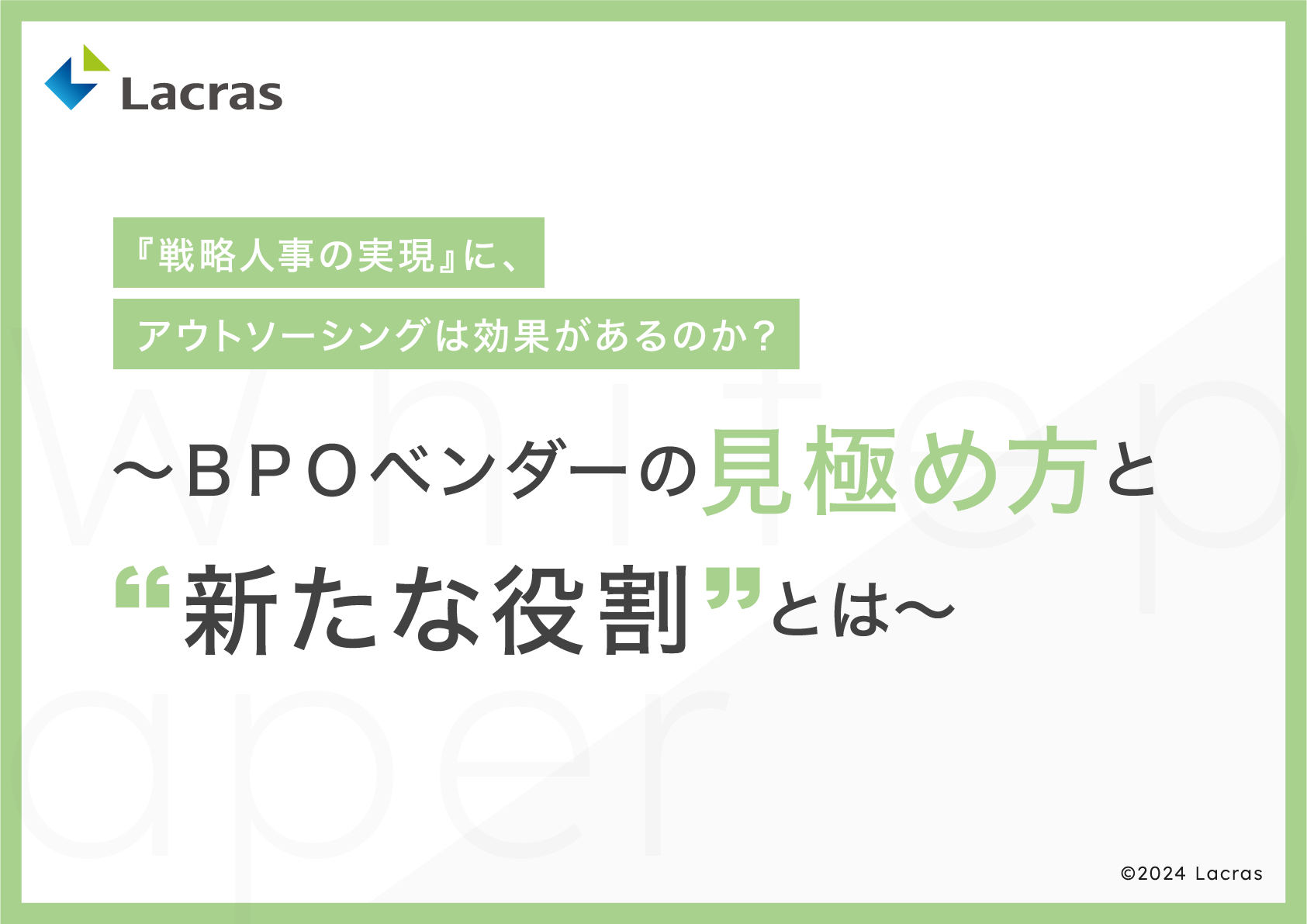入社手続きに必要な書類とは?
社会保険や税金関連の手続き、全体スケジュールも解説

本記事では、新人の入社手続きについて基礎知識や必要書類、税金と各種保険における加入手続きのポイントを解説します。
また、入社手続きを効率化する方法についてもご紹介します。
新入社員の入社手続きをしっかりと理解したい方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
近年のビジネス環境では転職が一般化してきたこともあり、人事担当者が行う入社手続きの頻度が高まりやすくなっています。こうしたなかで、新卒社員や中途社員をスムーズに受け入れるためには、入社手続きの概要や必要書類を理解するなど可能な限りの準備をしておくことが重要です。
そこで本記事では、新しく入る人の入社手続きについて基礎知識や必要書類、税金と各種保険における加入手続きのポイントを解説します。記事の後半では、今後も件数が増えることが見込まれる入社手続きについて「効率化する方法」も紹介していきます。
従業員の入社手続きをしっかりと理解したい方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
入社手続きの基礎知識
入社手続きは、新しい従業員を受け入れるために必ず行わなければならない業務です。
必要な入社手続きを期限までに行ううえでは、人事部門の担当業務における位置づけや目的、重要性などを理解しておく必要があるでしょう。
ここではまず、「入社手続きとはどういった業務なのか?」や「なぜ期限までに行う必要があるのか?」といった基本について解説していきます。
人事労務管理と入社手続きの関係
人事労務管理とは、一般的な人事部門が担う業務の総称です。人事労務管理は、「人事」と「労務」の2つで構成されており、それぞれに以下の役割や目的があります。
|
【人事】
【労務】
|
新人の入社手続きは、上記の人事と労務の両方に関係するものです。
一般的な企業では、各従業員の教育における進捗や人事評価の結果などを、パソコン上で管理していることが多いでしょう。
こうした人事管理を始めるためには、たとえば専用のExcelシートや人事専用のシステムなどに本人の名前・学歴・保有資格などの基本情報を入力する必要があるはずです。
このような入力作業も、人事部門が行うべき入社手続きの一つになります。
また、新入社員の安全や健康を守るために労務の仕事を進めるうえでも、入社手続きが大事な役割を果たすことになります。
たとえば、内定後に発行する「労働条件通知書」は、その従業員が働くうえでの条件や会社との間で合意したルールが書かれた大切な書類です。労働条件通知書どおりの業務指示や働き方をするからこそ、会社は従業員の健康や法律を守れることになります。
また、給与の支給後に、従業員本人に代わって社会保険料や税金を納めるためにも、入社手続きで行う書類のやり取りはとても重要です。
従業員の入社手続きは、このように人事・労務の両方と密接な関係があります。そして、人事部門が入社手続きを完了させることには、従業員をさまざまな意味で守るための「土台を築く」という意味があるでしょう。
人事と労務についての詳細は、以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひチェックしてください。
【関連記事】
人事と労務の違いとは?それぞれの仕事内容や特徴を詳しく紹介
入社手続きの重要性
近年のビジネス環境では、さまざまな要因から「会社が適切な入社手続きを行うこと」の重要性が高まるようになりました。
たとえば今の時代は、いわゆる検索サイトや生成AIを使えば「会社側の入社手続きが適切かどうか?」について、誰でも簡単に調べられる時代です。
だからこそ企業は従業員からの信用を損なわないために、法律に則った正しい入社手続きを行う必要がでてきています。
また、仮に入社手続きの内容が間違っていたりいい加減な対応をしていたりした場合、その内容に気づいた従業員が、内部告発に近い形で個人のSNSや口コミサイトなどに投稿する可能性もあるでしょう。投稿内容が拡散されると、「コンプライアンス違反」のイメージがつき、幅広いステークホルダーから信頼を失ってしまうかもしれません。
近年は転職が一般化したことで、新人・若手の早期離職が起こりやすくなっています。
こうしたなかで優秀な社員を定着させるうえでは、採用活動で築いた信頼を失墜させないために、適切な入社手続きを行う必要があるでしょう。
入社手続きに必要な書類
入社手続きで取り扱う書類には、「会社が用意するもの」と「従業員から提出してもらうもの」の2種類があります。ここでは、各書類の概要を確認しましょう。
会社側が用意する必要書類一覧
従業員の内定~入社までに会社側で発行すべき書類は、以下の5つです。
|
|
それぞれの書類について解説をしていきます。
・採用通知書(内定通知書)
採用通知書(内定通知書)は、最終選考に合格した応募者に対して、以下の2つのことを知らせるために発行する書類です。
|
|
会社側が独自に出すものであるため、法律で定められた必要項目などはありません。
・雇用契約書・労働条件通知書
雇用契約書と労働条件通知書は、内定から入社までのプロセスで発行するものです。
この2つの書類のうち特に重要となるのは、法律で発行が義務付けられた「労働条件通知書」です。その理由は、従業員と会社が雇用契約を締結する際に労働条件を書面で明示すべきことについて、労働基準法第15条第1項で定められているからです。
|
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
<引用>:労働基準法 | e-Gov法令検索
|
また、労働条件通知書を作成する際には、原則として法律で定められた以下の事項を記載しなければなりません。
(5については、昇給に関する事項を除く)
|
<引用>:採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか。(厚生労働省)
|
ですから、労働条件通知書は厚生労働省が公開している以下のフォーマット形式で作成する必要があります。
<参考>:労働条件通知書(厚生労働省)
<参考>:様式集(厚生労働省|東京労働局)
一方で雇用契約書は、民法623条に基づく雇用契約を証明する書面ですが、法律で義務付けられたものではありません。その理由は、雇用契約を含めた各種契約は、書面を交わさず口頭で成立させることも可能だからです。
ですから、雇用契約書は使用者と労働者の間で雇用契約内容への合意がなされたことを証明したい場合に作成するとよいでしょう。
<参考>:民法|e-Gov法令検索
- 入社誓約書(内定承諾書・内定同意書)
入社誓約書とは、内定をもらった応募者が会社に対して「入社の意思があること」を示す書類です。内定承諾書や内定同意書と呼ばれたりもします。
昨今では新卒者の内定辞退が増えており、入社誓約書などを早く発行して応募者に「入社の意思があること」を示してもらおうとする企業が多くなっています。しかし、日本においては憲法22条で保障されている基本的人権「職業選択の自由」がまず優先されるため、入社誓約書には残念ながら“法的拘束力はない”と考えるのが原則です。
新入社員との雇用契約を締結するうえで企業に発行義務があるのは、先述の「労働条件通知書だけ」となります。内定者に署名してもらい回収する入社誓約書は、どちらかといえば、日本の採用活動における慣習的なものと位置づけられるでしょう。
<参考>:日本国憲法(衆議院)
・扶養控除等申告書
扶養控除等申告書は、社会保険や税金関係の入社手続きで使う書類です。新しく入る社員の扶養者の有無に関わらず、すべての従業員に提出してもらう必要があります。なお、新しく入る社員が自社以外の会社でも雇用されている場合、扶養控除等申告書は「1つの事業所」でしか提出できません。
最新の様式や記載例などは、国税庁のページからダウンロードできます。
<参考>:A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告(国税庁)
・健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届
新入社員に被扶養者がいる場合、「健康保険被扶養者異動届」と「国民年金第3号被保険者届」を提出してもらいます。これらの様式は一体化されており、日本年金機構のホームページでは以下のように説明されています。
|
この届書は、健康保険被扶養者(異動)届と被扶養配偶者の国民年金第3号被保険者関係届が一体化した様式となっています。
<引用>:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き(日本年金機構)
|
従業員に入社前に用意してもらう必要書類一覧
従業員側には、会社に給与の支払いや社会保険料・税金の納付などをしてもらうために、入社までに以下の書類や情報を準備して提出してもらう必要があります。
|
|
こちらも、それぞれの書類や情報について解説していきます。
・雇用保険被保険者証番号
雇用保険被保険者番号は、雇用保険加入者一人ひとりに割り当てられるものです。「4桁・6桁・1桁」で構成される11桁の番号になります。
従業員が以前、雇用保険の適用事業所に雇用されていて雇用保険の加入要件に該当していた場合、以前働いていた会社を通じて交付される以下の書類などから雇用保険被保険者番号を確認することができます。
|
<参考>:被保険者に関する手続き(厚生労働省 大阪労働局 大阪ハローワーク)
|
・基礎年金番号
基礎年金番号は、年金加入記録を管理するキーになるものです。実際の番号については、以下のいずれかの方法で確認できます。
|
【書類で確認する】
【オンラインで確認する】
<参考>:自分の基礎年金番号の確認方法を教えてください。(日本年金機構) <参考>:基礎年金番号・基礎年金番号通知書・年金手帳について(日本年金機構)
|
・給与振込先の口座情報
給与振込先の銀行口座番号は、以下のいずれかの方法で収集します。
|
|
・源泉徴収票
源泉徴収票は、前の会社を退職するときに交付されるものです。前職の退職年と自社の入社年が同じ場合は年末調整で使用するため、提出を求めます。
<参考>:F1-1 給与所得の源泉徴収票(同合計表)(国税庁)
なお、年末調整業務については、以下の記事でも詳しく解説しています。あわせてチェックしてみてください。
【関連記事】年末調整業務の進め方ガイド|担当者がやるべき手続きの流れや必要書類の種類などを解説
・マイナンバー
マイナンバーは、日本に住民票を有するすべての人に発行されている番号です。税金や社会保険の手続きで使用するため、以下のいずれかの方法で確認・提出してもらう必要があります。
|
|
各種保険の加入手続きについて
従業員の受け入れ時に各種保険への加入手続きが発生する可能性があるのは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)・雇用保険・労災保険の3種類です。ただし、実際に加入すべきかどうかの判断は、事業所および従業員本人ごとに異なります。
ここでは、各種保険の加入要件と加入手続きについて、基本的なポイントを見ていきましょう。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件と加入手続き
社会保険の加入要件は、適用事業所と被保険者の2点で見ていく必要があります。
その理由は、厚生年金保険が事業所単位で適用されるものだからです。
まず、適用事業所には強制と任意の2つがあり、それぞれに以下の特徴があります。
| 強制適用事業所 | 任意適用事業所 |
|
株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)が対象。 従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除き厚生年金保険の適用事業所となる。 被保険者となるべき従業員を使用している場合は、加入手続きが必要。 なお、令和4年10月より「法律・会計にかかる業務を行う士業」に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用する事業所についても、強制適用事業所の対象に。 |
適用事業所以外の事業所でも、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請を行えば、厚生労働大臣の認可を受けることで適用事業所となることが可能。 |
<参考>:適用事業所と被保険者(日本年金機構)
続いて従業員個人は、以下の4要件のすべてに該当した場合、法律上において社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入対象になります。
|
(1)週の勤務時間が20時間以上 (2)給与が月額88,000円以上 (3)2ヵ月を超えて働く予定がある (4)学生ではない
<参考>:従業員のみなさま|社会保険加入のメリットや手取り額の変化について(厚生労働省)
|
・社会保険の加入手続き
新たに従業員を採用した場合、事業主は5日以内にその被保険者に関する「被保険者資格取得届」を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)に提出する必要があります。
<参考>:適用事業所と被保険者(日本年金機構)
雇用保険の加入要件と手続き
新しく入る社員が以下の1・2の両方に該当する場合、雇用保険の被保険者(加入対象)になります。
| 1 |
31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。 具体的には、右記のいずれかに該当する場合。 |
・期間の定めがなく雇用される場合 ・雇用期間が31日以上である場合 ・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合 ・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 |
| 2 | 1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。 |
─ |
<出典>:雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!(厚生労働省)
こちらの要件を端的にあらわすと、「1週間の所定労働時間が20時間以上であり、なおかつ31日以上の雇用見込みがあれば必ず加入しなければならない」ということです。
・雇用保険の加入手続き
新たに雇い入れた従業員が被保険者の要件に該当する場合は、その従業員が被保険者になった日の属する月の翌月10日までに「資格取得届」をハローワーク(公共職業安定所)に提出します。
公共職業安定所の長の確認を受けると、「雇用保険被保険者証」とあわせて「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」が交付されることになります。確認通知書は、被保険者本人に交付しましょう。
<参考>:雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!(厚生労働省)
労災保険の加入要件と加入手続き
労災保険は、農林水産に関する事業の一部を除き、アルバイト・パートタイマーを含めた労働者を1日・1人でも雇っていれば、必ず加入しなければならないものになります。
・労災保険の加入手続き
実のところ労災保険は、先述の雇用保険との関係が深いものです。厚生労働省では、労災保険と雇用保険を総称して「労働保険」と呼んでいます。労働保険の加入手続きは、事業の種類(一元適用事業・二元適用事業)ごとに変わってきます。
労働保険の手続き全体で見ると、一元適用事業と二元適用事業で以下の違いがあります。
| 一元適用事業 | 二元適用事業 | ||
| 概要 |
二元適用事業ではないすべての事業のこと。 労災保険と雇用保険を一つの労働保険として取り扱う。 |
以下の事業。雇用保険と労災保険を別々に取り扱うもの。 ①農林水産の事業 ②建設の事業 ③港湾労働法の適用される港湾において行う事業 ④都道府県及び市町村並びにこれに準ずるものの行う事業 |
|
| 提出物 | 労働基準監督署 |
労働保険保険関係成立届(労災・雇用) 労働保険概算保険料申告書(労災・雇用) |
労働保険保険関係成立届 労働保険概算保険料申告書 |
| 労働基準監督署 |
雇用保険適用事業所設置届 雇用保険被保険者資格取得届 |
労働保険保険関係成立届 労働保険概算保険料申告書 雇用保険適用事業所設置届 雇用保険被保険者資格取得届 |
|
<出典>:ひとりでも労働者を雇ったら、労働保険(労災・雇用)に入る義務があります。<PDF>(厚生労働省)
なお、労働保険の加入手続きには、さまざまな注意点があります。詳細については、上図の出典元である厚生労働省の資料を参考にしてください。

税金に関する手続きについて
入社手続きでは多くの場合、税金(所得税と住民税)に関する手続きも必要です。各税金についてポイントを見ていきましょう。
所得税に関する入社手続き
所得税に関する入社手続きは、新しく入る社員に「扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらい、その内容にもとづいて源泉徴収簿を作成していきます。源泉徴収簿とは、年末調整の計算を行う際のベースとなる情報を記載した1人1枚ずつの帳簿で、以下のような情報があります。
|
毎月の給与額 / 賞与額 / 源泉徴収税額 / 年末調整申告の控除情報 など
|
受け入れ対象が中途採用(転職者)の場合には、前職の源泉徴収票も提出してもらいましょう。
なお、源泉徴収税の納付期日は、給与が発生した翌月の10日です。入社手続きを行う際には、この日程を意識した早めの案内が必要となるでしょう。
<参考>:A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告(国税庁)
<参考>:A2-2 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿の作成(国税庁)
住民税に関する入社手続き
住民税には、以下の2種類の納付(税金の徴収)方法があります。所得税の源泉徴収義務がある事業所は、一部の例外を除いて法律で特別徴収することが義務付けられています。
|
【普通徴収】 【特別徴収】
|
住民税の場合、新しく入ってくる社員が以下のどのパターンに該当するかで行うべき手続きが変わります。
|
新しく入ってくる社員の状況 |
会社が行うべき手続き | |
| 新入社員 | 住民税に関する特別な手続きは不要。入社2年目から特別徴収が開始される。 | |
| 中途社員 | 普通徴収から特別徴収に切り替える場合 | 「特別徴収切替届出(依頼)書」を、従業員の居住市区町村に提出する。 |
| 前職から引き続き特別徴収を希望する場合 | 「特別徴収にかかる給与所得者異動届書」を、従業員の居住市区町村に提出する。 | |
<参考>:特別徴収の流れ(東京都北区)
従業員の入社前にやっておくべき社内準備
ここまで紹介した手続きは、「会社と従業員」や「会社と公的機関」の間で行われるものです。新たな従業員を受け入れる際には、入社日までに社内で整備しておくべき事項もあります。
ここでは、大半の企業で必要となる「法定三帳簿の準備」と「職場環境の準備」について解説しましょう。
入社日までに行う「法定三帳簿の準備」
法定三帳簿とは、労働基準法が労働者を雇い入れる事業者に整備・保存を義務付けている4つの法定帳簿(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿・年次有給休暇管理簿)のことです。ちなみに従来は3つの帳簿ということで「三帳簿」と呼ばれていましたが、少し前に年次有給休暇管理簿が加わったことで、実質的には「四帳簿」に変わりました。
これらの帳簿は、以下のように各法律で定められたルールに沿った様式・項目で作成しなければなりません。
| 帳簿の名称 | 労働基準法の関連条文 | 必要項目 | 保存期間・起算日 | 様式 |
| 労働者名簿 | 第107条 |
|
3年 (労働者の死亡・解雇・退職の日) |
様式19号 (項目に漏れがなければ独自のフォーマットでも可能) |
| 賃金台帳 | 第108条 |
|
3年 (労働者の最後の賃金を記入した日) |
様式20号・21号 (項目に漏れがなければ独自のフォーマットでも可能) |
| 出勤簿等 | 第108条関係 |
|
3年 (労働者の最後の出勤日) |
任意でOK |
| 年次有給休暇管理簿 | 施行規則第24条の7 |
|
3年 (労働者に有給休暇を与えた期間の満了日) |
任意でOK |
<出典>:労働者を雇用したら帳簿などを整えましょう~労働関係法令上の帳簿等の種類と保存期間について(簡易版)~(厚生労働省)
法定三帳簿は、社会保険事務所や労働基準監督署での調査・手続きなどで使用する書類です。法律で定められたルールにもとづく作成と保存は、使用者の義務になります。そのため、新しい従業員を雇用する際には、入社日までに必ず上記4つの帳簿を用意する必要があるでしょう。
法定三帳簿(法定四帳簿)については、以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひチェックしてください。
【関連記事】法定三帳簿とは? 必須記載項目や作成方法、保存期間などを詳しく解説
入社日までに行う「職場環境の整備」
新入社員が会社で働き始めるためには、ここまで紹介した事務手続きはもちろんのこと、仕事で使う備品や貸出物などの「ハード面」と、受け入れ部門にその人を知ってもらい早期戦力化を促す「ソフト面」の準備も必要です。
受け入れの準備で用意すべき備品・貸出物には、以下のようなものがあります。準備のポイントも簡単に紹介しましょう。
| 用意するもの | ポイント |
| 制服 | 入社日に手渡しするのであれば、あらかじめサイズを聞いておきます。 内定式などの際に試着してもらってもよいでしょう。 |
| 社員証/名刺 |
社員証は入社日から必ず携帯すべきものです。セキュリティ対策が強固な会社では、ビルの入退室やタイムカードなどでも社員証を使用します。 労働条件通知書などを見て作成し、入社当日の最初に渡せるようにしましょう。 |
| メールや業務システムなどのIT環境 |
社内のセキュリティや情報システムを管理する部門に依頼し、新しいメールアドレスや業務で使うアカウントを発行してもらいます。 一括採用の場合、たくさんのアカウント発行が必要となるため、新入社員の入職が確定した段階で早めに一覧共有などをしたほうがよいでしょう。 |
| 机・椅子・パソコン・電話など |
新しく入る社員の配属先が決まったら、オフィス内で机・椅子・業務用の携帯電話・事務用品などを用意します。 場合によっては、席替えや机のレイアウト変更が必要になる可能性もあります。現場にはその旨を早めに伝えたほうがよいでしょう。 |
入社手続きに関するQ&A
入社手続きは、タスク量自体が膨大であるうえに、さまざまな部署や機関とのやり取りが発生する複雑な業務です。入社手続きの経験が浅い担当者の場合には、手続きを進めるなかでさまざまな疑問に直面しやすいでしょう。
ここでは、入社手続きの担当者が頭を悩ませることが多い2つのポイントについて、QA形式で回答していきます。
Q.内定者への案内はいつどのように行えば良い?
内定者に対する書類提出などの案内は、「内定者フォロー」のなかで行うのが理想です。
その理由は、たとえば「内定~入社までの案内が届かない」や「人事担当者に質問しても返答がない」といった問題が起きた場合、信用が低下し内定辞退につながる可能性があるからです。
内定者フォローのなかで各種案内を行う際のポイントは、「定期的」と「具体的」の2つです。
たとえば、ある新卒社員の内定を7月に出し、その直後に内定通知書や内定同意書を取り交わしたと仮定します。
この場合に、11月の内定式まで何の音沙汰もなければ、新卒社員の側に「このまま何もしなくて大丈夫かな?」とか「本当に入社できるのかな?」といった不安が生じるかもしれません。また、不安が増大するなかで競合から熱心なスカウトなどがあれば、気持ちがそちらに移ってしまう可能性もあるでしょう。
こうした問題を防ぎ、内定者の入社意欲を低下させないためには、たとえば以下のように定期的な情報発信とコミュニケーションを図ることが理想です。
|
【7月】内定通知書と内定同意書を発行する 【8月】内定者の懇談会を実施する 【9月】会社の沿革や近況がわかる資料とメッセージを送付する 【10月】内定式を行う など
|
また、今後の流れやスケジュールが未確定の場合は、「9月下旬には決定します。10月第1週までにスケジュール共有予定です。もう少しお待ちください」のように、今わかっている具体的な情報を示してあげるとよいでしょう。
Q.収集したマイナンバーは
どのように管理すれば良い?
マイナンバーを取り扱ううえで注意したいのが、2016年から本格運用されている「マイナンバー法」の存在です。マイナンバー法の第9条(別表第1)では、マイナンバーは「限定的に定められた事務の範囲内で、利用目的を特定して利用すること」を定めています。
人事担当者が新入社員からマイナンバーを収集した場合は、社会保険料や税金以外の手続きでは「使わない」のはもちろんのこと、人事以外のメンバーがその情報にアクセスして「使えてしまう問題」を防ぐ対策も必要です。
大事な個人情報であるマイナンバーを提出してくれた従業員の信頼を失墜させないためにも、人事部門ではマイナンバーなどの個人情報に関する安全かつ適切な取り扱いや保管方法を整備する必要があるでしょう。
<参考>:マイナンバー(個人番号)ハンドブック|個人番号保護委員会
入社手続きの効率化のポイント
入社手続きでは「会社と従業員」「会社と行政機関」といったさまざまなやり取りが発生するため、場合によってはスケジュール通りに作業が進まず、人事担当者の悩みの種になることがあるかもしれません。
こうしたなかで手続き全般を入社日までに終わらせるには、さまざまなITツールを活用するのも一つの方法です。入社手続きにおける業務効率化の観点から、ポイントを見ていきましょう。
ポイント(1)人事労務管理システムを活用する
業務効率化を図るうえで取り入れやすいのが、人事労務管理システムです。人事や労務のシステムにはさまざまな種類があり、具体的な機能やメリットは、導入サービスごとに異なります。
たとえば、人事労務の業務を総合的に管理できるシステムの場合、入社手続きの際に従業員の基本情報(氏名・生年月日・経歴・保有資格・適性検査の結果)を入力すると、その内容を人材教育・評価・配置や、毎日の出退勤などの労務管理で活用できるでしょう。
また、一般的なシステムでは、労働条件通知書などのフォーマットも用意しているため、ITツールを使う人事担当者は提供された最新の様式に必要項目を入力するだけで、新入社員に配布する書類の準備も進められるはずです。
こうした専用システムを使えば、事務手続きの負担が減ることで、人事担当者は近年特に重要性が増している内定者フォローやオンボーディングなどにも力を入れやすくなるでしょう。
ポイント(2)電子申請を導入する
人事労務管理システムとあわせて導入を検討してほしいのが、社会保険手続きのオンライン申請(電子申請)です。このサービスには、24時間どこからでも申請できる利点があります。
また、電子申請の環境を整備すると「保険料納入告知額」や「領収済額通知書」、「社会保険料額情報」などもオンライン上で取得できます。定時決定や随時決定も行えるため、入社手続き以外でも大いに役立つ仕組みとなるでしょう。
なお、オンライン申請の具体的な方法は、労務管理システムの有無やその機能の影響を受けて以下のフローのように決まります。
【事業所別おすすめ申請方法の判定フロー】

<引用>:電子申請・電子媒体申請(事業主・社会保険事務担当の方)(日本年金機構)
なお、社会保険の定時決定や随時決定については下記の記事にて詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
入社手続きのスケジュールと追加手続きが必要なケース
入社手続きは、「新人の入社日までにすべてを終わらせれば良い」といったシンプルなものではありません。たとえば、社会保険や税金関連の手続きには、法律で定められた期限があります。
また、新卒学生の内定が早い時期に出た場合には、内定通知書の発行~入社日まで1年以上の内定者フォローが求められることもあるでしょう。こうした長期戦のなかで各手続きの期限を守りながらすべての作業をこなしていくためには、内定~入社手続き完了までのスケジュールをしっかりと作成することも重要になります。
ここでは、人事担当者が行うべき入社手続きや準備の全タスクを一覧表にまとめてみます。また、スケジュールに間に合わないことで追加手続きが発生してしまうケースについても解説していきます。
入社手続きと内定者フォローの一般的な流れとスケジュール
新入社員の一般的な受け入れでは、以下の流れで各種手続きや準備を進めていきます。はじめて入社手続きに携わる方は、以下の表をチェックリスト代わりに活用してもよいでしょう。
| 項目 | 概要 | 法定期限 | |
| 内定~入社1ヵ月前まで | 内定通知書の発行と入社手続きの案内 | 内定通知書・内定承諾書・労働条件通知書などを発行して、 内定者から入社の意思および書類内容への合意を得る |
─ |
| 必要書類の準備と案内 |
入社までに提出してほしい以下書類や情報の入手方法や期限などを案内する
|
||
| 税・社会保険関連手続きの準備 | 日本年金機構や市区町村役場への手続きをスムーズに行うために、様式や手続き方法などを確認しておく | ||
| 定期的な内定者フォロー | 入社日まで、定期的な情報収集やコミュニケーションを続ける | ||
| 内定式などのイベント開催 | 内定者懇談会や内定式などのイベントを実施する | ||
| 入社1ヵ月前~1週間前 | 職場環境の整備 | 机・椅子・ロッカー・社用携帯・社員証などの手配をする |
─ |
| システム環境の整備と設定 |
社内メールアドレスや業務システムなどのアカウントを発行してもらう 人事労務管理システムに新入社員の基本情報や適性検査の結果などを入力する |
||
| 労務関連書類の最終確認 | 雇用契約書や労働条件通知書が回収済みであるか、 そこに署雇用保険・労災保険の加入手続き名捺印があるかを確認する |
||
| 入社当日 | 提出書類の受領とチェック | マイナンバーや口座情報などの必要書類・情報を受け取る |
─ |
| 就業規則と社内ルールの説明 | 就業規則・労働条件通知書・各種資料を示しながら、 勤務時間や休日、福利厚生、コンプライアンスなどについて説明する |
||
| オフィスツアー | 実際に働くオフィスや休憩室などを案内する | ||
| 業務システムの説明 | タイムカード入力や勤怠管理、日報報告などに使うシステムの使い方を教える | ||
| 社員証や備品の提供 | 社員証・制服・専用ロッカー・PC・事務用品などを配布する | ||
| 入社日~1ヵ月以内 | 社会保険の手続き完了 | 健康保険・厚生年金保険の加入手続き | 雇用開始から5日以内 |
| 雇用保険・労災保険の加入手続き | 雇用した月の翌月10日まで | ||
| 税金の手続き完了 | 所得税の手続き | 給与支払日の前日まで | |
| 住民税の手続き | 雇用した日の翌月10日まで | ||
| 法定三帳簿の作成 |
|
入社日から使えるようにしておく |
追加手続きが必要なケース
各種保険の手続きで上記の期限を守れなかった場合、追加書類の提出などを求められる可能性があります。
たとえば、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続きが遅れた場合、法定三帳簿である賃金台帳と出勤簿の追加提出が求められます。また、健康保険の手続きが間に合わないと保険証の交付も遅くなり、新入社員や家族の通院などに支障が出ることになってしまいます。
雇用保険も3ヵ月以上遅れると、賃金台帳と出勤簿に加えて所定の提出物が求められ、6ヵ月以上遅れる場合は遅延理由書の提出が求められることになります。
会社が法定期限を守れない場合、行政機関や新入社員からの印象が悪いものになってしまいます。新入社員の受け入れ手続きを行う際には、法定期限を意識したスケジューリングと進捗管理を行う必要があるでしょう。
人事労務のアウトソーシングならラクラスへ
本記事では、新人の入社手続きについて基礎知識や必要書類、税金と各種保険における加入手続きのポイントを解説してきました。入社手続きには多くの書類や注意点があるため、人事部のなかでも負担に感じている方は多いのではないでしょうか。
もし人事業務における業務効率化をお考えであれば、ラクラスにお任せください。ラクラスなら、クラウドとアウトソーシングを掛け合わせた『BpaaS』により、人事のノンコア業務をアウトソースすることができコア業務に集中できるようになります。
ラクラスの特徴として、お客様のニーズに合わせたカスタマイズ対応を得意としています。他社では難色を示してしまうようなカスタマイズであっても、柔軟に対応することができます。それにより、大幅な業務効率の改善を見込むことができます。
また、セキュアな環境で運用されるのはもちろんのこと、常に情報共有をして運用状況を可視化することも心掛けています。そのため、属人化は解消されやすく「人事の課題が解決した」という声も数多くいただいております。
特に大企業を中心として760社86万人以上の受託実績がありますが、もし御社でも人事の課題を抱えており解決方法をお探しでしたら、ぜひわたしたちラクラスへご相談ください。