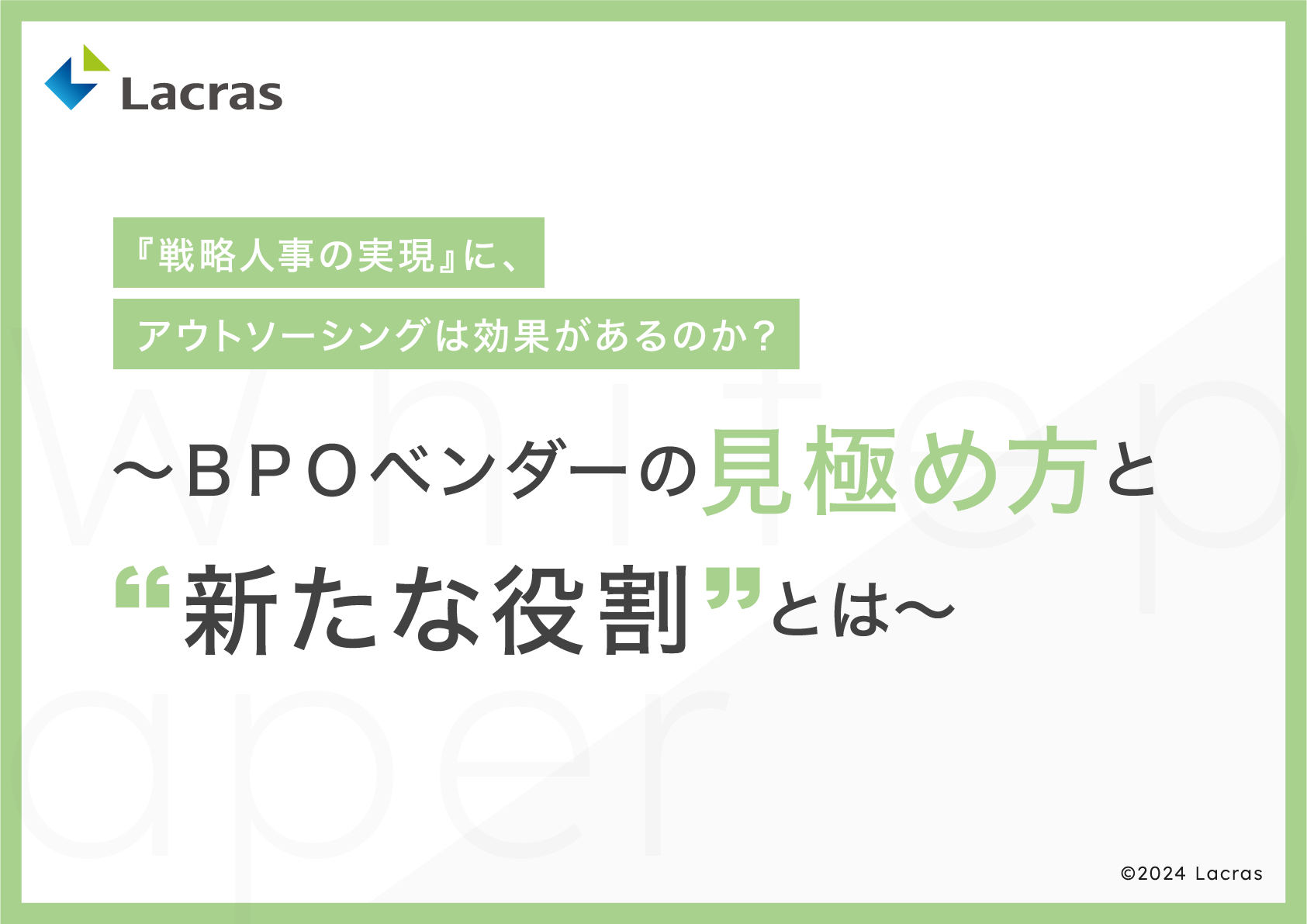人事業務を効率化するには?効果的なツールや効率化できる業務の種類、事例をご紹介

本記事では、人事の業務内容と効率化の必要性、効率化できる仕事などを確認していきます。また、人事業務の効率化をする際の流れや役に立つツール、人事・労務の業務効率化を実現した事例も解説していきますので、ぜひ最後までお読みいただき参考にしてください。
近年のビジネス環境では、人材の流動化や国をあげての働き方改革が進むなかで、人事の役割にも変化が生じるようになりました。また、人事部門にとって大きな負担がかかるような動きも増加しています。たとえば、新卒採用の早期化・長期化などが挙げられるでしょう。
こうしたなか、人事として優秀な人材を獲得し活躍や定着を促していくためには、人事業務を効率化することも重要になってきます。
そこで本記事では、人事の業務内容と効率化の必要性、効率化できる仕事などを確認していきます。後半では、人事業務の効率化をする際の流れや役に立つツール、人事・労務の業務効率化を実現した事例を紹介してまいります。
人事の業務が増えるなかで、少しでも負担を減らしたいと考える方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
人事の業務とは
人事が担う業務は、企業活動に不可欠な経営資源の一つ「ヒト(人)」に関係するもの全般です。そして人事の業務には、大きく「人事管理」と「労務管理」の2種類があります。それぞれの特徴を見ていきましょう。
人事管理
人事管理とは、企業が目標達成や成長を遂げていくために、従業員が最大限の成果をあげられる体制や仕組みをつくる活動の総称です。具体的な業務範囲は企業によって異なる部分もありますが、一般的には以下のカテゴリが人事管理に該当するでしょう。
|
【採用】求人広告の作成、会社説明会の実施、応募者との面談、内定者フォロー 【育成】各種研修の設計・実施、キャリア開発・支援 【評価】人事評価制度の設計・運用、評価者研修の実施 【配置】適材適所の人員配置、最適化に向けた情報収集・ヒアリング 【その他】MVVの浸透、心理的安全性の向上、柔軟な働き方に対応した制度設計、モチベーションが高まる仕組みづくり
|
労務管理
労務管理とは、労働基準法を中心とする法律の定めに従い、従業員の労働に関する事項の整備や管理を行うことです。一般的には、以下の業務が労務管理に該当します。
|
|
労務管理は、人事管理のうち労使関係や労働条件に関する一部分を指すことが多いです。これに対して人事管理は、人材の処遇全体をカバーするイメージになるでしょう。
人事の業務で効率化が必要な理由
近年のビジネス環境では、複合的な要素の影響から人事業務の効率化が急務になっています。ここでは、多くの人事部門に該当する3つの要因を解説しましょう。
理由(1)人事業務が増大・複雑化している
人事業務の効率化が求められる大きな要因は、政府による以下のような施策や社会環境の影響から、人事部門の仕事に増大や複雑化が生じている点です。
|
|
『ダイバーシティ経営』についての詳細は、下記のコラム記事をご確認ください。
【コラム】ダイバーシティとインクルージョンの違いとは?多様な人材が活躍する環境の作り方、成功事例を解説
たとえば、終身雇用の崩壊で転職が一般化すると、それだけ従業員の出入りも多くなり、人事部門が担う事務手続きも増加しやすくなります。
また、自社の価値を高める目的で「働き方改革」や「ダイバーシティ経営」に取り組むと、新たな仕組みの設計・運用・見直しが求められることで、負担が大きくなるでしょう。
理由(2)人事の人材確保が難しくなっている
人事部門の業務負担が増えるなかでさらに追い打ちをかけているのが、人材確保の難しさです。パーソル総合研究所の調査結果によると、約6割の企業で人事の人材不足が生じていることがわかっています。
<参考>:人事部大研究 調査結果<PDFファイル>(パーソル総合研究所)
また、近年のビジネス環境では、多くの業種で売り手市場が続くなかで、人件費も上昇しやすくなっています。こうしたなかで、たとえば「働き方改革」や「ダイバーシティ経営」に向けた制度設計などもできる人事の人材を確保するとなれば、採用コストと提示する報酬(給与)の両面で厳しい状況に直面するでしょう。
理由(3)人事部門の重要性がさらに高まっている
「仕事が増える・良い人材が獲得できない」といった悪循環のなかでも、ビジネス環境における人事部門の重要性はさらに高まる兆しがあります。その要因として非常に大きいのが、政府が推進する『人的資本経営』の影響です。
人的資本経営とは、人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげていく経営のあり方になります。
経済産業省が公開する「人的資本経営コンソーシアム好事例集」では、従来の「人事」に、これからの時代は「人材戦略」のアクションが求められるとしています。両者の違いは以下のとおりです。
|
【人事】人事諸制度の運用・改善が目的。経営戦略と連動していない。 【人材戦略】持続的な企業価値の向上が目的。経営戦略から落とし込んで策定。
<引用>:人的資本経営コンソーシアム好事例集<PDFファイル>(経済産業省)
|
上記の内容は、人事の役割における「守り」から「攻め」への変革を求めるものでしょう。また政府では、日本経済発展の一環として、各企業に対して人的資本の情報開示を段階的に求めはじめています。
こうしたなかで、近年の人事部門には「仕事が増える・良い人材が獲得できない」の二重苦が生じやすくなっています。
この状況で人事部門が「攻めの人材戦略」に携わるためには、従来から続く業務の棚卸しや効率化が不可欠です。業務効率化によって人事部門のメンバーが「コアな業務」に専念できる環境を整えることが、人的資本経営を進めるための鍵になるでしょう。
【関連資料】『戦略人事の実現』に、 アウトソーシングは効果があるのか? ~BPOベンダーの見極め方と “新たな役割”とは~
人事の業務で効率化できる仕事とは?
人事部門で効率化できる業務はいくつも挙げられます。ここでは、大きく4つを挙げて詳しく見ていきましょう。
(1)人材採用
人材採用は、企業の将来を左右する重要業務です。そのなかで効率化できるカテゴリには、以下のようにさまざまなものがあります。
|
|
人材採用における業務効率化のポイントは、上記の各工程が連動していることから、上流工程のやり方やベクトルを見直すことで、下流工程にも好循環が生まれやすくなる点です。
たとえば、これまで「自社ホームページと大手のサービスに求人を出す」というどちらかといえば受け身の方法で母集団形成をしていた会社が、自社の現状分析をしっかり行ったうえで、採用戦略・計画をしっかり立案する方向性に転換したと仮定します。
そうすると、「自社が求める人材はどの市場にいるのか?」や「どうすれば競合優位性を高められるか?」といった考えにもとづく攻めの採用活動が行えるようになり、結果として選考・内定・定着支援に生じていた問題や負担も改善しやすくなるでしょう。
また、もともと採用力が低かったり効果的な活動を行うリソースがなかったりする場合には、採用活動の代行機能がついた人材紹介やダイレクトリクルーティングなどのサービスを活用してもよいでしょう。
(2)就業管理
就業管理とは、いわゆる勤怠管理のことです。近年のビジネス環境では、ダイバーシティ経営や雇用形態の多様化などの影響から、就業管理の複雑性が増しています。
また、リモートワークの導入が進んだ場合、「自宅などで働く人」と「オフィス出社する人」がでてくるわけですから、従来はメンバー全員がオフィスで打刻していたタイムカードでは、就業管理の運用ができなくなることもあるでしょう。
ビジネス環境にこうした変化が進むなかで、近年ではデータ登録の場所を限定しないクラウド型の就業管理システムを導入する企業も増えるようになりました。位置情報や生体認証などがついたシステムで勤怠データを登録してもらうと、不正も防ぎやすくなるでしょう。
(3)人事評価
近年のビジネス環境では、終身雇用・年功序列制度が崩壊し多様な人材の共創・協働が必要となるなかで、人事評価の効率化と適正化の両方が求められるようになりました。
人事評価の適正化は、自社に合う優秀な人材の活躍・定着を促すためにも必要なものです。それはつまり、人事評価の適正化が企業の人材採用・育成の課題を改善するうえでも、非常に重要な役割を担うことを意味します。
また、近年では、1人の従業員が複数プロジェクトに参加する「マトリクス組織」への注目も集まっています。仮にマトリクス組織を導入した場合、1人の従業員に対して複数の上司が存在することもあるでしょう。
このように組織形態や社員の働き方が複雑化するなかで適正な人事評価を行うためには、従来の紙・Excelでの運用から専用システムに変えるといった効率化も必要となります。
(4)給与計算
給与関連の業務効率化では、クラウド型のシステム導入や給与計算アウトソーシング(外部業者への委託)が選択されることが多いです。アウトソーシングを選択する場合、以下の仕事の全部もしくは一部を切り出して委託するイメージになります。
|
|
また、毎月の給与計算にはさまざまなプロセスがありますから、棚卸しを通して一つひとつの仕事を見直すことも効率化につながる施策となるでしょう。給与計算を業務委託するメリットやデメリットについては、下記のコラムも参考にしてみてください。
人事の業務を効率化する流れは?
人事業務の効率化で高い効果を得るためには、適切な方法・流れで作業を進める必要があります。ここでは、多くの企業で行われている5つのステップについて、詳しく解説しましょう。
ステップ(1)すべての業務を洗い出す
限られた費用・工数で業務効率化の効果を最大化するためには、まず、人事部門が行っているすべての業務を洗い出すことが重要です。ここで1つでも漏れがあると、ベストな選択が難しくなる可能性もあります。
業務の洗い出しは、施策の範囲を決めるうえでも重要になるものです。多くの時間をかけてでも可視化していきましょう。
ステップ(2)課題を整理する
すべての業務を洗い出せたら、次は人事部門にどんな課題があるかを見ていきます。具体的には、以下のようなものが挙げられるでしょう。
|
【採用】母集団形成の時間とコストを削減したい 【採用】人手不足で内定者フォローまで手がまわらない 【給与】締め日以降の残業が増えている 【給与】年末調整のアルバイト応募が少ない 【人事評価】評価内容に対する若手からの不満が多い 【人事評価】評価シートが複雑すぎて評価者の負担が大きくなっている など
|
人事部門の業務にはたくさんのカテゴリや種類がある一方で、効率化に使えるコストや工数は限られていることが多いでしょう。そういったなかで効果の高い施策を選択・実行していくためには、洗い出した課題に優先順位をつけることも重要になります。
ステップ(3)業務効率化のゴールを設定する
業務効率化の効果を高めるためには、「何がどういう状態になると成功といえるか?」というゴールや目標を設定することも必要です。ゴール設定のポイントとしては「内容が具体的かつ達成可能であり、あとで効果測定ができること」があげられるでしょう。
こうした要素を満たすゴールを設定するためには、下記のように目標設定のフレームワークである『SMART』を活用するのも一つの方法です。
|
|
たとえば、人材採用で業務効率化をする場合、SMARTに当てはめた目標は「◯◯サービスを利用して内定者フォローに力を入れることで、2025年度の内定承諾後の内定辞退率を10%以下にする(2023年度は60%)」といったものが設定できるでしょう。
ステップ(4)効率化する範囲と施策を決める
ゴールが明確になったら、その目標を達成するために、「どこからどこまでに、どういう施策を実施するか?」を考えます。一般的な施策としては、以下の種類があるでしょう。
|
【廃止】その業務自体をやめてしまう 【集約】作業場所や作業時期を集約する 【代替】担当者や作業手順を入れ替える 【外注化】全部もしくは一部業務を切り出してアウトソーシングする 【標準化】業務マニュアルを作成し、属人化を解消する 【簡略化】作業をシンプルにする 【自動化】専用システムやアプリを導入する など
|
業務効率化にそれなりの費用をかけられる場合は、外注化や自動化も選択しやすいはずです。一方で、少ない費用・人員のなかで効率化をはかる際には、廃止・集約・代替・簡略化・標準化が中心になるでしょう。
ここで一つ注意点があります。それは、非効率な作業や本質的な問題を残したままで一部のアウトソーシングを行っても、自社が求める成果が得られない可能性がある点です。
アウトソーシングのようにそれなりの費用がかかる施策を選択する場合は、それによって高い費用対効果が得られる状態になる程度まで、現場業務の廃止・集約・代替・簡略化などを進めておく必要があるでしょう。
ステップ(5)施策を実行する
先ほどのステップ(4)で決めた施策を実行していきます。リソースに余裕があれば、中途半端にならない範囲内で並行して進めてもよいでしょう。
ステップ(6)実行結果を振り返り改善する
人事の業務効率化は、施策を導入・実行して終わりではありません。何らかの施策を行った場合、それによる効果・結果を以下のように見ていく必要があります。
|
|
基本的には、PDCAを回しながら効率化の施策および人事部門の業務全体をブラッシュアップし続けるイメージになるでしょう。

人事業務の効率化に役立つツールのご紹介
人事の業務効率化では、専用のITシステム・サービス・ソフト・アプリをうまく活用すると効果的です。ここでは、人事部門で導入されることが多い4つのツールについて、それぞれの特徴を見ていきましょう。
(1)Excel
Excelは、Microsoft社が開発・販売する表計算ソフトです。法人SaaSの比較メディアUtillyの調査結果によると、20歳以上60歳未満の社会人(公務員・経営者・役員・会社員)の約6割が表計算ソフトを使っており、そのうち7割がMicrosoftのExcelであることがわかっています。
<参考>:Microsoft Excelがトップ。Googleスプレッドシート・Numbersの割合が増加 | 表計算ソフトの利用に関する調査(2024年4月)(株式会社GO TO MARKET)
ビジネス環境でこれだけ普及しているExcelであれば、アナログな方法からの業務効率化においても、紙で管理していた人事情報をExcelで管理したり、給与計算をExcelのマクロ関数で効率化したりするなどで導入しやすいでしょう。
ただし、自部門で独自にマクロを組んだExcelシートは、法改正のたびに自分たちでメンテナンスする必要があります。ですから、マクロ関数に詳しい人が離職してしまった場合には、Excelでの運用が難しくなってしまうかもしれません。
(2)人事管理システム
人事管理システムには、大きく分けて以下の2つの種類があります。
|
|
後者は、人事業務の総合システムのようなイメージです。具体的な機能・範囲はサービスごとに異なりますが、人事管理システムを導入すると、以下の業務データを一元管理できることが多いでしょう。
|
|
上記機能を搭載したシステム導入をした場合、たとえば「従業員に入力してもらった勤怠データは、人事担当者がシステム上でチェックする。そのデータをもとに給与計算をする」といった運用も可能になるでしょう。
(3)採用管理システム
採用管理システムは、求人や応募者の管理を行い、効果的な採用活動につなげていくものです。採用管理システムの場合、「新卒採用に強いもの」や「アルバイト・派遣採用に強いもの」のように、ターゲットごとに選ぶべきサービスが変わる傾向があります。
一般的な採用システムには、以下の機能が搭載されていることが多いでしょう。
|
|
近年の採用環境では、新卒学生の通年採用もかなり拡大しています。こうしたなかで、長期に渡ってインターン参加者や応募者とコミュニケーションをはかり、優秀な人材の獲得につなげていくためには、専用システムによる応募者管理が必要になってくるでしょう。
(4)労務管理システム
労務管理システムは、労働基準法などの法律にもとづき、従業員の勤怠管理・給与管理・労務に関する各種手続きを効率的に行うためのものです。労務管理全体のカバーができるシステムには、以下の機能が備わっている傾向があります。
|
|
従業員の働き方や属性が多様化するなかで、労務管理システムの必要性は特に高まっているでしょう。
人事や労務の業務効率化を実現した事例
人事・労務の業務効率化には、さまざまな種類があります。これから初めて効率化にチャレンジするが、何から始めるべきかわからないという場合、各企業の成功事例を参考にするとよいでしょう。
ここでは、人事労務領域で行える業務効率化の成功事例を2つ紹介しましょう。
事例(1)ペーパレス化の推進
たとえば、各種届出書・一覧表・年末調整の書類などを「紙」で管理している場合、以下のような問題が起こりやすくなります。
|
|
これらの問題を解消するためには、可能なものからペーパレス化を進めることも一つの方法です。ペーパレス化の多くは、いま話題のDX化につながるものでしょう。たとえば、年末調整を紙運用からITシステム運用に変える場合、「従業員に申請書類を配布する」「記入した書類を回収する」といった作業から開放されることになります。
事例(2)アウトソーシングの推進
「そもそも人手が足りない」や「給与計算や年末調整のミスが多発している」などの問題を抱えている場合、業務の一部もしくは全部を切り出して外部の事業者にアウトソーシングしてもよいかもしれません。
アウトソーシングを利用すると、人事担当者の負担が軽減されることに加えて、プロによる適切な事務手続きが進められるメリットも得られます。それはつまり、人事業務の質が向上するということでもあります。人事業務のクオリティが上がれば、従業員に生じていた以下のような不満も解消できるかもしれません。
|
|
また、近年の人事部門では、先述のとおり自社に合う人材を獲得するための採用戦略やダイバーシティ経営を浸透させるための仕組みづくりといった、非定型なコア業務も多くなっているのが課題といえます。
こうした業務の優先度が高まるなかで質の高い仕事を進めるためには、たとえば給与計算などの定型業務を切り出し、人事アウトソーシングに委託することも必要になってくるでしょう。
給与計算アウトソーシングについてはこちらのコラムで詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
人事業務の課題解決ならラクラスへ
本記事では、人事の業務内容と効率化の必要性、効率化できる仕事などを紹介させていただきました。人事・労務の業務効率化を実現した事例もとりあげましたが、まだまだ効率化を果たせていないご担当者も多いのではないでしょうか。
もし人事業務における業務効率化をお考えであれば、ラクラスにお任せください。ラクラスなら、クラウドとアウトソーシングを掛け合わせた『BpaaS』により、人事のノンコア業務をアウトソースすることができコア業務に集中できるようになります。
ラクラスの特徴として、お客様のニーズに合わせたカスタマイズ対応を得意としています。他社では難色を示してしまうようなカスタマイズであっても、柔軟に対応することができます。それにより、大幅な業務効率の改善を見込むことができます。
また、セキュアな環境で運用されるのはもちろんのこと、常に情報共有をして運用状況を可視化することも心掛けています。そのため、属人化は解消されやすく「人事の課題が解決した」という声も数多くいただいております。
特に大企業を中心として760社86万人以上の受託実績がありますが、もし御社でも人事の課題を抱えており解決方法をお探しでしたら、ぜひわたしたちラクラスへご相談ください。