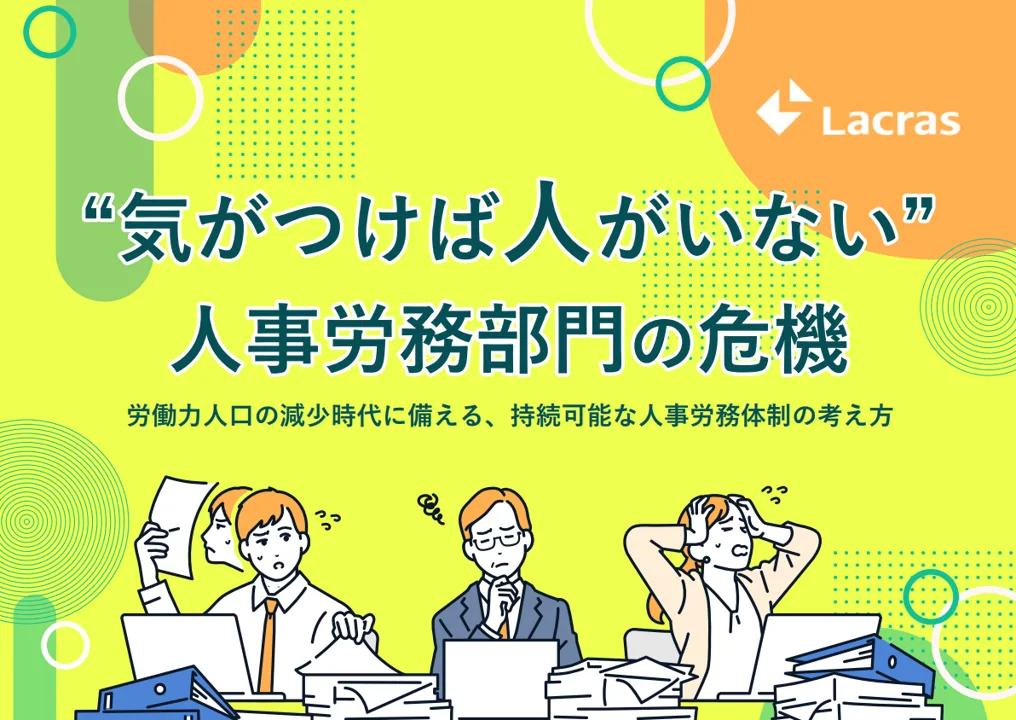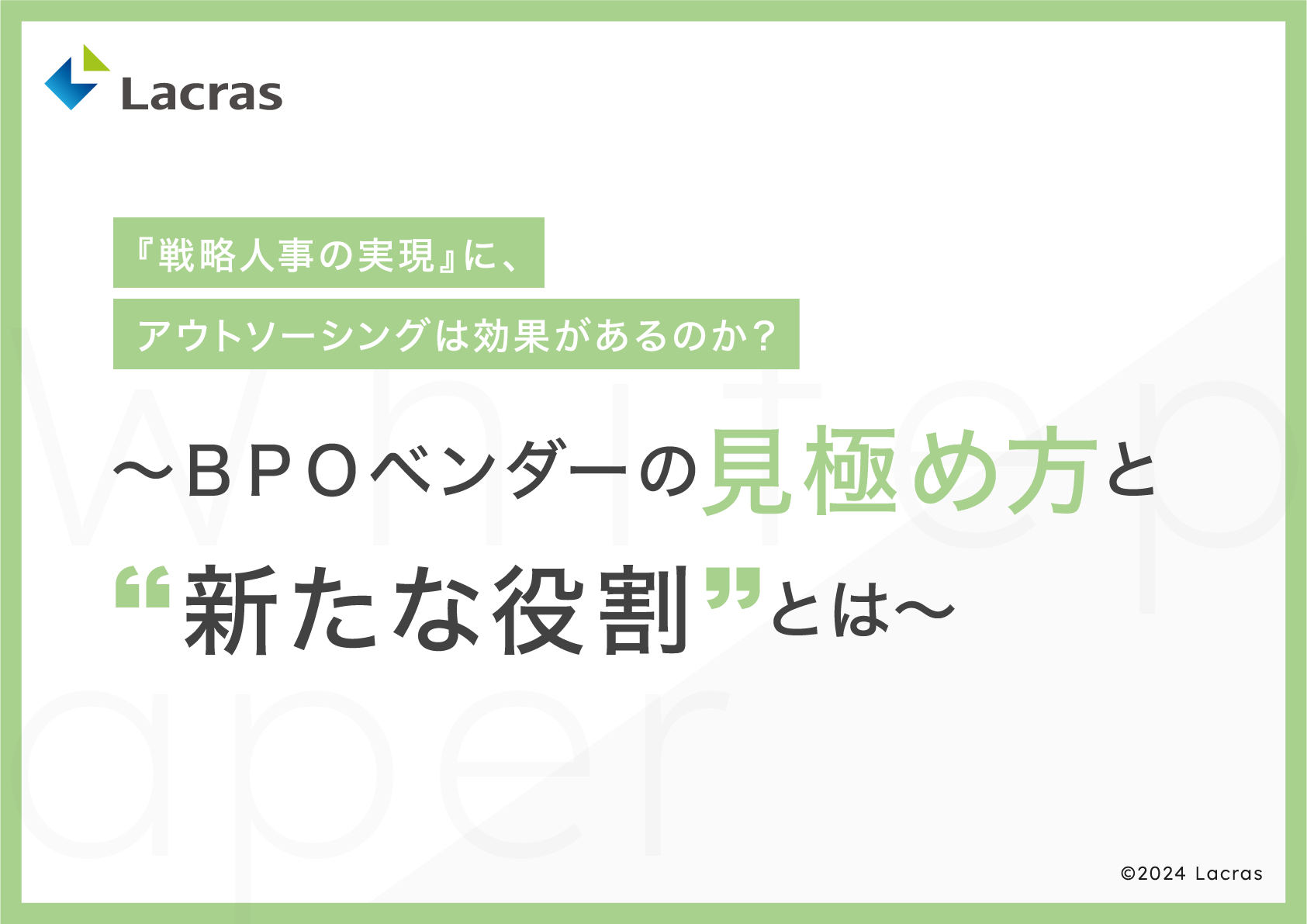ダイバーシティとインクルージョンの違いとは? 多様な人材が活躍する環境の作り方、成功事例を解説

本記事では、ダイバーシティとインクルージョンという概念の意味や違いをわかりやすく解説していきます。ダイバーシティ&インクルージョンに関連する法律や、関連施策を導入する際の進め方やポイント、成功事例なども紹介してまいりますので、ぜひ参考にしてください。
近年のビジネス環境では、政府が推進するさまざまな施策や多様化する顧客ニーズなどの影響から、『ダイバーシティ』と『インクルージョン』を重視した組織づくりの重要性が高まるようになりました。
こうしたなかで、多様な人材が定着・活躍しやすい環境を整備するためには、ダイバーシティとインクルージョンという各概念の意味や目指す状態を理解することが必要です。また、人事部門の大事な役割である『人材採用』や『オンボーディング』の効果を高めるうえでも、ダイバーシティとインクルージョンは大きな鍵を握る概念だといえるでしょう。
そこで本記事では、ダイバーシティとインクルージョンという概念の意味や違いをわかりやすく解説していきます。記事の後半では、ダイバーシティ&インクルージョンに関連する法律や、関連施策を導入する際の進め方やポイント、成功事例なども紹介してまいります。
ダイバーシティ&インクルージョンが実現する仕組みや環境づくりに関心がある方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
「ダイバーシティ」と「インクルージョン」の違い
「ダイバーシティ&インクルージョン」を構成する2つの言葉には、それぞれに異なる意味があります。この概念を深く理解して自社の環境整備に役立てるうえでは、各用語が目指す状態を知ることも重要です。
ここでは、まず『ダイバーシティ』と『インクルージョン』について、各用語の意味や違いを整理していきましょう。
ダイバーシティとは?
ダイバーシティ(diversity)の直訳は、「多様性」です。内閣府の『令和元年度 年次経済財政報告』では、ダイバーシティを「多様な人材」としています。
近年のビジネス環境では、政府が推進する働き方改革やいわゆる女性活躍推進などの影響から、雇用形態や性別などの面でさまざまな“違い”を持つ多様な人たちが一緒に働くことが多くなりました。また、日本で働きたい外国人の労働参加も進んでおり、働く人たちの国籍や価値観の“差異”も生じやすくなっています。
|
<参考>:令和元年度 年次経済財政報告|第2章 第1節 多様な人材が労働参加する背景(内閣府)
|
インクルージョンとは?
インクルージョン(inclusion)の直訳は、「包括」です。
2022年に第八版が発刊された三省堂国語辞典では、インクルージョンを「いろいろな人が個性・特徴を認めあい、いっしょに活動すること」としています。また、前述した内閣府の『令和元年度 年次経済財政報告』では、「多様な人材がそれぞれの能力を活かして活躍できている状態」と定義しました。
<参考>:令和元年度 年次経済財政報告|第2章 第1節 多様な人材が労働参加する背景(内閣府)
インクルージョンの考え方が日本のビジネス環境で使われるようになったきっかけは、2010年に日本経済団体連合会(経団連)が公開した「企業行動憲章実行の手引き(第6版)」です。この資料内における以下の部分が、ダイバーシティ&インクルージョンにあたると考えられます。
|
(2)多様な人材の就労参加 従業員が相互にさまざまな考え方や価値観を認め合い、刺激を与え合うことが企業にダイナミズムと創造性をもたらす。こうした認識の下、バリアフリーやノーマライゼーションの促進なども含めて、意識・風土の改革などを進めながら、国籍、性別、年齢、障がいの有無などを問わず、多様な人材が十分に能力を発揮できる職場環境を整備する。
<引用>:企業行動憲章 実行の手引き<PDF>(社団法人 日本経済団体連合会)
|
ダイバーシティとインクルージョンの違い
ここまでの内容をまとめると、組織におけるダイバーシティとインクルージョンには、以下の違いがあることが見えてきます。
|
【ダイバーシティ】多様な人材が存在する状態(一定割合の多様性が存在する状態)
【インクルージョン】多様な人材が互いの違いを認め合ったうえで能力を発揮し、活躍できている状態
|
ダイバーシティは、どちらかといえば多様な人材を「組織に受け入れること」に重きを置いた概念です。これに対してインクルージョンは、「お互いの違いを認めて活かし合うこと」に主眼が置かれているでしょう。
「ダイバーシティ&インクルージョン」とは
ここまで各用語について見てきましたが、では「ダイバーシティ&インクルージョン」とは、どういう意味なのでしょうか。
ダイバーシティ&インクルージョンとは、多様な人材が互いの異なる価値観や考え方などを受け入れ、各自が自分のスキルや能力を最大限に発揮できる状態をつくることです。
多様な人材には、仕事の進め方や考え方、生活習慣などでさまざまな「違い」があります。組織のメンバーがこの「違い」を認められなければ、信頼関係が築けません。また、お互いを信頼できなければ、組織のゴール達成に不可欠な協働・共創も難しくなるでしょう。
ダイバーシティ&インクルージョンでは、各自が「違い」を認め合ったうえで、組織のゴール達成に向けて「お互いを活かし合うこと」が求められます。
経済産業省では、ダイバーシティ&インクルージョンの考え方を重視し、自社の価値創造やイノベーションにつなげていく経営を、「ダイバーシティ経営」と位置付けて推進しています。ダイバーシティ経営の定義は、以下のとおりです。
|
多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営
<引用>:ダイバーシティ経営の推進(経済産業省)
|
また、多くの企業で実施されている以下のような取り組みも、ダイバーシティ&インクルージョンとの関連性が高いものといえます。
|
|
「ダイバーシティ&インクルージョン」が求められる背景
近年の日本企業では、ダイバーシティ&インクルージョンが求められるようになってきていますが、その背景には、いくつかのポイントがあります。ここでは、主要な背景を3つ挙げて見ていきましょう。
背景(1)労働人口の減少や採用難による人手不足
昨今の日本では、少子高齢社会の加速に伴う労働人口減少などの影響から、自社に合った優秀な人材の獲得が難しくなっています。また、新卒の採用市場には早期化・長期化・複雑化なども起きており、自社に適した新卒・若手社員の採用に苦戦する会社も増えるようになりました。
こうしたなかで注目されているのが、ダイバーシティ(=多様な人材)です。
近年では、経済産業省もダイバーシティ経営を推進するなかで、日本の従来型組織を支えてきた「フルタイム勤務の男性社員」ではない人材属性に目を向けるようになりました。そうして、いわゆる“ブルーオーシャン”の中で優秀な人材を獲得しようとする企業が増えてきているのです。
また、日本で働きたい外国人が増え、人手不足に悩む企業との間でマッチングがしやすくなったことも、ダイバーシティ&インクルージョンの浸透に大きな影響をもたらしているでしょう。
<参考>:第3節 我が国における外国人労働者の現状と課題<PDF>(内閣府)
<参考>:ダイバーシティ経営の推進(経済産業省)
背景(2)ビジネスのグローバル化と顧客ニーズの多様化
さまざまな価値観や文化的背景を持つ人材が求められるようになった背景には、市場・産業のグローバル化と顧客ニーズの多様化・細分化が進んだ影響もあります。
お客様が求めていることが掴みづらい時代に新商品・サービスの開発などを行ううえでは、女性・外国人・LGBTQ・障害者といった多様な人材からの視点やアイデアが必要となるのです。
背景(3)日本型組織と多様な人材のミスマッチ
ここまで紹介した2つの要素は、どちらかといえばダイバーシティが普及した背景です。そこにインクルージョンが加わった背景には、従来の日本型組織にありがちな以下の特徴が影響しています。
・同調性が高く、上司や先輩への忖度が生まれやすい
・高い才能や個性を持つ人材が「出る杭は打たれる」になることもある
・高い排他性から自由な発想や意見が生まれづらい
これらの特徴を持つ典型的な日本型の組織に、価値観や考え方などが異なる外国人人材やフリーランス、若い世代などが入ってくると、既存のメンバーが「自分たちとの違い」を受け入れられなくなることがあります。そうして、差別や衝突、ハラスメントといった問題が起こりやすくなってしまうのです。
企業側としては、その「違い」を求めて多様な人材を獲得しているわけですから、既存のメンバーが働きづらくなってしまうのは本末転倒でしょう。
また近年は、個人がインターネット上で自由に考えを発信できる時代です。差別やハラスメントの事実がSNSなどに投稿された場合、自社の悪い評判が拡散されて社会的信用の低下に繋がってしまうことも起こりかねません。
こうしたなかで最近の日本企業では、多様な人材を組織に受け入れる「ダイバーシティ」に加えて、お互いの違いを認め合い、各自が活躍しやすい環境づくりをする「インクルージョン」の仕組みが求められるようになったのです。
「ダイバーシティ&インクルージョン」に関連する法律や制度
政府では、各企業におけるダイバーシティ&インクルージョンを推進するために、さまざまな法律や認定制度などを整備しています。社内でダイバーシティ&インクルージョンに力を入れる際には、法律に則った仕組みをつくっていくことが大切です。
ここでは、代表的な4つの法律や制度について解説しましょう。
(1)女性活躍推進法
女性活躍推進法とは、働く場面で「女性が活躍しやすい社会」を構築するために作られた時限立法です。時限立法とは、一定の有効期間を付した法律となり、女性活躍推進法の有効期間は2016年4月からの10年間です。
女性活躍推進法の主な役割は、企業に対して女性活躍推進につながる行動計画の策定と、女性活躍に関する情報の公表を義務付けている点です。たとえば、一般事業主が行うべき取り組みとして以下の項目が義務付けられています。
|
【常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主】
(1)自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析 (2)「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」と「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」の区分ごとに1項目以上(計2項目以上)を選択し、それぞれ関連する数値目標を定めた行動計画の策定、社内周知や公表 (3)行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出 (4)女性の活躍に関する「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」の区分から男女の賃金の差異を含めた2項目以上、「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」の区分から1項目以上を選択し、合計3項目以上の情報公表
<引用>:女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!<PDF>(厚生労働省)
|
|
【常時雇用する労働者の数が101人以上300人以下の事業主】
(1)自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析 (2)1つ以上の数値目標を定めた行動計画の策定、社内周知、公表 (3)行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出 (4)女性の活躍に関する1項目以上の情報公表
<引用>:女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!<PDF>(厚生労働省)
|
厚生労働省では、一般事業主行動計画の策定・届出等を行った事業主のうち、女性活躍推進に向けた取り組みの実施状況が優良な企業に対して、「えるぼし認定」を与えています。自社の女性活躍推進に力を入れる場合は、より水準の高い「プラチナえるぼし認定」を目指してもよいでしょう。
<参考>:女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)(厚生労働省)
(2)障害者雇用促進法
障害者雇用促進法は、障害者の自立を促進するための措置を総合的に講じることに加えて、障害者の職業安定を図ることを目的に創設された制度です。この法律は、大きく分けて以下の5つのカテゴリで構成されています。
|
<出典>:障害者雇用促進法の概要(昭和35年法律第123号)<PDF>(厚生労働省)
|
障害者雇用促進法は、近年の時勢に応じた改正の多い制度です。特に2023年4月以降は、ダイバーシティ&インクルージョンにも関係する以下の改正が実施されています。
|
【2023年4月~】
【2024年4月~】
【2025年4月~】
<参考>:障害者雇用促進法の概要(厚生労働省)
|
(3)高年齢者雇用安定法
高年齢者雇用安定法とは、働く意欲がある人なら誰でも年齢に関係なく能力を十分に発揮できるように、高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律です。この制度では、高年齢者を雇用する際のルールとして、以下の5つを定めています。
|
<出典>:高年齢者の雇用|雇用する上でのルール(厚生労働省)
|
また、高年齢者雇用安定法では、各事業所の実情に応じた以下の措置を実施することを企業側に求めています。
|
<引用>:高年齢者の雇用|雇用する上でのルール(厚生労働省)
|
(3)外国人を雇用する際の届け出
日本国内における外国人の就労活動は、出入国管理及び難民認定法(いわゆる入管法)で定められた在留資格の範囲内で認められるものです。そのため、外国人人材を雇い入れる際には、本人が所持する在留カードもしくはパスポートなどを確認し、就労が認められるかどうかを判断しなければなりません。
また、外国人労働者を雇用する場合、外国人が求職活動に必要な雇用情報や雇用慣行に関する知識を十分に有していないことに鑑み、職場における能力の有効な発揮や、職場適応を容易にするための施策を行う必要があります。
具体的に実施すべき措置の内容は、2020年6月に施行された「労働施策総合推進法」に基づくものです。詳細については、厚生労働省のページや資料を確認してください。

「ダイバーシティ&インクルージョン」の進め方
ダイバーシティ&インクルージョンは、多様な人材が違いを認め合い、それぞれがチーム内で活躍できてこそ「効果があった」といえるものです。この取り組みの有効性を高めるためには、適切な流れで導入準備や運用をしていく必要があります。
ここでは、一般的に行われている6つのステップを詳しく解説しましょう。
ステップ(1)現状を分析したうえで目的・目標を設定する
ダイバーシティ&インクルージョンの取り組みでは、次のようなことが求められます。
・自社における多様な人材に関する課題の解決
・「女性活躍推進法」「高年齢者雇用安定法」「障害者雇用促進法」などの制度基準をクリアするための施策であること
これから新たにダイバーシティ&インクルージョンの施策を導入する場合、以下のような観点から自社の課題を洗い出すことが必要です。
|
|
既存の制度で義務もしくは努力義務になっている項目は、なるべく早めに着手し課題を解決する必要があるでしょう。それ以外については、現状のリソースでできる施策に優先順位を付けたうえで、1つずつ導入・実行していきます。
また、ダイバーシティ&インクルージョンの取り組みを始める際には、自社が目指す数値目標やビジョンを設定することも大切です。
たとえば、「女性人材の3年定着率70%以上」などの数値目標に加えて、「全メンバーにとって心理的安全性が高い組織をつくる」や「ハラスメントのない組織を目指す」といった組織文化の変革や定性的な指標を入れてもよいでしょう。
ステップ(2)経営層にコミットメントしてもらう
経営層に責任を持ってリーダーシップをとってもらうことは、ダイバーシティ&インクルージョンの成功に欠かせない要素です。
たとえば、従来組織のなかで、一部の属性に対する差別問題があったと仮定します。そこで経営層にも差別意識があった場合、「社長だって差別しているのだから、従業員の自分も差別していいだろう」などの考えがひろがってしまうと、現場における意識変革は進みづらくなるでしょう。
こうした問題を防ぐためには、経営陣がダイバーシティ&インクルージョンに力を入れることを発信し、自らリーダーシップをとるなかで「有言実行」を続けていくことが重要です。
経営層のコミットメントによって、「社長も変わったから、自分たちの意識も変えていかなければ!」と感じられる状態を作ることが理想といえるでしょう。
ステップ(3)インクルーシブな環境・仕組みを設計する
ダイバーシティ&インクルージョンでは、すべての人材が以下のように感じられる状態を目指していくべきです。
|
職場の一員として認められており、自分の独自性や能力は組織の成功のために必要とされている
<引用>:多様な個を活かす経営へ~ダイバーシティ経営への第一歩~<PDF>(経済産業省)
|
このような実感(ゴール)から逆算して必要な仕組みや環境を構築すれば、従業員の認識との乖離が生まれづらくなるはずです。
また、ダイバーシティ&インクルージョンの土台になるのが、心理的安全性の高いチームづくりになります。心理的安全性とは、組織で働く人たちが心的ストレスを抱えることなく業務に従事したり、意見の発信や質問を自由にできたりする状態です。
心理的安全性の高いチーム内では、たとえば国籍や文化的背景が異なる人が独自の意見を発信したときに、「会社のために意見を言ってくれている」や「斬新な意見で面白い」などのポジティブな受け取りが多くなります。
さらに、ダイバーシティ&インクルージョンでは、以下のような取り組みが有効になる場合もあるでしょう。
|
|
ステップ(4)意識変革につながる社員教育を実施する
ダイバーシティ&インクルージョンを成功させるためには、研修を通して従業員の意識を変えていくことも大切です。具体的なプログラムには、以下のような項目が入るでしょう。
|
|
ダイバーシティ関連の研修には、社内での内製のほかに外部講師に依頼する方法があります。自社でのプログラム設計や指導が難しい場合、外部の専門講師に相談してもよいでしょう。
ステップ(5)多様な人材を採用する
ある程度の仕組みを設計・導入し、意識変革につながる教育を終えたら、多様な人材を実際に獲得するためのダイバーシティ採用に入っていきます。多様な個性を持つ優秀な人材を獲得するためには、以下のポイントを押さえながら採用活動を進めていく必要があるでしょう。
|
|
外国人や障害者を雇用する際には、厚生労働省のパンフレットを活用するのもおすすめです。障害者雇用の資料には、面接ポイントや質問例も書かれています。
なお、LGBTQなどの性的マイノリティの場合、応募や一次面接の段階でその属性がわからない可能性もあります。
各人材の属性や文化的背景などがわからないなかで公平な採用を行うためには、想定されるひと通りの属性について理解を深めたうえで、相手に失礼にならない質問例などを考えておく必要があるでしょう。
<参考>:(1)障害者雇用の進め方(初めての障害者雇用)<PDF>(厚生労働省)
<参考>:外国人雇用はルールを守って適正に<PDF>(厚生労働省)
<参考>:多様な人材が活躍できる職場環境づくりに向けて~ 性的マイノリティに関する企業の取り組み事例のご案内 ~<PDF>(厚生労働省)
ステップ(6)定期的な評価と施策の改善を続ける
ダイバーシティ&インクルージョンの施策は、導入して終わりではありません。1つの施策を導入したあとは、現場の反応や離職率・定着率などのデータを見ながら効果を振り返り、必要に応じて見直しをする必要があります。
また、仮に多様な人材の定着率や生産性が高まり、組織風土の変革がうまくいった場合でも、高年齢者雇用安定法や障害者雇用促進法などの改正内容に従いながら、自社のダイバーシティ&インクルージョンをさらにブラッシュアップしていくことが重要でしょう。
「ダイバーシティ&インクルージョン」の取り組み事例
ダイバーシティ&インクルージョンの取り組みを導入・実施する際には、自社と同じ業種・業界の企業が行っている事例を参考にしてみるのもおすすめです。ここでは、経済産業省や経済団体連合会が注目する4社のダイバーシティ&インクルージョン事例を紹介しましょう。
事例(1)日本生命保険相互会社
日本生命保険相互会社では、多様な人材が活躍できる風土の醸成を目指し、男性社員や管理職の意識変革を中心とするさまざまな施策を実施しています。
なかでも特に力を入れているのが、男性育児休業の促進です。具体的には以下の推進フローを実施することで、8年連続100%の取得率を達成しているようです。
|
|
<参考>:男女ともに活躍できる組織風土づくり(日本生命保険)<PDF>(公益財団法人 関西経済連合会)
【コラム】男性の育休取得が義務化?産後パパ育休制度の概要や育休取得率を上げるコツなども詳しく解説
事例(2)株式会社アシックス
スポーツ用品メーカーの株式会社アシックスでは、昇格候補の人選などをする際に「無意識の偏見」をチェックするステップをつくり、管理職の意識変革と公平な人選を目指しています。
たとえば、昇格候補の人選や人事評価会で男性ばかりの推薦があった場合に、「女性の候補者は本当にいないのか?」などの問いかけを人事部門から行うというものです。また、女性社員における管理職候補研修への選抜割合で「全体の約4割」という数値目標を設定することで、女性活躍が促進されやすい組織を目指しているようです。
<参考>:評価のタイミングで「無意識の偏見」を再認識(アシックス)<PDF>(公益財団法人 経済団体連合会)
事例(3)BIPROGY株式会社(旧・日本ユニシス)
BIPROGY株式会社は、ダイバーシティ推進を経営成果に結びつけている先進的な企業として、経済産業省から「新・ダイバーシティ経営企業100選」の表彰を受けています。
BIPROGY株式会社では、「社会課題を解決する企業」として、イノベーション創出の源泉となる経験・知見を多様な社員から引き出す目的で、ダイバーシティ&インクルージョンの取り組みを実施したようです。
この会社の事例で特に注目したいのが、経営陣だけで以下の3つもの取り組みを行っている点です。
(1)中期経営計画にダイバーシティ推進を含む「風土改革」を重点施策として明記、ガバナンス体制にも反映しトップダウンの推進力強化を図る
(2)ダイバーシティの専任組織とグループの SDGs 経営、ESG 経営を推進する意思決定機関として2つの委員会を設置し、メリハリのある推進体制を実現
(3)経営幹部及びそのパイプラインにおいてもダイバーシティ経営への理解・実践を重要なコンピテンシーとして位置づけ
<引用>:令和2年度 新・ダイバーシティ経営企業 選 プライム ベストプラクティス集<PDF>(経済産業省)
BIPROGY株式会社の事例は、ダイバーシティ&インクルージョンに対する経営陣の関わり方として参考になるものといえるでしょう。
事例(4)東和組立株式会社
東和組立株式会社は、令和2年度の新100選を受賞した企業です。
この会社には、1990年代から外国人材、1971年から聴覚に障がいがある人材を採用してきた歴史があります。また、2021年1月時点では、以下のように多様性の割合がとても高い状態となっています。
|
【総従業員数】135人 【女性】40人 【外国人】38人 【チャレンジド(障害者)】15人
|
東和組立株式会社におけるダイバーシティ&インクルージョンの大きな特徴は、多様な人材との円滑なコミュニケーションを図るために、さまざまなIoTツールを活用している点です。
たとえば、聴覚障がいのある従業員には「スピーチキャンパス」、知的障がいがある従業員では「アクションボード」といったツールを活用しています。人材教育でもIoTツールを使うことで、育成スピードの向上にもつなげているようです。
人事業務の課題解決ならラクラスへ
本記事では、ダイバーシティとインクルージョンという概念の意味や違いを解説させていただきました。関連する法律や、関連施策を導入する際の進め方やポイント、成功事例などもご紹介しましたが、仕組みや環境づくりにはさまざまなポイントや注意点があるため、人事部のなかでも負担に感じている方は多いのではないでしょうか。
もし人事業務における業務効率化をお考えであれば、ラクラスにお任せください。ラクラスなら、クラウドとアウトソーシングを掛け合わせた『BpaaS』により、人事のノンコア業務をアウトソースすることができコア業務に集中できるようになります。
ラクラスの特徴として、お客様のニーズに合わせたカスタマイズ対応を得意としています。他社では難色を示してしまうようなカスタマイズであっても、柔軟に対応することができます。それにより、大幅な業務効率の改善を見込むことができます。
また、セキュアな環境で運用されるのはもちろんのこと、常に情報共有をして運用状況を可視化することも心掛けています。そのため、属人化は解消されやすく「人事の課題が解決した」という声も数多くいただいております。
特に大企業を中心として760社86万人以上の受託実績がありますが、もし御社でも人事の課題を抱えており解決方法をお探しでしたら、ぜひわたしたちラクラスへご相談ください。