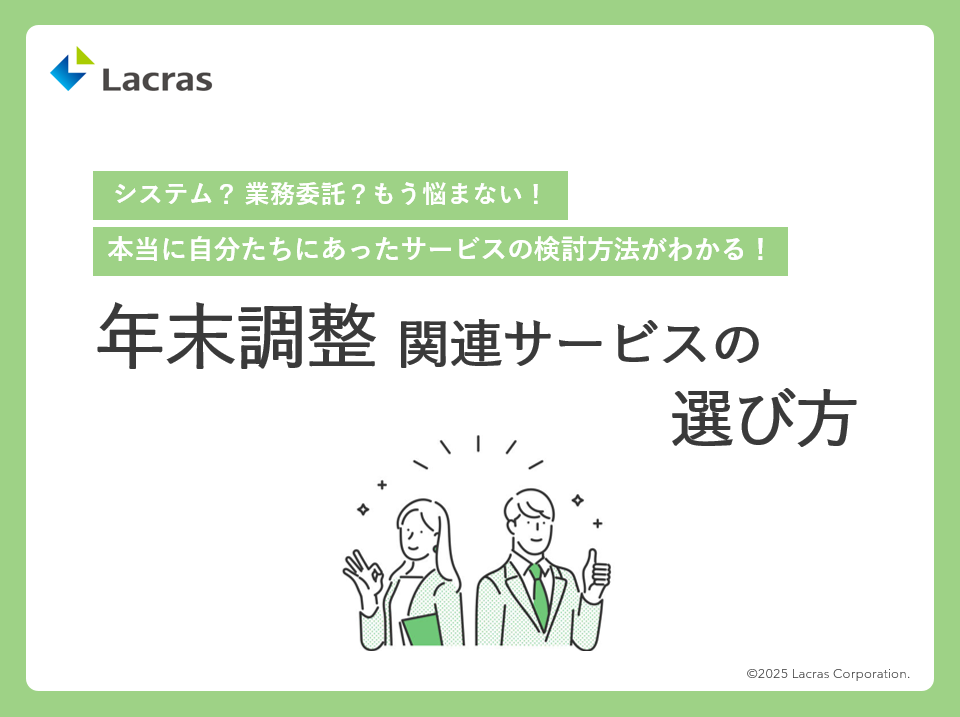年末調整システムのメリットとデメリットを徹底分析! 選び方や注意点を押さえよう

本記事では、年末調整システムの概要と種類、導入メリット・デメリットを確認したうえで、選び方のポイントを解説していきます。年末調整システムを含め「何らかのサービスを活用して手続きの負担を軽減したい」とお考えでしたら、ぜひ本記事を参考にしてください。
年末調整システムの導入は、人事業務の効率化につながる選択肢の一つといえます。
しかし、システム導入に向けて情報収集を始めると、あまりにも種類が多すぎてどれを選べば良いかわからないこともあると思います。また、費用対効果を高めるのであれば、自社にとって導入メリットが大きいシステムを選びたいものでしょう。
そこで本記事では、年末調整システムの概要と種類、導入メリット・デメリットを確認したうえで、選び方のポイントを解説します。後半では、年末調整システムの導入価格例や生成AIが普及した時代の最新トレンドなども紹介していきます。
年末調整システムの新規導入やリプレースに向けて情報収集されている方は、ぜひとも本記事を参考にしてください。
年末調整システムの基本理解
自社に合う年末調整システムの導入をするためには、「そもそも、年末調整システムはどういうものか?」を理解しておくことが大切です。この章では、年末調整システムの概要と重要性、主な役割などを解説していきます。
年末調整システムとは何か?
年末調整システムとは、年末調整業務の電子化・効率化に用いるITシステムやソフトウェアの総称です。
かつての日本では、「紙書類」を用いた年末調整が一般的でした。紙による年末調整では、たとえば以下のような手続きややり取りが当たり前に行われていたのです。
|
|
紙書類による年末調整には、人事担当者を悩ませるさまざまな問題が発生しやすい状況でした。具体的には、以下のような問題がよく生じていたでしょう。
|
|
人事担当者は、紙書類の回収ができなければ、年末調整手続きを期限どおりに終わらせることが難しくなります。
また、従業員本人が入力した数字が間違っていた場合、修正依頼をすることで、やはり期限までの申告は難しくなってしまいます。こうした諸問題は、ただでさえ忙しい人事担当者の負担を大きくするものでした。
年末調整システムは、上記のような「紙」での運用による問題を解決する方法の一つとして注目されているものになります。
年末調整システムの特徴やIT化できる範囲は、利用サービスや契約内容ごとに異なります。しかし一般的には、以下のような機能を持つ年末調整システムが多いでしょう。
|
|
年末調整の重要性とその役割
年末調整業務とは、わかりやすい言葉で表現すると「企業と従業員が正しい税額をおさめるための計算を行う年1回の業務」です。
<参考>:Ⅱ 年末調整とは<PDF>(国税庁)
企業は、所定の源泉徴収税額表を用いて従業員から源泉徴収する税額を決めていますが、「実際に源泉徴収した1年間の合計額」と「年間の給与総額に基づく年税額」は一致しないことが通常です。年末調整とは、この一致しない部分を解消して、適切な税額を決定・納付するために行う一連の手続きになります。
そこで人事担当者が年末調整を行わなかったり、算出した数字が間違っていたりした場合、企業および従業員は適切な税金を納付することができません。
納期限までに税金を支払わない状態が続くと、本来おさめるべき税金のほかに延滞金などのペナルティが課せられることになってしまいます。また、会社側で適切な税金の計算・納付を行わないとなれば、従業員や社会からの信用も低下するでしょう。
<参考>:税金を納めないとどうなるの?(大津市)
こうした問題を防ぐためにも、年末調整は国で定めた計算方法を使って適切な数字を算出し、期日までに必ず終わらせるべき手続きになります。
年末調整システムの種類
年末調整システムには複数のタイプがあり、使える機能や価格相場は種類ごとに違いがあります。ここでは、よく導入されている4つの種類における一般的な特徴を見ていきましょう。
(1)年末調整特化型システム
その名のとおり、年末調整業務に特化したITシステムです。
この種類のシステムには、簡単な質問に答えるだけで申告データが作成できる機能や、提出書類の集計・管理が容易になる機能などが搭載されています。これらの機能は、後述する他の種類にも搭載されていることが多い年末調整の基本機能です。また、特化型の場合、給与計算システムとのデータ連携ができるものも多くなっています。
特化型は、年末調整機能に限定されているため、他の種類と比べて少ないコストで導入できる利点があります。
(2)給与計算システムとの統合型
統合型というのは、給与計算システムのなかに年末調整機能が備わっているタイプです。
この種類を使うと、年末調整特化型の機能に加えて、システム内の給与情報や扶養情報を参照・共有することも可能となります。独立したシステム同士のデータ連携(取り出し・取り込み)や転記の必要もなく、そういった作業による手間やミスを防げるメリットがあるでしょう。
この統合型の場合、給与計算もできる多機能のシステム導入が必要となるため、特化型と比べて多くの導入コスト・工数がかかる可能性が高くなります。
(3)労務管理システムとの統合型
この種類は、労務管理システムのなかに年末調整機能が備わっているタイプです。
労務管理の範囲はメーカーごとに異なりますが、そのなかには、人事評価やタレントマネジメントができるものもあります。また、年末調整の手続きに欠かせないマイナンバーの管理機能を有しているシステムも多いです。入社手続きで入力した従業員データベースも、年末調整と連携して使えるでしょう。
労務管理システムとの統合型も数々の機能があることで、特化型と比べて規模や導入コストが大きくなりやすい傾向があります。
(4)総合型の人事給与労務管理システム
この種類は、人事部門が担当する管理業務全般に対応した総合型システムのなかに、年末調整の機能が備わっているイメージです。
具体的な機能はメーカーによって異なりますが、一般的には、給与計算・勤怠管理・労務管理の機能に加えて年末調整も行えるものが多いでしょう。
労務管理や勤怠管理のデータは、毎月の給与計算とも大きな関係があるものです。また、年末調整を行ううえでは給与データが必要であるため、それらの情報を1つのシステム内で取り扱えることは、各オペレーションを効率化するうえでも大きなメリットになるでしょう。
また、労務管理・給与計算・年末調整のシステムが1つになれば、従業員本人や扶養家族などの情報を変更する作業も効率化できます。
総合型の人事給与労務管理システムの場合、他の3つと比べてかなり規模が大きくなるため、導入時の手間やコストも大きくなりがちです。
年末調整システムの導入メリット
年末調整システムを導入すると、人事担当者を中心とする企業と従業員の両方にさまざまなメリットが生まれます。ここでは、一般的な年末調整システムを取り入れることで得られる効果・メリットを見ていきましょう。
企業側のメリット
人事担当者側から見た年末調整システムの導入メリットは、以下の4つです。
・担当者の負担と工数削減
・人的ミスの予防
・コミュニケーションコストの減少
・ペーパレス化による書類管理の効率化
年末調整業務をシステム化すると、各従業員はオンラインの画面上で必要事項の入力や書類データの添付などを行うことになります。この変化によって解消できるのが、紙運用では不可欠だった「紙資料の印刷・配布・回収・保管」といった作業です。
また、申告データの入力画面には、「ここには◯◯に記載された数字を入れてください」などの入力ガイドもついています。こうしたガイドに従って入力作業を進めると、紙運用で起こりやすかった「記入もれ」や「記入ミス」などもかなり少なくなるはずです。
システム化によって生じる数々の変化は、人事担当者に年末調整業務にかかる負担や工数の削減効果をもたらすでしょう。
また、年末調整システムのなかには、サポートデスク機能がついたものもあります。こうした機能のあるシステムを導入すると、年末調整時期に集中していた「この項目には何を記入するの?」や「この添付書類はこれで合っている?」などの問い合わせ対応を業者側で行うことになります。
年末調整時期のコミュニケーションコストがかなり増大している場合には、こうしたサポートデスク機能や入力ガイド機能が充実したシステムを選ぶことも視野に入れるとよいかもしれません。
従業員側のメリット
年末調整システムは、従業員側に以下の2つのメリットをもたらします。
・申告書類作成の手間や負担が軽減する
・前年のデータを参照・活用できる
年末調整システムの入力画面には、入力ガイドやヘルプ機能がついています。これらの機能をうまく使うと、人事担当者に質問などをしなくても、従業員本人の判断で適切な情報入力を進められるでしょう。
また、従業員本人がその場で疑問を解決できる状況は、従来の紙運用のときに生じていた「人事担当者からの返事を待つ時間」の削減にも役立つものです。
このほかに、多くのシステムでは、前年度のデータを参照・活用できたりします。
年末調整は頻繁に行う手続きではないため、書き方に慣れない従業員には「ここには何を入力すれば良いんだっけ?」などの混乱が生じやすい傾向があります。しかしそこで、前年度のデータを参照して、その内容を真似る形で今年度の情報入力をしてもらうと、作業をスムーズに進めやすくなるでしょう。
また、電子データの控除証明書を反映できるシステムであれば、その情報を記入(手入力)する手間も省けます。
年末調整システム導入のデメリット
年末調整システムには、企業にとってデメリットになる要素もあります。ここでは、2つのデメリットと注意点を見ていきましょう。
デメリット(1)導入コストと運用コスト
年末調整システムを使う際には、導入と運用の両方で「多くのお金」がかかります。具体的な金額は、新たに導入するシステムの料金はもちろんのこと、従来の運用方法やシステムの規模、連携範囲などによって変わってくる形です。
たとえば、以下の環境で年末調整システムを使っている企業が、これからリプレースを予定していると仮定します。
・特化型の年末調整システムを導入済み
・給与計算と労務は別システムで管理中
今回のリプレースを機に年末調整・給与計算・労務管理のすべてを統合しようとする場合、この3つが動く総合型システムの料金に加えて、各システムからデータを移行・統合するための手間やコストがかかってくるでしょう。
また、年末調整システムの導入後は、運用するための費用が必要です。年末調整単独のシステムと、給与や労務管理がベースとなるシステムを比べた場合、やはり後者のほうに多くの費用がかかってくる可能性が高いでしょう。
デメリット(2)従業員の教育とサポート
年末調整システムによる業務効率化は、各従業員がオンラインの画面上で情報入力や申請などの一連の手続きができてはじめて、実現するものです。
仮にそこで、パソコンの入力自体が苦手な従業員が多かったり、屋外での現場仕事などでオンライン画面を開くパソコンやタブレット端末などがなかったりする場合、ストレスになってしまいます。
多くの年末調整システムには、入力ガイドやサポートデスクなどの機能が備わっていますが、従業員に疑問や不安が生じやすい導入直後の時期は、人事部門での直接的な支援も行ったほうがよいかもしれません。

年末調整システムの選び方
導入する年末調整システムは、どんなものでも良いわけではありません。
費用対効果が高く「導入して正解だった!」と人事担当者と従業員の両方が感じられるシステムを導入するためには、いくつかのポイントを確認しながら選定を進めていく必要があります。
ここでは、自社に合う年末調整システムの導入を検討する皆さんのために、選び方のポイントを4つほど紹介しましょう。
ポイント(1)全従業員にとっての使いやすさ
年末調整システムは全従業員が使うものです。システム導入により、従業員から不安や不満の訴えが生じないようにするためには、以下のような機能が充実していて、操作しやすいシステムであることが求められます。
|
|
PCおよびタブレット端末の操作スキルや使用環境にかなりの個人差がある場合、たとえば、PC操作自体があまり得意ではない従業員でもストレスを感じにくいシステムを選ぶ必要があるかもしれません。
また先述のとおり、操作方法に慣れるまでは業者のサポートデスクなどに丸投げせず、人事部門でも使い勝手のヒアリングや支援をする体制・姿勢も重要でしょう。
ポイント(2)費用対効果のバランス
年末調整システムは、予算の範囲内で自社が抱える課題をなるべく多く解消できるものを選ぶことが大切です。
費用対効果のバランスを見るうえでは、まず自社が年末調整システムに期待する効果を明確にする必要があります。それはつまり、「どういう問題がどのように解決できたときに“効果があった”と判断できるか?」ということです。
また、現状の年末調整業務に多くの問題がある場合、システム導入で解消したいポイントに優先順位を付けることも必要になります。
なお、年末調整システムの場合、各社の機能がすべて同じというわけでもないため、料金体系も単純には比較しづらい傾向があります。しかしそれでも、費用対効果が高い年末調整システムを選ぶためには、明確な要件で複数の見積もりを取り、各社が示す料金を把握することが重要になるでしょう。
ポイント(3)サポート体制の充実
年末調整システムの場合、「人事担当者のサポート」と「従業員のサポート」の両面でサポート体制を見ていく必要があります。
人事担当者のサポートは、たとえば年末調整の計算中にわからないことがあった場合にすぐ問い合わせることが可能であり、また、早く回答がもらえる体制になっているかどうかです。年末調整業務は限られた期間内に申告・納税まで行う必要があるため、サポート担当とすぐにつながることが重要となります。
これに対して従業員向けのサポートは、人事担当者を介することなく、従業員が直接業者のサポートデスクに相談できる仕組みがあるかどうかです。各従業員がスムーズに疑問を解消して入力作業を進めるためには、たとえば、「年末調整期間中の平日は10時~18時まで窓口開設している」などの体制があることが理想でしょう。
ポイント(4)セキュリティ対策の充実
年末調整システムを使う場合、従業員本人や家族の個人情報や給与情報といったさまざまな重要データをシステム上に入力・アップロードすることになります。こうした重要データの漏えいや不正利用などを防ぐためには、各社でどのような情報セキュリティ対策が行われているかの確認も必要です。
情報セキュリティ対策は、業者ごとに取り組み内容が異なります。一般的な事業者のホームページには、以下のような施策が並ぶことが多いでしょう。
|
|
年末調整システムの最新トレンド
近年のビジネス環境では、業務効率化以外の理由でも年末調整システムに注目が集まることが多くなっています。また、ここ数年で急速に普及している生成AIも、年末調整システムの機能に大きな影響を及ぼしているようです。
ここでは、「年末調整の電子化」と「生成AI」の2点から、年末調整システムの最新トレンドを見ていきましょう。
トレンド(1)年末調整における電子化の推進
国税庁では以前から年末調整の電子化を推進しており、前々年度に発行した年末調整が種類ごとに見て100枚以上の企業に対しては、法定調書の電子申告を義務付けるようになりました。
<参考>:年末調整手続の電子化に向けた取組について(国税庁)
また、令和9年以降は、義務付け条件である法定調書の枚数が30枚に下げられることで、対象企業の範囲がさらに広くなります。
こうした流れから、かつては「紙」でのやりとりが主流だった年末調整業務も、専用のITシステムなどを使った「電子データ」の作成・申告に移行しつつあると考えてよいでしょう。
<参考>:年末調整手続の電子化で業務の効率化<PDF>(国税庁)
トレンド(2)AIと自動化の活用
生成AIの普及が著しいなかで、このテクノロジーを活用する年末調整システムも多く登場するようになりました。
たとえば、ある年末調整システムでは、従来から使われている光学文字認識(OCR)という仕組みと生成AIを組み合わせた技術「AI-OCR」を用いて、従業員がアップロードした生命保険料控除などのデータを読み取り、自動入力する機能をリリースしています。
このシステムでは、AIが人事担当者に確認箇所を提案することで、確認作業の効率化も図られている形です。
また、ある年末調整システムでは、対話型AIチャットボットが従業員からの質問に回答することで、人事担当者の負担を軽減する仕組みを提供しています。
このように生成AIは、多くの年末調整システムに機能充実をもたらしながら、人事業務のさらなる効率化や自動化の実現に寄与していると考えてよいでしょう。
年末調整システム導入の価格例
年末調整システムの導入価格は、「どういう種類のシステムを、どの規模で、どういう環境に導入するか?」で変わるものです。
たとえば、これまで使っていた年末調整システムから新しい環境へのデータ移行が必要であったり、給与計算システムとの統合を行ったりする場合、その作業を年末調整システムの提供業者にお願いするとなれば、データ加工や移行の費用が別途請求されたりするかもしれません。
こうしたなかで、ひとつの目安になるのが、各社が公開している参考価格の情報です。
参考価格は、導入時にかかる初期費用・基本料金・利用料金などをわかりやすく示したものになります。主要な年末調整システム業者では、以下の一覧のとおり情報を公開しています。
| 初期費用 | 基本料金 | 利用料金 | 備考 | |
| A社 | 50,000円 | 年額10,000円 | 年額350円/ユーザー | |
| B社 | 200,000円~ | なし | 年額500円/ユーザー | 利用人数が500名未満の場合、利用料金は250,000円 |
| C社 | 無料 | なし | 月額400円/ユーザー | |
| D社 | 無料 | なし | 月額500円/ユーザー | |
| E社 | 50,000円 | なし | 年額300円~/ユーザー |
具体的な導入費用が知りたい場合は、現状分析を通じて以下のような項目を洗い出したうえで、各事業者に見積もり依頼をしてみましょう。
|
|
各社に同じ条件を示せば、相見積もりもしやすくなるはずです。
コストに見合った効果や価値の重要性
年末調整システムの導入で重視すべきことは、やはり費用対効果です。費用対効果をわかりやすくたとえると、「事業者に支払った費用に見合った効果が得られているかどうか?」になります。
たとえば、「安かろう、悪かろう」の考え方で最も価格が高いシステムを導入しても、自社の従業員にとっては使い勝手が非常に悪く不評だった場合、そのシステムは「費用対効果があまり高くない」といえるかもしれません。
一方で、導入価格および運用価格が安くシンプルなシステムでも、人事担当者と多くの従業員が「使いやすい」「これなら簡単に手続きできる」と感じていて、年末調整の諸課題が解決されているのであれば、それは「自社にとって費用対効果が高いシステム」になる可能性が高いでしょう。
いずれにせよ費用対効果は、「そのシステムは自社にどういう価値を提供してくれるか?」という独自の視点で見ていくものです。この視点で評価や比較をするためには、まずは自社が抱える年末調整の課題や導入目的を明確にしていく必要があるでしょう。
年末調整システムに関するよくある質問
これから年末調整システムの導入や運用を始めるうえでは、さまざまな疑問が生じると思います。ここでは、年末調整システムについて人事部門の担当者からよくある質問と回答を紹介しましょう。
Q.国税庁が提供する年末調整ソフトも活用できますか?
活用可能です。ただし、国税庁のソフトは近年人気の高いクラウド型ではなくインストール型になります。このソフトで年末調整業務を行うためには、人事担当者と全従業員のパソコンやスマートフォン、タブレット端末にソフトウェアのインストールが必要です。
無料で使えるシンプルなソフトであるため、各事業者が提供する有料版と比べると機能が少なく感じられるかもしれません。こうした特徴から国税庁の年末調整システムは、必要最低限の機能を無料で使いたい企業におすすめの選択肢となるでしょう。
<参考>:年末調整手続の電子化について ~年調ソフト編~(国税庁)
Q.導入後はずっと同じシステムを使い続けるものですか?
年末調整自体は年1回の手続きですから、費用対効果を見ながら年に1度より良いシステムに変えていくのも一つの考え方です。
ただし、給与計算システムや労務管理システム、総合型の人事管理システムのなかに年末調整システムが入っていたりする場合、データを再移行する手間や従業員の教育コストなどを考えても、高頻度でのシステム見直しはあまり現実的ではないかもしれません。
しかしそれでも、人事部門が年末調整などのIT化や業務効率化を成功させたいのであれば、そのシステムを使う従業員の意見や感想に耳を傾けたうえで、多くの人の負担にならない運用方法などの模索や定期的な改善をする必要があります。
また、「入力画面が使いづらい」や「ヘルプ機能がわかりづらい」などの意見は、年末調整システムを次に買い替える(リプレース)際の大事な判断材料になってくるでしょう。年末調整後のアンケートなどを通して、従業員の率直な意見を集めることも重要な取り組みです。
年末調整のアウトソーシングならラクラスへ
本記事では、年末調整システムの概要と種類、導入メリット・デメリットを確認したうえで、選び方のポイントを解説してきました。もし年末調整システムを含め「何らかのサービスを活用して手続きの負担を軽減したい」とお考えでしたら、ぜひラクラスにご相談ください。
ラクラスの年末調整BPOサービスなら、必要な機能と業務をフルパッケージ化しています。また、カスタマーサポートも実施していますし、カスタマイズ対応も可能です。
AI-OCRとオペレーターの目視を組み合わせた読取代行により、品質と効率の両立を実現しており従業員は証明情報の入力が不要になります。また、人事担当者の回収とチェックも必要ありません。
クラウドシステムはすべて国内で運用されており情報セキュリティも万全ですし、大企業向けに開発された様々な設定やオプションもご用意しています。導入を検討いただくうえで何かご不明点などありましたら、お気軽にご相談ください。