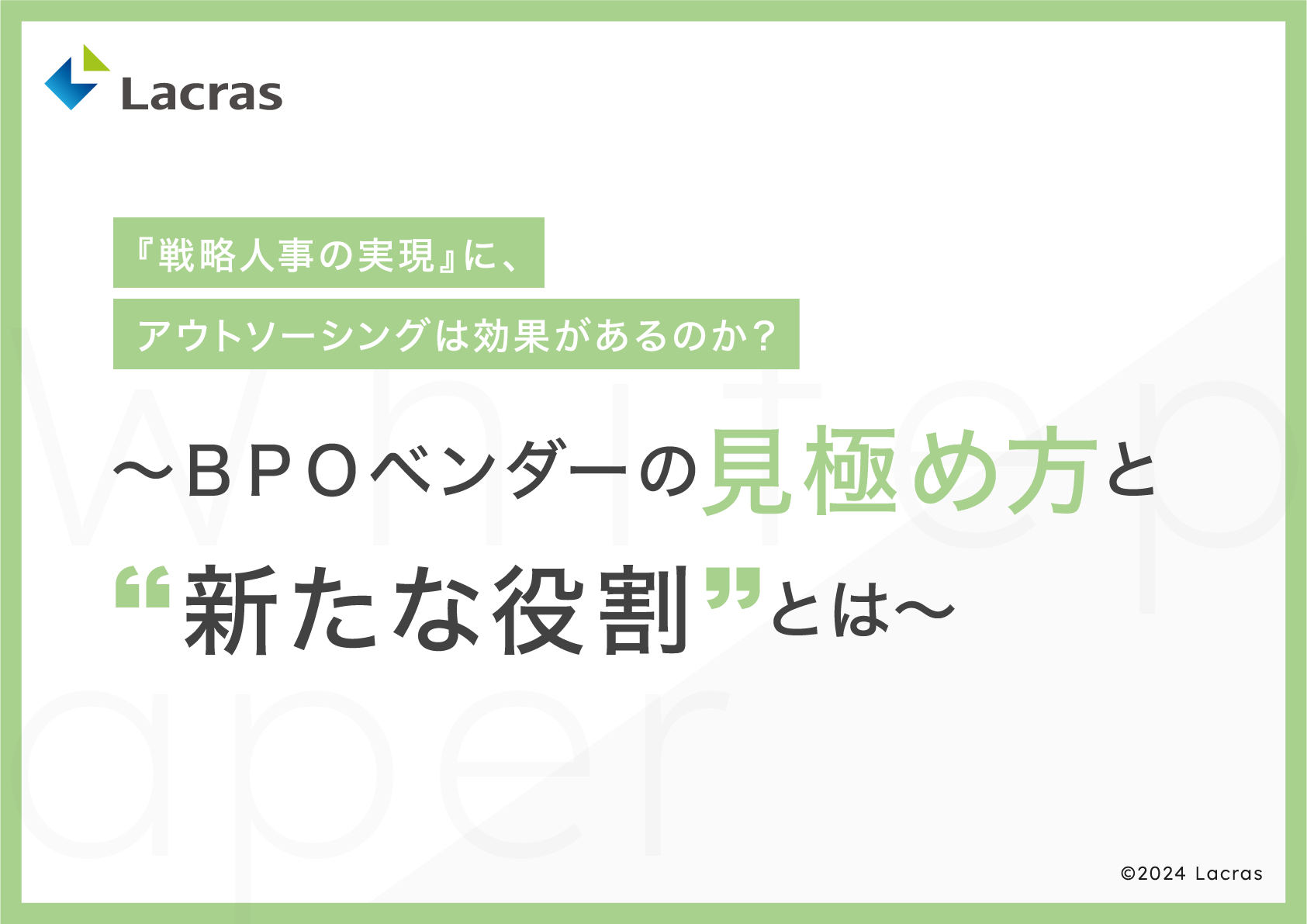人事評価とは? 効果を最大化する最新トレンド手法や成功事例、導入ポイントを解説

本記事では、人事評価の定義や目的、メリットを確認したうえで、効果の高い仕組みの導入手順や注意点について解説します。また、最新の人事評価トレンドやフィードバックの重要性についても紹介していきます。
これから人事評価に携わる方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
人事評価とは、従業員の業績や貢献度を評価し、それに見合う等級や報酬を決定することです。
近年のビジネス環境では、転職が一般的となり若手の早期離職が増えるなか「公平性や透明性の高い人事評価の重要性」が今まで以上に高まるようになりました。
また、予測不能な出来事が生じやすい“VUCA”時代に効果的な評価を行っていくためには、最新トレンドの手法を取り入れていくことも重要でしょう。
そこで本記事では、人事評価の定義や目的、メリットを確認したうえで、効果の高い仕組みの導入手順や注意点について解説します。
記事の後半では、最新の人事評価トレンドやフィードバックの重要性についても紹介していきます。
人事評価制度の導入や再設計を検討している方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
人事評価とは?その基本と重要性
自社の現状に合う効果的な人事評価を行うためには、まず“人事評価”という概念の意味や目的、基本的な枠組みを理解することが重要です。
ここでは、人事評価の設計・運用の前提となる基礎知識を確認しましょう。
人事評価の定義と基本的な枠組み
人事評価とは、従業員が一定期間に行った仕事の実績や能力を評価することです。
人事評価の仕組みを総称して「人事評価制度」と呼ぶこともあります。
一般的な人事評価は、以下の3つの枠組み(評価制度・等級制度・報酬制度)で構成されています。これらが互いに関連し合いながら、従業員の給与(賞与)の決定や昇進昇格に影響することが多いでしょう。
|
【評価制度】 従業員の貢献度を中心に評価するものです。この制度の評価は、等級・報酬にも大きく影響します。一般的には、目標の達成度や実績、勤務態度、求められる役割を担うための能力などが総合的に評価されるでしょう。
【等級制度】 従業員の職務内容や能力ごとにランク分けする制度です。たとえば、一般社員が「1~2等級」、主任が「3等級」、課長が「5~6等級」のようなイメージでしょう。等級の序列により求められる役割やスキル、給与などの処遇が変わります。
【報酬制度】 給与・賞与・インセンティブなどの待遇を決める制度です。たとえば、「ランクと評価が高ければ給与もアップする」のように、等級および評価と強く影響し合う形です。
|
なお、賞与の評価については下記の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
人事評価と人事考課の違い
人事評価と似た概念として、“人事考課”があります。
人事考課は、主に従業員の能力・成果をもとに評価を行う仕組みの総称です。これに対して人事評価では、従業員の能力は適性なども含めた人事考課よりも広範囲の視点で評価することが多いでしょう。
ただし、大半の企業では、違いを明確化することなく“ほぼ同義”として使うことが一般的です。
人事評価の目的と意義
一般的な人事評価制度は、以下の3つの目的と意義によって設計・運用されるものです。それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
目的(1)適切な人材配置と公平な処遇
従業員が納得できる適切かつ公平な処遇につなげることは、人事評価制度の大きな目的です。具体的な評価基準・項目が見えるなかで、その結果に応じた「報酬」や「ランク」を決めるからこそ、従業員は決定内容に納得して働けるようになります。
現時点で人材配置や処遇に不満を持つ従業員が多い場合には、人事評価を適切な仕組みに見直す取り組みを早めに実施したほうがよいでしょう。
目的(2)企業のビジョンと目標の明確化
各企業には「自分たちはこのような社会を作りたい」や「こういったサービスを全国展開して、業界のリーディングカンパニーになりたい」などのビジョンや目標があるはずです。
企業がこれらを実現していくためには、各従業員がビジョンや目標に合った行動をし、会社と同じベクトルのなかで成果を出し続けることが必要です。そのため、人事評価にこうした企業のビジョン・目標に関連する項目を盛り込めば、従業員はそれらを意識しながら成果を出しやすくなります。
また、たとえば「まずは顧客のニーズに耳を傾ける」といった評価項目を設けると、成果を出すまでのアプローチも統一され「全メンバーが同じやり方で成果を出し、同じベクトルで目標達成をする」といったことも実現しやすくなるでしょう。
目的(3)従業員の成長とキャリア開発
明確な評価項目と評価基準にもとづく人事評価は、従業員の成長やキャリア開発にも役立つものです。
たとえば、営業部門の評価項目に成果を出すうえで欠かせない以下の要素を並べておくと、定期的な評価をすることでメンバーの強み・弱みが見えやすくなります。
|
|
また、評価者側も「なぜ売上が伸び悩んでいるのか?」「これからどうすればよいのか?」などの課題解決について、本人の現状に合う適切なフィードバックを行いやすくなるでしょう。
なお、いまの時代は働く人のキャリアが多様化したことで、会社は従業員と信頼関係を築きつつ、キャリアに寄り添う姿勢を見せる必要が出てきています。こうしたなかで導入・運用される人事評価制度は、透明性を高くすることで労使における信頼関係の構築にも大きく役立つでしょう。
適切な人事評価の導入メリット
自社の現状に合った適切な人事評価を設計・導入すると、先述の“目的”が実現されることで以下のようなメリットが得られます。3つを挙げて見ていきましょう。
メリット(1)
従業員のモチベーションやパフォーマンスの向上
適切な項目・基準に基づく人事評価を導入すると、従業員に生じていた不公平感や違和感が緩和します。それによって向上しやすくなるのが、従業員のモチベーションです。このメリットは、これまで上司の主観が中心で客観性の低い評価を行っていた場合に特に得られやすいものとなります。
また、適切な人事評価によって本人の強み・弱みが明確になると、目標達成につながる具体的な施策がわかることで仕事のパフォーマンスも向上しやすくなるでしょう。
メリット(2)組織文化の強化と信頼性の向上
人事評価制度が「組織のビジョン」や「中長期的な目標」と紐づいていると、上司とメンバーは、その仕組みをベースに日々の業務やフィードバックを行うことになります。そうなると、組織で働く全従業員が同じビジョンや目標を共有しやすくなっていきます。
また、たとえば「新規顧客とはラポール形成に多くの時間をかける」などの大事な価値観・文化が共有されると、成果を出す手法や考え方のズレも生じにくくなるでしょう。その結果として上司と部下、メンバー同士で良い関係も構築されやすくなっていくはずです。
メリット(3)企業全体の生産性向上
適切な人事評価制度の導入により組織の文化が浸透し、働く人の関係が強固になると“従業員エンゲージメント”が向上します。そうなると、目標達成までのスピードやサービス品質も上がりやすくなるでしょう。
それはつまり、組織全体の生産性向上を意味します。生産性が高まり会社としての利益が増えれば、賞与という形で従業員への還元がしやすくなるかもしれません。またそれは、さらなるモチベーションやエンゲージメントの向上という形で労使の間に好循環をもたらすでしょう。
“従業員エンゲージメント”は、『人的資本経営』における重要概念です。詳細については、以下の記事もぜひチェックしてみてください。
【関連記事】従業員満足度(ES)と従業員エンゲージメントの違いとは?高めるメリットや方法も解説
人事評価制度の注意点
人事評価制度は、「導入して実施さえすれば効果が出るもの」ではありません。導入した制度に問題があると、逆効果になってしまうこともあります。また近年では、労働者の働き方が多様化したことで、従来にはない制度設計の注意点も生まれています。
ここでは、人事評価制度を設計・運用するうえでの代表的な注意点を3つ挙げて見ていきましょう。
注意点(1)評価基準の不明確さ
最も逆効果になりやすいのが評価項目・基準が不明確な人事評価制度です。
たとえば、営業部門の評価基準が漠然としたものであったり、そもそも評価基準がなく、上司の主観で適当な評価を行ったりしている場合、以下のように被評価者である部下に不満や違和感が生じやすくなるでしょう。
|
「自分は今期の営業成績トップだったのに、10位だった同期のAくんよりも評価が低いのはなぜだろう……」
「自分より業績も努力も少ないBさんCさんが高評価されている。自分は何を頑張れば良いのかまったくわからない……」
|
こうした不満・違和感が大きくなると、上司と部下における信頼関係が崩れるのはもちろんのこと、モチベーションの低下や離職意向の高まりにつながっていくかもしれません。また、「何をどうすれば評価が上がるかわからない」という状況は、会社のビジョンや目標に基づく人材の成長も妨げることになるでしょう。
注意点(2)評価者のバイアスによる評価の偏り
上司のバイアスも、人事評価の質を落とす課題です。バイアスとは、評価者の個人的な認識やイメージの歪み・偏りを指しますが、その影響で適切な評価が行えないことを「評価バイアス」と呼びます。いわゆる「思い込み」もバイアスの一種でしょう。
たとえば、ある上司がAくんを個人的に気に入っていて、次のリーダーにしたいと考えていたと仮定します。その場合の人事評価に上司の歪んだ主観(評価バイアス)が入ると、「お気に入りのAくん」と「実力トップではあるがお気に入りではないBくん」との間に以下のような評価の歪みが生じるかもしれません。
|
【お気に入りのAくん】 ⇒今期の営業成績は部門6位で昨期も5位。しかし「Aくんは絶対にハイパフォーマーになる」という上司の期待と根拠のない願望から、人事評価は最高の「A評価」になっている。
【実力トップではあるがお気に入りではないBくん】 ⇒Aくんの2学年下の後輩。3年連続営業成績トップだが、どれだけ高い実績をあげても人事評価は「B評価」。なぜかAくんを超えられない。
|
ちなみに人事評価を歪ませる「バイアス」には、以下のようにさまざまな種類があります。
|
|
これだけのバイアスの影響を最小限にしながら適切な評価を行うためには、「評価項目」と「評価基準」をもとに、具体的な内容に設計していく必要があるでしょう。
認知バイアスの詳細については、総務省の資料などを参考にしてください。
注意点(3)リモートワーク環境での評価の難しさ
コロナ禍以降、一気に普及したリモートワーク(テレワーク)も、人事評価に難しさを与えています。困難が生じる一般的な理由には、以下のものがあるでしょう。
|
|
リモートワーク社員の評価では、上記の問題を踏まえたうえで、適切かつ公正・公平になる仕組みを設計することが重要です。また、勤務態度や時間を把握しづらい問題を解決するためには、いわゆるテレワーク管理ツールの導入を検討してもよいでしょう。
効果的な人事評価手法とは
人事評価の仕組みは、自社の業種や考え方に合うものを自由に設計・導入することが可能です。
ただし、ここまで紹介した「上司と部下における認識のズレ」や、「従業員の不満・不公平感」などを減らすためには、多くの企業が導入する代表的な評価手法のなかから「自社に合うものを選ぶ・アレンジする」といったやり方を選択する必要があるでしょう。
ここでは、効果の高い人事評価の手法として定評がある「MBO(目標管理制度)」「360度評価」「コンピテンシー評価」の3つについて、特徴やメリットを簡単に紹介します。
(1)MBO(目標管理制度)
MBO(目標管理制度)とは、組織・個人の目標を設定したうえで、その達成度合いを評価に活かしていく仕組みです。たとえば「今期は営業部門全体で3億円の売上達成を目指すから、リーダーであるAくんは7,000万円、新人のBくんは3,000万円の目標を設定して……」というイメージでしょう。
MBOの概念を生み出したのは、マネジメント理論の提唱者であるピーター・ドラッカーです。ドラッカーがMBOを生み出した背景には、2つの本質的な目的があります。
まず、1つ目の目的は、目標設定によって従業員個人の主体性を引き出すことで、セルフマネジメントを促進させる点です。たとえば上記のAくんであれば、「7,000万円の売上を達成するために、どういう行動計画が必要か?」を自分で考えたうえで、PDCAを回しながらゴールに向かって自走するイメージです。
2つ目の目的は、具体的な個人目標を設定することで、各メンバーの成果を組織のゴールに集約できる点です。
たとえば上司が「今期はみんなで3億円を目指しましょう!」と言っただけでは、組織がゴール達成できるかわかりません。MBOの場合、そこで組織の数字を個人目標に落とし込み、各自が7,000万円や3,000万円を目指すからこそ、組織のゴールも達成しやすくなります。
MBOにも活用できる目標設定の基本については、以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひチェックしてみてください。
(2)360度評価
360度評価は、一般的に行われる「上司と部下」の二者評価ではなく、「上司・部下・ほかのメンバー」などの多方面から評価する手法です。
企業のなかには管理職だけに360度評価を導入しているところもありますが、人事評価ではなく従業員育成の目的でこの仕組みを活用することも可能です。
360度評価の特徴は、さまざまな人が評価をすることで偏りが減り、納得感・公平性が高い評価を行いやすくする点です。ただし、評価者・被評価者の組み合わせによっては、評価に歪みが生じることがあります。
360度評価を導入する場合は、ほかの評価手法と組み合わせていきながら評価のバランスをとっていく必要があるでしょう。
(3)コンピテンシー評価
コンピテンシー評価とは、職務や役割ごとに高い成果をあげる人(ハイパフォーマー)の行動特性を洗い出し、それをもとに評価項目や評価基準を決める手法です。わかりやすくいえば、各項目において「どこまでハイパフォーマーに近づけたか?」を見ていく考え方になります。
コンピテンシーの評価項目は、以下のようにどちらかといえば定性的になることが多いです。
|
【冷静さ】 【慎重さ】 【リスクテイク】 【チーム精神】
|
コンピテンシーの考え方は、人材採用・育成・配置でも活用可能です。
自社が大切にする価値観や行動指針にマッチする行動をして成果を挙げる“ハイパフォーマー”の特性を「採用基準」や「評価基準」に落とし込むことで、企業風土の最適化も進めやすくなるでしょう。

効果的な人事評価制度の導入手順と運用ポイント
人事評価制度の効果を最大化するためには、適切な流れで設計・導入・運用をすることが重要です。ここでは、一般的な人事評価における導入と運用のポイントを解説しましょう。
ポイント(1)現状の課題整理と目的の明確化
導入前の準備段階でまず行うべきことは、新しい人事評価の仕組みを使って「何をどのように評価していきたいのか?」「人事評価にどんな効果を求めるのか?」と目的を明確にする点です。
そのために必要となるのが自社のMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の確認と人や組織に関連する課題の整理になります。
たとえば、「自社が大切にする価値観や行動指針を守りながら、組織と個人の目標達成を促していきたい」という場合、定性的な評価項目にMVVを落とし込み、定量的な評価では「MBO」をベースに設計するのも一つの方法でしょう。
また、管理職によるハラスメントやその下で働く若手人材の離職が多い場合には、評価の公平性を高める目的から「360度評価」と組み合わせる選択肢もでてくるはずです。
効果的な人事評価制度で活用する手法や項目は、企業が「どういった姿になりたいか?」や「どういった問題を解決したいか?」で変わります。
また、これらのポイントがズレてしまうと、効果を最大化することも難しくなるかもしれません。
人事評価制度を設計するための準備や目的の設定は、それなりの時間をかけてしっかり行うことが重要になります。
ポイント(2)導入スケジュールを決定する
新制度の導入によって評価軸が大きく変化すると、従業員の評価・報酬・等級に大きな影響が生じます。
そういったなかで現行制度とのバランスをとりつつ、目的に合った制度を構築させていくためには、いきなり本番運用してはいけません。
現行の仕組みと並行して2回程度の仮運用を行い、制度をブラッシュアップしていくとよいでしょう。
この仮運用期間は、従業員に支払う報酬や等級とは直結させず、新旧のズレを検証していくイメージです。
たとえば、半期に1度の評価を行っている場合は仮運用を2回するとなれば、検証・修正だけで1年の時間が必要です。
また、評価項目の設計にたとえば半年かけると考えると、設計開始~本運用の開始までに1年半のスケジュールを予定する必要があるでしょう。
現行制度の運用をしながら新制度の設計およびブラッシュアップをすることは、人事担当者にとって大きな負担になるはずです。
そのなかでより良い仕組みを設計して軌道に乗せるためには、現実的なスケジュールを決めて、進捗管理を的確にすることが重要でしょう。
ポイント(3)評価項目と評価基準を決める
スケジュールが決まったところで、評価制度の中身の設計に入ります。ここでのポイントは、評価者と被評価者の認識のズレを防ぐために、評価項目および評価基準を明確にすることです。
たとえば、「業務効率化の推進」という項目がある場合、以下のような5段階評価のなかで「何がどこまでできているか?」を示すことで、納得感の高い評価を行いやすくなるはずです。
| レベル | 状態 | 点数 |
| レベル1 | 指示があるまで何もしない | 2点 |
| レベル2 | 自身に与えられた施策をこなすことができる | 4点 |
| レベル3 | 明確な意図や目的を持って、能動的に業務効率化に取り組んでいる | 6点 |
| レベル4 | 業務効率化につながる活動について工夫を行い、現状を変化・打破しようと努めている | 8点 |
| レベル5 | 独自性の高い発想を打ち出し、上司やメンバーを巻き込みながらアイデアを実現している | 10点 |
また、仮に「売上目標3,000万円」といった定量的目標の達成度を評価する場合も、「設定目標と同等の実績⇒レベル3」や「設定目標を500万円以上超える実績⇒レベル5」といった明確な基準で評価していく必要があるでしょう。
なお、厚生労働省では、成果につながる職務遂行能力を業種・職種・職務別に整理した「職業能力評価基準」を公開中です。
<参考>:職業能力評価基準(厚生労働省)
このページを開くと、さまざまな業種の一覧からモデル評価シートなどのサンプルをダウンロードできるようになっています。評価項目や基準の参考資料やテンプレートがほしい方は、ぜひチェックしてみてください。
ポイント(4)評価者研修を実施する
人事評価の項目と基準が決まったら、次はその仕組みを使って評価を行う上司(評価者)に教育を行います。こうした研修が必要となる理由は、主に以下の2つです。
|
|
まず、新しい評価の仕組みを適切に実施してもらうためには、「なぜ新しい制度が必要なのか?」や「新しい制度によってどういう利点があるのか?」といった点の理解・共感が必要です。
たとえば、人事評価の不公平感から若手の早期離職が続いていて管理職の負担も大きくなっている場合、以下のような目的・効果を伝えることで、新制度の運用に協力してもらいやすくなるでしょう。
|
|
また、主観やバイアスにもとづく評価で生じる問題などを伝え「評価の質」を上げることも、評価者研修を実施する大きな目的です。人事評価を上司と部下の関係構築や個人の成長促進につなげるためには、適切なフィードバックのやり方も教える必要があるでしょう。
ポイント(5)被評価者向けの研修も実施する
人事評価の仕組みを変えると、いままで高評価だった人のランクが下がるとか、その逆に低評価人材の評価がアップしたりする現象も起こりやすくなります。こうした問題については、「経営層からのメッセージ」と「被評価者向けの研修」を通して目的および新しい仕組みの理解と納得感を促すことが重要です。
納得感を促すためのポイントは、先述した評価者向け研修と同じです。
現状の課題を紹介したうえで、新制度がそれを解消することを伝えるとよいでしょう。ここでのポイントは、たとえば「日々の頑張りが報酬に反映されやすくなる」とか「若手も最短2年でリーダーになれる」といったメリットを多く伝えることです。
また、新制度の影響で評価・報酬・ランクが下がりやすくなる従業員のために、これらの評価を上げるための対策なども共有しておく必要があるでしょう。
ポイント(6)
PDCAを回しながら制度をブラッシュアップする
評価者研修を終えたら、いよいよ仮運用の開始です。仮運用では、従来の制度と並行して評価をしてもらいながら、評価結果のズレや運用方法の問題などをチェックしていきます。
運用後は評価者と被評価者の両方にアンケートを行い、以下のような意見に耳を傾けましょう。
|
|
そうして、修正を加えながら評価項目および運用方法の見直しを図っていくべきです。
人事評価における適切なフィードバックの重要性
新しい人事評価の仕組みを成功させるうえで大事なカギになるのが、評価者によって行われる適切なフィードバックです。フィードバックには、以下のような3つの目的・メリットがあります。
|
|
従業員のモチベーションや成長促進を促すためには、『フィードフォワード』の考え方で会話をすることが大切です。フィードフォワードとは、未来の成功に向けて目標達成につながるアドバイスや意見を伝える考え方になります。
たとえば、一生懸命頑張ったのにも関わらず営業成績が伸び悩んだ部下に対しては、「良い成績が出せていない!」というネガティブなことよりも、「未来の成功のために何をすべきか?」という視点で以下のようなフィードバックをしていきます。
|
今期は売上5,000万円ということで、少し残念な結果だったね。でも、アポイント獲得率やキーパーソン接触率などのKPIはとても高い状態だから、来期はそこからのクローズを達成すれば良い数字がでてくるはず。日々の取り組みは間違っていないし、チーム力向上ためにも積極的に行動してくれていて本当に感謝しているよ。来期もこの勢いで頑張っていこうね。応援しているよ。
|
上司と部下の信頼関係構築とコミュニケーションの重要性
ここまで紹介したフィードバックや人事評価制度は、上司と部下の関係が良好であってこそ高い効果を発揮するものです。
逆にいえば、たとえば部下が上司に著しい不満や不信感を抱いていたり、上司が部下にハラスメント的な叱責を行っていたりする場合、そこでいきなりフィードフォワードの考え方にもとづくアドバイスをしても、成長促進などのより良い効果は得られにくいでしょう。
人事評価制度の効果を最大化するためには、部下が上司のフィードバックを素直に受け入れられる関係や、評価内容に認識のズレがある場合にそれを素直に伝えられる関係性の構築が必要です。それはつまり、「心理的安全性の高い状態」といえるでしょう。
人事評価のブラッシュアップをするなかでは、「心理的安全性の高い状態が構築されているか?」という視点を持つことも重要でしょう。
最新の人事評価トレンド
近年のビジネス環境では、目標達成に向けて仕事を進めるなかで、コロナショックやウクライナ侵攻などの外的環境の変化が起こりやすくなっています。つまり、計画どおりに仕事を進めてもゴールにたどり着くことが難しい状況ともいえるでしょう。
こうしたなかで従業員のモチベーションを高め、状況に合った成果を出していくためには、従来とは異なる仕組みで人材の評価やフィードバックを進めていくことも重要です。
ここでは、最新の人材評価トレンドとして、ノーレイティング制度とリアルタイムフィードバック、ピアボーナス制度を紹介しましょう。
ノーレイティング制度とリアルタイムフィードバック
ノーレイティング制度とは、従業員に対して業績に応じたランク付け(レイティング)を行わない人事制度のことです。
従来型の制度では、四半期・半期・年1回のペースで評価を行い、「これまでの評価と振り返り」をするのが一般的でした。これに対してノーレイティング制度では、その場での声掛け(リアルタイムフィードバック)や頻度の高い1on1などを重視する形です。
たとえば、Aさんのテレアポ件数が伸び悩み、営業成績も上がらない状況が続いていると仮定します。従来型の評価制度では、四半期や半期に1回「営業成績が上がらなかったが、それはどうしてか?」のように過去について上司と部下が一緒に考え、最適な対策などを検討していきます。
これに対してノーレイティング制度では、Aさんのテレアポ件数の伸び悩みに気づいた直後の1on1などでそれを指摘し、「外回り営業に行く前に実施するとよい」や「テレアポ研修にでてみるとよいのでは」などのアドバイスを通じて今後のことを考えていきます。
ノーレイティング制度の場合、問題発生~フィードバックまでの期間が短いため、未来に向けたフィードフォワードの会話もしやすくなります。また、うまくいかない状態が続くとモチベーションも下がりやすくなりますが、その前に上司がフォローをすることで、やる気の低下による悪循環も生じにくくなるでしょう。
なお、ノーレイティング制度の試みは、マイクロソフト・GE・GAP・アドビシステムズといった米国を代表するグローバル企業を中心に世界で広がっています。また、日本でもサッポロが相対評価による考課ランクを廃止し、ノーレイティング制度に変えたことで、さまざまな企業からその事例が注目されています。
ピアボーナス制度
近年のビジネス環境では、リモートワークが普及し労働者の働き方が多様化するなかで、「メンバー同士が直接顔を合わせる機会がないまま、同じプロジェクトに従事する」といった状況も当たり前になっています。
こうしたプロジェクトでメンバー間のコミュニケーションやエンゲージメントを活性化させるためには、自社に合った『ピアボーナス』のアプリやツールを導入してもよいでしょう。
『ピアボーナス』とは、従業員同士がお互いの仕事の成果や貢献度を認め合い、それに対して感謝や称賛のメッセージと少額の報酬を送り合う仕組みです。この仕組みを導入するGoogleのホームページには、自社のピアボーナスに関して以下の文章が掲載されています。
|
Google では、部門間のつながりを奨励し実現するために「ピアボーナス」という制度を取り入れています。これは、Google 社員が別の部門の社員の貢献を認めるために、互いのマネージャーの承認を得たうえでボーナスを送り合う仕組みです。ピアボーナスは小額の報酬で、他のチームメンバーや Google 社員にもわかるように指名者が感謝のメッセージを添えます。
<引用>:イノベーションが生まれる職場環境をつくる|Google re:Work
|
ピアボーナス制度の具体的な効果・メリットは、使うアプリなどによって変わってきます。たとえば、従業員が送り合った社内通貨を各種ポイントサービスやギフト券などに交換できる仕組みは、会社の福利厚生にもなるでしょう。
また、導入の効果は非常に多くあり、従業員同士でサンクスカードやスタンプ・拍手などで「感謝の気持ち」を送り合う仕組みは、以下のような効果があると考えられます。
|
|
ノーレイティング制度やピアボーナス制度など、何か新しい人事評価制度を検討してみてもよいのではないでしょうか。
人事労務のアウトソーシングならラクラスへ
本記事では、人事評価の定義や目的、メリットを確認したうえで、効果の高い仕組みの導入手順や注意点について解説してきました。人事評価には多くのやるべきことや注意点があるため、人事部のなかでも負担に感じている方は多いのではないでしょうか。
もし人事業務における業務効率化をお考えであれば、ラクラスにお任せください。ラクラスなら、クラウドとアウトソーシングを掛け合わせた『BpaaS』により、人事のノンコア業務をアウトソースすることができコア業務に集中できるようになります。
ラクラスの特徴として、お客様のニーズに合わせたカスタマイズ対応を得意としています。他社では難色を示してしまうようなカスタマイズであっても、柔軟に対応することができます。それにより、大幅な業務効率の改善を見込むことができます。
また、セキュアな環境で運用されるのはもちろんのこと、常に情報共有をして運用状況を可視化することも心掛けています。そのため、属人化は解消されやすく「人事の課題が解決した」という声も数多くいただいております。
特に大企業を中心として760社86万人以上の受託実績がありますが、もし御社でも人事の課題を抱えており解決方法をお探しでしたら、ぜひわたしたちラクラスへご相談ください。