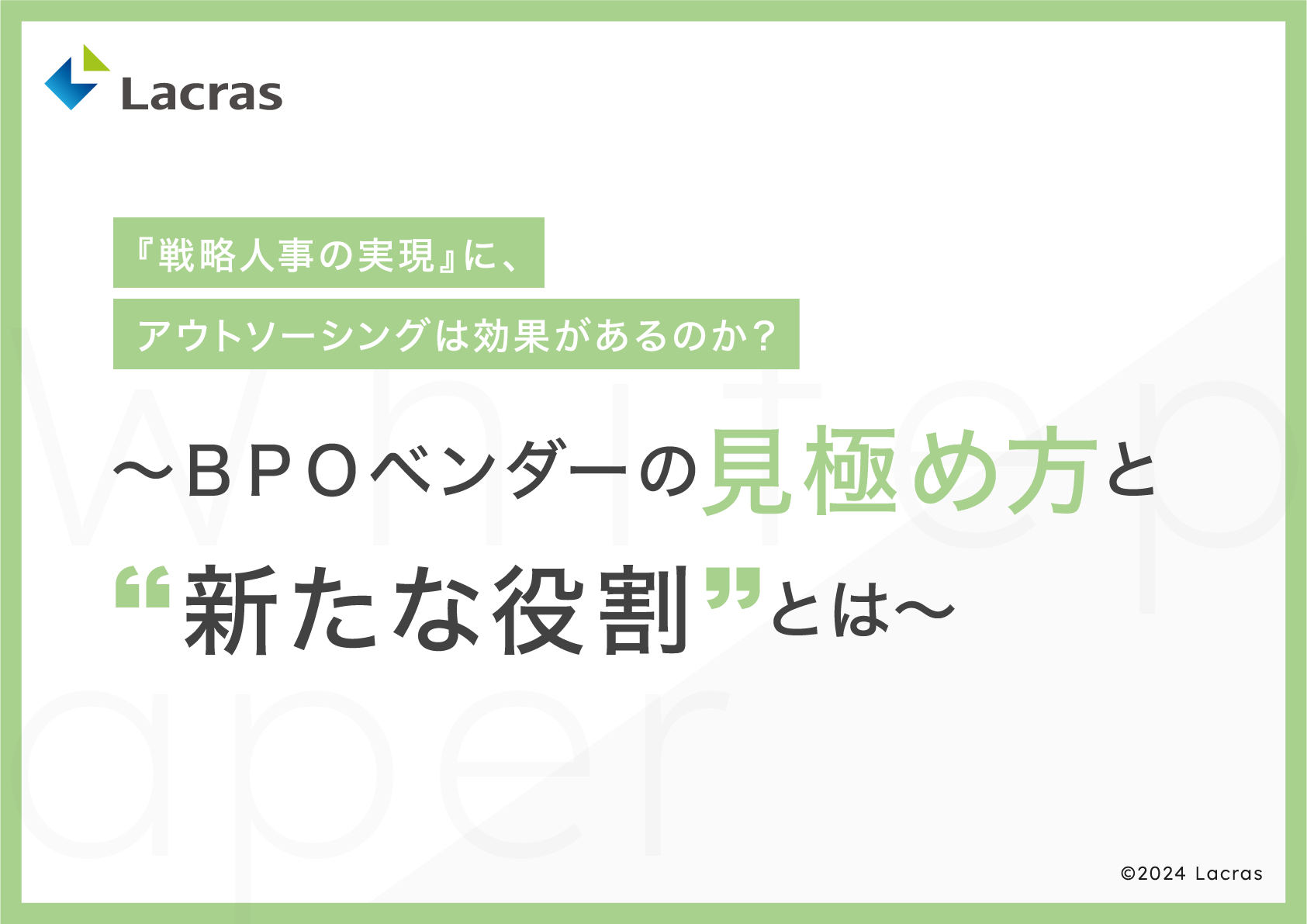HRとは何か? 人事との違いや人材価値を最適化する業務内容、HRTech(HRテック)を詳しく解説

本記事では、HRの定義や人事との違い、業務内容などを詳しく解説します。また、HRの最適化に不可欠なHRTech(HRテック)について、定義やメリット、導入ポイントなども紹介していきます。HR戦略の立案や最適化に取り組む方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
HRは、人事部門の領域でよく耳にするキーワードです。たとえば、人事担当者が採用活動や人事評価、人材教育などを行う場合は「HRの最適化」を意識した戦略の立案や施策の実施が必要となります。
そこで本記事では、“HR”の定義や人事との違い、業務内容などを詳しく解説します。記事の後半では、HRの最適化に不可欠なHRTech(HRテック)について、定義やメリット、導入ポイントなどを紹介していきます。
HR戦略の立案や最適化に取り組む方は、本記事を参考にしてください。
HRとは何か?
HRに関して、人事担当者が適切な施策を行うためには、「そもそもHRとは何か?」という定義や重要性を知ることが大切です。
また、HR関連施策の歴史や変遷に触れることで現代のビジネス環境において人事の仕事にHR戦略を重視した進化・変革が求められる理由もイメージしやすくなるでしょう。
ここではまず、HRの基礎知識として、定義・重要性・歴史を詳しく見ていきます。
HRの定義とは
HRとは、「Human Resources」を略した言葉です。直訳すると「人的資源」になります。
人的資源とは、組織で働く従業員およびそれぞれが持つスキル・能力を経営資源とみなす考え方です。人的資源は、企業がマネジメントすべき4大経営資源「ヒト・モノ・カネ・情報」の一種でもあります。
HRとHRMの違い
HRMは「Human Resource Management」の略語であり、人的資源管理や人材マネジメントを指す言葉です。つまりHRMは、HR(人的資源)を有効活用するための仕組みの総称になります。具体的には、人材の採用・教育・評価・配置などを総称した概念になるでしょう。
ただし、実際の経営層や人事領域のなかでは、HRとHRMの両方を「人的資源全般に関わる仕組み・業務」という同じ意味で使うことも多くなっています。たとえば、HRMを使わず「HR戦略の策定」という表現でも、大意が伝わるケースが多いでしょう。
HRと人事の違い
HRは、どちらかといえば人材の能力や価値を最大化し、事業・組織の成長や経営目標の達成につなげる「戦略的側面」が強い概念です。
HRでは常に企業全体の成長や利益向上を見据えて、戦略の立案および実行をしていきます。
これに対して人事は、どちらかといえば日常的な人事労務管理という「実務的側面」が強い概念です。
たとえば、人事部門が行う人材採用・教育・評価・配置・労務などの業務は、経営戦略およびHR戦略がどうであれ日々行わなければならないものでしょう。
また、特に就業規則の作成や社会保険手続き、従業員のタイムカードの労務管理は、企業が労働基準法や労働安全衛生法を遵守し、労働者の健康や安全を守るために必ず行わなければならない側面もあります。
人材資源の価値の最大化および有効活用は、人事部門の日々の業務が適切に行われてこそ、実行・達成できるものです。また、適切な人事管理や労務管理が実施されている土台があるからこそ、たとえば中長期的な経営戦略と連動した優秀な人材の獲得やスペシャリスト人材の育成といった攻めのHR戦略・施策の成功が見えてきます。
そういった意味で人事部が行う人事労務の仕事には、企業のHRマネジメントを支え発展させる土台的な役割があります。
なお、人事労務管理の概要や具体的な業務については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
【関連記事】人事労務管理の重要性とは? 人事管理と労務管理の基本概念から業務内容までを徹底解説
HRの歴史と変遷
戦略的なHRが行われるようになったのは、18世紀後半から19世紀前半に英国で起こった産業革命がきっかけと言われています。
経営者が労働者を雇用して仕事に従事させる組織体系というのは、産業革命の前からも多く存在していました。しかし、産業革命以降は工場での大規模生産が増えることになり、そこで働く人も増加するなかで従来の属人的かつ感覚的な管理では人材の有効活用が難しくなったのです。
そういったなかで、以下のように経営学者や心理学者による科学的な労務管理理論が誕生し、人的資源の管理に活用されていくようになりました。
|
|
1970年代以降になると、人的資源のマネジメントは「単なる労働者の管理監督の域を超えたものである」という考え方が浸透し、労働者のモチベーションやモラルを高める工夫が実践されるようになっていきます。
そして1990年以降、中長期的な成功には「経営層や管理職自身の人間性向上が不可欠である」という考え方から、現場の作業者だけでなくリーダーやマネージャーの育成にも重きを置く人的資本管理の手法などが浸透するようになりました。
近年の日本におけるビジネス環境では、戦後から長く続いてきた終身雇用と年功序列の仕組みが崩壊し、1つのプロジェクト内で正社員・フリーランスのプロフェッショナル人材・他部署の副業社員……といった多様な人材が協働することも多くなっています。また転職が一般化したことで、若手を中心とする早期離職も増えている状況です。
それはつまり、かつてのように「自社で直接雇用した従業員を、同じ組織の上司がマネジメントする」とか「新卒入社した従業員が、定年まで同じ会社にとどまる」といった考えが通用しない時代であることを意味します。
また日本政府でも、持続的な企業価値の向上に不可欠な要素として「人的資本経営」をあげている状況です。
<参考>:人的資本経営 ~人材の価値を最大限に引き出す~(経済産業省)
こうしたなかで企業のHRおよび人事部門の役割は、著しい転換期に入っていると考えられます。また、このような時代に適切なHR戦略を立案し組織の成長につなげていくためには、自社の事業および組織の維持・成長に求められるHR戦略がどういうものかについて、一度見直してみる必要があるでしょう。
HRの成功に不可欠な業務内容
HRを成功させ経営戦略に好循環をもたらすためには、人事部門が日々行う業務について法律を遵守するのはもちろんのこと、いわゆる「攻めの施策」を実施していく必要があります。
ここでは、HRの成功を支える人事部門の業務内容を6つ挙げ、詳しく見ていきます。
業務(1)戦略的採用
HRを成功に導く採用活動とは、経営戦略から落とし込まれた人材戦略を理解したうえで、組織のゴール達成に必要な人材ターゲットを分析・設定し、その層に対して適切なアプローチを実施していくことです。
この考え方は「戦略的採用」と呼ばれるものであり、都度発生する問題に対処しているだけで計画性がない「場当たり的採用」とは大きく異なるものになります。
戦略的採用の場合、中長期的な経営戦略の成功に寄与する人材の獲得を目指すことが多いです。
それは、単なる優秀な人材の採用とも違うものでしょう。
まず、自社が求めるスキルを持つ人材を定着させるためには、自社の価値観や考え方にマッチする「カルチャーフィット」を重視した選考が必要です。
また、たとえば「市場認知度が低く採用リソースが少ない中小企業」が自社に合う人材を確実に獲得するためには、大企業が多い大きな市場ではなく第二新卒の市場を狙ったり、ダイレクトリクルーティングなどの攻めの採用手法を選択したりすることも求められるでしょう。
業務(2)人材育成・研修
HRの成功につながる人材育成とは、“キャリア共律”の考え方を軸に「経営戦略および現場のニーズ」と「従業員のニーズ」をマッチしたところで、具体的な教育や研修を実施していきます。
“キャリア共律”とは、リクルートが「企業情報の開示と組織の在り方に関する調査2024」の第四弾で提唱した概念で、企業と従業員が協働してキャリア自律を実現するという概念です。
<参考>「企業情報の開示と組織の在り方に関する調査2024」第四弾<PDF>(リクルート)
たとえば、システム部門に入社したAさんに「将来はプロジェクトマネージャーになりたい」という夢や目標がある場合、以下のような育成をすることで会社と従業員本人にWin-Winの状態が生まれやすくなるでしょう。
|
【新人研修~2年ほど】
【2年目~4年目ぐらい】
【4年目~】
|
逆にいうと、会社の戦略・都合・期待を一方的に押し付けるような育成を行うと、従業員本人のキャリアビジョンとの間に大きな乖離が生まれる可能性もあります。
そこで「この会社では自分の夢を実現できない」となれば、多くのコストをかけて獲得した人材の早期離職を招いてしまうかもしれません。
企業が存続するためには、組織の中長期的な成長や事業計画の成功につながる人材の育成が不可欠です。しかし、働く人のキャリアが多様化し転職が一般的な時代のなかでは、キャリア共律の考え方を意識した育成計画を立案する必要があるでしょう。
業務(3)適切な人事評価と等級・報酬制度
HRを成功させるためには、透明性や公平性が高く、従業員のモチベーションや目標達成度を高める人事評価・等級・報酬制度の設計・運用も必要になります。
たとえば、「評価項目・基準が明確な評価・等級・報酬制度」と「目標管理制度」を組み合わせると、従業員側では「今期の売上目標7,000万円を達成すると、人事評価が25点以上になって報酬が◯万円ぐらいアップする。この成果を出し続けると来年には等級も上がってリーダーになれるだろう」といったように、自分の評価・等級・報酬の予測がつきやすいことになります。
それはつまり、自分が立案した計画と努力で等級・報酬といった成果をコントロールできる状態です。この状態は、各従業員に仕事への面白さや自己効力感(自信)をもたらすでしょう。
このように、多くのコストをかけて獲得した人材のモチベーションを高め、その価値を最大化するためには、適切な人事評価・等級・報酬を与える仕組みを“動機付けの装置”として設計する必要があるのです。
人事評価や賞与評価については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
【関連記事】人事評価における目標設定の基本とは?目標の活用法、運用時の注意点を詳しく解説
【関連記事】人事評価とは? 効果を最大化する最新トレンド手法や成功事例、導入ポイントを解説
【関連記事】賞与評価の重要性とは?|不当査定を防ぐための基準や実践的手法、就業規則のポイントを解説
業務(4)組織環境および風土の変革
従業員の価値や能力を最大化するためには、すべての人が働きやすい環境・風土を整備することも大切です。ただし、この働きやすい環境・風土は、時代の流れや政府の方針を受けて変わりやすいものでもあります。
たとえば、近年の日本は著しい少子高齢社会へと向かっています。そういったなかで国をあげて推進しているのが、「女性活躍」や「育児・介護と仕事の両立支援」などの取り組みです。
企業がHR戦略を成功させるためには、優秀な人材が育児・介護などを理由に仕事を辞めなくていい仕組みなど、各自の事情に理解・共感を示し組織全体でサポートする風土が必要です。
逆にいえば、育児・介護と仕事との両立を目指す従業員への理解や支える姿勢がない組織では、どんなに素晴らしい育休制度などを整備しても、従業員の定着が難しくなるはずです。
また、近年では国内の労働力人口が減少するなかで、障がいを持つ人や外国人などを積極採用し、多様な人材同士で「認め合い、受け入れ、活かす」取り組みを行う企業も増えています。いわゆる『ダイバーシティ経営』もその一つでしょう。
障害者採用や外国人採用といったダイバーシティ経営を成功させるうえでも、やはり“仕組み”と“風土”を両輪で回す考え方が重要となります。
ただし、組織風土はその職場の「当たり前」でもあるため、一朝一夕で変革できるものではない側面もあります。
しかし、中長期的にHR戦略を成功させ続けるうえでは「育児や介護をする人を支える風土」や「違いを認め活かし合う風土」を目指し、さまざまな取り組みを実施していく必要があるでしょう。
障害者雇用やダイバーシティに関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
【関連記事】障害者雇用の現状と重要性|最新データを踏まえて雇用促進の対策と未来の展望を解説
【関連記事】ダイバーシティとインクルージョンの違いとは? 多様な人材が活躍する環境の作り方、成功事例を解説
業務(5)MVVの設計と浸透
MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)は、HR戦略を成功に導く“指針”のようなものです。MVVを構成する3要素には、一般的に以下の意味が込められています。
|
【ミッション】 【ビジョン】 【バリュー】
|
たとえば、先述のように組織風土の変革を行う場合、MVVに以下のような文章が入っていれば、その内容を組織に浸透させて「組織の当たり前」にすることで、変革も自然と成功しやすくなるでしょう。
|
|
MVVは、戦略的採用活動や目標管理制度、人事評価・等級・報酬制度とも連動すべきものです。自社のメンバーを導く適切なMVVを設計し、それらが社内に浸透してこそ、中長期的なHRの成功につながってくるでしょう。
業務(6)労務管理
労務管理とは、労働基準法や労働安全衛生法、育児・介護休業法といった法律の定めに従い、従業員が働く環境の整備・管理を行う業務の総称です。
具体的には、以下のような業務が労務管理にあたります。
|
|
社内の人的資源の価値を最大化し、経営戦略の成功につなげていくためには、法令に従った労務管理を行い、会社としての信用性と健全性の両方を高める必要があります。
ビジネスシーンでは、このことを「コンプライアンス」と呼ぶことが多いでしょう。また、コンプライアンスを遵守するためには、健全な経営を行うための内部管理体制(ガバナンス)の強化も必要です。
法律を守り健全な経営を行う組織体制であるからこそ、自社にマッチする優秀な人材からの応募が増え、活躍・定着につながっていきます。また、多くの人材に健康な心身で能力を発揮してもらうためには、労務管理のなかで時間外労働の上限などを適切に監視していくことも重要でしょう。
HRが企業に与える影響
HRの成功を目指して人事労務管理の施策を設計・実行していくと、企業内には様々な好影響が生まれやすくなります。
ここでは3つを挙げて解説します。
影響(1)人的資本の価値が高まる
企業がHR戦略を意識した人事労務管理を適切に行うことで生まれるのが、従業員個人および組織の価値が最大化する状態です。
たとえば、自社の価値観や考え方にマッチする人材(Aさん)を獲得したと仮定します。そのAさんのキャリアビジョンをヒアリングしたうえで、“キャリア共律”の考え方を軸に適切な育成や教育を行うとどうなるでしょうか。
「この会社は自分のキャリアを応援してくれる」とか「この環境なら自分は成長できる」などのポジティブな思いが生まれ、結果として従業員エンゲージメントが向上しやすくなるでしょう。
また、こうしたポジティブな状態がほかのメンバーにも生まれると、多くの人がチームへの愛着を持ち「仲間のために目標達成したい」や「仲間と一緒に成長したい」などと考えることで、組織の価値や生産性も最大化するかもしれません。
適切な考え方や手法にもとづくHR戦略の立案・実施は、このような好循環から個人と組織の価値を数倍にも高めてくれる可能性もあるのです。
なお、従業員エンゲージメントの詳細については以下の記事にて解説しています。あわせてご確認ください。
【関連記事】従業員満足度(ES)と従業員エンゲージメントの違いとは?高めるメリットや方法も解説
影響(2)企業文化の醸成
企業文化とは、組織内に存在する考え方・価値観・行動規範の集合体であり、先ほど触れたMVVに近いものになります。
人材資源の価値を最大化するためには、個人および組織のモチベーション・パフォーマンス・エンゲージメントなどを高めることが重要です。モチベーション・エンゲージメント・パフォーマンスなどを「木の枝葉」と考えると、企業文化はその下で個人と組織を支える「木の根」のイメージになるでしょう。
企業文化やMVVが確立・浸透していると、組織のメンバーは「自分が何をすべきなのか?」を理解した状態で各自の目標達成を目指すことになります。また、一緒に働く仲間も同じ価値観に共感している状態であるため、考え方や行動の違いによる衝突も生じにくいでしょう。
しっかりとした木の根(企業文化)が確立しているからこそ、個人および組織は逆境が多いビジネス環境のなかでも倒れることなく困難を乗り越え、主体的にゴールへと向かい続けることが可能となるのです。
影響(3)人件費の大幅な削減
企業文化の醸成・浸透が成功し、個人と組織のモチベーション・エンゲージメント・パフォーマンスが向上すると、以下のような仕事による時間およびコストの浪費がおさえられます。
|
|
優秀な人材に多くのコストをかけて採用してもすぐに辞められてしまったり、たくさんの教育費用をかけているのにも関わらず次世代リーダーの育成が進まなかったりすることもあると思います。
そのような場合は、人材採用・教育・評価・配置などの諸活動が人的資源に最大化を目指す内容になっているかを一度見直しても良いかもしれません。

HR担当者に求められるスキル
人材資源の価値を最大化するためには、さまざまなテクニックが必要です。このテクニックを日々の人事労務管理のなかで導入・実施していくうえでは、HRを行う担当者にもそれなりの能力および適性が求められます。
ここでは、HRを成功させるうえで担当者に求められるスキル(知識・能力・適性)について、詳しく見ていきましょう。
スキル(1)自社および市場の現状分析力
「人材資源の価値を最大化する」といっても、その中身や方向性は企業ごとに異なります。そういったなかで自社に最適なHR施策を導入・推進するためには、自社および市場の現状を俯瞰的に見ることができる「目」が必要です。それはいわゆる“メタ認知”と呼ばれるものでしょう。
そのなかで大切なポイントの一つに自分たちを疑ってみることがあります。
たとえば、求職者の誰もが知る総合求人サイトに募集を出しても全く応募が来ない場合、その理由を外的要因のせいにしてしまうと「少子化で労働力人口が不足しているから来ない」という要因が見えてくるかもしれません。
しかしそこで「自社(社内)にも理由があるのではないか?」と考えると、以下のような要因が見えてきたりします。
|
|
自社が抱える本質的な課題を解決したうえで人的資源の価値を最大化するためには、上記のように自社および市場・業界に存在する「不都合な問題」にもしっかりと目を向けて分析する姿勢が必要でしょう。
スキル(2)専門知識
自社および市場・業界の現状が見えたら、次は「その現状をどのように改善すべきか?」や「どのように目標達成すべきか?」を考えます。そこで必要となるのが、採用・評価・教育・労務管理などに関する専門知識です。具体的には、以下のようなテクニック・サービス・手法・用語などを指すことが多いでしょう。
|
【採用】
【評価】
【教育】
【その他】MVV、パーパス経営、ダイバーシティ経営、エンゲージメント強化、福利厚生サービス、労務管理システム など
|
上記のように各カテゴリで使える引き出しが多いと、人材資源の価値を最大化するためにさまざまな挑戦もしやすくなります。また、経営層や現場管理職と建設的な話をするうえでも、専門知識はたくさん持っていたほうがよいでしょう。
スキル(3)戦略的思考
戦略的思考とは、HRの成功に向けた合理的な戦略を立案して、プロジェクトを推進するためのプロセスおよび思考力のことです。
たとえば、人事部門の新任担当者は、上司から仕事を教えてもらいながら、採用活動や教育プログラムの設計などを「言われたとおりに行うこと」が多いでしょう。それは「受動的な姿勢」ともいえます。
一方でHRの担当者には、たとえば従来の手法による採用データや採用課題を理解したうえで、「A手法よりもB手法のほうが自社に合っているのではないか?」といったことを論理的に考え、「主体的な姿勢」で仕事を推進していく姿勢が求められます。
それはつまり、限られた人材資本の価値を最大化する担当者には、自社のHR領域について常に「問い」を立て、必要なデータなどを分析しながら最適解を求め続ける姿勢と思考力が求められるということなのです。
スキル(4)人間力とコミュニケーション能力
HRを最適化する担当者には、周囲を動かすためのコミュニケーション力が必要です。そのために必要となるのが、高いヒューマンスキル(人間力)になります。
まず、コミュニケーション力の基本である「話すこと」と「聞くこと」は多くの人が当たり前にやっていることだと思います。しかしそこで、“人を動かすためのコミュニケーションを図る”となると、難易度が少し上がります。その理由は、自分の主張や意見を一方的に話しただけでは、相手は基本的に動いてくれないことが多いからです。
たとえば、HRで新しい施策を実施する際に、それを経営層や現場管理職に受け入れてもらって協力につなげるためには、日頃から良い関係を築き「相手に心を開いてもらっている状態」が必要となります。逆にいえば、相手がこちらに心を開いていない場合、協力を得たり話を聞いてもらったりすることはかなり難しいでしょう。
そこで重要となるのが、HR担当者の「傾聴力」と、信頼関係を築くための「ヒューマンスキル(人間力)」です。
「傾聴力」とは、相手の話を深く聴くことです。
たとえば、開発現場で時間外労働が増加しすぎている現状がある場合、それをマネジメントする管理職の気持ちに寄り添いながら相手の悩みや課題を「聴く」ことで、深い関係の構築につながりやすくなります。
また、相手が「この人は自分の話を聞いてくれる人だ」や「自分の悩みに寄り添ってくれる人だ」と感じると、そこから信頼関係が醸成され、こちらの話も伝えやすくなるかもしれません。
HR戦略を進めていくためには、経営層や現場の管理職から「人として信頼される状態」をつくることが土台になります。その土台があってこそ、自分のまわりに協力してくれる人が集まり、HR領域における好循環を起こしやすくなるでしょう。
HR成功に役立つHRTech(HRテック)とは?
ここまで紹介したとおり、担当者がHRを最適化するためには、さまざまなスキルや専門知識が必要です。しかし知識やスキルは、一朝一夕で身につくものではありません。
そういったなか、担当者の負担を減らす存在として注目されているのが、HR Tech(HRテック)と呼ばれるテクノロジーです。
ここでは、HRテックの定義と目的、メリット、近年の進化とトレンドについて詳しく見ていきます。
HRTech(HRテック)の定義と主な目的
HRTech(HRテック)とは、IT技術を活用した人事労務分野のシステム・ソフトウェア・ソリューションの総称です。読み方は「エイチアールテック」になります。
HRTech関連サービスの多くは、データベースや生成AIなどの技術を活用して、HR領域の業務効率化や最適化をする目的で開発されています。
具体的な機能は導入サービスごとに異なりますが、近年では人材採用・育成・評価・配置・タレントマネジメント・労務・給与・社会保険手続きといった大半の業務のなかで、何らかのHRTech関連サービスが登場しているでしょう。
HRTech(HRテック)の導入メリット
具体的な導入メリットは各種サービスの機能の影響を受けることになりますが、一般的には以下のような効果を感じる企業担当者が多くなっています。3つを挙げて解説しましょう。
メリット(1)人事労務管理が効率化され、担当者の負担が減る
たとえば、タイムカードの電子データと勤怠管理・給与計算などが連動しているシステムを使うと、タイムカードの情報をExcelなどに転記する作業がなくなります。また、給与計算も打刻データをもとに行えるため、転記時に発生していた手間とミスの両方が減ることになるでしょう。
メリット(2)HR戦略の立案・実施といったコア業務に専念しやすくなる
HRTechの導入で勤怠・給与計算・年末調整などの業務が効率化すると、人事部門の担当者は余裕が出たリソースを使ってHR戦略の立案や施策の実施といった“コア業務”に専念しやすくなります。
逆にいえば、戦略人事のニーズが高まるなかで担当者がHRの最適化に力を入れるためには、比較的負担が大きい勤怠・給与計算・年末調整などの業務をHRTech上で行い、コア業務に使えるリソースを増やす取り組みが求められるでしょう。
メリット(3)データドリブンな意思決定が可能となる
HRTechを導入・活用すると、蓄積した日々のデータから例として以下のような傾向が見えるようになります。
|
|
これはつまり、自社の人および組織についてデータにもとづく現状把握や分析が可能になるということです。
HR領域において、経営層や現場管理職に納得してもらえる施策を打ち出すためには、勘や経験に頼りがちな従来の意思決定から脱却し、根拠のあるデータを示していくことが重要になります。
また、HRTechを通して収集したデータは、実施施策の評価や振り返りにも活用できるものです。
「データ」という客観性の高い情報を参考にするからこそ、自社の現状に合う施策の実施や適切な改善を行いやすくなるでしょう。
HRTechの進化とトレンド
HRTechの市場で近年注目されている技術には、以下の4つがあります。
|
【クラウド】 クラウドサービスは、HRテックが提供するソリューションの主流です。クラウド上で構築されたサービスは、インターネットにつながっていれば「いつでも、どこでも」利用可能となります。
【モバイル】 クラウド×モバイルの普及により、たとえば出張先やリモートワークを行う自宅からタイムカードの打刻や、年末調整書類の入力・提出といった作業も行えるようになっています。これらは多様化する働き方と相性が良い技術でしょう。
【RPA】 RPA(Robotic Process Automation)は、これまで人間がやってきたパソコン操作などを自動化する技術です。RPAの仕組み上で操作をルール化すると、勤怠データのチェックや別システムからのデータインポートなども自動で実行されます。
【人工知能(AI)】 AI技術も、HRテックに分析や自動化などのさまざまな機能を提供しています。たとえば、生成AIを活用した採用AIエージェントのなかには、自社に合う最適な候補者探し~スキルチェック~面接日時の調整~面接までを行えるものも存在します。
|
HRの未来と展望
ここまで紹介したとおり、多くのHRTechはさまざまな最新技術を取り入れることで、単なる「業務効率化のツール」から、人間よりもはるかに俯瞰的かつ客観的な分析や意思決定を行う「人事の参謀」的な存在に変化しつつあります。
一方で、近年のビジネス環境では、労働者の価値観や働き方、会社に求めることなどが多様化しています。また、“コロナショック”や“インフレ”などの問題が重なると、労働者のライフスタイルやニーズがさらに複雑化することでそれらを適切に把握することも難しくなるでしょう。
そういったなかで人・組織・市場について高度な分析を行いながら適切な意思決定につなげるためには、生成AIやビッグデータなどの技術を活用したHRTechの導入が不可欠になります。
また近年では、国税庁でも年末調整や法定調書の電子申請を推進しています。人事労務領域におけるHRTechの活用は、これからさらに重要性が増してくる可能性が高いでしょう。
HRTech導入の流れ
HRTechには、さまざまな種類があります。そのなかで自社のHR最適化に効果的なサービスを選ぶためには、適切な流れで選定作業を進めていく必要があるでしょう。ここでは、費用対効果の高いHRTechを選ぶ際のポイントをふまえた導入ステップを解説します。
ステップ(1)導入目的の明確化
自社にとって最適なHRTechは、解決すべき課題や目的ごとに変わります。
HRTechを選ぶうえでは、まず自社の課題を洗い出したうえで、「我々はなぜHRTechを導入するのか?」という目的を明確にしましょう。具体的には、以下のような目的を洗い出せるはずです。
|
|
ステップ(2)HRTechサービスの比較と選定
自社の目的が明確になったら、次はその目的を叶えるHRTechサービスの比較と検討をしていきます。ここでのポイントは、「安ければいい」といった単純な視点ではなく、「自社にとって費用対効果が高そうなサービスを探す」ということです。
もっともわかりやすい視点としては、「自社と同じ業種・規模の組織に導入事例があるか?」でしょう。目的・規模・業種が同じ実績があれば、サービス提供業者への相談もしやすいはずです。
また、勤怠管理や年末調整のHRTechの場合、一般従業員にも操作・入力してもらうことが重要です。一般従業員も不満なく使用できるサービスを選ぶためには、お試し版などを使って現場の意見を聞くことも必要でしょう。従業員および自社の大事なデータを入力するうえでは、各社のセキュリティ対策にも注目しなければなりません。
各社のサービス・機能が似ていて比較検討が難しい場合は、自社の目的・使用環境・予算などを各社に示して相見積もりをとるとよいでしょう。
ステップ(3)効果測定と改善
HRTechを導入して実際に使用した後は、必ず効果測定と評価を行います。
たとえばそこで、「導入の主目的は達成したが、AとBの部分で多くの従業員から不満が生じた」などの問題があれば、別のサービスへの変更や運用方法の見直しが必要になってくるかもしれません。
いずれにせよ、HRTechを活用してHRの最適化を図るためには、実際に使用する従業員の声に耳を傾けながら、「導入サービスそのもの」と「運用方法」の両方をブラッシュアップしていく姿勢が大切でしょう。
人事労務のアウトソーシングならラクラスへ
本記事では、HRの定義や人事との違い、業務内容などを解説してきました。HR戦略の立案や最適化に取り組むうえでは多くの注意点があるため、人事部としても進めていくのはリソース面で負担に感じている方も多いのではないでしょうか。
もし人事業務における業務効率化をお考えであれば、ラクラスにお任せください。ラクラスなら、クラウドとアウトソーシングを掛け合わせた『BpaaS』により、人事のノンコア業務をアウトソースすることができコア業務に集中できるようになります。
ラクラスの特徴として、お客様のニーズに合わせたカスタマイズ対応を得意としています。他社では難色を示してしまうようなカスタマイズであっても、柔軟に対応することができます。それにより、大幅な業務効率の改善を見込むことができます。
また、セキュアな環境で運用されるのはもちろんのこと、常に情報共有をして運用状況を可視化することも心掛けています。そのため、属人化は解消されやすく「人事の課題が解決した」という声も数多くいただいております。
特に大企業を中心として760社86万人以上の受託実績がありますが、もし御社でも人事の課題を抱えており解決方法をお探しでしたら、ぜひわたしたちラクラスへご相談ください。