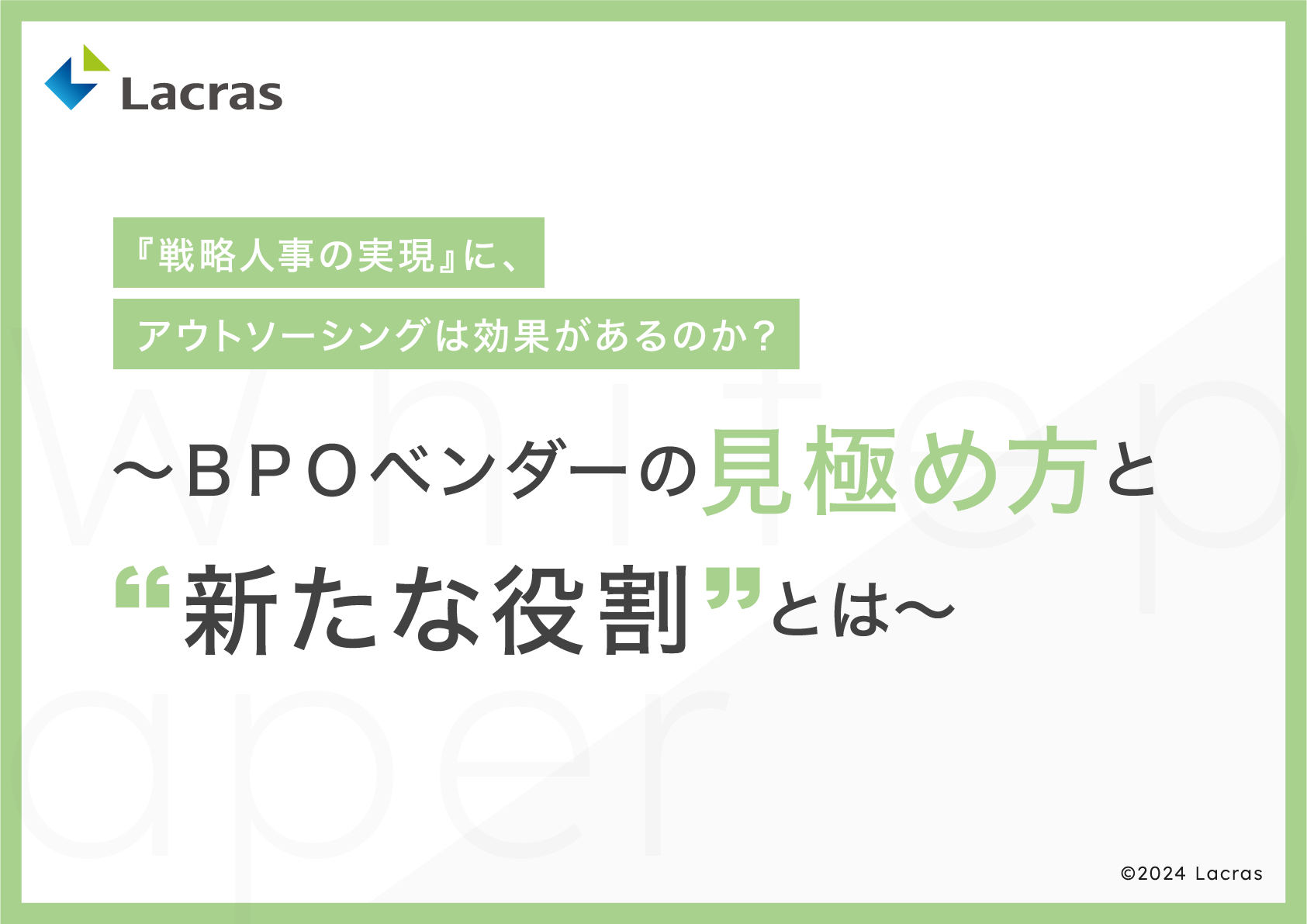人事と労務の違いとは?それぞれの仕事内容や特徴を詳しく紹介

本記事では、人事と労務の用語の意味や主な業務内容だけでなく、それぞれの違いについて明確にしながら解説します。また、人事労務の担当者としてスキルアップを考えている人のために、必要なスキルやキャリアパスに関しても解説をしてまいります。ぜひ参考にしてみてください。
人事と労務は、多くの企業で混同されやすい業務です。しかし、これらの仕事にはそれぞれの役割や目的があります。人事労務部門のなかで仕事を分担する場合も、人事と労務の範囲や仕事内容を理解することで、自分に求められる役割が見えやすくなるでしょう。
そこで本記事では、用語の意味や主な業務内容などから、人事と労務の違いを明確にしていきます。また、人事労務の担当者としてスキルアップを検討する人のために、必要なスキルやキャリアパスに関しても解説します。
人事と労務について詳しく知りたい人は、ぜひこの記事を参考にしてください。
人事と労務の違いとは
人事と労務の業務を適切に行うためには、それぞれの定義や目的を理解することが重要です。そうすることで、自分の役割や業務範囲もイメージしやすくなるでしょう。
ここでは、人事と労務の概要を紹介しながら、その違いを明らかにしていきます。
人事の意味・役割・目的
人事は、組織の安定や持続可能性を高める目的から、人材活用を促す役割です。
具体的には、人材戦略や採用戦略を立案し、人材および組織に対して適切な施策を講じていきます。こうした業務の特徴から、人事の担当者は、組織を率いる管理職や各人材と直接関わることが多くなります。
労務の意味・役割・目的
労務は、労働基準法などの法律にもとづき、従業員が安心して働くための管理や環境整備を行う役割を担います。
労務はバックオフィス的な役割となるため、管理職および従業員と直接関わる機会は、人事と比べて少なくなります。しかし、勤怠データなどの確認中に「長時間労働を強いている傾向がある」とか「健康面で問題がありそう」といった気づきがあれば、管理職または従業員本人に声掛けすることは発生するでしょう。
人事の主な業務内容
人事の主要業務は、人材の採用・育成・評価・配置の4つです。ここでは各業務の概要を見ていきましょう。
(1)人材の採用活動
1つは、経営資源のなかで最も重要である「人材」を雇い入れる活動です。人材採用は、新卒採用と中途採用の2つが中心になります。
新卒採用は長期化しており、従来から行われている会社説明会や採用面接のほかに、インターンシップや内定者フォローなども多くの企業で実施されるようになりました。
中途採用は、各部署のニーズや経営戦略を踏まえて、必要な人材に適切な方法で訴求していく形が多いでしょう。
(2)人材の育成
会社の成長や経営目標を達成するためには、人材を育てることも重要です。各人材に行う教育(研修)には、以下のように多くの種類があります。
|
【階層別研修】 年次や経験で区分して、各階層で必要なスキルやマインドなどを身につけるもの。
【職種別研修】 そのスキルや専門知識を身につけるもの。
【スキル研修】 全従業員を対象とする「ハラスメント研修」もスキル研修の一種。
【マインド研修】 重要にすべき価値観や考え方などを身につけるもの。
|
上記の研修は、プログラム設計~実施までを社内で行う「内製(社内研修)」のほかに、専門講師による「外部委託」という選択肢もあります。
(3)人材の配置
組織の生産性を最大化するためには、「各人材のスキル」および「各部署の課題」を含めた状況把握をしたうえで、適材適所の配置を行う必要があります。人材配置を最適化することで、従業員のパフォーマンスやモチベーションの向上、定着率の改善といったメリットが期待できるでしょう。
なお、近年では、配置を決める際に従業員本人の志向やキャリアプランを考慮する考え方も一般的になっています。
(4)人事評価制度の設計と運用
人事評価は、従業員の給料や階層にも影響することから、公平性・納得性・透明性が高いものを設計すれば、生産性向上や従業員の成長に役立ちます。
多くの従業員が納得できる人事評価を行うためには、評価者である管理職の教育も必要です。制度の設計後は、評価者と被評価者の意見や感想に耳を傾けながら、手間・不満・違和感などを少しずつ解消していく必要があるでしょう。
人事評価や目標設定について詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてみてください。
労務の主な業務内容
労務の仕事の大前提は、労働基準法や労働安全衛生法といった法律を守りながら、以下の4つを適切に進めていくことです。
|
(1)労働に関するルールをつくる (2)従業員の働き方・時間・休日などを管理する (3)給与を支払い、社会保険料・税金を納める (4)従業員の健康や安全を守る
|
それでは、(1)~(4)の中身を詳しく見ていきましょう。
(1)労働に関するルールをつくる
常時10人以上の従業員を使用する場合、使用者は就業規則を作成して所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。
また、従業員数が少なく、制度上は就業規則の作成が不要であっても、労働条件通知書のなかで「どういう条件やルールで仕事をするか?」を示し、交付しなければなりません。
なお、労働に関するルールには以下の4つがあります。従業員との間でどのような約束をする場合でも、必ず最上位の法令を遵守してください。
|
法令(労働基準法など)>労働協約(会社と労働組合の約束)>就業規則(社内の統一的なルール)>雇用契約書(各従業員と会社の約束)
|
(2)従業員の働き方・時間・休日などを管理する
法令を遵守し従業員の健康やワーク・ライフ・バランスを守るためには、勤務時間、残業時間、休憩時間、有給休暇の取得状況、休日出勤、遅刻欠勤などの管理が必要です。これらの管理を総称して、「勤怠管理」と呼びます。
企業倫理を守り従業員の健康を維持するためには、「長時間労働が続いていないか?」とか「遅刻・欠勤・早退が多くないか?」といった視点を持つことも重要です。
勤怠管理をしっかり行うと、「慢性的な人材不足である」とか「適材適所の配置ができていない」といった人事面の課題が見えてくるケースもあるでしょう。
(3)給与を支払い、社会保険料・税金を納める
毎月の勤怠データがまとまったら、労働基準法第24条で定められた「賃金支払いの五原則」を守り、期日までに給与の計算と支払いを行います。また、給与の計算では源泉徴収税および社会保険料を差し引き、従業員本人に代わって納める手続きも必要です。
<参考>:賃金の支払方法に関する法律上の定めについて教えて下さい。(厚生労働省)
毎年10月~翌1月末にかけては、実際の年税額を計算して精算を行う年末調整も実施します。年末調整にはいくつもの期限やルールがあるため、労務の担当者は期日までにミスなく手続きを終わらせる必要があります。
(4)従業員の健康や安全を守る
従業員の安全と健康を守るためには、安全衛生管理が必要です。安全衛生管理では、以下のような施策を実施します。
|
|
福利厚生も、従業員の健康やモチベーションの向上、生活の安定などに役立つものです。福利厚生には、法律で義務付けられた「法定福利厚生」のほかに、以下のように会社が独自に設定できる「法定外福利厚生」があります。
|
|
人事労務が重要である理由
人事労務は、企業のなかで特に重要性が高い仕事です。特に近年では、以下の2つの理由と役割から、やりがいと期待度の両方が大きく高まるようになりました。それぞれ見ていきましょう。
理由(1)会社組織の運営に携わるから
人事労務は、会社という大きな組織を俯瞰して見ながら、必要な人材の採用・育成・配置・評価などを行い、中長期的な成長や経営目標の達成につなげていく仕事です。
企業は「人」がいなければ事業ができません。そのため、人に関するさまざまなアプローチを実施する人事労務は、非常に重要性が高くやりがいが大きい仕事になります。
たとえば、「3年後、東北に新営業拠点を開設する」という経営計画がある場合、そこに向けて経営陣や営業部門の管理職とコミュニケーションを図りながら、「新営業拠点のメンバーおよびリーダーは育てるのか?新たに現地採用するのか?」などの採用・育成計画を立案する必要があります。
また、同時期に「開発部門で慢性的な人員不足がある」とか「営業部門で若手離職者が増えている」といった課題が露呈すれば、現場の管理職と相談しながら人事と労務の両面から施策を考え、改善する必要があるでしょう。
近年のビジネス環境は、終身雇用の崩壊による人材の流動化や早期離職者の増加、転職の一般化などにより、人材計画も立てにくい時代です。こうしたなかで必要な人材を獲得し、定着させ、会社を支える存在へと育成する人事労務の役割は、今後も大きくなっていく可能性が高いでしょう。
理由(2)企業の価値観や文化の形成に従事するから
近年のビジネス環境では、政府が推進する“働き方改革”や“ダイバーシティ経営”などの影響から、働く人の属性および価値観が多様化しています。
また、いまは『VUCA』と呼ばれる激動の時代であり、たとえばコロナ禍やウクライナ侵攻などが突然起きたように、企業側でも予測できない出来事が複合的に発生したりする時代です。ECサイトの普及や産業のグローバル化などの影響から、顧客ニーズの多様化や変化も起こりやすいでしょう。
こうしたなかで企業が自社の方向性を見失わないためには、人事部門が主導して立案するMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)などの価値観や企業文化が重要になります。
たとえば、食品・医薬品製造のキリングループでは「キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します」というミッションを定めています。
<参考>:経営理念(キリングループ)
こうした明確なミッションが示されていれば、「自分たちはどこを目指すべきか?」がわかるため、外的環境の変化に振り回されにくくなるはずです。
また、MVVなどの価値観や企業文化は、人材採用でも役立つものです。その内容に共感してくれる人材を獲得すれば、“あり方”の部分でのミスマッチが生じにくくなるからです。
企業のみんなが同じベクトルで働くための文化・価値観を考え、それを浸透させる人事担当者の役割は、VUCA時代のなかで特に重要性が高まっていくと考えられます。
人事・労務担当者に必要なスキルと向いている人の特徴
人事・労務の担当者として会社組織の運営に携わるうえでは、以下のスキルを身につけることが理想となります。それぞれ見ていきましょう。
スキル(1)コミュニケーション能力
人事・労務の仕事では、経営層・現場の管理職・社内研修の受講者(一般社員)といった幅広い人との関わりを持ちます。また、採用活動では「会社の顔」として求職者とのやり取りを進めていくため、社内外のさまざまな立場の人と適切なコミュニケーションを図れる能力が必要です。
採用面接でのコミュニケーションでは「見極める力」や「魅力づけする力」が必要ですし、経営層や管理職との連携では、立案した人事戦略などを「理解・納得してもらう力」が求められるでしょう。
スキル(2)問題解決能力
問題解決能力とは、問題発生時に速やかに原因を見つけ出し、問題の本質を見極めたうえで適切な解決策を考え、実行していくスキルの総称です。
企業における人事労務の課題は、以下のような要因でいきなり発生・露呈することも多くあります。
|
|
会社組織を維持・運営し、中長期的な成長につなげるためには、上記のような課題の早期発見・早期解決をする必要があります。また、「連日の長時間労働」や「人事評価制度のミスマッチ」などは、現場の状況に関心を持ってこそ見つけられる課題です。
上記のような課題を1日でも早く見つけるためには、新しい施策を導入したあとのアンケート調査や管理職へのヒアリングなどを行い、現場を知ろうとする姿勢も求められるでしょう。
スキル(3)データ分析スキル
先述の「連日の長時間労働」などは、勤怠データのチェック・集計時に発見できる課題です。
人事労務の課題を見つけ出し、適切な対策を迅速に講じていくためには、従業員の労働時間・有給休暇の取得状況・残業時間・離職率……といった多くのデータに関心を持ち、「なぜ昨年から若手の3年内離職率が上がったのか?」などデータに対して問いを立てられることが重要になります。
スキル(4)人間観察力
人事労務を担当する場合、「人を見る力」も必要です。
採用面接では、応募者にさまざまな質問をしながら「自社に合う人材か?」を見極める必要があります。また、適材適所の配置をするなかでは、「あのチームに馴染めそうか?」とか「あのリーダーとうまくやっていけそうか?」といった“相性を見る力”も求められるでしょう。
このような人を見る力は、労務管理でも役立つものです。たとえば、特定の従業員に対して「先週から顔色が悪い」や「人事評価が著しく下がっている」などの異変に気付いた場合、そこから勤怠データを確認して、長時間労働が続いているようであれば声掛けをするなどのサポートもできるでしょう。
スキル(5)ヒューマンスキル
人事労務では、以下のように“人を動かす仕事”が多くなります。
|
|
こうした役割をこなしていくうえで重要になるのが、周囲と健全なコミュニケーションを図り、必要な信頼関係を構築するためのヒューマンスキル(人間力)です。
ヒューマンスキルは、どちらかといえば「人と良い関係を築き、動かすため」ための複合的な能力です。詳細は、人事担当者の仕事内容や階層で変わる部分もありますが、一般的には、以下のような能力をバランスよく身につけたうえで、「この人なら信頼できる」と感じてもらえる状態をつくる必要があるでしょう。
|
|

人事労務担当者のやりがいとキャリアパス
人事労務は、やりがいが得られやすい職種です。また、人事労務の仕事で培ったスキル・経験は、ほかのキャリアパスでも活かせる傾向があります。
人事労務からステップアップできる役職や職種を知ると、そこに向けた努力や成長機会も見出しやすくなるはずです。ここでは、人事労務のやりがいとキャリアパスを詳しく見ていきましょう。
人事労務の仕事で得られる“やりがい”
人事労務のやりがいは、大きく「組織運営に関するもの」と「各人材に関するもの」の2つあります。
組織運営では、自社が抱える人・組織の課題を発見し、その解決に向けてさまざまな施策や調整を行っていきます。
たとえば、いわゆる男性社会のような企業で、女性が子育てと仕事の両立で使える制度や文化が乏しく、妊娠・出産・子育てをきっかけに離職する女性社員が多い傾向があったと仮定します。
こうしたなかで、育児休業を取得しやすい環境づくりや、職場復帰後もリモートワークや時短勤務などを活用しながら無理なく働き続けられる仕組みを整備すると、「女性離職者の減少」という定量的な実績とあわせて、「産後も仕事を続けられるようになってよかった!」などの喜びの声が聞けることもあるでしょう。
また、こうした仕組みによって定着した人材が無理のない範囲で活躍してくれることも嬉しいものです。そのなかから例えば「女性初のリーダー職」が誕生するなども人事労務担当者としてやりがいが感じられる瞬間になるはずです。
優秀な女性人材の離職が減少すると、組織としても計画的な人材育成や配置が可能になります。結果的に、管理職の負担軽減や採用育成コストの減少といった副次的な効果も得られるでしょう。
また、人事担当者は、各人材の採用や受け入れ、オンボーディングにも関わることが多い職種になります。そのため、日々の仕事を通して「組織の成長」と「従業員の成長」の両方に関われる点も、大きな魅力といえるでしょう。
人事労務担当者のキャリアパス
豊富な経験とスキルを持つ人事労務の担当者には、さまざまなキャリアパスが存在します。代表的なものを見ていきましょう。
・人事労務部門のスペシャリストになる
スペシャリストとは、人事労務の仕事に携わるなかで、自分が最も興味を持ったり多くの実績をあげたりした得意分野を伸ばしていき、専門人材になるというものです。
たとえば、労務管理の担当として就業規則や労働条件通知書の作成、勤怠管理などに携わっていた場合、それらの業務に関係する法律を深く学び、社会保険労務士の資格を取得するのも一つの例でしょう。
資格取得後はそのまま人事労務担当者として働くことのほかに、会社から独立して自分の事務所を設立するなどのキャリアも考えられます。
また、人材採用の経験が豊富な場合は、採用スペシャリストやリクルーター、人材スカウトとして、人の見極めと魅力づけに特化した仕事に従事する道もあるでしょう。
・人事労務の管理職や責任者(人事課長・部長・CHRO(最高人事責任者))になる
人材採用、勤怠管理、給与計算、年末調整…といったひと通りの仕事に従事できる環境であれば、社内で多くの実績をあげて、自社の人事部門を管理する課長・部長や、経営層の一員として人事戦略を策定するCHRO(最高人事責任者)を目指すのもよいでしょう。
ただし、これらのポジションは、誰でもなれるわけではありません。人事課長・部長・CHROを目指すのであれば、成長後に自分が就任できる「空き枠があること」と、大事な人材戦略を任せてもらえるだけの「人望があること」が大きな鍵になってきます。
社内に空き枠がない場合は、人事労務管理の経験を積んでから、人事課長・部長・CHRO(最高人事責任者)の社外求人に応募して転職する道もあるでしょう。
・人事労務専門のコンサルタントになる
人事に関する総合的な知識を身につけたあとは、人事専門のコンサルタントになる道もあります。具体的には、コンサルティング会社への転職もしくはフリーランスのコンサルタントとして独立する形になるでしょう。
人事コンサルタントの場合、クライアントの経営目標に応じた人材戦略の立案や、現状分析からの課題解決策の提案・実施などの役割が多くなります。こうした仕事のなかで、クライアントにとっての最適解を導き出すためには、会社組織全体を俯瞰して見る力も磨いておく必要があるでしょう。
人事労務の仕事で直面しやすい課題
人事労務の仕事にはやりがいが大きい反面、さまざまな課題に直面しやすい特徴があります。人事労務担当者として日々の仕事をこなしながら、自社の課題解決や人材戦略どおりの計画実行をしていくためには、自分たちが直面しやすい課題について知ることも重要です。
ここでは、人事労務で発生しやすい課題を紹介しましょう。
課題(1)作業計画が狂いやすい
人事労務は、人や組織の影響を受けて仕事の計画が狂いやすい職種です。
たとえば、新卒の採用活動を進めるなかで「3人の内定辞退が出た」となれば、さらに新卒採用を続ける必要がありますし、そういったなかで社内に離職者や休職者などが出た場合、想定外の事務手続きも同時期に行う必要が出てくるでしょう。
このように、人および組織の都合による「想定外」が多発するなかで仕事を進めていくには、毎月の給与計算や年1回の年末調整などから業務の効率化を進めることが重要です。
課題(2)小さなミスが大問題に発展することがある
人事労務の仕事は、さまざまな法律と関係しています。そのなかで担当者が「ミス」を起こし、適切な対処が行われないと、そこから以下のように「大問題」に発展する可能性もあるでしょう。
|
|
人事労務の担当者としてさまざまな仕事をするうえでは、各業務に関係する法律や専門知識はもちろんのこと、「それを守らないとどういうペナルティがあるか?」まで理解することが重要です。
また、小さな「うっかりミス」が会社にとって大問題に発展することもあります。業務効率化などを進めながら、ヒューマンエラーを防ぐ工夫もしていく必要があるでしょう。
課題(3)人を動かせないと成果があがらない
人材採用・教育、MVVの浸透、働き方改革……といった仕事は、経営層や担当者のビジョンどおりに人が動いてこそ、成功したといえるものです。ただし、これらの仕事には、やり方を間違えると「現場からの反発が起こる」とか「優秀な人材が離職する」のように逆効果になる側面もあります。
人事労務の担当者としてさまざまな施策を考え、良い組織づくりのために人を動かすためには、多くの従業員に協力してもらえるだけの関係構築やヒューマンスキルを磨いておく必要があるでしょう。
人事労務の業務を効率的に運用する方法
人事労務の課題を減らすためには、業務を効率化して担当者の負担を減らすことが重要です。ここでは、人事労務管理の仕事を効率化するためのポイントと、多くのメリットが期待できる「クラウド型労務管理」の導入について解説しましょう。
人事労務における業務効率化の流れと方法
人事労務の業務を効率化するための主な流れは、以下のとおりです。
|
|
効果が高い業務効率化の方法は、「人事労務にどんな仕事があって、そのなかにどういう課題があるか?」を知ったうえで見えてくるものです。そのため、最初にすべきことは「全業務の洗い出し」であり、そこから自分たちが「困っていること」や「やめたいこと」などを探ることで、適切な効率化の手段が明確になってきます。
なお、業務効率化に使える施策としては、以下のような多くの種類があります。
|
|
業務効率化の方法は、自社の課題はもちろんのこと「どれだけのコストをかけられるか?」でも変わります。業務効率化をするうえであまりコストをかけられない場合、これまで各支社で行われていた仕事を本社だけで行う「集約」や、無駄な作業をやめてしまう「廃止」が選択肢に入ってくるでしょう。
クラウド型の人事労務管理システムの導入
人事労務の業務効率化をするうえでそれなりのコストを使える場合は、クラウド型の人事労務管理システムを導入するのもおすすめです。具体的な機能は契約内容・各システムによって異なるものですが、一般的なクラウド型システムを導入すると、従業員データの一元管理や可視化が可能となります。
たとえば、従業員の育成計画や配置計画を立てる際にも、人事評価や本人のスキル・経験などのデータから「適切な研修」や「適切なポジション」などが見えてくるでしょう。また、教育・配置・評価・勤怠・給与などの情報が1つのシステム内で連携されると、個別管理で起こりがちな「入力ミス」や「転記ミス」などもなくなるはずです。
クラウド型の人事労務管理システムは、人事担当者の大事な役割である組織運営の精度を高めるうえでも非常に役立つツールといえるでしょう。
人事労務のアウトソーシングならラクラスへ
本記事では、人事と労務の用語の意味や主な業務内容などから、違いを明確にしながら解説してきました。また、人事労務の担当者としてスキルアップを検討する人のために、必要なスキルやキャリアパスに関してもご紹介しました。
もし人事労務についてアウトソーシングをお考えであれば、ラクラスにお任せください。ラクラスなら、クラウドとアウトソーシングを掛け合わせた『BpaaS』により、人事のノンコア業務をアウトソースすることができコア業務に集中できるようになります。
ラクラスの特徴として、お客様のニーズに合わせたカスタマイズ対応を得意としています。他社では難色を示してしまうようなカスタマイズであっても、柔軟に対応することができます。それにより、大幅な業務効率の改善を見込むことができます。
また、セキュアな環境で運用されるのはもちろんのこと、常に情報共有をして運用状況を可視化することも心掛けています。そのため、属人化は解消されやすく「人事の課題が解決した」という声も数多くいただいております。
特に大企業を中心として760社86万人以上の受託実績がありますが、もし御社でも人事の課題を抱えており解決方法をお探しでしたら、ぜひわたしたちラクラスへご相談ください。