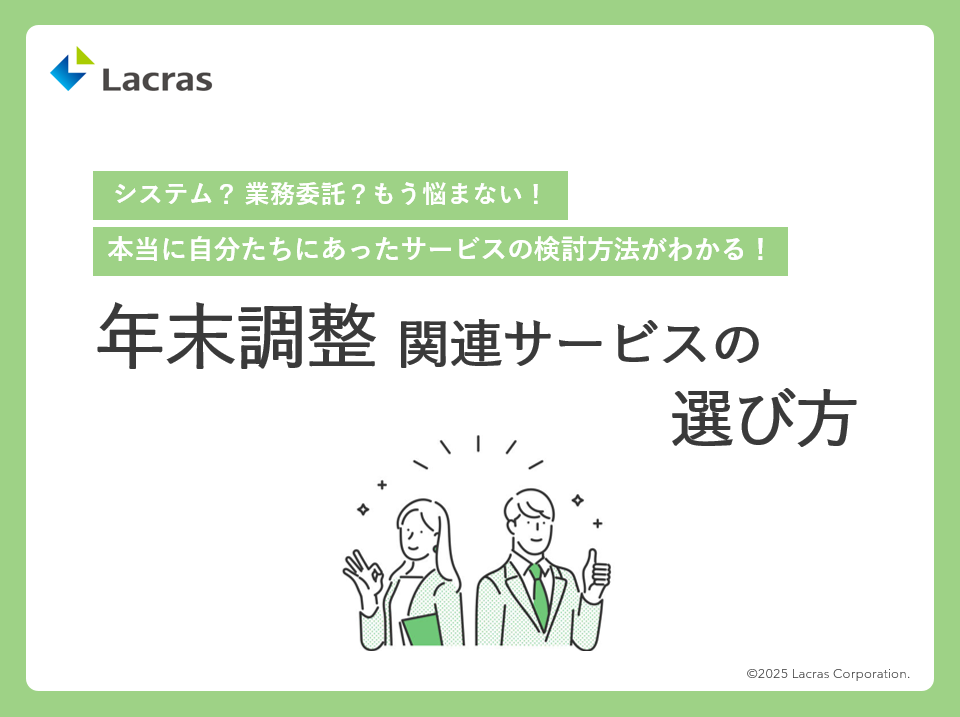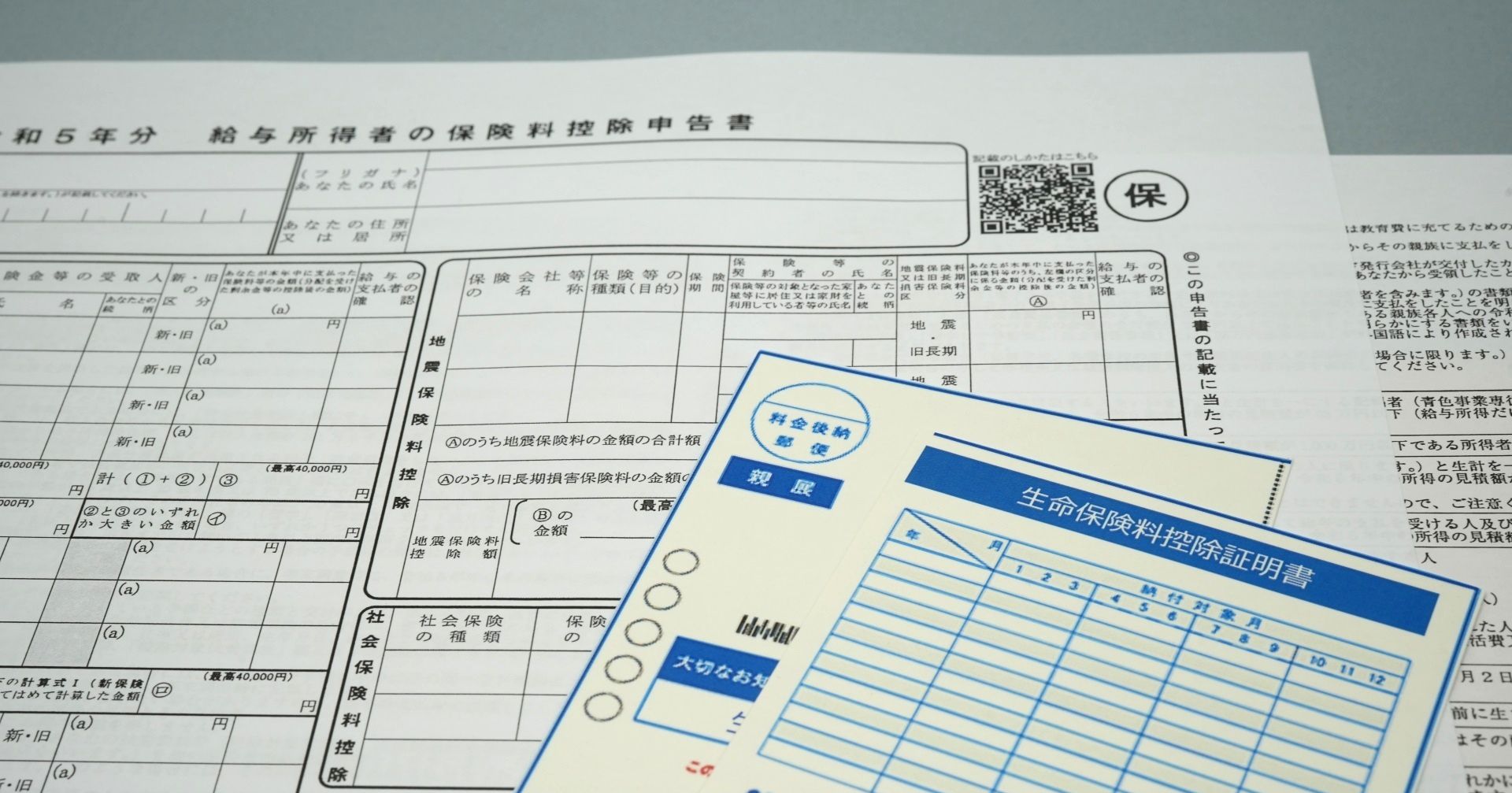年収の壁とは? 令和7年改正の見直しポイントと具体的な対策を徹底解説

本記事では、年収の壁の概要と種類などを確認したうえで、従業員に年収の壁を超えて働いてもらうためのアクションプランを解説します。年収の壁に関する知識を得たい方や、年収の壁の影響でシフト調整の問題などを抱えている人は、ぜひ本記事を参考にしてください。
監修者:社会保険労務士 伊藤大祐
「年収の壁」は、人事担当者が従業員の働き方やシフト管理の仕組みを考えるうえで、注意しなければならないトピックです。
近年の国会では、政府が「女性活躍」や「人手不足」への対策を推進するなかで、年収の壁の見直しに関する議論や制度改正への動きも活発化するようになりました。そして令和7年の税制改正では、「103万円の壁」や「106万円の壁」などにさまざまな見直しが入っています。
そこで本記事では、年収の壁の概要と種類などを確認したうえで、従業員に年収の壁を超えて働いてもらうためのアクションプランを解説します。年収の壁に関する知識を得たい方や、年収の壁の影響でシフト調整の問題などを抱えている人は、ぜひ本記事を参考にしてください。
年収の壁とは?その背景と影響
年収の壁に対して適切な対策を講じるためには、「年収の壁とは、そもそも何を指す概念なのか?」という定義や概要を理解することが大切です。また、近年の国会で見直しの議論が活発化し、法制度の改正に至った背景も理解する必要があるでしょう。
ここではまず、「年収の壁」の基礎知識として、この言葉が示す意味や近年の日本で見直しが求められた背景、重要性などを確認します。
「年収の壁」とは
年収の壁とは、パートタイマー・アルバイトなどの非正規労働者が「壁」となる年収額を超えて働いた場合に、社会保険料や税金の負担が増えて本人・配偶者・世帯の手取り額が減る現象および壁自体を指す概念です。
“手取り額”とは、給与の額面から税金や社会保険料などを差し引き、労働者が実際に受け取れる金額です。
非正規労働者のなかには、年収の壁の影響で手取り額が減ることを防ぐために、就労日数や時間数を調整する人が多い実態があります。つまり、年収の壁というものが従業員本人および企業にとって「それ以上は働けない壁」になっているわけです。
なお、詳細は後述しますが、年収の壁には以下のように3つのカテゴリがあります。
|
|
国会や企業で「年収の壁」が注目される背景
近年の国会や民間企業で「年収の壁」が注目される背景としては、少子高齢化が加速し労働人口が不足する日本社会で、さまざまな労働者がたくさん活躍できる環境をつくることが急務になっているからです。ここでいう“活躍できる環境”とは、日数・時間数の両面で「たくさん働ける環境」のことを指します。
一方で現在の日本には、先述のようにさまざまな年収の壁があることから、パートタイマーやアルバイト従業員の中に「壁を超えてたくさん働くこと」を控える人が多い傾向があります。
たとえば、自社のパートタイム女性従業員(Aさん)が旦那さんの扶養に入っており、旦那さんの会社で配偶者手当を受けるために「130万円の壁」を超えられない場合、会社側ではこの壁を意識したシフト調整を行う必要があります。
そこでたとえば、急な繁忙や予期せぬトラブルが生じて多くの従業員に残業や休日出勤をお願いせざるを得ない場合でも、Aさんについては130万円の壁のなかでしか働いてもらえない可能性が高いわけです。
近年の日本では、社会の少子高齢化が加速するなかで労働力人口が不足しています。特に中小企業では、自社に合った優秀な人材の獲得が難しい状況です。こうしたなかで企業が自社の経営目標を達成し、中長期的な成長を遂げていくためには、Aさんのような既存社員に「壁」を意識することなく、好きなだけ働いてもらえる制度や仕組みが必要なのです。
そういったなかで注目されているのが「“年収の壁”の見直し」であり、令和7年以降は、税金と社会保険関係の両方でこの「壁」にさまざまな変更や廃止などが行われていくことになります。
<参考>:「年収の壁」への対応(厚生労働省)
<参考>:いわゆる「年収の壁」対策(首相官邸)
7つの「年収の壁」の概要について
厚生労働省が公開している資料「年収の壁について知ろう|あなたにベストな働き方とは?」では、税金・社会保険・配偶者手当の3カテゴリで、全部で7つの年収の壁が示されています。
ただし最近は、令和7年の税制改正が行われたことで、7つの年収の壁の内容に、大きな変化が生じている状況です。
ここでは、従来から存在する7つの壁の概要を確認したうえで、令和7年税制改正によるそれぞれの壁へ影響や変更点を見ていきましょう。
(1)税金に関わる4つの壁
まず、税金に関わる従来の壁として以下の4つがあります。
|
|
それぞれ簡単に説明します。
・100万円の壁
住民税の支払いが発生する一般的な年収です。ただし、住民税が非課税になる基準は自治体ごとに違いがあります。詳細については、従業員本人の住所地の自治体に確認する必要があるでしょう。
<参考>:個人住民税(総務省)
・103万円の壁(令和7年以降は「160万円の壁」・「123万円の壁」に変更)
103万円は、以前から問題視されてきた非常に重要かつ複雑性の高い壁であり、令和7年の税制改正で大きな見直しが行われたところでもあります。
まず、従来の制度では以下の3つの事項に関わる壁でした。
|
|
それが令和7年の税制改正以降は、上記3つの壁の基準が以下のように変わっています。
|
【パートタイム・アルバイトで働く本人に所得税の納付義務が発生】
【配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わる】
【扶養控除の対象になる(配偶者・大学生年代の子以外)】
【19~22歳に該当する親族の収入が103万円を超えても世帯手取りが減らない】
<参考>:「年収の壁」への対応(厚生労働省) <参考>:いわゆる「年収の壁」対策(首相官邸)
|
<参考>:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
・150万円の壁
従来の150万円の壁とは、自身の年収に応じて配偶者特別控除額が段階的に減額されていくラインでした。これが令和7年以降は、配偶者特別控除への切り替えが160万円になったことで、配偶者特別控除額における150万円の壁も160万円に引き上げられます。
ただし令和7年税制改正では、大学生世代の子等の親族に関する「特定親族特別控除」が創設されています。この制度は、19歳~22歳までに該当する大学生などの収入が103万円を超えても、150万円までは世帯の手取りが減少しない仕組みです。
特定親族特別控除が創設されたことで、「150万円の壁」という概念は言葉の意味を変えて残る形になります。
<参考>:いわゆる「年収の壁」対策(首相官邸)
<参考>:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
<参考>:特定親族特別控除申告書及び所得金
・201万円の壁
201万円の壁とは、配偶者特別控除額を受けられなくなる壁です。配偶者控除および配偶者特別控除額の概要は、国税庁のそれぞれのページで確認してください。
<参考>:No.1191 配偶者控除(国税庁)
<参考>:No.1195 配偶者特別控除(国税庁)
(2)社会保険に関わる2つの壁
社会保険に関わる壁は以下の2つです。
それぞれの概要を見ていきましょう。
|
|
・106万円の壁
106万円の壁とは、従業員50人超の企業などで週20時間以上勤務している場合に、厚生年金保険と健康保険の加入対象となるものです。ただし国では、働き方に中立的な制度を構築するなどの理由から、令和7年6月から3年以内にこの壁を撤廃することを決定しています。
・130万円の壁
130万円の壁とは、年収が130万円を超えた場合に、社会保険における配偶者の被扶養要件から外れて、本人が自分で社会保険(国民健康保険・国民年金)に加入しなければならない壁です。
なお、130万円の壁は、諸手当や残業代を含む実収入で見ていく必要のある壁になります。厚生労働省の資料では、106万円と130万円、それぞれの壁の算定対象となる収入について、以下のように違いを示しています。

<引用>:「年収の壁について知ろう」あなたにベストな働き方とは?<PDF>(厚生労働省)
<参考>:「年収の壁」への対応(厚生労働省)
<参考>:「年収の壁」対策がスタート!パートやアルバイトはどうなる?(政府広報オンライン)
(3)配偶者手当の「壁」
最後の7つ目である配偶者手当の壁とは、企業が独自に創設する以下のような制度に影響するものです。
|
|
具体的な要件は企業ごとに異なりますが、多くの場合、従業員本人に扶養家族(配偶者や子ども)がいれば支給対象になる形です。ただし、被扶養者に一定以上の収入があると、支給対象から外れる可能性が高くなります。一般の企業では、従来の所得税や社会保険料の壁とあわせて、103万円もしくは130万円を一つの基準にすることが多いでしょう。
<参考>:「年収の壁について知ろう」あなたにベストな働き方とは?(厚生労働省)
【令和7年税制改正】
年収の壁の最新情報と見直しポイント
近年のビジネス環境では、先述のとおり令和7年税制改正などの影響から、日本社会に長く根付いていた「年収の壁」にも、さまざまな見直しが行われています。そのため、人事担当者が従業員の労務管理や社会保険手続きなどを適切に行うには、「年収の壁」に関する最新の状況を把握しておくことが重要です。
令和7年税制改正による年収の壁の新しい種類と要件については、以下の表で確認しておきましょう。黄色でマーキングしたものが、令和7年に見直されたものです。
| 壁の種類 | パートタイム労働者本人への影響 | パートタイム労働者の配偶者もしくは世帯における影響 | パートタイム労働者本人もしくは世帯の手取りへの影響 | |
| ①税金に関わる壁 |
100万円の壁 |
130万円の壁 | 手取りに影響なし | |
| 123万円の壁 | 扶養控除の対象になる(配偶者・大学生年代の子以外の人) | 手取りに影響なし | ||
| 150万円の壁 | 特定親族特別控除の対象上限 | 世帯の手取りに影響する | ||
| 160万円の壁 | 所得税が発生 | 配偶者特別控除の適用になる | 世帯の手取りは逆転しない | |
| 201万円の壁 | 配偶者特別控除の対象ではなくなる | 世帯の手取りは逆転しない | ||
| ②社会保険に関わる壁 | 106万円の壁 |
勤務先によって社会保険加入の対象になる |
手取りに影響あり | |
| 130万円の壁 |
社会保険の被扶養者要件から外れて、 |
手取りに影響あり | ||
| ③配偶者手当に関わる壁 |
主に103万円or 130万円の壁 |
パートタイムで働く本人の収入により、配偶者が配偶者手当などの支給対象外になる (※103万円の壁が160万円になったことで、対象範囲が変わる可能性あり) |
世帯の手取りに影響あり | |
<参考>:いわゆる「年収の壁」対策(首相官邸)
<参考>:「年収の壁について知ろう」あなたにベストな働き方とは?<PDF>(厚生労働省)
<参考>:「年収の壁」への対応(厚生労働省)
<参考>:「年収の壁」対策がスタート!パートやアルバイトはどうなる?(政府広報オンライン)
税制改正による「年収の壁」の変更がもたらす効果
「年収の壁」は、パートタイム労働者を中心とする従業員のシフト管理や社会保険手続き、各種手当を支給する給与計算業務と大きく関係する概念です。
令和7年税制改正で「年収の壁」の制度や各概念の中身が変わると、人事部門が行う人事労務管理のあり方・やり方の両方に対応が必要となります。
では、令和7年税制改正などによる「年収の壁」の変更は、さまざまな従業員を雇用する企業および従業員にどのような効果をもたらすのでしょうか。ここでは、一般的な効果を簡単に解説します。
(1)年収の壁が変わることによる
「従業員側の効果」
「年収の壁」の中身が変わることによる従業員側の大きな効果は、本人が所得税の課税や自分もしくは世帯の手取りを気にしていた場合に、壁が103万円だった頃よりもたくさん働きやすくなる点です。
基礎控除の見直しによって「103万円の壁」が「160万円の壁」に変わったことは、個人の収入に所得税がかかり始める年収水準が103万円から160万円まで引き上げられたことを意味します。
たとえば、所得税を非課税にするために、これまで103万円を超えないような働き方で調整していた従業員は、今後は従来よりも57万円多く働いても所得税をゼロにできるわけです。
また、特定親族特別控除が創設されたことで、大学生年代(19歳~22歳まで)の子の収入が150万円までは世帯の手取りが減少しない仕組みになりました。つまり、大学生などの子どもがアルバイトをする場合に、従来よりも多くのシフトに入りやすくなることを意味します。
これまで103万円を超えないようにしていた従業員が、150万円や160万円ぎりぎりまで働こうとした場合、それぞれの手取りが大きく増える可能性が高くなります。
(2)年収の壁が変わることによる「企業側の効果」
年収の壁が103万円から150万円や160万円になる企業側の効果としては、パートタイム・アルバイトの各従業員が働ける時間が拡大することで、シフト調整などのマネジメントがしやすくなる点が挙げられます。
たとえば、時給1,200円のパートタイムAさん・Bさんがこれまで103万円を超えない範囲で働いていた場合、103万円×2人÷1,200円⇒年間で約1,716時間、毎月で約143時間分の労働力(労働時間)があったことになります。(※時間外労働の割増賃金や各種手当は加味していません)
そこで、この2人が160万円まで働けるようになった場合、160万円×2人÷1,200円⇒年間で約2,666時間ですので、毎月で約222時間(2,666-1,716)まで労働時間が増えることになります。
壁が103万円だった頃と比べて最大で毎月79時間もの労働力(労働時間)が増えると、0.5人~1人の人材を新たに雇う必要がなくなるかもしれません。そうなると、優秀なパートタイムやアルバイト従業員だけで少数精鋭のマネジメントが実現するでしょう。
近年のビジネス環境では、少子高齢化による労働力人口の低下などの影響から、採用難や人材難に陥る企業が多くなっています。そうしたなかで、各人材が働ける時間が増え、少ない人数でもシフト作成ができる状況は、企業にとって大きな効果といえるでしょう。
税制改正による「年収の壁」の変更後に残る問題点
令和7年に実施されたのは「税」の部分の制度改正です。今回の改正により税部分に関する壁の問題が大きく緩和しても、社会保険に関する壁の問題は残り続けます。
また、厚生労働省では、最低賃金の引き上げにともない必要性が薄れていることなどを理由に、令和7年6月から3年以内に106万円の壁を撤廃する方向です。
厚生労働省では、社会保険加入における企業規模要件の撤廃も検討していることから、そこで106万円の壁が撤廃されると、従業員が週20時間以上働いた場合に必ず社会保険料の負担が生じる可能性が出てきます。
130万円の壁については、年収が130万円を超えると扶養から外れ、国民年金・国民健康保険に加入が必要になります。その保険料は、勤務先で加入する厚生年金・社会保険よりも高くなる傾向があります。
また、国民年金による老後の給付は基礎年金のみであるため、130万円の壁を超えて新たに加入をしても、将来の年金は勤務先で加入する厚生年金ほど増えません。こうしたなかで手取りと年金額の両方を減らさないために生じているのが、労働者のなかに「年収130万円を超えずに扶養のままで働くか?」「労働時間を増やして社会保険に加入してしまうか?」といった迷いをもたらす問題です。
そうなると、令和7年税制改正で税の壁が150万円や160万円に上がっても、社会保険の問題がそのまま残ることで、上限の160万円まで働くことを迷ってしまう非正規労働者がでてくることになるでしょう。
<参考>:いわゆる「年収の壁」対策(首相官邸)

年収の壁を超えるための
具体的なアクションプラン
ここまで紹介したとおり「年収の壁」は、令和7年税制改正によって「税の壁」が大きく緩和された一方で、「社会保険の壁」による問題は残ります。
こうしたなかで、各非正規労働者の労働時間を増やし、少ない人員で多くの労働時間を使える状態にするためには、年収の壁問題を解消・緩和するために国が用意した仕組みをうまく活用するのもよいでしょう。
ここでは、年収の壁を超えるために活用できる施策を紹介していきます。
施策(1)「106万円の壁」に対する
支援強化パッケージを活用する
厚生労働省では、106万円と130万円の壁について、年収の壁を超えるために活用できる支援策(支援強化パッケージ)を用意しています。106万円の壁で使えるパッケージは、「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」というものです。
このコースをわかりやすく説明すると、年収の壁および社会保険加入の問題をクリアする目的で以下いずれかの施策をとった場合に、国から助成金がもらえる仕組みになります。(※厚生労働省が示す要件の該当が必要です)
|
(1)【手当等支給メニュー】
(2)【労働時間延長メニュー】
(3)【併用メニュー】
<出典>:キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)(厚生労働省) <出典>:年収の壁・支援強化パッケージ
|
・「社会保険適用促進手当」とは
上記ででてきた社会保険適用促進手当とは、短時間労働者への社会保険適用を促進する目的で、労働者が社会保険に加入するにあたり、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給を行う手当の総称です。
給与・賞与とは別支給であり、社会保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないことが可能となります。なお、この措置は最大2年間有効です。
<参考>:年収の壁・支援強化パッケージ Q&A (キャリアアップ助成金関係)(厚生労働省)
・キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の支給金額
このキャリアアップ助成金で支給される金額は、「選択するメニュー」「要件」「何年目か」で大きく異なります。金額として最も大きいのは、「(2)労働時間延長メニュー」と、「(3)併用メニュー」の2年目の“6ヵ月で30万円”です。ただし大企業の場合、“6ヵ月で22.5万円”になります。
これに対して「(1)手当等支給メニュー」の3年目では“6ヵ月で10万円(大企業は7.5万円)”になります。
従業員の社会保険加入を促進するためにこの助成金を活用する場合は、社会保険適用促進手当のコストを支給金額で賄えるかを確認しておく必要があります。
また、社会保険適用促進手当が標準報酬月額の算定に考慮されない措置は最大2年、キャリアアップ助成金の助成期間は最大3年です。非正規労働者が安心してたくさん働き社会保険に入り続けられるようにするためには、これらの措置や助成期間が終わったあとの支援についても検討が必要でしょう。
厚生労働省のホームページでは、各メニューの助成額を以下のように公開しています。またこのページでは、具体的な活用モデルも公開中です。ぜひチェックしてください。
【(1)手当等支給メニュー】

<引用>:キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)(厚生労働省)
【(2)労働時間延長メニュー】

<引用>:キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)(厚生労働省)
【(3)併用メニュー】
 <引用>:キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)(厚生労働省)
<引用>:キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)(厚生労働省)
・キャリアアップ助成金を受給するための手続き
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)を活用する場合、まず厚生労働省が公開する以下のフローを使い、対象となる労働者がこの助成金の支給要件に該当するかを確認します。

<引用>:キャリアアップ助成金(社会保険適用処遇改善コース)(厚生労働省)
要件に該当することを確認できたら、取り組みを開始する日の前日までに、管轄の労働局まで「キャリアアップ計画書」を提出します。キャリアアップ計画書の様式は、以下のページからダウンロードできます。
<参考>:申請様式ダウンロード(キャリアアップ助成金)(令和6年4月1日以降の取組に係る様式)(厚生労働省)
書類に不備があると当日に受理されません。余裕を持って用意をしたほうがよいでしょう。
なお、キャリアアップ助成金の社会保険適用処遇改善コースにおける各メニューの詳細やFAQなどは、以下の資料に記載されています。あわせてチェックしてください。
<参考>:キャリアアップ助成金(社会保険適用処遇改善コース)(厚生労働省)
施策(2)「130万円の壁」に対する
支援強化パッケージを活用する
厚生労働省では、たとえば繁忙期に労働時間を延ばすなどの理由で収入が一時的に上がり、「130万円の壁」に達してしまうケースを想定しています。その結果、扶養から外れて国民年金や国民健康保険に加入せざるを得なくなる場合があります。
こうした状況を防ぐために、事業主が「一時的な収入増である」ことを証明すれば、引き続き扶養にとどまれる仕組みを用意しています。これは「事業主の証明による被扶養者認定」と呼ばれる制度です。この仕組みの対象は、「一時的な収入変動」に限られます。
手続きは、厚生労働省のページから「事業主証明様式(正式名称:被扶養者の収入確認に当たっての『一時的な収入変動』に係る事業主の証明書)」をダウンロードし、必要事項を記入します。
そのうえで、被扶養者認定や資格確認の際に収入を確認するための添付書類として、被保険者の事業所や健康保険組合などの保険者に提出します。
<参考>:被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書(厚生労働省)
記載内容の確認にあたり、この書類とは別に雇用契約書などの提示・提出を求められる場合があります。
なお、130万円の壁に関する事業主の証明による被扶養者認定については、以下の資料で詳しく解説されています。ぜひチェックしてください。
<参考>:パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆さまへ(厚生労働省)
施策(3)配偶者手当を見直す
パートタイム労働者の就業調整(働く時間の調整)は、配偶者手当を意識して行われることもあります。厚生労働省の調査によると、配偶者のいる女性パートタイム労働者のうち就業調整をしている人のなかで、「配偶者の会社の配偶者手当がもらえなくなるから」という理由をあげた人は、15.4%もいることがわかっています。
<参考>:「配偶者手当」の在り方について企業の実情も踏まえた検討をお願いします(厚生労働省)
配偶者手当は、配偶者を扶養する側に支給される手当です。そのため、たとえば夫婦が同じ事業所で働いているケースなどを除くと、多くの企業にとっては制度を改善しても直接的なメリットを感じにくいかもしれません。
しかし、配偶者を扶養する労働者にとっては、配偶者手当は納得感の高い賃金制度といえます。対象範囲が広がれば、その会社で長く働く動機にもつながるでしょう。
また、令和7年の税制改正では、これまで複数の役割を担っていた「103万円の壁」が見直され、123万円や160万円に変更されました。これは、従業員の配偶者が、自社とは別のパート先で103万円を超えて働くよう打診を受ける可能性があることを意味します。
こうした状況のなかで、配偶者を扶養する従業員が自社で家族手当や配偶者手当を受けられなくなる問題を防ぐにはどうすべきか。その一つの方法として、従業員のニーズや配偶者の働き方に耳を傾け、新しい年収の壁に合わせた仕組みに見直すことが考えられます。
なお、厚生労働省の資料では、配偶者手当を含む賃金制度の見直しに向けた適切な基準について、以下のような4ステップのフローチャートを示しています。

<引用>:配偶者手当を見直して若い人材の確保や能力開発に取り組みませんか?|いわゆる「年収の壁」対策<PDF>(厚生労働省)
年収の壁に関するよくある質問
「年収の壁」は、税金・社会保険・配偶者手当の仕組みにもとづく複雑な概念です。特に令和7年度は、古くから続いてきた103万円の壁に大きな変更が入るなかで、人事担当者に混乱が生じる場面も多くなっているかもしれません。
ここでは、年収の壁について人事担当者からよくある質問とその回答を紹介します。
Q.就業調整(働く時間の調整)で
最も割合が大きい理由はなんですか?
配偶者がいる女性パートタイム労働者の就業調整理由で最も大きいのは、社会保険に関する「130万円の壁」です。厚生労働省の資料によると、調査対象者の57.3%がこの理由を挙げていることがわかっています。
次いで多いのは、自分自身が所得税を払わなければならない理由です。
厚生労働省の調査結果では非課税限度額が103万円となっていますが、今後はこの壁が160万円となり、引き続き強く意識されていく可能性が高いでしょう。
厚生労働省の資料をもとに理由と割合を簡単にまとめると、以下のようになります。
| 就業調整の理由 | 割合 (複数回答あり) |
| 130万円の壁 (扶養から外れて、国民健康保険・国民年金への加入) |
57.3% |
| 所得税の非課税限度額 (従来は103万円、令和7年以降は160万円) |
49.6% |
| 配偶者控除がなくなり、配偶者特別控除の額が減る | 36.4% |
| 配偶者手当がもらえなくなる | 15.4% |
<参考>:「配偶者手当」の在り方について企業の実情も踏まえた検討をお願いします<PDF>(厚生労働省)
Q.「年収の壁」はこの先どうなりそうでしょうか?今後の展望がわかれば教えてください。
従来の日本では、103万円を中心とするさまざまな壁や、企業が独自に整備した配偶者控除・家族控除などの仕組みの影響から、被扶養者である非正規労働者の女性が就業を調整せざるを得ない実態がありました。
一方で近年の日本は、少子高齢社会へと進むなかで労働力人口が減少し、政府と民間の両方が「多くの女性や非正規労働者にたくさん活躍してほしい」と望む状態です。
そういったなかで、非正規労働者が就業調整を行わずにたくさん働けるようにするためには、令和7年税制改正で行われたように壁の上限を上げるのはもちろんのこと、これから3年以内に行われる「106万円」のように、壁自体を撤廃することも必要になってきます。
企業側ではこうした政府の動向を鑑み、さまざまな壁が大きく変わる未来を予想しながら、女性および非正規労働者が働きやすい環境を整備する必要があるでしょう。
<参考>:女性の就労の制約と指摘される制度等について( いわゆる「年収の壁」等 )<PDF>(厚生労働省)
年末調整のアウトソーシングならラクラスへ
本記事では、年収の壁の概要と種類などを確認したうえで、従業員に年収の壁を超えて働いてもらうためのアクションプランを解説してきました。年収の壁は種類が多いため、年末調整業務などで負担を感じている方は多いのではないでしょうか。
もし年末調整を進めていくうえで「手続きの負担を軽減したい」とお考えでしたら、ぜひラクラスにご相談ください。
ラクラスの年末調整BPOサービスなら、必要な機能と業務をフルパッケージ化しています。また、カスタマーサポートも実施していますし、カスタマイズ対応も可能です。
AI-OCRとオペレーターの目視を組み合わせた読取代行により、品質と効率の両立を実現しており従業員は証明情報の入力が不要になります。また、人事担当者の回収とチェックも必要ありません。
クラウドシステムはすべて国内で運用されており情報セキュリティも万全ですし、大企業向けに開発された様々な設定やオプションもご用意しています。導入を検討いただくうえで何かご不明点などありましたら、お気軽にご相談ください。
この記事の監修者:監修者:社会保険労務士 伊藤大祐
社労士試験合格後、社労士事務所勤務を経て、ソフトバンクグループのシェアードサービス企業で給与計算業務に携わるとともに人事システムの保守・運用を担う。
その後、人事業務のアウトソーシングサービスを提供する企業の立上げに参画。
主に業務構築、システム運用に従事。
その他、人事領域以外のアウトソーシング企業等での勤務も経験し2019年に独立。
現在、人事・給与計算システムの導入支援を中心に社労士として顧問企業の労務面のサポートも行う。