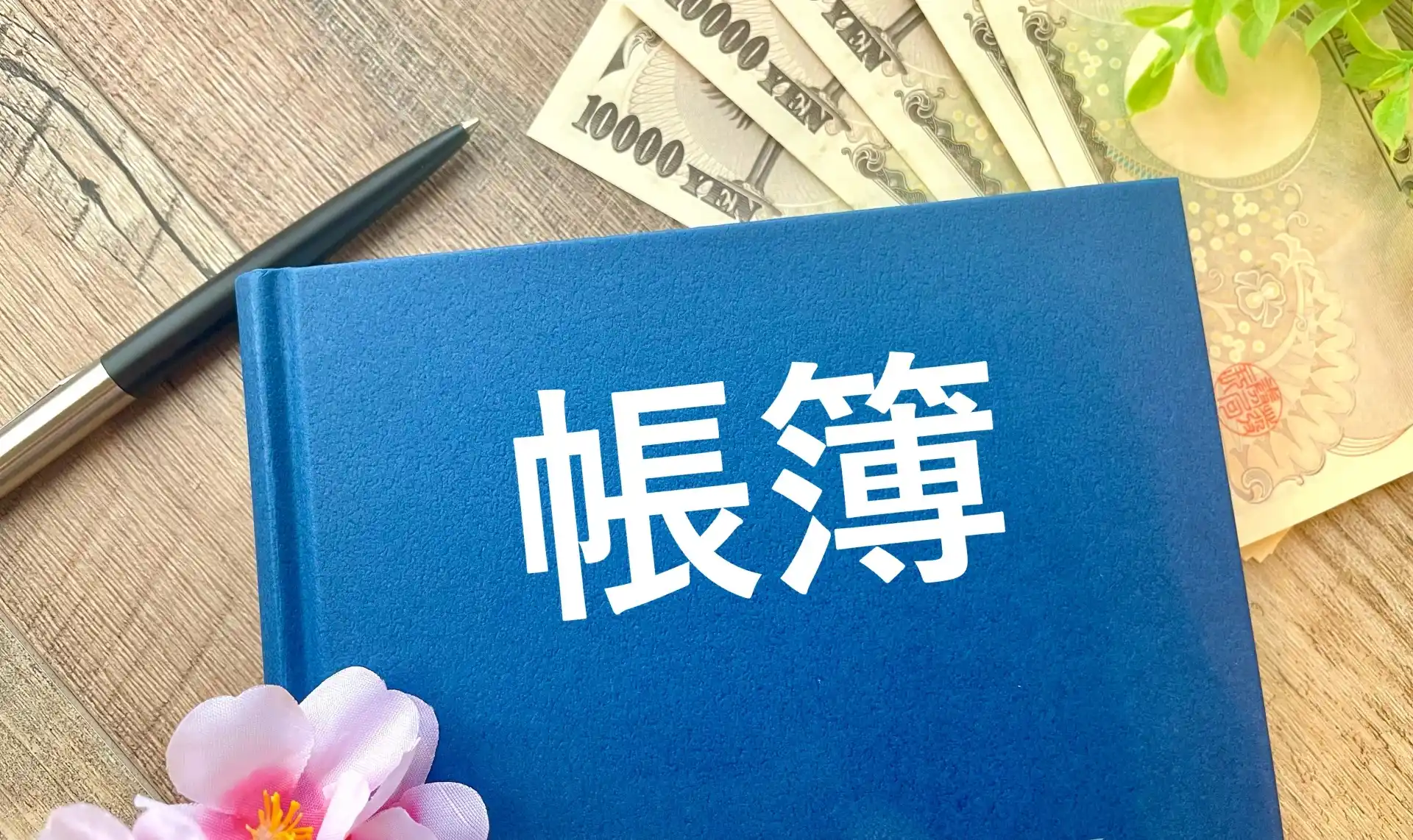発令とは? 人事異動の内示・辞令との違いや用語の使い方、適切な手続きの流れを詳しく解説


関連資料
給与計算の業務スケジュールとポイント【チェックリストつき】
「年間の業務スケジュール」をシンプルに整理し、ミスを防ぐためのチェックリストをご用意しました。安心して日々の業務に取り組めるようご活用ください。

関連記事
人事の役割とは?人事部の業務一覧や仕事内容、求められるスキルなどを徹底解説
人事の役割とは何なのでしょうか。人事部の業務一覧を表示しながら、人材採用や人事評価、人材育成や労務管理など、人事部の仕事内容について解説します。
本記事では、人事でよく使われる発令と、類似する他の概念(内示・辞令・任命)の違いを整理します。また、人事発令の効果を高め人事トラブルを防ぐためのポイントや、適切な手続きの流れを解説していきます。人事発令を出すためのマニュアルとして、ぜひ本記事を参考にしてください。
人事異動にともなう発令は、人事部門の大きな役割の一つです。
人事の発令には、人事異動の内容を全社員に伝えることに加えて、自社の組織活性化や人材育成などにつなげる目的もあります。効果の高い発令をするためには、この概念の意味を理解したうえで、適切な流れで手続きなどを進めることが重要です。
そこで本記事では、人事でよく使われる発令と、類似する他の概念(内示・辞令・任命)の違いを整理します。そのうえで、人事発令の効果を高め人事トラブルを防ぐためのポイントや、適切な手続きの流れを解説していきます。
人事発令を出すためのマニュアルとして、ぜひ本記事を参考にしてください。
発令とは
発令の“令”は、「言いつける」や「命じる」を指す言葉です。このことから発令は、辞令や法令などの公的な言いつけ(指示)を出す、公表することをあらわす概念になります。
発令の具体的な意味は、同じく人事業務などで取り扱うほかの概念と比較することでよりイメージしやすくなります。ここでは、発表・内示・辞令・任命との違いを見ていきましょう。
発令と発表の違い
発表は、何らかの通知や案内などを、「世間一般に広く知らせること」を意味する概念です。一方で発令は、辞令・法令などの「指示を出す」ものになります。
発令と内示の違い
内示は、公にせず内々に伝えることです。
たとえば、人事異動の件について、本人や関係部署の上長だけといった内々に伝えることが内示になります。一方で発令は、人事異動を命ずることを書面での掲示や朝礼など公の場で出すものです。
発令と辞令の違い
人事異動を例にあげると、発令と辞令には以下の違いがあります。
|
【辞令】人事異動の内容を当事者に決定事項として通知するための「文書」 【発令】人事異動の指示を出す「行為そのもの」
|
なお、人事部門が作成する辞令には、以下のようにさまざまな種類があります。
|
|
発令と任命の違い
任命とは、特定の役職や官職に就くことを命じるものです。国会や報道などで、「官僚の任命責任」といった表現が使われるのを見たことがあると思います。
これに対して発令は、「部長に任命する」や「事務次官に任命する」などの指示を公に伝える行為になります。
発令という言葉の使い方と具体例
発令は、私たちの身近なところでもよく使用される言葉です。ここでは、国や行政などの使用例を見ていきましょう。
国や行政などによる「発令」の事例
各省庁や地方自治体などでは、「発令」を以下のようなシーンで使用しています。
|
【厚生労働省】令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県の一覧について 【総務省】情報通信審議委員の発令 【千葉県】インフルエンザ警報の発令について 【関市立桜ヶ丘中学校】気象警報(暴風・大雨・洪水・特別等)発令時の対応
|
上記のリンクから各ページを開くと、総務省と千葉県のサイトには「発令」を使用した以下の文章が記載されています。
|
【総務省】情報通信審議会委員の任命について、本日付けで発令しました
【千葉県】本県では、2024年第49週(12月2日~12月8日)に県内におけるインフルエンザの定点当たり患者報告数が13.23人となったため、インフルエンザ注意報を発令したところです。
|
総務省の「本日付けで発令しました」という文章は、一般企業の辞令・任命でも活用できるはずです。
人事発令の概要とその目的
人事発令とは、企業が従業員に人事異動などの指示を公に発表することです。人事発令は多くの場合、いくつかの目的があり実施されます。ここでは、その目的別にポイントを見ていきましょう。
目的(1)人材の育成
日本に多い「メンバーシップ型」の組織では、従業員にさまざまな部署や職種で経験を積んでもらうなかで適性を見極める“ジョブローテーション”という仕組みが一般的です。
このジョブローテーションでは、たとえば最初にカスタマーサポート部に配属された人が3年後に営業部に入り、さらに3年後に経営企画部へ……といった異動が行われることもあるでしょう。
そのため、メンバーシップ型の組織で働く従業員は、人事発令によって新しい部署や役職で新たな経験を積む機会を得ることになります。頻繁にジョブローテーションが行われる組織であれば、人事発令の頻度も高くなることが多いでしょう。
目的(2)組織の活性化
公平性・透明性の高い人事発令には、従業員に以下のようなポジティブな印象を与える効果があります。
|
<人事発令による反応例> ・来月から営業部の課長になる。ここまで頑張ってきて良かった…… ・同期のAさんがシステム開発部のリーダーになった。自分も頑張らないと…… ・自分がOJT教育をした若手のBさんが営業部に入ってきた。成長した彼と一緒に働けて嬉しい…… など
|
本人および周囲が納得する人事発令を出せば、組織に良い意味での競争心や向上心が生まれやすくなります。また、自他の人事発令に対する「もっと頑張ろう」などの想いは、モチベーションやパフォーマンスの向上につながるものでしょう。
なお、人事発令を組織の活性化につなげるためには、各メンバーが自分の意見や想いなどを自由に表現できる“心理的安全性”が高い組織を構築しておく必要があります。
目的(3)新プロジェクトへの関心度が上がる
人事発令は、特定のプロジェクトやチームに従業員の関心を向けるうえでも役立つものです。
たとえば、「社内DXの推進による組織変革」や「全社をあげて取り組む、社長の肝いりプロジェクト」などを実行する場合、人事発令のなかで参画メンバーの氏名とあわせてプロジェクト名を公表します。そうすると、以下のような気付きからプロジェクトへの関心が高まりやすくなるでしょう。
|
<人事発令による反応例> ・社内DXチームには開発部のAさんとBさんが入っている。かなり力を入れているプロジェクトなのかな…… ・社長の肝いりプロジェクトには、うちの部門から3人も入ったのか。あの3人には多くの経験を積んできてほしいな…… など
|
以上のように、従業員の理解や協力が不可欠なプロジェクトを進める際にも、人事発令を活用するとよいでしょう。
人事発令の種類
人事発令は、組織のなかで人が動くさまざまなシーンで出せるものです。ここでは、改めて一般企業で出されている人事発令を10種類挙げて解説していきましょう。
(1)昇進・昇格
昇進は、仕事の成果や能力が認められて、より高い役職に上がることです。たとえば、高い営業成績を出した人が高評価を受けて、一般社員から係長に上がるといったイメージでしょう。
これに対して昇格は、自社の職能資格制度内で評価が上がるものです。たとえば、これまで最も低い6等級だった新人が、高い成果を出したことで5等級に上がるイメージになります。
(2)降格・降職
先ほどの昇進・昇格と対を成す言葉です。
降格は、たとえば「課長から係長」や「管理職から一般職」のように、下の役職に落とされるものです。降職は、先ほど紹介した職能資格制度などのなかで、「5等級から6等級に落ちる」といったイメージになります。
なお、降格による減給では限度額が決められています。具体的には、月給の1割かつ1日の平均賃金の半額です。これに対して、降職の場合は限度額が適用されません。人事発令にともない報酬額などが変わる際には、注意しましょう。
(3)任命・解任
任命は、対象従業員に対して「システム部マネージャー」のような役目や官職に就くように命じることです。
解任は、いまの任務を解いて職務をやめさせるものです。高い成果を出してもらうために任命し、期待する業績などがあげられないときなどに解任することが多いでしょう。
(4)転勤・転任
転勤は、従業員の勤務場所を継続的に変えることです。たとえば、「勤務地が新宿支店から横浜本社になる」などが転勤にあたるでしょう。
転任は、同一の組織内でほかの勤務地や職務に変更することになります。たとえば、「第一営業部のなかで、勤務地が新宿から横浜に変わる」といったイメージです。
(5)定年退職・退職勧告・退職勧奨
定年退職は、就業規則で決められた年齢を超えたときに雇用契約が解除されるものです。定年になる年齢や定年日は、60歳以上であれば各社が任意に設定できるものになります。一般的には、以下の定年日を設定する会社が多いでしょう。
|
|
退職勧告は、雇用解除の申し入れを事業主側が行い、従業員に自発的な退職を促すものです。退職勧告と似た概念に退職勧奨があります。退職勧告と退職勧奨には、以下の違いがあります。
|
【退職勧告】事業主側から雇用解除の申し入れを行い、従業員の自発的な退職を促すもの 【退職勧奨】事業主側から従業員に「辞めてくれないか?」などの言葉で、退職を勧めること
|
(6)解雇
解雇は、事業主側からの申し出により一方的な雇用契約の解除が行われることです。解雇には、以下のように3つの種類があります。
|
【普通解雇】整理解雇・懲戒解雇以外のもの 【整理解雇】企業の経営悪化による人員整理を目的とした解雇 【懲戒解雇】従業員が極めて悪質な非行や規律違反を行ったときに、懲戒処分として実施する解雇
|
解雇は、先述の退職勧告・勧奨よりも強力な効力を持つ特徴から、実行するためにはさまざまな要件を満たす必要があります。解雇の詳細については、厚生労働省の資料でも確認することができます。
<参考>:しっかりマスター労働基準法 解雇編<PDF>(厚生労働省)
<参考>:第5章 仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき<PDF>(厚生労働省)
(7)免職
免職は、公務員が何らかの罪を犯した際に懲戒処分として解雇するものです。公務員の懲戒処分には以下の5つがあり、免職はそのなかで最も重い種類になります。一般企業でいえば、懲戒解雇にあたるでしょう。
|
|
(8)配置転換
配置転換とは、同じ会社のなかで勤務地や仕事内容が変わることです。先述の転勤・転任も、配置転換の一種になります。
配置転換は、適材適所や組織活性化の実現や、能力差による不平等を解消する等の目的で行われることが多いです。しかし、なかには従業員を退職に追い込むことを目的とする悪質な配置転換も存在します。
(9)出向・転籍
出向とは、一時的かつ一定期間、自社に籍を置いたまま他社に在籍するものです。これに対して転籍は、自社を退職したうえで、関連会社や他企業で雇用されることです。
(10)新規採用
企業によっては、従業員を雇い入れた際に人事発令を出すことがあります。新規採用には、新卒と中途の2種類があります。
説明するまでもありませんが、新卒は学校を卒業したばかりの人を採用するものです。新卒では多くの場合、就労経験がありません。
中途は、過去に社会人経験がある人を採用することです。中途の募集や面接などの採用活動は、企業側で新たな人材がほしいときに行われることが多いでしょう。
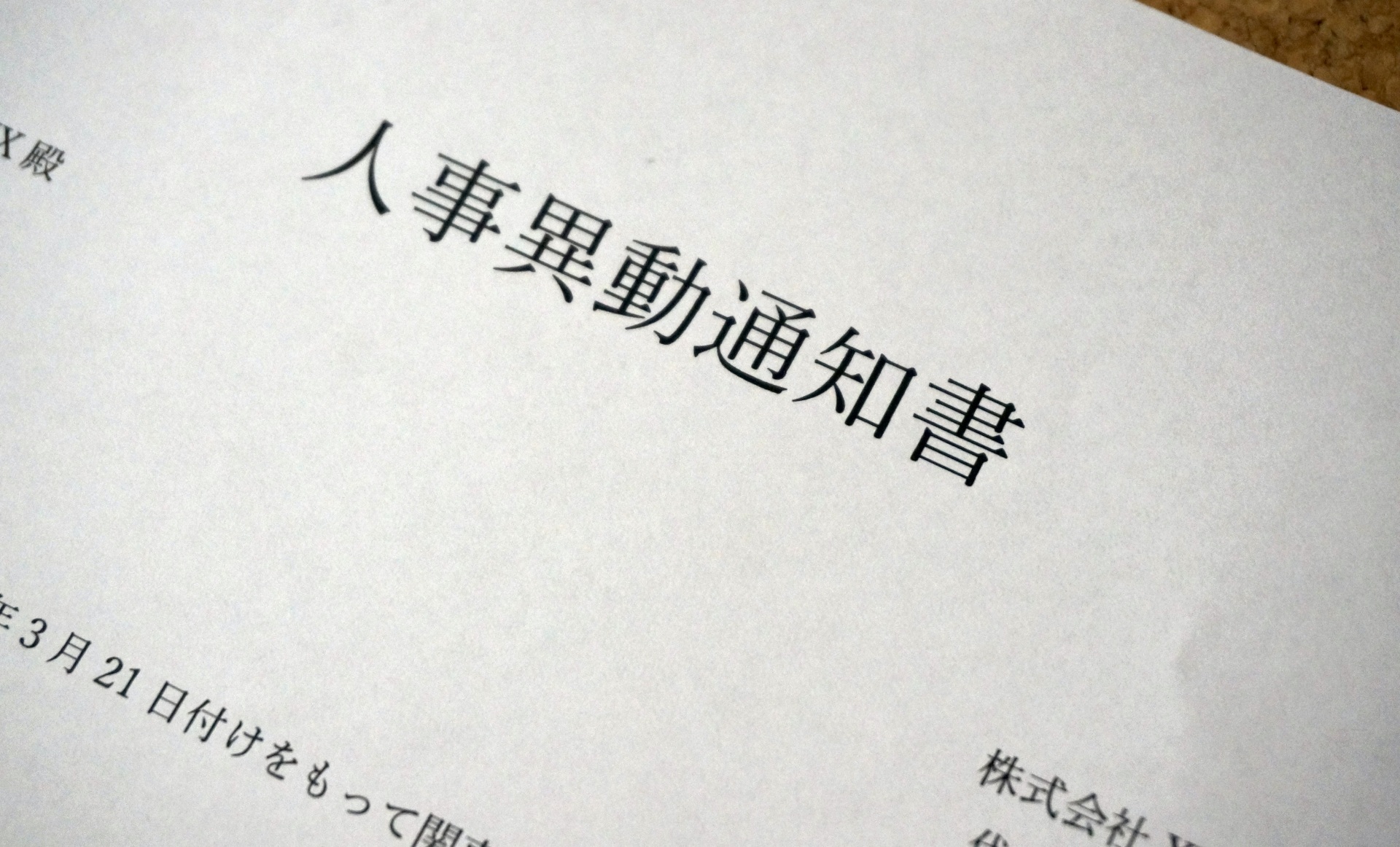
人事発令の時期
人事発令の時期は、厳密には企業や業種によって異なります。一般企業で多いのは、以下のように企業の決算期や閑散期にあたる時期です。
|
【一般企業の決算期】2~3月、9~10月 【アパレル業界】季節商品のセールが一段落した時期 【鉄道業界】7月(新年度の混雑期が落ち着いた時期) など
|
メンバーシップ型の組織でジョブローテーションを導入している場合は、従業員に幅広い経験をさせる方針から、1~3年周期で配置転換をするケースもあります。
また、3年周期の人事発令は公務員にも多いです。公務員では多くの場合、異動の7~14日前に内示を出し、4月1日付けの異動が一般的になります。
人事発令までの基本的な流れ
人事異動に伴う発令までの手続きは、多くの場合、以下の流れで進められていきます。ここでは、各ステップについて簡単に解説していきましょう。
ステップ(1)人事異動が必要な部署と人材要件を洗い出す
最初に、経営戦略や現場からあがってきた人材不足などの相談にもとづき、人事異動が必要な部署と求められる人材の適性や資格といった要件を洗い出します。適材適所の人材配置をするうえでは、以下のように細かな人材要件を考える必要があります。
|
<要件の例>
|
ステップ(2)要件に合う候補者を選定する
スキル・経験・人物像などの面から、人材要件に合う従業員を探していきます。ここで重要なことは、本人が思い描くキャリアビジョンや大切にしている価値観などにも目を向けることです。
企業側の視点で考えれば、人事異動を通じた経営戦略の実行や組織の活性化は、自社の成長に不可欠なものです。ただし、そこで本人が希望するキャリアとは全く異なる部署や職種への異動を無理強いした場合、モチベーションやパフォーマンスの低下から離職につながってしまうこともあるでしょう。
本末転倒ともいえるこうした問題を防ぐためには、たとえば、スキル・経験面で要件にマッチする人材だとしても、本人のなかに「自分は東京で活躍したい」や「転勤や単身赴任は難しい」といった強い想いがあれば、その気持ちを尊重するのが理想です。
ステップ(3)内示を出し本人の意向を確認する
ヒアリングを通じて、大きな問題がなく好感触の人材が見つかったら、正式な辞令を発令する前の内示を出します。内示のあとは、本人の意向を確認しましょう。
ここで重要となるのは、本人に納得してもらうことです。納得のうえで了承してもらうためには、以下のように具体的な話をしていく必要があります。
|
<具体例> 【対象になった理由】 次世代リーダーとして期待しているから。大阪で多くの経験を積んで欲しいから。 【異動後の業務内容】 大阪営業部の開設準備。営業メンバーの管理と育成。
|
また、人事異動によるデメリットがあれば、その内容を率直に伝えたうえで、サポートする姿勢を見せる必要もあるでしょう。
ステップ(4)辞令を発令する
本人から了承を得たら、正式な辞令を全社に発令します。発令内容は全社に通知しましょう。
人事発令における人事側の注意点
人事発令の多くは、従業員の仕事や生活に大きな変化をもたらすものです。
従業員に発令内容を受け入れてもらい、人材育成や組織の活性化などにつなげていくためには、いくつかのポイントに注意をしながら手続きなどを進める必要があります。また、人事部門の配慮は、トラブルを防ぐうえでも重要なことです。
ここでは具体的な注意点を4つ挙げて解説していきましょう。
人事側の注意点(1)必ず書面を交わす
後々のトラブルを防ぐためにも、内示や発令の内容は書面など「文章として残る形」で伝えることが大切です。
仮に、候補者選定のヒアリング段階で「実は大阪営業部でリーダー候補を……」といった話が始まり、本人からポジティブな返答をもらえたとしても、後々「言った」「言わない」のトラブルになりかねません。
そういったトラブルを防ぐためには、その内容を書面に起こして共有したうえで合意してもらうことが重要になります。
人事側の注意点(2)合理性の高い理由を考える
人事異動の内示や発令で大切なのは、従業員本人の納得感をもって異動してもらうことです。そのためには、合理性の高い理由が必要となります。
一方で、合理的な理由の共有がないなかで従業員側に「なんとなく選んだ」などのネガティブな印象を与えてしまうと、仮に内示や発令内容を受け入れてもらえたとしても、会社への違和感や不信感から以下のような問題が起こりやすくなるでしょう。
|
<起こりうる問題例>
|
人事側の注意点(3)現場のことも考えた発令を行う
人事発令に組織の活性化や人材育成といった効果があったとしても、それを実行することで現場の業務に支障が出てしまっては本末転倒です。
たとえば、新事業Aのために2人の優秀な人材をB部門から異動させる場合、この2人が抜けることで想定されるB部門の業務・業績面での支障まで考えた対応も人事部門の役割になるでしょう。
また、仮に自社の大きな課題を解決する目的から、「どうしても2人を異動させなければならない」といった場合は、その理由や対応策をB部門の上長に伝える姿勢も大切です。
そういう意味で人事発令に対する理解や納得感は、異動対象となる本人のみならず、これまで所属していた部門の上長やメンバーなどに対しても必要なものとなるでしょう。
また、これまで重要な役割を担っていた人材が異動する場合、十分な引き継ぎ期間を設けることも大事なポイントとなります。
人事側の注意点(4)候補者の不安や課題に寄り添う
例えば、内示をもらった候補者に以下のような不安があり、その想いを解決できないまま配置転換に応じてしまうと、本人のやる気が損なわれて生産性の低下や離職などにもつながりやすくなります。
|
<不安の例>
|
こういった本心を引き出すためのポイントになるのが、質問の仕方です。たとえば、候補者選定のヒアリング段階で以下のような質問を行うと、従業員は自分が思い描くキャリアビジョンを語りやすくなるでしょう。
|
<質問の例> Aさんは、システム開発部に入って5年目になりますけど、将来的にはどちらの方向でキャリアアップしていきたいですか? システム開発だと、マネージャーやスペシャリストなどの選択肢があるかな。それだけでなく、Bさんのようにネットワーク系に進んだ先輩もいますよね。
|
上記のように本人が自由に回答できる質問を『オープンクエスチョン』と呼びます。一方で、「大阪に転勤してくれるかな?」とか「営業部のリーダーにならない?」といったYes・Noのいずれかでしか返答できない質問は『クローズドクエスチョン』です。
従業員の不安や違和感を解消し、納得感を持って異動をしてもらうためには、日頃からオープンクエスチョンを活用して、本人の意向やキャリアビジョンを汲み取る姿勢が必要となります。
人事発令における従業員側の注意点
人事異動の内示や発令では、従業員側にも注意すべきことがあります。詳細を見ていきましょう。
従業員側の注意点(1)内示情報は周囲に明かさない
内示は、非公式の通達です。そのなかには、全社員には明かしていない新プロジェクトのような機密情報が含まれることもあります。ですから、原則として意思決定に関係する家族や上司以外への口外はNGになるので注意が必要です。
従業員側の注意点(2)「立つ鳥跡を濁さず」を目指す
内示には、正式な人事発令までに引き継ぎや引越しなどの準備を進めてもらうために、内々で早く通知をする目的もあります。配置転換の内示が出たら、以下の3つの準備に入りましょう。
|
(1)自分の担当業務の引き継ぎ準備 (2)オフィスや自宅の引越し準備 (3)同僚・取引先・お客様への挨拶準備
|
たとえば、(1)の引き継ぎでは、人事発令が出るまでの間に資料やマニュアルを整理しておくとよいでしょう。
また、転勤などをする場合は、お世話になった方々への挨拶まわりも必要です。人事発令が出るまでは、原則として内示内容を明かすことはできません。しかし、そこで上司の許可が降りれば、「1月の第2週は東北エリアのお客様、第3週は近畿エリア……」などの出張予定を立てておいても良いかもしれません。
内示から発令が出るまでの間は、さまざまな制限があるなかで「立つ鳥跡を濁さず」となるような準備をコツコツ進めることが大切です。
人事発令の拒否は認められるのか
発令された人事異動への拒否は、基本的に認められるものではありません。その理由は、事業主側には従業員に対する人事権があるからです。
人事権とは、労働者の処遇や地位を決められる権限になります。人事異動に応じない労働者がいた場合、企業側では懲戒処分にすることも可能なのです。
また、厳密な話をすれば、先述の“内示への拒否”も基本的にはできません。ただし、人事権を行使して人事異動を強制・強要してしまうと、従業員のモチベーション低下や、場合によっては離職要因になってしまうことがあるでしょう。
こうした悪循環を防ぐために、内示をする際には従業員の意向をしっかり聞くことが必要です。
正当な理由があれば人事異動を拒否できることがある
内示や発令した人事異動は、どのようなときでも認められるわけではありません。就業規則の内容や従業員の事情によっては、発令内容が「不当な異動命令」とされることがあります。従業員からの拒否が認められやすい正当な理由には、以下のようなものがあります。
|
<異動を拒否する正当な理由>
|
たとえば、就業規則に「会社は業務上必要があるときは、従業員に異動を命ずることがある」「従業員は正当の理由なくして、異動を拒んではならない」と書かれていたと仮定します。
この場合も、対象従業員や家族に重度の病気や親の介護の必要が高いなどの理由があり「どうしても東京を離れられない」といった場合、転勤命令が無効と認められることがあります。
なお、厚生労働省では転勤に関する裁判例を公開しています。人事異動の対象者を選定する際には、ぜひ参考にしておくとよいでしょう。
人事業務のアウトソーシングならラクラスへ
本記事では、人事でよく使われる発令とほかの概念の違いや、人事トラブルを防ぐポイント、適切な手続きの流れなどを解説させていただきました。人事発令にはさまざまな注意点があるため、人事部のなかでも負担に感じている方は多いのではないでしょうか。
もし人事業務における業務効率化をお考えであれば、ラクラスにお任せください。ラクラスなら、クラウドとアウトソーシングを掛け合わせた『BpaaS』により、人事のノンコア業務をアウトソースすることができコア業務に集中できるようになります。
ラクラスの特徴として、お客様のニーズに合わせたカスタマイズ対応を得意としています。他社では難色を示してしまうようなカスタマイズであっても、柔軟に対応することができます。それにより、大幅な業務効率の改善を見込むことができます。
また、セキュアな環境で運用されるのはもちろんのこと、常に情報共有をして運用状況を可視化することも心掛けています。そのため、属人化は解消されやすく「人事の課題が解決した」という声も数多くいただいております。
特に大企業を中心として760社86万人以上の受託実績がありますが、もし御社でも人事の課題を抱えており解決方法をお探しでしたら、ぜひわたしたちラクラスへご相談ください。