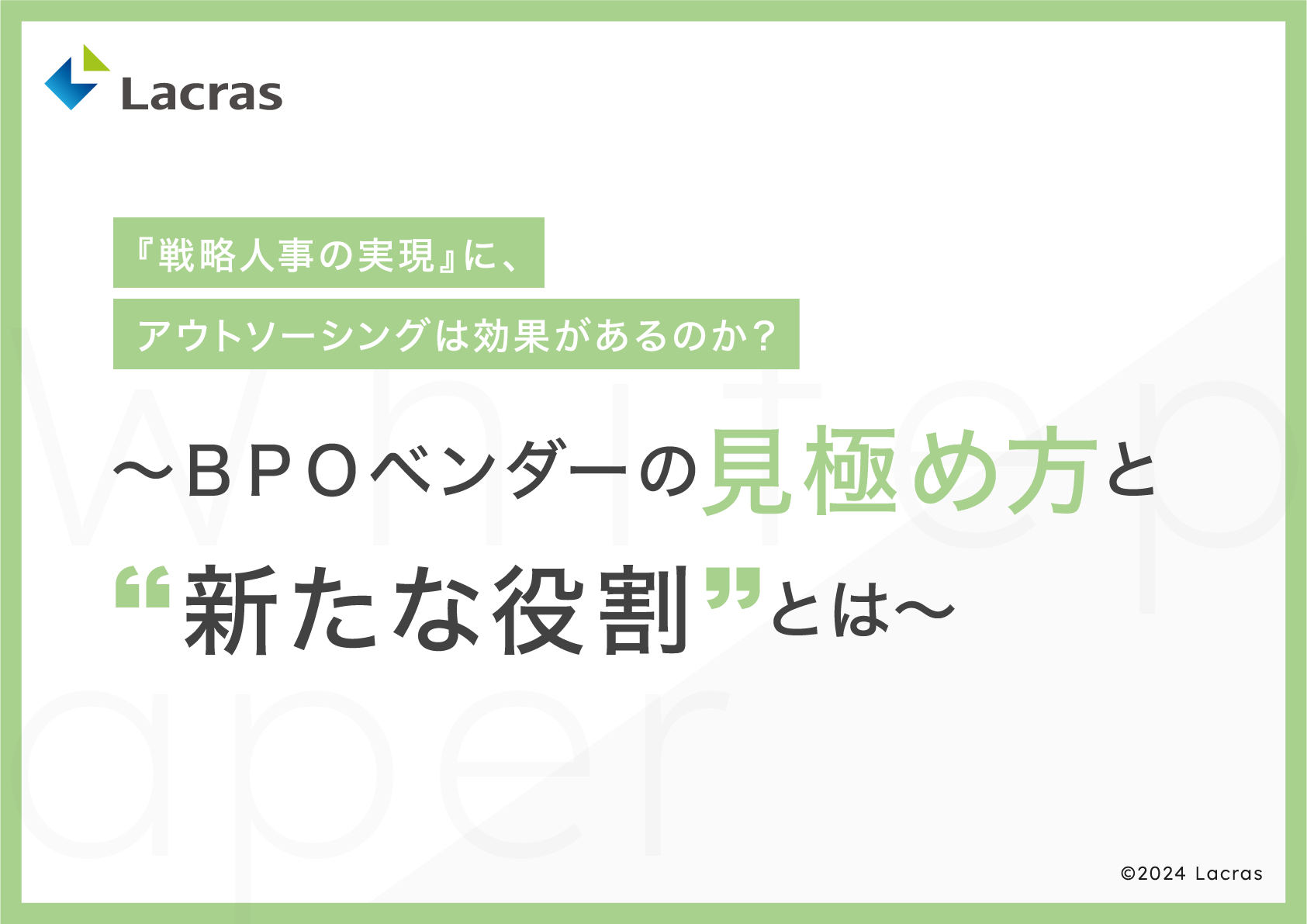人事評価における目標設定の基本とは?目標の活用法、運用時の注意点を詳しく解説

本記事では、人事評価および目標設定の基本を確認したうえで、適切な目標を立てるときに使えるフレームワークやプロセスなどを解説します。人事評価や目標設定のポイントを理解して人事業務をスムーズに進めていきたい方は、ぜひ参考にしてください。
人事評価を通じて従業員のモチベーションや生産性などを高めていくためには、正しい考え方で設定された目標と評価制度をうまく組み合わせることが大切です。
ただし、人事部門の担当者がこれからはじめて人事評価および目標設定の仕組みを構築する場合、そもそも「適切な目標とはなんなのか?」や「なぜ目標設定と人事評価を連携させる必要があるのか?」といったことがわからない場合もあるでしょう。
そこで本記事では、人事評価および目標設定の基本を確認したうえで、適切な目標を立てるときに使えるフレームワークやプロセスなどを解説します。記事の後半では、目標設定に関するよくある質問や業種別の設定例も紹介していきます。
自社の人事評価制度と効果的な目標設定を連携させたい方は、ぜひとも本記事を参考にしてください。
人事評価における目標設定の基本
「従業員の成長」や「組織の業績アップ」につながる適切な人事評価を行うためには、この取り組みで重要な役割を担う『目標設定』がどういったものなのかを理解することが必要です。
ここでは、目標設定の概要と人事評価との関連性を確認しましょう。
目標設定とは何か
目標設定とは、人や組織が目指すべきゴールを示したものです。
目標は、人事評価に限らず、普段の仕事や資格試験の勉強といったさまざまなシーンで設定されます。多くの場面で目標設定が行われる理由は、明確なゴールがないと「何をどうやるか?」という具体的な計画が立てられないからです。
たとえば、ある人事担当者が業務マニュアルを作成すると仮定します。
そのときに、「私はマニュアルをつくる!」とだけ宣言しただけでは、その作業が「どういう内容でどの程度のボリュームなのか?」や「いつ完成するのか?」、「どのくらいのペースで作業を進めたらいいのか?」といったことは誰も把握できません。
しかしそこで「私は採用面接官向けのマニュアルを作成する。50ページ前後で内容は◯◯が中心、6月中に完成させる」という明確な目標を設定すると、そこから「6月末までに10週間あるから、毎週5ページずつ作ればよい」といった具体的な計画に落とし込めるようになるわけです。
さて、具体的な目標に基づく計画は、進捗管理や業務の改善に役立つ指標となります。明確なゴールを最初に設定するからこそ、そこまでの道筋が決まり、うまく進まないときの判断や対処も迅速に行いやすくなるでしょう。
人事評価との関連性
目標設定は、従業員の成長につながる人事評価を行ううえでも重要なものです。
たとえば、上司と部下が一緒に「6月末までに商品Aを30個売る。販売手法はB中心。難しい場合は手法Cでも良い。」という目標を立てたと仮定します。この場合、上司が6月以降に行う評価では、「商品Aを何個売ったか?」や「販売手法はどれを使ったか?」の2点を中心にチェックしていくことになるでしょう。
このことは上司と部下の間で同じ目標を共有していれば、上司が評価やフィードバックをする際にも認識のズレが生じにくくなることを意味します。
近年のビジネス環境では、「人事評価の不公平感」や「上司への不信感」などの理由から、若手人材の離職が起こりやすくなっています。
こうしたなかで、人事評価や日々のコミュニケーションにおける上司と部下の認識のズレを減らし、信頼関係の構築や部下の成長といった好循環につなげていくためには、後述する方法で設定した「目標」と「人事評価の仕組み」を関連付けることが重要になります。
目標設定がもたらすメリット
従業員個人や組織の目標を適切に設定・管理・評価すると、以下のようなメリットが生まれます。
メリット(1)従業員のモチベーション向上
良い目標と計画は、日々の仕事や努力の方向性を明確にするものです。
たとえば、ある従業員が「業務マニュアルを1日3ページずつ作成して、6月末までに終わらせる」という目標を立てたと仮定します。
この人が、目標を立てた翌日から毎日3ページのマニュアルをつくり続けた場合、「他の業務が忙しくても3ページぐらいなら問題なく続けられる」という自信と経験が得られます。そこから生まれるのが「自分でもできる作業量だから来週も続けてみよう」という前向きな気持ちです。
適切な目標と計画を立てて、ゴールに向かってそれらを実践する行動は、従業員のモチベーションを高めやすくするのです。
メリット(2)業務の生産性向上
適切な目標設定による前向きな気持ちは、仕事の生産性向上にも寄与します。
また、具体的な目標および計画は、仕事が思うように進まないときの軌道修正にも役立つものです。
たとえば、今週はほかの業務が忙しくて「1日3ページのマニュアル作成」がまったく進んでいない場合、具体的な目標と計画が立案されていれば、すぐに「進捗が悪い」や「思うように進んでいない」といった判断ができるはずです。
この判断から仕事の進め方ややり方などを見直すと、当初は低下していた生産性を少しずつ向上させられたりもするでしょう。
メリット(3)企業文化の強化
適切な目標設定は、企業にとって大切な文化や価値観を強化するうえでも役立つものです。
たとえば、ある小売業で何の個人目標も設定されていなければ、従業員はそれぞれが自由な方法で多くの商品を売ろうとするかもしれません。また、販売実績という数字だけが評価される組織であれば、いわゆる“押し売り”などの失礼な方法が選択されてしまう可能性もあるでしょう。
こうしたなかで、自社が大切にしている価値観として、たとえば「まずはお客様の話に耳を傾ける」を目標に盛り込むと、販売員の売り方や振る舞いが統一されていきます。
また、人事評価のなかで「お客様の話に耳を傾けられているか?」といった評価項目を設けることで、さらなる企業文化の浸透・強化が実現しやすくなるでしょう。
人事評価における目標設定のフレームワーク
人事評価制度のなかで立てる目標は、いくつかの要素をクリアしてこそ高い効果を発揮するものです。効果が高い目標を簡単に立てるためには、目標設定に特化したフレームワークを活用するのが良いでしょう。
ここでは、ビジネスシーンでよく使われる3つのフレームワークを紹介します。
(1)SMARTの法則
SMARTの法則は、具体的かつ達成可能な目標を立てるためのフレームワークです。SMARTは、以下に記載している5つの要素の頭文字をとった言葉になります。これらの5つは、「良い目標」を立てるうえで不可欠な要素です。
・【Specific】具体的である
・【Measurable】計測できる
・【Achievable】達成できる
・【Related】上位目標との関係性がある
・【Time-bound】期限が設定されている
たとえば、現状で月100万円しか売れていない人が立てた「今月は1億円売る」や、「とにかくたくさん売る」といったものは、現実性が乏しくどちらかといえば夢や理想に近いものです。
非現実的なゴールを掲げても、その達成に向けた計画は立てられないですし、やる気もでてこないでしょう。こうした形で目標が形骸化してしまう問題を解消するためには、SMARTの法則を使って具体的で達成可能な目標を立てることが大切です。
たとえば、営業部門全体の目標が1億円だとした場合、「2025年の上期末までに、1,000万円売る」という個人目標を立てると、そのゴールに到達するまでの具体的計画を立案できます。
また、具体的なゴール設定は進捗管理も可能にするものです。進捗管理や計画の見直しを定期的に行うことで、ゴールへの到達が確実に近づいていくでしょう。
(2)OKR(Objectives and Key Results)
OKRは、Google社やMeta社など先進的企業も取り入れる目標設定・管理の手法です。OKRの特徴は、アグレッシブな目標設定によってメンバーの主体性や熱量を向上させることで、組織パフォーマンスを高めることを目的にしています。
OKRでは、以下の2つを設定したうえで、達成に向けて取り組んでいきます。
・【Objectives】目標
・【Key Results】指標となる主要な結果
目標(Objectives)では、どちらかといえば組織全体でワクワク感を共有できるチャレンジングなものを設定します。たとえば、「国内シェアNo.1」や「顧客満足度がダントツで高いオンラインゲームを開発する」といった内容です。
OKRの目標は、普通に取り組むだけでは60~70%程度の達成度になってしまうもので構いません。それは「このゴールを達成したら自分たちはすごいことになる!」とワクワクできるものであり、先述の『SMART』とは大きく異なる目標になるでしょう。
続いてKey Resultsは、1つの目標に対して2~4つ設定します。たとえば、「顧客満足度がダントツで高いオンラインゲームを開発する」が目標の場合、以下のようなKey Resultsの項目が考えられるでしょう。
・課金したユニークユーザー数
・ゲームをプレイした全ユーザーにおける課金率
・ゲームプレイした全ユーザーにおけるアクティブ率
・アプリ市場における平均評価とレビュー数 など
なお、OKRの場合、四半期ごとに振り返りを行い、達成度をスコアリングします。スコアリングの結果を踏まえて新たなOKRを設定する、というサイクルをまわしていく形になるのが一般的です。
MBO(目標管理制度)
MBOは、マネジメント理論の提唱者である経営学者、ピーター・ドラッカーが生み出したものです。個人や部門で設定した目標およびその達成度合いを、人事評価に活かす仕組みの総称になります。
MBOを行ううえでのポイントは、まず組織や部門全体の目標を設定することです。そして、個人目標は部門の目標から落とし込んだものになります。そのイメージとしては、以下のようになるでしょう。
組織のMVV(ビジョン・理念) > 組織の目標 > 部門の目標 > 個人の目標
MBOにおける目標は具体的かつ達成可能であることが求められます。先述のSMARTの法則を使って設定する必要があるでしょう。
MBOによって組織・個人の目標と人事評価を関連付ける際には、組織の中長期的な活動やチームワークに支障がでないようにすることも重要です。
たとえば、営業部門全体の売上目標から落とし込んだものを各メンバーの個人目標にするとします。その場合、各自が数値目標の達成に専念することで、たとえば「新人のサポートをする」や「来春の展示会の準備を進める」といった具体的な成果にならない仕事を疎かにしてしまうかもしれません。
しかし、会社や営業部門全体としては、新人の育成や展示会の準備も非常に重要な業務になります。
こうした仕事を疎かにしないためには、売上や販売個数などのわかりやすい業績評価に加えて、プロセスや中長期的な成長を評価するための目標も設定する必要があるでしょう。
業種別の目標設定例
これからはじめて目標設定を導入する場合、各部門や業種に合った内容が思いつかず、ワンパターンな内容に偏ってしまうことがあるかもしれません。
しかし、少し視点を変えてみると、目標として設定できる対象は、それぞれの仕事や組織のさまざまなところに眠っています。ここでは、4つの業種における目標設定の具体例を紹介しましょう。
(1)営業職の目標設定例
営業職は、組織や本人の活動実績を数値化できるため、他と比べて目標設定しやすい業種といえます。先述したSMARTの法則を使うと、以下のような目標が設定できるでしょう。
【営業職の定量的目標】
・新宿エリアの◯◯系企業に週20件のテレアポ営業を行い、2025年6月末までに50件以上のアポイントメントをとる
・2025年末までに商品Aを1,000個以上販売して、今年度の新人営業賞を獲得する
営業職の中長期的な成長を考えた場合、以下のような定性的な目標を設定して、5段階評価をしても良いでしょう。
【営業職の定性的目標】
・ルート営業の訪問数が少ないため、◯◯を改善しながら業務効率化を図ってみる
・新人AくんのOJTで◯◯に力を入れることで、今年度の新人営業賞を獲得してもらう
定性的な目標を評価する場合、以下のような5段階にそれぞれ点数を割り当てるのも良いでしょう。この考え方は、ほかの業種にも応用できるはずです。
・【努力レベル以上の成果を達成できた】5点
・【努力レベルに達した】4点
・【必達レベルを達成できた】3点
・【必達レベルには達しなかったが、前回よりも向上できた】2点
・【必達レベルに達しなかったし、前回からの改善もなかった】1点
(2)技術職の目標設定例
技術職においても、SMARTで設定できる定量的な目標に加えて、作業品質や組織力の向上などにつながる定性的な目標を設定することが重要になります。
【技術職の定量的目標】
・2025年上半期におけるエラーやバグの発生率を◯%以内にする
・発生トラブルの◯%以上を◯◯時間以内に解決する
【技術職の定性的目標】
・週1回の勉強会参加でプログラミング知識を増やし、コードの可読性と保守性を向上させる
・最新技術◯◯に関する全メンバーの理解力を高めたうえで、自社の全アプリケーションに実装していく
(3)管理職の目標設定例
管理職の場合、組織開発や人材育成などの業務も増えることから、中長期的な視点で目標を考える姿勢が特に求められるようになります。
【管理職の定量的目標】
・部門内の目標達成率を70%から95%に上げる
・チームの労働環境を改善するために、部門内の残業時間を20%削減する
・プロジェクトAのコストを10%削減する
【管理職の定性的目標】
・定期的な1on1を行い、多くの部下と信頼関係を構築する
・◯◯の施策を通じて、心理的安全性の高い組織づくりをする
・自分とメンバーのセルフマネジメント力を向上させるために、外部研修を10回受講し、そこで得た知識を週1回のミーティングや1on1でメンバーに共有していく
(4)サービス業の目標設定例
飲食やホテル、レジャーなどのサービス業では、売上・販売数・クレーム率・リピート率といったものはお店(組織)全体で達成する指標であることが多いです。
この場合、組織の目標を自分事にすることが難しく、従業員のモチベーションや主体性が下がりやすくなる可能性があります。個人の販売個数などを集計・管理できないことは仕方がありませんが、そういったなかで各自が主体的に働ける目標を考えることが重要でしょう。
【サービス業の定量的目標】
・新製品◯◯の販売数で全国1位になって、社長から高級な焼き肉をご馳走してもらう
・各自が1日10回以上のサジェストを行うことで、新サービスAのリピート率を30%に上げる
【サービス業の定性的目標】
・ホスピタリティ勉強会を月1回開催して、おもてなし力向上につながる案をみんなに出してもらう
・11月末までは閑散期に入るので、デイリークレンリネスの習慣化に力を入れる
・大学4年生が卒業するまでに、新人3人を育成してレベルにする

目標設定のプロセス
従業員個人や組織の目標は、「1度設定さえすればOK」というものではありません。目標設定によって人材・組織の成長や業績アップなどの高い効果を得るためには、設定した目標は以下のプロセスで運用していくことが重要です。
(1)個人の目標設定前にサポートを行う
従業員本人の生産性やモチベーション向上につながり、なおかつ組織の文化や方向性ともリンクする目標を立ててもらうためには、人事評価を行う上司や人事部門がいくつかのサポートをする必要があります。
サポート① MVVや大切にする価値観の共有をする
まず目標設定前に提供(共有)すべきものは、企業や部門が大切にする価値観と上位目標です。各目標と企業の価値観には、以下の関係性があります。
組織のMVV(価値観・理念) > 組織の目標 > 部門の目標 > 個人の目標
多くの企業が設定するMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)は、企業の方向性やそこに向かうための行動指針などをあらわしたものになります。
このMVVを浸透させるための社会教育などを行うことで、従業員は適切な指針や価値観に合った目標や計画を立てられるようになっていきます。
サポート② 上位目標の共有をする
もう1つ共有すべきことは、組織や部門の目標です。
個人の目標は、部門の目標から落とし込んだものになります。そのため、たとえば営業部門の目標が「商品Aを1,000個売り、2025年上半期の売上を5,000万円にする」であれば、そのなかで働く従業員(営業担当者)の目標にも、「2025年上半期の売上」や「商品Aの販売個数」が入ってくるイメージになるでしょう。
サポート③ 目標の意味づけをする
主体的にゴールに向かう目標を立てるためには、本人にとってそれを達成する「意味」や「目的」を考えてもらうことも大切です。それはつまり、上司が一方的に押し付けたりした目標では、主体性や高いモチベーションなどが生まれにくくなることを意味します。
たとえば、「6月末までに商品Aを1,000個売る」というのは、組織にとっての意味は大きくても、従業員本人の意味はあまり大きくない目標かもしれません。しかしそこで、以下のような目標達成する個人および周囲の人間関係などに関連するメリットを考えてもらうと、ゴール達成に向けたポジティブな気持ちや主体性が生まれやすくなってきます。
・商品Aを1,000個売り、新人トップの成績で社内表彰される
・社内表彰の賞金で、家族旅行に行く
・営業部門全体の目標を達成して、先輩方とみんなでお祝いする など
上記のようなメリットは、「自分/他者」「有形/無形」という2つの軸(4つの観点)で考えていきます。
「6月末までに商品Aを1,000個売る」だけでは非常に味気ない目標も、上記のような
メリットを具体的にイメージすることで、ワクワクする内容に変えやすくなるでしょう。
(2)進捗の確認と調整
ゴール達成に向けて計画の実行を始めたら、1on1などの際に上司と部下が一緒に進捗確認をしていきます。
進捗確認のポイントは、仮に進捗が悪くても、考えられる理由や原因を聞いたうえで一緒に改善策を考えることです。また、本人や市場などに著しい環境変化が生じたときには、無理に当初のゴールに向かわせるのではなく、状況に合った軌道修正を促すことも必要でしょう。
このような柔軟な対応をすることで、従業員のモチベーションは下がりにくくなります。
(3)目標期間後の評価とフィードバック
SMARTの法則で設定した期間が終了したら、達成度や結果を踏まえた理由などを必ず評価します。この作業は、人事評価面談のタイミングで実施してもよいでしょう。
また、フィードバックをする際には、「フィードフォワード」の考え方で話をするのがおすすめです。フィードフォワードとは、どのような状況でも「否定的な批判」をせず、「未来の成功や成長につながる話」をすることです。
たとえば、ある従業員の売上成績が悪く、数値目標の達成率が50%だったと仮定します。そこでフィードフォワードの考え方で話をするならば、以下のようなアドバイスになるでしょう。
|
今期の目標達成率は50%だったけど、新人AくんのOJTと春の展示会の準備を進めながらこの数字を出したことには、もっと自信を持って良いと思うよ。これからリーダーになるためには、マネジメントスキルやヒューマンスキルを高める必要があるから、今期はその良いトレーニングになったと考えよう。来期はもうOJTや展示会もないから、目標達成率100%以上を目指して頑張ってね。
|
人事評価における目標設定の注意点
目標も設定の仕方を誤ると、逆効果になってしまうことがあります。ここでは、目標設定からさまざまな効果を生み出すために注意すべきポイントを3つ紹介しましょう。
注意点(1)あいまいな目標は避ける
以下のように曖昧で漠然とした内容は、どちらかといえば「願望」や「理想」、「夢」に位置づけられます。
・今期は営業活動をたくさん頑張る
・(毎月売上100万円未満の人が)今月は1億円稼ぐ
・(業界の右も左もわからない新人が)今年中に億万長者になる
夢や希望を持つことはもちろん大切です。
しかし、その夢や希望を現実のものにするためには「今月」「上半期」「2025年」といった短期間で達成できる目標を設定し、その達成を積み上げることで中長期的な夢や目標にたどり着く必要があります。
また、明確な期限や計測できる数字がない漠然とした目標では、それを達成するための具体的な計画も立案できません。達成することを前提に個人の目標設定するのであれば、SMARTの法則を使って具体的なものを考える必要があるでしょう。
注意点(2)部下の意見を尊重する
設定したゴール達成に向けて主体的に行動してもらうためには、部下の意見を尊重したうえで、納得感のある目標を一緒に考えることも大切です。
たとえば、「今期は新人のOJTをやりながら自分の営業活動をする」や「6月は展示会の準備であまり個人の営業活動ができない」といった事情がある場合、そういったなかで無理に組織の目標から落とし込んだ数字を上司が強要してしまうと、仕事の質が低下してしまうかもしれません。
また、部下の意見を無視して、上司の都合や主観で無理な数字を一方的に強要した場合でも、信頼関係の構築は難しくなるでしょう。
目標設定やそれにともなう1on1、人事評価面談などと通じて上司と部下の良い関係を構築するためには、相手の意見に耳を傾けたうえでその背景にある事情などに関心を持つ姿勢が必要なのです。
注意点(3)中長期的な視点を持つ
人事評価で目標設定を活用するうえでは、上司と部下の両方が中長期的な視点を持つことも重要です。
たとえば、3ヵ月や半年といった短期で見ると「商品Aを1,000個売る」や「売上5,000万円を達成する」などの目標がベストかもしれません。しかし、個人や組織の成長を中長期的なスパンで考えると、以下のような目標の達成が必要になってくることが多いでしょう。
【組織の中長期的な目標】
・若手の営業力を向上させる(1~2年のトレーニングが必要)
・テレアポ研修を実施できる人材(先輩社員)を育てる
・2027年に大阪に営業所をつくる(それまでに管理職人材の育成が必要)
・顧客ニーズの多様化にあわせて組織全体の営業手法をひろげる
【個人の中長期的な目標】
・テレアポ営業のスキルを向上する
・A先輩の営業に多く同行して飛び込み営業の手法を学ぶ
・2027年までにリーダーになれるように努力する
・チームの新人(Aさん・Bさん)を一人前にする
「販売個数」や「売上」といった短期的な業績目標にこだわりすぎると、中長期的な事業成功に不可欠な組織づくりや人材育成などが疎かになるかもしれません。また、部下が組織のなかでキャリアアップしていくためには、高い業績を単純にあげ続ければ良いわけでもないのです。
たとえば、その人材が組織のリーダーやマネージャーなどを目指すのであれば、業績に直結しないマネジメントや部下の育成スキルなどを身につける必要がでてきます。また、これらのスキルは一朝一夕で身につくものではなく、習得するまでには年単位の時間が必要です。
人材育成および組織開発のこうした本質を考えると、目標設定と結びつけた人事評価を行う際には、従業員本人と組織における中長期的な視点を持ち、各自の成長や成功に至るまでの過程も評価することが重要でしょう。
人事評価の目標設定に関するよくある質問
人事評価の目標設定の進め方について、人事担当者からよくある質問と回答を紹介しましょう。
Q.目標設定の頻度はどのくらいが理想ですか?
目標管理制度(MBO)を実施する場合、「半年~1年に1回」を目安に評価と新たな目標設定を行うのが一般的です。
なお、パーソル総合研究所による「人事評価と目標管理に関する定量調査」では、54.3%もの企業が「半年に1回」、38.4%が「1年」と回答しています。これに対して「6ヵ月より短い期間」とする企業は4.3%、「1年より長い期間」は3.1%と著しく少ない傾向がありました。
<参考>:人事評価と目標管理に関する定量調査(パーソル総合研究所)
目標設定の適切な期間は、企業の業種や携わるプロジェクト、人事評価制度の仕組みによって変わる部分もありますが、これから目標管理の仕組みを導入するのであれば、多くの企業が実施している「半年に1回」もしくは「1年に1回」からはじめてみるとよいでしょう。
Q.目標達成が難しい場合の対処法は?
部下の目標達成が難しい場合に最初にすべきことは、上司が部下に寄り添い一緒に達成できない原因を考えることです。目標達成ができない主な原因には、以下のようなものがあります。
・目標がSMARTの法則で作られていない(曖昧・抽象的である)
・本人のレベルやリソースから見て、実現できない目標や計画を立てている
・目標達成までの進捗を管理できていない
・想定外の問題や環境変化が起こり、計画通りに作業を進められなくなった など
原因が見つかったら、次は対応策を考えます。ここでのポイントになるのは、本人にとって大きな負担や無理にならない範囲内で対応策や新たな目標を立案することです。無理のない範囲を知るためには、自己分析を通して以下のような内容を知る必要があるでしょう。
・自分の強み・弱み
・平均的な作業スピード
・活用できるリソース
・計画の実行を妨げることが多い要因 など
たとえば、ある部下が「業務資料を1日3ページ作成する」という目標を掲げて、「資料作成は毎日16時から始める」という計画を立てたと仮定します。しかし、16時以降にお客様の問い合わせや先輩からの急な作業依頼が入ることが多ければ、この計画はあまり現実的ではないかもしれません。
そこで自己分析を行い「出社直後の10時までなら集中して作業できる」という気づきが得られると、本人にとって無理がなく現実的な作業計画を立てられるようになります。
目標達成できない背景には、“外的要因”があることも考えられます。
しかし、自己分析をしっかり行い「自分はここまでならできる」「こういう状況では難しい」などのパターンがわかると、自分ではコントロールできない外的要因のなかでもベストを尽くせる計画の立案が可能になるでしょう。
部下の目標達成が難しいときには、先ほど紹介した『フィードフォワード』の姿勢で寄り添いながら、本人および外的要因の分析をし、そこからの改善策の検討をサポートしてあげてみてください。
人事業務のアウトソーシングならラクラスへ
本記事では、人事評価および目標設定の基本を確認したうえで、適切な目標を立てるときに使えるフレームワークやプロセスなどを解説してきました。人事評価や目標設定には多くの注意点があるため、人事部のなかでも負担に感じている方は多いのではないでしょうか。
もし人事業務における業務効率化をお考えであれば、ラクラスにお任せください。ラクラスなら、クラウドとアウトソーシングを掛け合わせた『BpaaS』により、人事のノンコア業務をアウトソースすることができコア業務に集中できるようになります。
ラクラスの特徴として、お客様のニーズに合わせたカスタマイズ対応を得意としています。他社では難色を示してしまうようなカスタマイズであっても、柔軟に対応することができます。それにより、大幅な業務効率の改善を見込むことができます。
また、セキュアな環境で運用されるのはもちろんのこと、常に情報共有をして運用状況を可視化することも心掛けています。そのため、属人化は解消されやすく「人事の課題が解決した」という声も数多くいただいております。
特に大企業を中心として760社86万人以上の受託実績がありますが、もし御社でも人事の課題を抱えており解決方法をお探しでしたら、ぜひわたしたちラクラスへご相談ください。