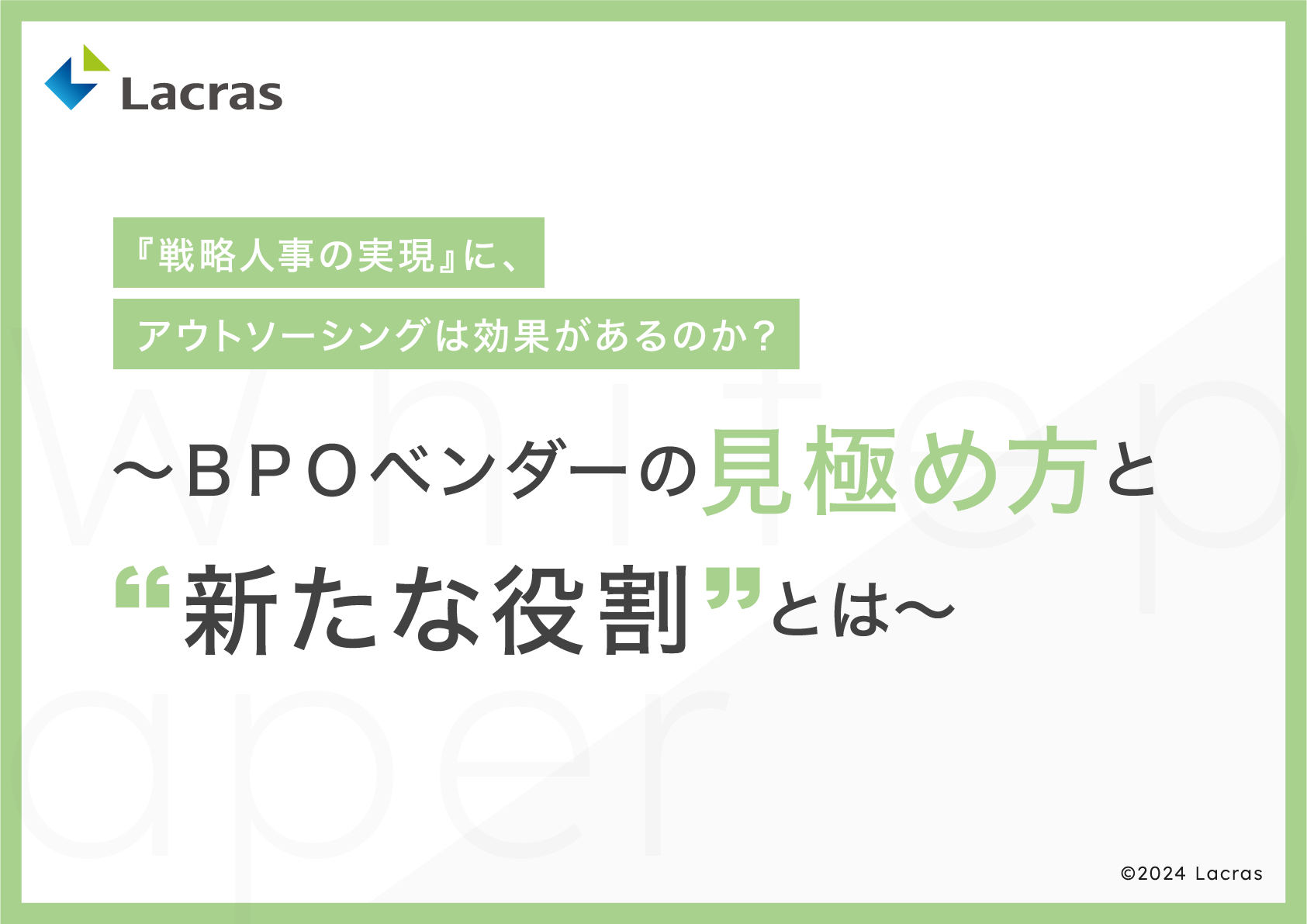異動希望の理由とその正当性とは?
職場環境を改善する方法や異動願の例文・書き方を解説

本記事では、人事担当者や上司の皆さんに向けて異動希望の概要や重要性・正当性などを解説します。また、会社側に異動希望を出すべきか考えている従業員向けに、異動希望の正しい書き方や伝える際のポイント、異動希望を通すためのコツなども紹介していきます。
従業員からの異動希望に対応される方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
終身雇用制度が崩壊し、働く人のキャリアが多様化するなかで増えているのが、従業員から出される「異動希望」です。
異動希望は、人事部門や上司にとって時には“悩みの種”になることもあるでしょう。一方で異動希望を出す従業員側からすると、さまざまな葛藤を抱えるなかで「最適な環境で活躍したい」という想いから生まれる強烈な“メッセージ”でもあるはずです。
この記事の前半では、人事担当者や上司の皆さんに向けて異動希望の概要や重要性・正当性などを解説します。
後半では、会社側に異動希望を出すべきか考えている従業員向けに、異動希望の正しい書き方や伝える際のポイント、異動希望を通すためのコツなどを紹介していきます。
異動希望の基本理解
異動希望に対して適切な対応を行うためには、まず「そもそも異動希望とはなにか?」を理解することが大切です。また近年では、従業員が出す異動希望の重要性が高まっています。そういった背景を理解しておくことで適切な対応につなげやすくなるでしょう。
ここではまず、異動希望の概要と重要性を解説します。
異動希望とは何か?
異動希望とは、従業員から出される「部署異動の希望」です。
一般的には「異動願い」と呼ばれたりもします。
具体的には、「システム部門から営業部門に異動したい」といったイメージですが、なかには「東京本社から大阪支社に移りたい」といった勤務地変更の希望も生じるかもしれません。
異動希望は、何らかの理由から「いまの部署で働き続けるのが難しい」「ほかの環境で働いてみたい」などの想いが強くなったときに提出されることが多いものです。
異動希望の重要性
異動希望の重要性は、希望内容への対応を行う「会社側」と、それを提出する「従業員側」の両方で高まっている状況です。
まず、近年のビジネス環境では、終身雇用が崩壊したことで転職も当たり前になり、働く人が会社に求める条件やキャリアなどが多様化しています。
また、社会の少子高齢化が進み採用手法が多様化するなかで、採用難や人材難に悩まされる中小企業も多くなっています。
こうしたなかで従業員から出される異動希望は、自社で働く人の不満や現場が抱える問題などを知る良い機会になります。
また、異動希望が出されるということは、「会社に自分の悩みを知ってほしい」や「望みが叶えられたらこの会社にとどまっても良いかもしれない」という歩み寄りの姿勢である可能性も高いでしょう。
早期離職者の増加による人材難に悩まされる企業からすれば、異動希望を出す従業員は、諦めの気持ちから「何も言わずに静かに辞める人」よりもありがたい存在になるかもしれません。また、そういった層との対峙には、会社全体の人材課題解決につながる「ヒント」が隠れているものです。
現実的に考えて大半の企業は、すべての異動希望を叶えてあげられるわけではありません。しかしそれでも、異動希望の声に耳を傾けることの重要性は近年とくに高まっているといえるでしょう。
また、異動希望は、従業員側においても重要性が高まっています。
その理由は、先ほどと同じで『黙って辞められる状況を減らしたい』『従業員の悩みに寄り添いたい』と考える企業が増えているためです。
終身雇用が全盛だった時代の、いわゆる“メンバーシップ型組織”では、「ジョブローテーション」という仕組みの影響から、自分が希望する仕事に携われないことも当たり前でした。
一方で現在は“ジョブ型雇用”も登場しており、「働く人のキャリアビジョンや希望・適性を尊重する」といった考え方が浸透し始めています。
それはつまり、従業員が異動希望を出してみることで「何かが変わる可能性」が高まっていることを意味するのです。
ここまで紹介したさまざまな要因から、近年のビジネス環境では、異動希望を出す側・受け取る側の両方にとってその重要性が高まっていると考えてよいでしょう。
異動希望の理由とその正当性
異動希望への適切な対応は、その理由を中心とするさまざまな要素の影響を受けるものです。また、労使トラブルを防ぎ公平・公正な対応を行うためには「その異動希望に正当性があるのか?」という視点も必要でしょう。
ここでは、異動希望における3つの代表的な理由と、それぞれの正当性および適切な対応の基本的な考え方を紹介します。
理由(1)キャリアアップを目指す異動希望
1つ目は、キャリアビジョンが明確であり、チャレンジ精神が強い従業員の場合です。たとえば、「将来は金融系システムのプロジェクトマネージャーになりたいから、いまの第一開発部から第二開発部に異動したい」といった希望でしょうか。
この場合は、本人のニーズと組織のニーズが合致するかどうかで判断するのが一般的でしょう。
たとえば、第二開発部ですでに次世代リーダーの育成を始めている場合、そこに新たな管理職候補を入れるのは公平性の面で考えてもあまり現実的ではありません。しかしそこで、次世代リーダー候補の退職予定や人材不足などの状況があれば、キャリアアップを目指す異動希望も通しやすいでしょう。
ただし、その従業員の異動希望を受け入れる場合、現在の所属組織とのバランスをとることも重要になります。そういう意味で、異動希望を通すかどうかを考える際には、「現在の所属組織」と「異動希望先の組織」の両方のニーズを見ていく必要もあるでしょう。
理由(2)家庭の事情による異動希望
2つ目は家庭の事情による異動希望ですが、以下のような理由で発生することが多いでしょう。
・親の介護が始まった
・子どもの保育園が遠い場所にあり、送り迎えが大変である
・A市に転居して今のオフィスへの通勤が大変になった
・配偶者の単身赴任が決まった など
家庭の事情による異動希望の場合、大きな注意点があります。それは、育児・介護休業法(第26条)では子育て・介護と仕事の両立をする従業員に対して、個別の意向を聴取したうえで自社の状況に応じた「配慮」をしなければならないことを定めている点です。
厚生労働省の資料『育児・介護休業法のあらまし』では、このことについて以下のように述べています。
|
8 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮 ①仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取 ②聴取した労働者の意向についての配慮
<引用>:育児・介護休業法のあらまし(厚生労働省)
|
会社側ではもちろん組織全体のバランスを見る必要がありますし、たとえば「人事担当者が1人しかいない」「求人を出しているが応募がない」といった状況であれば、異動希望をすぐには通せないこともあるでしょう。
しかし、育児や介護をしながら仕事との両立を目指す従業員に対しては、育児・介護休業法の概要を理解したうえで、無理なく仕事を続けるための配慮を最大限に行う必要があるのです。
理由(3)職場環境の改善を求める異動希望
従業員のなかには、毎日の長時間労働や人間関係の問題などで疲弊した状態から「もうこの部署では働けない……」という想いで異動希望を出す人もいます。具体的には、以下のような理由が多いでしょう。
|
|
上記のような場合、『異動希望を通す』か『職場環境を改善する』のいずれかで対応することが多いでしょう。また、さらに以下の3点を慎重に見ていく必要があります。
(1)いま症状や被害が出ているか?
(2)違法性があるか?
(3)すぐに改善できそうな事案か?
たとえば、「3月からずっと長時間労働と休日出勤が続いていて、すでにうつ病に近い症状が出ている」といった理由の場合、“従業員の安全配慮義務”に関係する緊急性の高い事案です。
そこで従業員の健康を守るためには、上司と相談して「忙しいプロジェクトから一時的にはずれてもらう」などの対応を行う必要があるでしょう。また、産業医やカウンセラーが在籍している場合、本人と面談してもらうことも一つの手です。こうした対処を行ったうえで、異動希望を通すかどうかの検討に入ります。
それに対して「パワハラ気質の先輩がいる」や「上司からの急な呼び出しが多い」といった事案の場合、事実確認と問題従業員への個人指導をしたうえで、コンプライアンスやハラスメント研修を実施することも視野に入れるべきでしょう。
このように、職場環境の問題のなかには会社の仕組みや制度の問題というよりは、組織風土や企業文化の影響を受けて発生しているケースもあります。この場合、管理職を中心とするメンバーの意識変革が必要となるため、教育や被害者サポートなどを中長期的に続けていく必要があるでしょう。
なお、パワーハラスメント対策は事業主の義務になります。人間関係の問題で異動希望が頻発している場合、厚生労働省が公開する以下の資料を確認したうえで、自社の対策を見直すことも重要でしょう。
【従業員向け】
異動希望を通すコツと伝え方のポイント
ここからは、異動希望を出したい従業員の皆さん向けのポイントを見ていきましょう。
提出した異動希望を会社側に受け入れてもらうためには、「本人のニーズ×会社のニーズ」がマッチすることや、組織内の状況、法制度に則った正当性などの要素が必要です。また、自分の話に耳を傾けてもらうためには、適切な伝え方を実践する必要もあるでしょう。
ここではまず、異動希望を通りやすくするための“考え方”や“コミュニケーション”のポイントを見ていきます。
ポイント(1)会社側の方針や事情を理解する
最初に考えておきたいのが、自分が「異動希望を出したい」と考える背景にある会社側の方針や事情です。具体的には、以下のようなものがあるでしょう。
【異動希望:第一システム部から第二システム部に異動したい】
⇒第一が人員不足である一方で、第二は余剰気味
⇒第二では次世代リーダー候補を育成中であり、そこで管理職を目指すのは現実的ではない
【異動希望:給与計算の担当から外れて採用担当になりたい】
⇒現状、給与計算を行えるのは自分だけ
⇒求人を出しているようだが、応募が集まらない様子
⇒採用担当には、面接のスペシャリストAさんとBさんがいる
【異動希望:子育てを始めて通勤が大変だから自宅近くの部署に行きたい】
⇒自宅近くにあるのは営業所と倉庫だけ
⇒自分が得意とする事務職は本社勤務が原則
上記のような背景を理解することで見えてくるのが、「会社側にもやむを得ない理由がある」という点です。
こうした事情や方針が見えてくると、ネガティブな疑問や違和感が緩和され、会社に対して建設的な提案をしやすくなるかもしれません。具体的には、以下のような違いが生まれてくるでしょう。
|
【背景を理解していない場合】
【背景を理解した場合】
|
ポイント(2)ポジティブで具体的な理由を伝える
異動希望を受け入れてもらうためには、「会社にとってポジティブな要素をいれること」と「具体的であること」の2点を意識した理由にする必要があります。
たとえば、「東京営業部で年間成績1位だった経験を活かし、新拠点の大阪営業部で活躍していきたいです」のように社内での実績をアピールするのもよいでしょう。
また、若手の離職が多い企業で働いている場合、「第一営業部に行ったらA先輩の下で経験を積み、営業部門全体を引っ張れるリーダーになりたい」という理由であれば、会社への中長期的な貢献と定着を踏まえた強いメッセージになるはずです。
もう一つのポイント「具体的である」とは、漠然とした理由では説得力に欠ける可能性が高いという意味です。
たとえば、「第一開発部なら“自分に合っていると思う”ので“頑張れると思います”」では、「何がどう自分に合っているのか?」や、異動によって「どう頑張れるか?」がまったく伝わりません。
また、異動希望の理由として多い人間関係についても、「先輩Aさんがちょっと嫌なんです」や「あの人間関係は自分には無理かも」などの漠然としていて愚痴に近い表現では、自分が求める適切な対策につながりにくいかもしれません。
理想としては、以下のように「内容が具体的であること」と「なるべく愚痴らないこと(できればポジティブに)」の2つを意識することが重要になります。
|
自分は手先が不器用なので、いまの組み立て部門は不向きです。
|
ポイント(3)上司と良い関係を築いておく
異動希望は、上司や人事担当者に「あなたのキャリアを応援したい」「問題を解決してあげたい」と感じてもらえてこそ通りやすくなるものです。そのために必要となるのが、上司や人事担当者との良い関係になります。
上司との良い関係は、日々の仕事をスムーズに進めるうえでも不可欠なものです。健全なコミュニケーションを通じて信頼関係を築くためには、日頃から人間力(ヒューマンスキル)を高めておくことが重要になります。人間力というのは、以下の能力で構成されるスキルの総称です。
|
|
上記の能力を高めておくと、上司などから「Aさんは信頼できる人材だ」と感じてもらいやすくなります。そうなると、異動希望の説得力が高まりやすくなるでしょう。
ビジネスパーソンとしてさまざまな人と良い関係を築き、自分のニーズを叶えていくうえで、高い人間力は大事なカギになります。

【従業員向け】異動希望の正しい書き方
上司との間で「言った・言わない」のトラブルを防ぐためには、異動希望を「書面」で示すのがおすすめです。ただし、上司や人事部門に内容を理解してもらい、検討を進めてもらうためには、いくつかの必要項目を網羅し“マナー”を意識した適切な方法で書面を作成する必要があるでしょう。
ここでは、異動希望の基本的なマナーと基本項目、すぐに活用できる例文を紹介します。
異動希望届(異動願い)のフォーマットと基本項目
異動希望を申し出るための書面には、法律で決められたような専用様式はありません。会社に専用フォーマットがあればそれを使うのが一般的ですし、無ければWordなどを使って自分で文書を作成します。
自分でつくる場合、A4縦の紙に以下の項目が並ぶようにデザインするとよいでしょう。
|
|
異動希望の書面作成ですぐに使える理由の例文
ここからは、「キャリアアップ」「家庭の事情」「職場環境の問題」の3理由について、すぐに使える例文を紹介しましょう。
「キャリアアップを理由」とする異動希望の例文
|
このたび、東京営業部で培った経験を活かし関西エリアでの売上アップに貢献したいと考え、来年新設される大阪営業部への異動を希望しました。
私には新宿エリアの売上を前年比150%まで伸ばした実績がございます。
また、私は関西大学の出身であることから、大阪エリアの中小企業経営者にたくさんの人脈がある状況です。東京営業部の皆さんからご共有いただいたノウハウとこれまで積み上げた経験、豊富な人脈を活かして、大阪営業部を盛り上げさせていただきたいと考えております。
|
「家庭の事情を理由」とする異動希望の例文
|
これまで育児を手伝ってくれていた義母が、心臓病で長期入院することになりました。一方で長女には知的障害があり、毎日の送迎が必要です。
三鷹オフィスが実践する営業ノウハウは、私が一昨年まで構築していたものです。
|
「職場環境の問題」を理由とする異動希望の例文
|
1年限定で参加している開発プロジェクト(第一システム部)に問題があり、毎日22時頃までの残業が約半年続いている状況です。
先週は同僚のAさんがうつ病の診断を受け、長期の休職に入ってしまいました。こうしたなかで私自身も心と身体に不調を感じはじめており、明後日の15日に産業医の先生と面談させていただく予定になっています。
繁忙期プロジェクトからの離脱を希望することに、断腸の思いはあります。しかし、今後も公共分野の知見を持つ唯一のエンジニアとして、健康な心身で会社に貢献し続けるためにも、自分のパフォーマンスを最大化できる第二システム部に異動させていただきたいです。
|
異動希望のメリットとデメリット
異動希望を出して自分に合った働き方をしていくことは、従業員のキャリアやワーク・ライフ・バランスにさまざまな効果をもたらすはずです。
しかし、伝え方や異動先の状況によっては、異動希望がさまざまな意味でリスクになることがあります。
続いては、異動希望における一般的なメリットとデメリット・注意点を見ていきましょう。
異動希望を出すメリット
異動希望を出すメリットは、日々の仕事やキャリアに生じている問題が整理され、解決につながりやすくなる点です。
また、異動希望を通じて課題が解決すると、異動後の自分からストレス要素が減り、モチベーションやパフォーマンスの向上につながりやすくなるでしょう。
それはつまり、仕事や家庭生活に好循環が生まれやすくもなるはずです。
異動希望を出すデメリット
異動希望を出すリスクやデメリットには、さまざまな種類があります。少し詳しく見ていきましょう。
・ストレスや課題が完全解決するとは限らない
自分の希望を受け入れてもらい異動が実現しても、それによってストレスや問題が大きく改善するとは限りません。たとえば、新しい環境にも以下のような問題がある場合、前の部署で働いていたときよりも不安やストレスが増えてしまう可能性もあるでしょう。
・新部署の人間関係に馴染めない……
・新部署のOJT担当が意地悪で、なかなか仕事を教えてもらえない……
・これまでの評価がリセットされたため、
かなり頑張らないと認めてもらえない……
・新拠点の仕事内容は想像以上に難しいものだった……
・残業と休日出勤がゼロになったことで、給料がかなり下がった……
・異動希望がキャリアにマイナスを与えることがある
会社の風土や人事評価の基準によっては、以下のような異動希望の申し出が自分のキャリアにマイナスの影響をもたらすことがあります。
【先輩Aさんからパワハラをされている】
⇒この程度の指導でパワハラか。
先輩の指導をありがたく思えない人材は、この職場に不向きかも……
【毎日の残業でうつ病になりかけている】
⇒繁忙期のエンジニアは毎日残業が当たり前。
この程度でうつ病になりそうなら、エンジニアには不向きかも……
【保育園のお迎えに間に合わない】
⇒AさんやBさんも同じ保育園を利用している。
なぜあなただけ間に合わない?
あなただけ特別扱いするわけにはいかない……
仮にいま働いている部署や上司・メンバーの考え方に問題があったとしても、異動希望をすることで「うちの組織には不向き」や「これではリーダーは任せられない」などのネガティブな印象を持たれると、社内でのキャリアアップが難しくなるかもしれません。
異動希望が逆効果になる問題を防ぐためには、会社側の方針や事情をよく理解・想像したうえで、ポジティブかつ具体的な内容を中心に建設的な話をしていく必要があります。
異動希望が通らない場合の対処法
異動希望は必ず通るものではありません。今回の異動希望が通らないなかでも引き続き働いていくという場合、以下のいずれかの対処を選択することになるでしょう。
対処(1)次の機会を待つ
以下のような理由で断られてしまった場合、いまの部署で仕事をしながら希望が通りやすい時期や状況を待つのも一つの対処策です。
・異動希望先に空きがない
・異動希望先が求めるスキルが身についていない
・今の部署が著しい人員不足である
・今は新人育成期間であるため、タイミングが悪い など
ただ、「待つ」を選択する場合、上司や人事担当者に以下の2つを確認しておくことが重要になります。
・希望部署に空きがないことだけが問題なのか?
・どれだけのスキル・知識・資格があると受け入れてもらいやすいのか?
企業では、組織全体のバランスを見て人材計画を立てるのが一般的です。
そのため、「空きが出れば必ず希望が通る」というわけでもなく、場合によっては「今回は30歳以上の経験豊富なリーダー候補が必要だった」と断られることもあるでしょう。
しかし、同じ組織のなかで自己実現をしていくためには、異動希望先の部署が「どういった人材を求めているのか?」というニーズに関心を持ち、自分に足りない部分を補強する努力をしていく必要があるのです。
対処(2)現部署での成長を目指す
異動希望が却下されても同じ会社で働き続ける場合、「現部署でどのような成長ができるのか?」とか「いまの職種にどのようなキャリアがあるのか?」などを模索するのも一つの対処策です。
「自分は、ここで頑張って現部署に貢献できる人材になる」と腹を括り精一杯の努力を続けていると、その姿勢が認められて、自分のキャリアアップを応援してくれる理解者が増えやすくなるでしょう。
そのような好循環が続くと、現部署のなかでも自分が輝ける居場所が見つけられるかもしれません。
異動希望に関するよくある質問
最後に異動希望に関するよくある質問と一般的な回答を3つ紹介しましょう。
Q.異動希望が通らない理由は?
異動希望が通らない背景には、さまざまな理由が考えられます。具体的な理由を教えてもらえない場合には、以下のポイントをチェックしながら適切な希望や伝え方を再検討する必要があるでしょう。
・正当な異動希望の理由であるか?
・個人的な愚痴や恨み節ではない、具体的かつポジティブな理由になっているか?
・会社側の方針や事情に合う現実的な希望になっているか?
・上司との間で「応援したい」「課題を解決してあげたい」と思ってもらえる関係を構築できているか?
Q.異動希望を出す理想のタイミングは?
異動希望は、遅くとも希望時期の1ヵ月前に提出するのが理想です。
上司や人事担当者に話を聞いてもらうタイミングとして適切なのは、「相手の繁忙期以外で落ち着いて話せるとき」になります。
ただし、ハラスメント被害や長時間労働などで心身に不調が出ているとか、家庭の事情で緊急性が高い状況である場合には、正当性が高い理由を添えて早めに相談したほうがよいでしょう。
Q.異動希望が出ないよう職場環境を改善するには
これは人事担当者からの問い合わせで特に多い質問です。
従業員からの異動希望がなるべく出ないようにするためには、“心理的安全性”が高い組織の構築を目指しながら以下の施策を講じていくことが重要になります。
・各従業員のキャリアビジョンや悩みに耳を傾け、寄り添う姿勢を持つ
・会社の方針や価値観(MVV)を浸透させる
・従業員エンゲージメントを高める取り組みをする
・コンプライアンスやハラスメントの教育を実施する
・職場環境やメンタルヘルスの相談・解決体制を構築する
また、職場環境を改善するためには、「従業員の声を聞くこと」と「施策を振り返りブラッシュアップすること」も大切です。この2つを両輪で回し続けることで、従業員の不安や不満、異動希望につながる職場環境の問題も少しずつ改善していくでしょう。
【内部リンク】従業員満足度(ES)と従業員エンゲージメントの違いとは?高めるメリットや方法も解説
人事労務のアウトソーシングならラクラスへ
本記事では、人事担当者や上司の皆さんに向けて異動希望の概要や重要性・正当性などを解説してきました。異動希望への対応には多くの注意点があるため、人事部のなかでも負担に感じている方は多いのではないでしょうか。
もし人事業務における業務効率化をお考えであれば、ラクラスにお任せください。ラクラスなら、クラウドとアウトソーシングを掛け合わせた『BpaaS』により、人事のノンコア業務をアウトソースすることができコア業務に集中できるようになります。
ラクラスの特徴として、お客様のニーズに合わせたカスタマイズ対応を得意としています。他社では難色を示してしまうようなカスタマイズであっても、柔軟に対応することができます。それにより、大幅な業務効率の改善を見込むことができます。
また、セキュアな環境で運用されるのはもちろんのこと、常に情報共有をして運用状況を可視化することも心掛けています。そのため、属人化は解消されやすく「人事の課題が解決した」という声も数多くいただいております。
特に大企業を中心として760社86万人以上の受託実績がありますが、もし御社でも人事の課題を抱えており解決方法をお探しでしたら、ぜひわたしたちラクラスへご相談ください。